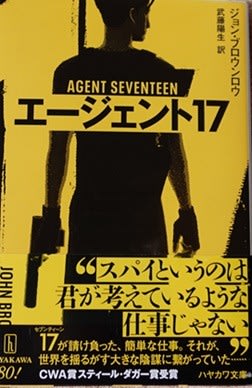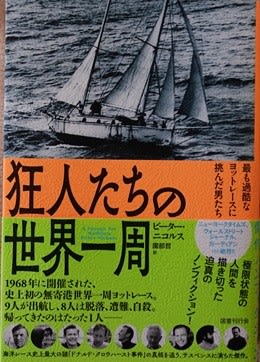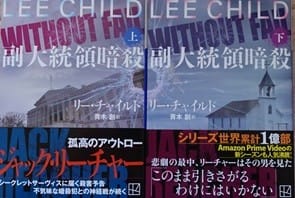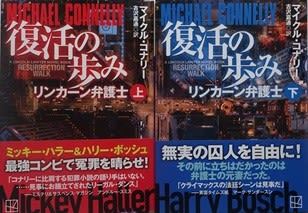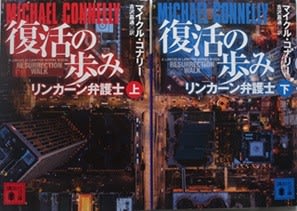週の初めにオクサンの友達の旦那さんが亡くなった。白血病だった。
息子の体育会クラブの顧問をと止めて頂いていた学者さんだった。引退して佐生年11月にはオクサンと東北旅行も楽しまれた。
今年の1月に血液の病気と聞いたが、治療はうまく行かず、白血病に変化していた。
余りに早い進行は残念に思う。79歳であられた。
手元に借りていたこの本があって、こちらも食道にガンを患って、5年が経過したのでちょっと記事にしてみることにした。
まずほんの方の前に私の食道がんの話になるけれど、その経緯は2020年4月17日からの当方の記事「monakaのガン入院アレアレ日記」に10回にわけて書いている。5年経ってもう一度見直すと下記になる。
剤焼酎は毎年期末に人間ドックを受けていたが、この年はうっかりしていて、オクサンに指摘されてあわてて受けたのが3月半ば。3月の後半土曜日には突然病院から上皮癌と指摘された。
翌月曜日に行きつけの病院に名医がいてみてもらった。その日からあれよあれよと検査が始まって入院、手術となった。
さて日本食道学会の分類にガン要因分類は3つに分かれてガンの進捗が特定される。
まずT因子といってガンの広がりを示すもの。T1a(がんが粘膜内にとどまる)ものからT4b(がんが食道周辺の組織まで広がって、切除できない状態までの6段階にわけられる。
次にリンパ節転移の状態で5段階にわける。最初がN0(リンパ節に転移がない)からN4(第4群リンパ説まで転移がある)に分けられる。もう一つが遠隔転移の有無でM0(ない)M1(あり)に分けられる。
私の場合の病理診断ではT1aN0M0となっていたわけできわめて初期、一般的にいうステージで0の段階だったわけです。食道がんでステージ0と1はかなり少ないパーセンテ―ジでの発見でよく見つかりましたの部類でした。
T病院の5年生存率のデーターに残ったなと、新たに幸運を感謝しながらこの本を読む。
本の方はガンを患った作家のガンを患っての書記になるわけだが、第1章青山文平氏(大腸がん)瀬戸内寂聴氏(胆のうがん)、井上荒野氏(結腸がん)そして第2章村田喜代子氏(子宮体がん)、杉本章子氏(乳がん)、宇江佐真理氏(乳がん)の書記は氏らが回復しているので、何とも軽い。軽すぎる私の記事にだってちかいといえないことはない。
問題は「最期のことば」という3章、4人の作家が登場するが、がんが発覚しほどなく死を迎えた人たち。
一人目が筑紫哲也氏で肺がんの宣告を受けた2007年7月15日から『残日録』というものを書いて2008年11月7日に亡くなっている。
次が米原万里氏で、抗がん剤治療のあとにいろいろな代替療法の本を身を以って体験したことが書かれていて、そのどれもの結果が記される。2006年卵巣がんにより56歳で死去。
次が藤原伊織氏で食道がん、実は氏が食道がんで亡くなったことはしっていたが、がんになった時と再発した時の二つの書記をのこしている。
これは私と同じガンなのでとても重い思いで読む。2005年2月に食事を嘔吐、3月14日に入院、結果放射線療法になった。
氏の一校はガンが発見された経緯と放射線療法の終了での良好な結果までだが、(この時点では結構著者も楽観した場面がある)しの書いた文をよむと、上記の分類に従えば、T4b(がんが食道周辺の組織迄広ががっていて、切除できない)N4(?)M1(?)でステージとしては3を通り越して4に入っている状態だと思う。この経緯をオール読物の2005年6月号に掲載している。
そして「がん再発始末」という記事は2006年7月号に掲載されるが、その前5月17日には59歳でなくなっている。
2006年3月にがんが再発し、手術が可能という判断で行って、4月27日に退院したが、力尽きた。
しの書いたこの稿には手術をして大変な思いをして、これから1年は生きないとと元が取れないとかいて、次のようにつづけている。だいぶ永くなってしまったけれど最後の文になるので引用しよう。
とまあ、かくのごとき境遇にいま私はいる。当誌には去年同様、無理をお願いしてこの稿を書かせていただいた。なのに、これは私の本来の仕事でないとの気分が膨らんできたのが面妖である。われながら、まことに身勝手な心変わりだと思うものの、特別な事情がないかぎり、この稿以降、病状への言及は控えるつもりであることを最後に孟子そえておきたい。
物書きの深い絶望がにじんでいる。
3章の最期は作家の北重人、2008年に胃がんの手術をうけ、よく2009年6月2日に再発をしらされる。
肝臓に転移した日から日記を書き始め、2ヵ月半後、8月26日になくなる。なくなる1週間前までの日記で、日々の辛さとそこに淡々と立ち向かうすがとが壮絶に思う。
4章は残された伴侶の手記で5章は対談になっているので割愛。
一度読んでおくと準備出来るのではと思う。