今年のノーベル物理学賞は、青色発光ダイオード(LED)を開発した赤崎勇・名城大終身教授、天野浩・名古屋大教授、中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授の3氏に授与されることに決まりました。なにかと世間の目を気にする日本人としては、スウェーデン王立科学アカデミーから認められたということに、この上もない喜びと誇らしさ・晴れがましさを感じていることでしょう。
授賞理由の説明で「20世紀は白熱灯が照らし、21世紀はLEDが照らす」と実に簡潔にまとめられていました(米ウォールストリート・ジャーナル紙は「LEDはエジソンの蛍光灯から完全に置き換わる」と報じました)。今回のノーベル賞は、何と言っても、同時代にその開発と実用化を目の当たりにしているものであるところに、感慨深いものがあります。敷衍すると、基礎理論での受賞が多いノーベル賞で、工学的な色彩が濃く、特に中村氏については実用化の功績が認められたことが、ある種の驚きでした。中村氏自身も、ハンダごてを片手に良質な結晶を作る装置を自作する日が続き、「半導体研究者と言うより機械技術者のようだった」と語っておられます。このあたりの事情について、赤崎氏と同じ名城大学の飯島澄男教授(カーボナノチューブの発見(1991年)で知られる)は、以前、「日本のノーベル賞受賞者は理論研究者が先行した。ひらめきが大切と思われがちだが、白川(英樹)先生(2000年化学賞)も田中耕一さん(2002年化学賞)も手を動かして色々と実験した。机の上で考えてもアイディアは出ない」と語っておられたものでした。
日本では「科学・技術」などと並べて言い表されることが多い「科学」と「技術」ですが、そもそも発祥は全く異なり、「技術」は生きるための必要に駆り立てられた身体的な行為であるのに対し、「科学」はとりあえずは生存とは切り離された好奇心に基づく頭脳的な思索であったと説明されます(木村英紀著「ものつくり敗戦」)。こうして本来は別々の「科学」と「技術」が車の両輪のような一体の協力関係が打ち立てられたのは、フランスにおいて「科学」を基礎に「技術」者を系統的に育てることを目的に設立されたエコール・ポリテクニクが誕生した18世紀末以降のこと、つまり明治維新になり開国して欧米から導入された「科学」と「技術」は、まさに「科学・技術」と一つの「」で括られるような関係にあって、日本人には初めからそれが当たり前のものとして受け止められたのだと解説されます。これが決して当たり前ではないのは、例えば中国や韓国では儒教のせいか科挙に蝕まれたせいか、「技術」が過度に軽んじられる(科挙のお勉強が幅をきかせる)ところからも知れます(中国では技術を育てることに経済的にガマンできず、サイバー攻撃に見られるように、てっとり早く盗もうとする)。対する日本人は「技術」を尊び「技術者」や「職人技」に敬意を払う国民性で、自然科学分野でノーベル賞受賞者が一人として出ていない中国や韓国(中国では平和賞・文学賞各1人、韓国では平和賞1人のみ)と17人(米国籍の南部陽一郎さんと中村修二さんを除く)に達する日本との違いを、あるいは説明する一つの背景になるのかも知れません。
余談ですが、ノーベル賞受賞者はまたしても東大ではなく、京大や名大や、今回、新たに徳島大の出身者でした。大学のカラーとして、トップ校としてのカタチが先ずあり、カタチを背負い、あるいはカタチを守ることを否応なく意識づけられ、何事もソツなくこなす秀才肌ではなく、カタチよりも内実に、しかも妙なこだわりがあったり、のびのびと自由な発想を育む次男坊、三男坊、さらには変人っぽいほどの(中村さんのことを異才と呼んだメディアがありましたが)異才・天才肌が、ノーベル賞には相性が良いのでしょうか(なんて勝手な想像ですが)。そう言えば、欧・米の間では、基礎研究ではアメリカが、応用研究ではヨーロッパが強いのだそうです。やはり形式に囚われない、精神の自由を保ち、イノベ―ティブなところこそ、ノーベル賞大国のアメリカらしさと思わせます。
授賞理由の説明で「20世紀は白熱灯が照らし、21世紀はLEDが照らす」と実に簡潔にまとめられていました(米ウォールストリート・ジャーナル紙は「LEDはエジソンの蛍光灯から完全に置き換わる」と報じました)。今回のノーベル賞は、何と言っても、同時代にその開発と実用化を目の当たりにしているものであるところに、感慨深いものがあります。敷衍すると、基礎理論での受賞が多いノーベル賞で、工学的な色彩が濃く、特に中村氏については実用化の功績が認められたことが、ある種の驚きでした。中村氏自身も、ハンダごてを片手に良質な結晶を作る装置を自作する日が続き、「半導体研究者と言うより機械技術者のようだった」と語っておられます。このあたりの事情について、赤崎氏と同じ名城大学の飯島澄男教授(カーボナノチューブの発見(1991年)で知られる)は、以前、「日本のノーベル賞受賞者は理論研究者が先行した。ひらめきが大切と思われがちだが、白川(英樹)先生(2000年化学賞)も田中耕一さん(2002年化学賞)も手を動かして色々と実験した。机の上で考えてもアイディアは出ない」と語っておられたものでした。
日本では「科学・技術」などと並べて言い表されることが多い「科学」と「技術」ですが、そもそも発祥は全く異なり、「技術」は生きるための必要に駆り立てられた身体的な行為であるのに対し、「科学」はとりあえずは生存とは切り離された好奇心に基づく頭脳的な思索であったと説明されます(木村英紀著「ものつくり敗戦」)。こうして本来は別々の「科学」と「技術」が車の両輪のような一体の協力関係が打ち立てられたのは、フランスにおいて「科学」を基礎に「技術」者を系統的に育てることを目的に設立されたエコール・ポリテクニクが誕生した18世紀末以降のこと、つまり明治維新になり開国して欧米から導入された「科学」と「技術」は、まさに「科学・技術」と一つの「」で括られるような関係にあって、日本人には初めからそれが当たり前のものとして受け止められたのだと解説されます。これが決して当たり前ではないのは、例えば中国や韓国では儒教のせいか科挙に蝕まれたせいか、「技術」が過度に軽んじられる(科挙のお勉強が幅をきかせる)ところからも知れます(中国では技術を育てることに経済的にガマンできず、サイバー攻撃に見られるように、てっとり早く盗もうとする)。対する日本人は「技術」を尊び「技術者」や「職人技」に敬意を払う国民性で、自然科学分野でノーベル賞受賞者が一人として出ていない中国や韓国(中国では平和賞・文学賞各1人、韓国では平和賞1人のみ)と17人(米国籍の南部陽一郎さんと中村修二さんを除く)に達する日本との違いを、あるいは説明する一つの背景になるのかも知れません。
余談ですが、ノーベル賞受賞者はまたしても東大ではなく、京大や名大や、今回、新たに徳島大の出身者でした。大学のカラーとして、トップ校としてのカタチが先ずあり、カタチを背負い、あるいはカタチを守ることを否応なく意識づけられ、何事もソツなくこなす秀才肌ではなく、カタチよりも内実に、しかも妙なこだわりがあったり、のびのびと自由な発想を育む次男坊、三男坊、さらには変人っぽいほどの(中村さんのことを異才と呼んだメディアがありましたが)異才・天才肌が、ノーベル賞には相性が良いのでしょうか(なんて勝手な想像ですが)。そう言えば、欧・米の間では、基礎研究ではアメリカが、応用研究ではヨーロッパが強いのだそうです。やはり形式に囚われない、精神の自由を保ち、イノベ―ティブなところこそ、ノーベル賞大国のアメリカらしさと思わせます。














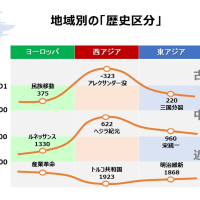




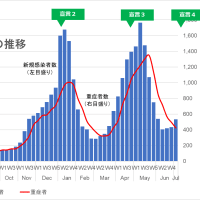





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます