先週、バスで出かけました。
長岡京まで。

大原から京都駅までバスで1時間ちょい。
それからJRで長岡京駅まで10分(笑)
複数人で出かけるならば、明らかに車の方が融通が利いてお得なんですが・・・
どうしても譲れない理由があって、バス。
それは・・・
サントリービールの京都工場の工場見学の申し込みをしたのでした。
当然試飲をするから、車は×。
飲まないともったいないですし。
最初はサントリー山崎のウイスキー工場に行きたかったのですが、
やはり朝ドラの影響からか大人気で、予約がいっぱい 連日満員です。
連日満員です。
まあ、いいか、ということで、ビール工場へ・・・
でも、お出かけの行程を考える時に気づいたのですが、
山崎って大阪だったのですね。
山崎と大山崎と長岡京は別行政区なのでした。島本町と大山崎町と長岡京市。
国道・高速・電車では、あっという間に過ぎる距離(5キロほどですが)なので、混同してしまいます。
で、サントリービール工場は、山崎じゃなくて、長岡京にありまして、長岡京駅に到着したのでありました。
工場見学は11時からの予約で、それまで何しようと思って地図を見ましたら・・・
なんと!
 お城と古墳、という、私には最高な組み合わせ。
お城と古墳、という、私には最高な組み合わせ。
隣で若!は苦笑い。
これは、神様のお告げだ、絶対に行くべし、と急にテンションが上がって
暑い中頑張って歩きました。

駅から徒歩5分ほど。
まっすぐ歩くと、この風景にたどり着きます。
 長岡京の代表花?キリシマツツジがきれいです
長岡京の代表花?キリシマツツジがきれいです
勝竜寺城・・・
細川ガラシャが新婚時代を過ごしたお城として有名。(ミーハーな言い方をしますと)
室町時代に京都の守護・畠山氏あたりが築城したと言われていて、
松永久秀や三好三人衆などが入った後、信長より拝領された細川藤孝(幽斎)がこの城に入りました。
そして、1578年、藤孝の息子・忠興と明智光秀の娘・玉(ガラシャ)が盛大な結婚式を挙げて、この城で新婚時代を過ごしたのだそうです。
 アルビノ?珍しい白いタンポポ
アルビノ?珍しい白いタンポポ
ちょうど、きのうファミマで買った歴史コミックに、勝竜寺城を端的に説明するくだりがあって、
それにならって説明しますと・・・
細川藤孝と明智光秀は互いに信頼し合い、姻戚でもある。
光秀が本能寺の変を起こした時、当然細川父子が加勢してくれるものだと考えていた。
しかし、細川氏も、同様に援軍を求めた筒井順慶も、味方についてくれなかった・・・誤算。
計算が外れた光秀、大幅な兵力の差、なすすべもなく、孤立。
一方、備中高松から驚異的なスピードで戻ってきた秀吉が天王山に集結した。
山崎の戦い。
光秀は、娘婿の居城・勝竜寺城に布陣し、態勢を整えるが、間に合わず・・・
「三日天下」と言われるような悲惨な結末に。
娘の玉(ガラシャ)は「逆臣の娘」として疎まれ、丹後の山深い地に幽閉された。


お堀を渡って、石垣に囲まれた敷地の中に入っていくと、
中はきれいに整備された公園になっていました。
櫓のような建物は管理棟。

そして・・・
下の写真 ↓

右端の建物、覗く時間がありませんでしたが、多分あそこにお城から発掘された石仏が祀られているみたいです。
安土時代のお城の石垣には、石仏が使われていますね~。
科学的にみると意味はなくても、仏像を石垣に使うなんて、ちょっと嫌ですね。
罰が…とか思いますが、どうでしょう。
安土城(信長)とか、福知山城(光秀)とか・・・

基本的には最近整備された公園という印象ですが
↑ ところどころお城の名残が感じられる部分があります。
萌え、ますね~

ガラシャさん、幽閉後も忠興公のところに戻っていますし、仲の良い夫婦だったみたいですが…

暑いし、時間が押しているので、ゆっくり説明板を読んでられませんでしたが、
こちらを管理されている方らしき紳士に、細川氏について、いろいろお話を聞かせて頂きました。
元首相の細川護熙氏は子孫にあたられるそうで・・・
応仁の乱とかで名前をよく聞く細川氏も、この細川氏で・・・
ビックリすることばかりでした。
歴史はほんと複雑ですけど、それを一つひとつ紐解いていくのが楽しい作業ですね~
さて。
予想以上にゆっくりしていたので、工場見学の時間が迫ってきました。
住宅地の中で、いかに道をショートカットしていくか・・・
野生の勘で進んでいたら、見事に迷ってしまい
こんなところに来てしまいました。

まあ、おかげで場所が把握できたし良かったですけど。
この古そうな線路の石橋に萌え~

JR東海道線のこの区間は明治9(1876)年に開業
なんとなく、その当時っぽいたたずまいじゃないですか。
きっと、この橋のどこかに施工年が書いてあるのでしょうけど。
気になります。
そして、小川の先には学校があって、その先に、古墳

あの曲線に萌え、ます。
恵解山(いげのやま)古墳

円墳部分は、市民墓地として使用されています。

方墳部分には竹林があり、小学生がタケノコ掘り?に来ていました。
目的がタケノコなのか、社会見学ついでにタケノコ掘りなのか・・・
向こうから挨拶してくれる気持ちいい子たちでした

昨年整備されたところで立派です。
こんな便利なところに、こんな素敵な古墳ができるなんて
長岡京市、あっぱれです

↑ すぐそこが線路なので、JRの電車から、よ~く見えますよ。

うれしいな、近くにこんな古墳ができるなんて
さて。
古墳から歩いて5分ほどで、
サントリービール工場に到着です。

時間がないし、すごい早足で歩いたから、もう汗だく

こんな快適空間に案内されて、幸せです
長岡京はタケノコの産地だから、やっぱりフロアからも竹林が見えています。

ビールの原料、ホップが花壇に植えられていました。

ホップ、麦じゃないのですね
麻科の植物で、ベルみたいな形の実がなります。
ビールの苦みの元になるそうです。

いよいよ、工場見学。あのタンクにビールの元がいっぱい入ってるらしいです。

温かい部屋に・・・(発酵臭がします)
冷たい部屋。

(瓶詰め作業、無人、とても衛生的です )
)
そして、最後に楽しい試飲

試飲?いや、本格的に飲む量ですよ、これは
(1杯目)プレミアムモルツ ↑
(2杯目)マスターズドリーム
(3杯目)↓ プレミアムモルツの違う盤、だったかな

この細かい泡に感激しました。
そして、サントリーの太っ腹にも
おつまみも美味しかったです。通販しているのなら買いたいです。
工場見学、もちろん、飲んだら運転禁止、ですが・・・
ここまで、ちょっとやそっとで醒めない量、飲ませてもらうとは
嬉しいような、申し訳ないような、でもやっぱり、もう一度行きたいな
次の日に、即!サントリー山崎・ウイスキー工場の見学を申し込んだのでした。
さて、ふわふわとした足取りで長岡天神に行きました。

キリシマツツジが満開です

背丈を超える大木です。

ここまで大きくするのは大変だったのでしょうね。

そして、長岡天神の境内に、どういうわけかトルコ料理のレストラン。
不思議なシチュエーションです。
ランチを頂きました。

お豆のスープに、料理とトルティーヤ(だったかな)
 インド料理に近い味
インド料理に近い味
豆料理が多いです。
地中海料理、っぽくもあるし・・・
お店の人も優しいし、ここは長岡に来たら必ず行く店になりそうです。

食べた後にお参り。

新緑と小鳥の声で爽やかです

緑が光っています

大木の深緑の新緑もきれい~

長岡天神のお池の端、菖蒲園では手入れをされていました。


長岡京は、京の工業地帯、あとは高速道路のイメージなのですが、
すごく充実したお出かけになりました。
ほかにも、遷都・長岡京の跡もありますし、史跡がいろいろ残っています。
まだまだ穴場が残っていそうです。

























 と突っ込まなければいけません。
と突っ込まなければいけません。 )
)










 )
)

































 (まあ、大原でも生えているんですが・・・)
(まあ、大原でも生えているんですが・・・)







 国宝 拝殿
国宝 拝殿




 大きい!
大きい!






 お城と古墳、という、私には最高な組み合わせ。
お城と古墳、という、私には最高な組み合わせ。

 長岡京の代表花?キリシマツツジがきれいです
長岡京の代表花?キリシマツツジがきれいです アルビノ?珍しい白いタンポポ
アルビノ?珍しい白いタンポポ




































 インド料理に近い味
インド料理に近い味







 霊山護国神社
霊山護国神社






 木戸孝允公の墓
木戸孝允公の墓 品川弥二郎の碑
品川弥二郎の碑
 円山公園の桜
円山公園の桜 石塀小路
石塀小路 知恩院前。
知恩院前。


 日本酒の苦手な方でも大丈夫
日本酒の苦手な方でも大丈夫
 鳥せい特製粕汁販売 1杯 200円 ボリュームたっぷりですよ
鳥せい特製粕汁販売 1杯 200円 ボリュームたっぷりですよ










 見逃しそうな看板です。
見逃しそうな看板です。
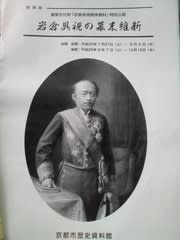























 )
)
 こういうとこ
こういうとこ



 ← 手前の建物が書院
← 手前の建物が書院 ここも落ちつく雰囲気で・・・
ここも落ちつく雰囲気で・・・


 朽ちかけ?の塀とアジサイの黄金の組み合わせ
朽ちかけ?の塀とアジサイの黄金の組み合わせ 光の芸術も見れます
光の芸術も見れます
 たぶん、ここが最高地点。
たぶん、ここが最高地点。

 お産の守護の御利益もあるそうですよ。
お産の守護の御利益もあるそうですよ。 緑がきれいでした
緑がきれいでした
 この辺の雰囲気にも、すごく人の活気を感じます
この辺の雰囲気にも、すごく人の活気を感じます








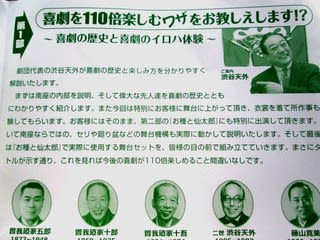
 京都新聞の広告より
京都新聞の広告より


 京都にお越しになる方は、ご予定に入れられてはいかがでしょうか?
京都にお越しになる方は、ご予定に入れられてはいかがでしょうか?
