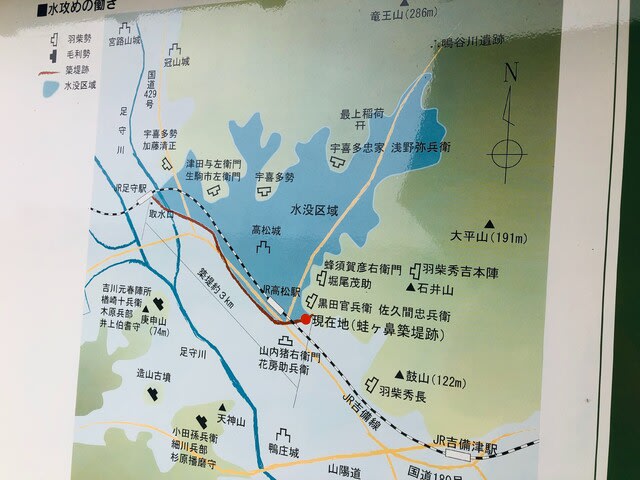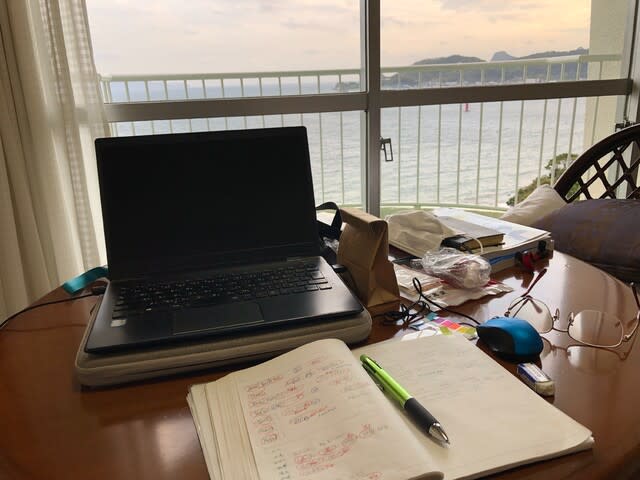知人を連れて、奥武蔵は子の権現と竹寺をハイクした。一行は3人だが私が先頭でペースを作る。実は集団で先頭を歩くのは初めてだ。ペースや休憩場所に気を遣う。雨上がりで暑くもなくちょうどいい気温、ただ途中から雨が降ってきた。
もうちょっとで大休止、雨具を出すのも面倒なため、傘をさして歩く。実は、登山で傘は厳禁だ。上高地などでは上高地より奥は、傘は叱られる。
子の権現に到着。ここはもう、大わらじの前の桜は満開だ。

次は、竹寺に向かって歩く。途中の峠で、「神送り場」という場所があった。峠は村境にあることが多く、昔は、疫病が流行ると、村人がここまで登ってきて、疫病神を追い払ったそうだ。今でいう、ロックダウンかな。

竹寺到着。ここで予約しておいた精進料理を頂く。ほぼ山菜のみの料理だ。料理には花と俳句が添えられている。凝った料理だ。お薬湯を頂く。日本酒のことだ。



最後に登山道で出会った花々の写真をアップします。春は一斉に花が咲きます、この季節、山を歩くのはいいですね。
(上:ヤマブキ、下:わかりません)


(上:ミツマタ、下:ツツジの仲間)