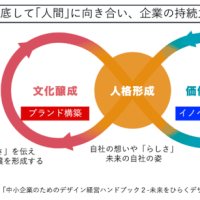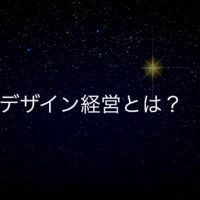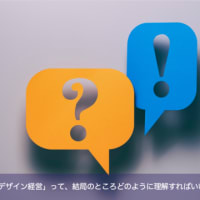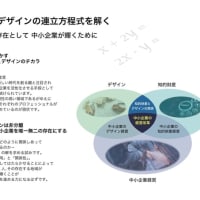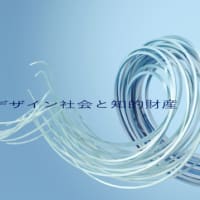先週金曜日に、知的財産推進計画2015が決定されました。
この決定について、次のような報道がされています。
「知的財産推進計画」決定 休眠特許の活用が柱(NHK)
・・・特許などの知的財産を地方でのビジネスの創出や拡大に結びつけることが重要だと指摘しています。
そして、▽大企業や大学などが保有しているものの使われていない、いわゆる「休眠特許」を中小企業が活用できる新たな仕組みを作るとともに、▽都市部の専門家を地方に配置し、中小企業が知的財産を活用できるようにするための支援体制を強化するとしています。・・・
大企業などの特許、地方中小の活用後押し 政府が推進計画(日本経済新聞)
・・・各地の自治体などに企業経営の経験者らを配置し、大企業や大学などが使わない「休眠特許」の中小企業の活用を促す。自治体や中小企業支援団体は、専門家の配置に財政的な支援を行う。
国内では現在、登録されている特許全体の半分に当たる約70万件が利用されていない。保有する特許の実施率を見ると、中小企業の66%に比べ、大企業は35%と低い。・・・
この計画策定のために設けられた「地方における知財活用の促進」タスクフォースに出席していたこともあり、少しでも誤解を解消できればということで書いておきますが(NHKや日経の報道に対して焼け石に水もいいところですが...)、知的財産推進計画2015の重点3本柱の1つである「地方における知財活用の促進」において、「休眠特許の活用」は柱にはなっていません。知的財産推進計画2015の本文を読んでいただければわかるとおり、「休眠特許」という概念すらどこにも出てこず、これらの報道は誤解に基づくものです。
知的財産推進計画2015の5p.~6p.には、「大企業が保有する知的財産を中小企業に開放し、それを活用して中小企業の新たな事業の創出につなげていく『知財ビジネスマッチング』」が紹介され、8p.には「大企業の知財活用については、知財活用途上型の中小企業が次なる一歩を踏み出すために必要な気付きと知恵を与えてくれる機会になることに鑑み、大企業が知的財産を開放して産産連携に積極的に参加するよう後押しをするなどの支援基盤の整備が求められる」と書かれていますが、ここに明らかにされているのは、大企業に特許技術の開放を促して、中小企業の知財活用を加速させようという問題意識です。その特許技術が「休眠」しているかどうかは問題ではありません。「開放」されているかどうかです。実際、知財ビジネスマッチングで先行している川崎市や近畿経済産業局の取組みでも、休眠していない、他でも利用されている特許技術の活用事例が多いと聞いています。
あくまで政策的な目標は、「地方創生の観点からも、地域中小企業がその持てる力を発揮するため、知的財産を創造し、活用していくサイクルを再構築していくこと」にあり、主役となるのは地域の中小企業です。以前から日経は「大企業の特許実施率が低い→休眠特許を活用すべし」といった文脈が好きなようで、知的財産推進計画には全く書いていないことを思い込みで記事にしていますが、大企業の遊休資産活用が政策的なテーマというわけではないので、中小企業に「休眠特許の活用」を促す理由はありません。中小企業の立場から見ると、大企業の特許技術の活用は、多くの場合は開発プロセスのショートカットや信用力の強化、PR効果に期待したいわけであって、実用レベルにあるかどうかが明らかでない「休眠特許」より、すでに他でも利用されている特許技術のほうが導入しやすいはずです。そのあたりはちゃんと議論した上で、今回の知的財産推進計画が作成されていることをご理解いただけると有難いです。
なお、「地方における知財活用の促進」のテーマで議論された中小企業の知財活用については、これまでは画一的に論じられることが多かった中小企業を、知財活用の状況から「知財活用挑戦型」(グローバルニッチトップのような先進的な知財活用企業)と「知財活用途上型」(下請け型など知財権取得の必要性が生じにくかった企業)の2つのタイプに区分し、施策の方向性を分けて検討していることが今回の大きな特徴です。前者については、これまでも検討されてきたような先進的な知財戦略をサポートする施策が、後者については様々な方法で意識啓発の機会を設ける施策が必要であり、大企業が開放している特許技術を導入して新規事業に取り組む「知財ビジネスマッチング」は、後者の施策の一つという位置付けになります。
<参考エントリ> 活かすべきは「休眠特許」ではなく「開放特許」
この決定について、次のような報道がされています。
「知的財産推進計画」決定 休眠特許の活用が柱(NHK)
・・・特許などの知的財産を地方でのビジネスの創出や拡大に結びつけることが重要だと指摘しています。
そして、▽大企業や大学などが保有しているものの使われていない、いわゆる「休眠特許」を中小企業が活用できる新たな仕組みを作るとともに、▽都市部の専門家を地方に配置し、中小企業が知的財産を活用できるようにするための支援体制を強化するとしています。・・・
大企業などの特許、地方中小の活用後押し 政府が推進計画(日本経済新聞)
・・・各地の自治体などに企業経営の経験者らを配置し、大企業や大学などが使わない「休眠特許」の中小企業の活用を促す。自治体や中小企業支援団体は、専門家の配置に財政的な支援を行う。
国内では現在、登録されている特許全体の半分に当たる約70万件が利用されていない。保有する特許の実施率を見ると、中小企業の66%に比べ、大企業は35%と低い。・・・
この計画策定のために設けられた「地方における知財活用の促進」タスクフォースに出席していたこともあり、少しでも誤解を解消できればということで書いておきますが(NHKや日経の報道に対して焼け石に水もいいところですが...)、知的財産推進計画2015の重点3本柱の1つである「地方における知財活用の促進」において、「休眠特許の活用」は柱にはなっていません。知的財産推進計画2015の本文を読んでいただければわかるとおり、「休眠特許」という概念すらどこにも出てこず、これらの報道は誤解に基づくものです。
知的財産推進計画2015の5p.~6p.には、「大企業が保有する知的財産を中小企業に開放し、それを活用して中小企業の新たな事業の創出につなげていく『知財ビジネスマッチング』」が紹介され、8p.には「大企業の知財活用については、知財活用途上型の中小企業が次なる一歩を踏み出すために必要な気付きと知恵を与えてくれる機会になることに鑑み、大企業が知的財産を開放して産産連携に積極的に参加するよう後押しをするなどの支援基盤の整備が求められる」と書かれていますが、ここに明らかにされているのは、大企業に特許技術の開放を促して、中小企業の知財活用を加速させようという問題意識です。その特許技術が「休眠」しているかどうかは問題ではありません。「開放」されているかどうかです。実際、知財ビジネスマッチングで先行している川崎市や近畿経済産業局の取組みでも、休眠していない、他でも利用されている特許技術の活用事例が多いと聞いています。
あくまで政策的な目標は、「地方創生の観点からも、地域中小企業がその持てる力を発揮するため、知的財産を創造し、活用していくサイクルを再構築していくこと」にあり、主役となるのは地域の中小企業です。以前から日経は「大企業の特許実施率が低い→休眠特許を活用すべし」といった文脈が好きなようで、知的財産推進計画には全く書いていないことを思い込みで記事にしていますが、大企業の遊休資産活用が政策的なテーマというわけではないので、中小企業に「休眠特許の活用」を促す理由はありません。中小企業の立場から見ると、大企業の特許技術の活用は、多くの場合は開発プロセスのショートカットや信用力の強化、PR効果に期待したいわけであって、実用レベルにあるかどうかが明らかでない「休眠特許」より、すでに他でも利用されている特許技術のほうが導入しやすいはずです。そのあたりはちゃんと議論した上で、今回の知的財産推進計画が作成されていることをご理解いただけると有難いです。
なお、「地方における知財活用の促進」のテーマで議論された中小企業の知財活用については、これまでは画一的に論じられることが多かった中小企業を、知財活用の状況から「知財活用挑戦型」(グローバルニッチトップのような先進的な知財活用企業)と「知財活用途上型」(下請け型など知財権取得の必要性が生じにくかった企業)の2つのタイプに区分し、施策の方向性を分けて検討していることが今回の大きな特徴です。前者については、これまでも検討されてきたような先進的な知財戦略をサポートする施策が、後者については様々な方法で意識啓発の機会を設ける施策が必要であり、大企業が開放している特許技術を導入して新規事業に取り組む「知財ビジネスマッチング」は、後者の施策の一つという位置付けになります。
<参考エントリ> 活かすべきは「休眠特許」ではなく「開放特許」