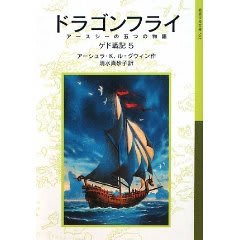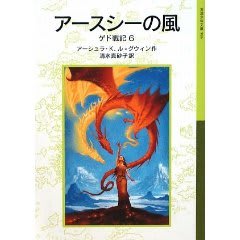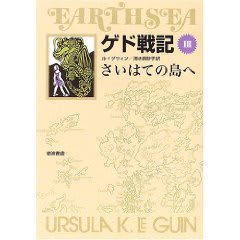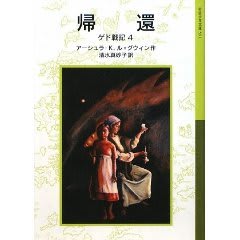休みも1週間経って、毎日更新もそろそろネタが尽きてきますので、だんだん与太話になって来ますが・・・(汗)
先日グイン・サーガのアニメを見ていて、グインが公女将軍アムネリスに向かって「女の身で鎧兜をまとっているが本物の戦士の前では笑止千万」とかなんとか言うシーンがあって、そういやこんなこと言ってたなあと・・・
原作の最新刊126巻でも、リンダが「国家の元首は男性でないと」というようなことを言っていて、ふーん、と思ったところだったんですね。
ちょうどゲド戦記を読んだところだったからというのもあるんですが、女性が書いていてこういうこと書くんだー、と。
グイン・サーガは当初は「ヒロイックファンタジー」というジャンルのつもりで書いていたはずで、なので原作序盤のアムネリスに対するこの台詞はまあそんなもんかな、と思うんですが、昨今の女性も活躍する作品が多い中で改めて聞くと、まあ古風だなあと思ってしまいました。まあ書かれたのも70年代ですが。
しかし、最新刊でもそんなに変わらないこと書いてるなあというのにちょっと驚いたというか。
たまたまキャラクター的にアムネリスもリンダも、一見気が強そうだけど実は女らしい性格、というキャラクターだというのもあるかもしれませんが、なんか行間からそれだけではないものを感じていまうんですね。
「女性だとダメ」というのが、もともとの性質の違いによるものなのか、それとも社会的なしくみで積み上げられてきたものなのか・・・というところですが、ゲド戦記を読んだ後だと、後者に軍配、と個人的には思ってしまうのですが。
まあ、社会的に古い段階にあると思われるファンタジーの世界の場合、女性が社会的に低い位置にいるのは当然とも言えるかもしれないんですが。
なんか、アメリカで育ったル=グインと、日本で育った栗本薫の違いを感じるかな、とも思いました。
そんな中でつい連想してしまうのは、トールキンは結構女性のキャラクターを重要な位置につけてるよなあ、ということです。
まあ、「終わらざりし物語」の「アルダリオンとエレンディス」を読んだりすると、トールキンも結構「女には男の気持ちは理解できない」みたいな考え方なんだなあ、というのが見えるのですが。そもそも女性の登場人物が異常に少ないことからも、決して女性を男性と同等には考えていないことがうかがえますし。
しかし、初めてエオウィンの活躍を読んだ時にはあまりに斬新なのでびっくりしたし、実は奥方の方が権力ありそうなガラドリエルも珍しいなあと思ったものです。
エオウィンについては、トールキンらしい、既存の神話・英雄伝説のパロディ的な「常識はずし」として女性のエオウィンを活躍させたのかなあとも思いますが、それにしてもあのエオウィンのカッコよさったら。初読時の驚きは忘れられません。
子供の頃から、ファンタジーのような冒険譚がわりと好きだったのですが、もっと女の子が活躍する話があればいいのになあ、と思って、やや不満だったんですよね。今だと女の子が主人公の話なんて、マンガでもライトノベルでも珍しくないかもしれませんが。
そんな中、あしべゆうほの「クリスタル・ドラゴン」を読んだ時には、こういうのが読みたかったんだ、と嬉しかったものです。(未だに完結してませんが・・・(汗))
でも、なかなか「これだ」というものに巡り合えないまま来て、まさか19世紀生まれのトールキンの作品でエオウィンのようなキャラクターに出会えるとは思ってなかったですね。ハマった理由はエオウィンだけではないですが。
本当に、19世紀生まれで結構保守的なトールキンになぜエオウィンのようなキャラクターが生み出せたのか、その理由がすごく知りたいんですけどね。なかなかそういうこと研究してる人もいないみたいであんまり聞きませんね・・・。ガラドリエルには母親の、ルシエンにはエディス夫人の存在が感じられたりもしますが、エオウィンはよくわからない・・・
まあとにかく、そういうところも「指輪」の魅力なんですよね。と無理やり指輪カテゴリーの内容に適合させて締めたりして(汗)
先日グイン・サーガのアニメを見ていて、グインが公女将軍アムネリスに向かって「女の身で鎧兜をまとっているが本物の戦士の前では笑止千万」とかなんとか言うシーンがあって、そういやこんなこと言ってたなあと・・・
原作の最新刊126巻でも、リンダが「国家の元首は男性でないと」というようなことを言っていて、ふーん、と思ったところだったんですね。
ちょうどゲド戦記を読んだところだったからというのもあるんですが、女性が書いていてこういうこと書くんだー、と。
グイン・サーガは当初は「ヒロイックファンタジー」というジャンルのつもりで書いていたはずで、なので原作序盤のアムネリスに対するこの台詞はまあそんなもんかな、と思うんですが、昨今の女性も活躍する作品が多い中で改めて聞くと、まあ古風だなあと思ってしまいました。まあ書かれたのも70年代ですが。
しかし、最新刊でもそんなに変わらないこと書いてるなあというのにちょっと驚いたというか。
たまたまキャラクター的にアムネリスもリンダも、一見気が強そうだけど実は女らしい性格、というキャラクターだというのもあるかもしれませんが、なんか行間からそれだけではないものを感じていまうんですね。
「女性だとダメ」というのが、もともとの性質の違いによるものなのか、それとも社会的なしくみで積み上げられてきたものなのか・・・というところですが、ゲド戦記を読んだ後だと、後者に軍配、と個人的には思ってしまうのですが。
まあ、社会的に古い段階にあると思われるファンタジーの世界の場合、女性が社会的に低い位置にいるのは当然とも言えるかもしれないんですが。
なんか、アメリカで育ったル=グインと、日本で育った栗本薫の違いを感じるかな、とも思いました。
そんな中でつい連想してしまうのは、トールキンは結構女性のキャラクターを重要な位置につけてるよなあ、ということです。
まあ、「終わらざりし物語」の「アルダリオンとエレンディス」を読んだりすると、トールキンも結構「女には男の気持ちは理解できない」みたいな考え方なんだなあ、というのが見えるのですが。そもそも女性の登場人物が異常に少ないことからも、決して女性を男性と同等には考えていないことがうかがえますし。
しかし、初めてエオウィンの活躍を読んだ時にはあまりに斬新なのでびっくりしたし、実は奥方の方が権力ありそうなガラドリエルも珍しいなあと思ったものです。
エオウィンについては、トールキンらしい、既存の神話・英雄伝説のパロディ的な「常識はずし」として女性のエオウィンを活躍させたのかなあとも思いますが、それにしてもあのエオウィンのカッコよさったら。初読時の驚きは忘れられません。
子供の頃から、ファンタジーのような冒険譚がわりと好きだったのですが、もっと女の子が活躍する話があればいいのになあ、と思って、やや不満だったんですよね。今だと女の子が主人公の話なんて、マンガでもライトノベルでも珍しくないかもしれませんが。
そんな中、あしべゆうほの「クリスタル・ドラゴン」を読んだ時には、こういうのが読みたかったんだ、と嬉しかったものです。(未だに完結してませんが・・・(汗))
でも、なかなか「これだ」というものに巡り合えないまま来て、まさか19世紀生まれのトールキンの作品でエオウィンのようなキャラクターに出会えるとは思ってなかったですね。ハマった理由はエオウィンだけではないですが。
本当に、19世紀生まれで結構保守的なトールキンになぜエオウィンのようなキャラクターが生み出せたのか、その理由がすごく知りたいんですけどね。なかなかそういうこと研究してる人もいないみたいであんまり聞きませんね・・・。ガラドリエルには母親の、ルシエンにはエディス夫人の存在が感じられたりもしますが、エオウィンはよくわからない・・・
まあとにかく、そういうところも「指輪」の魅力なんですよね。と無理やり指輪カテゴリーの内容に適合させて締めたりして(汗)