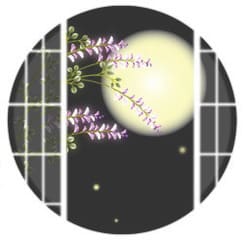ちょっと前に話題になったビジネス書。「孤独と貧困から自由になる、働き方の未来図 2025」という副題がついている。
著者のリンダ・グラットンさんは、ロンドン・ビジネススクールの教授で、働き方の研究をなさっている方らしい。彼女の言いたい事はこうだ。
2025年には、世界の人口のうち、50億人くらいがインターネットでつながっているので、パソコンを通じて、単純な労働は、皆、途上国の労働者の仕事になる。だから、私たちは高度な専門知識と技能を身に着け、友人とつながり、収入ではなく創造的な仕事をすべきだ…という事らしい。
なるほどね。でも、これって頭の良い人の話であって、そうでない人はどうすればいいの?
ていうか、50億の人間が、いっせいに、それぞれの専門知識や技能を持つことって、可能なんだろうか? ごく少数の人が持つからこそ、高度な専門知識なのであって、50億人が持っていたら、ありふれた物になるんじゃないの?
それとも、50億の専門分野があるんだろうか?
色々、考えてしまう。
それよりも、リンダさんが来日した時のインタビュー記事が、とても印象的だった。
リンダさんは、日本に来た時、空港のタクシー運転手が、日本人ばかりだったので、本当に驚いたそうだ。なぜなら、他の先進国では、タクシー運転手は移民の仕事らしい。
その理由として、彼女は日本語を挙げていた。
もちろん、日本政府が、移民に消極的な方針のせいもあるけど、何よりも、日本語の高い障壁が、外国人の参入を阻んでいると。
そうかもね。日本語って難しいものね。
日本全国どこに行っても、誰にでも英語が通じれば、専門性の低い仕事は、みな賃金が安い外国人労働者がやることになるだろう。
そうか、私たちは、日本語に守られているとも言えるのか。最終的には良い事か悪い事か、わからないけれど。
著者のリンダ・グラットンさんは、ロンドン・ビジネススクールの教授で、働き方の研究をなさっている方らしい。彼女の言いたい事はこうだ。
2025年には、世界の人口のうち、50億人くらいがインターネットでつながっているので、パソコンを通じて、単純な労働は、皆、途上国の労働者の仕事になる。だから、私たちは高度な専門知識と技能を身に着け、友人とつながり、収入ではなく創造的な仕事をすべきだ…という事らしい。
なるほどね。でも、これって頭の良い人の話であって、そうでない人はどうすればいいの?
ていうか、50億の人間が、いっせいに、それぞれの専門知識や技能を持つことって、可能なんだろうか? ごく少数の人が持つからこそ、高度な専門知識なのであって、50億人が持っていたら、ありふれた物になるんじゃないの?
それとも、50億の専門分野があるんだろうか?
色々、考えてしまう。
それよりも、リンダさんが来日した時のインタビュー記事が、とても印象的だった。
リンダさんは、日本に来た時、空港のタクシー運転手が、日本人ばかりだったので、本当に驚いたそうだ。なぜなら、他の先進国では、タクシー運転手は移民の仕事らしい。
その理由として、彼女は日本語を挙げていた。
もちろん、日本政府が、移民に消極的な方針のせいもあるけど、何よりも、日本語の高い障壁が、外国人の参入を阻んでいると。
そうかもね。日本語って難しいものね。
日本全国どこに行っても、誰にでも英語が通じれば、専門性の低い仕事は、みな賃金が安い外国人労働者がやることになるだろう。
そうか、私たちは、日本語に守られているとも言えるのか。最終的には良い事か悪い事か、わからないけれど。