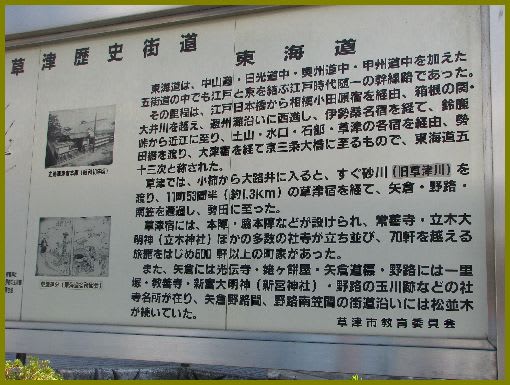大阪ステーションシティのノースゲートビル。11階の風の広場から階段で14階へあがる。



そこには「天空の農園」がある。
案内パンフレットによれば、「都市の中で自然を実感し、憩いと潤いを与えるオアシス空間。
緑地機能のみならず、心と体に居心地のよい広場を目指す」とあった。
今度の改装で、大阪駅は「エコ」に気を配っている。
風力発電や太陽光発電の試みに挑戦し、ホームを覆うドームでは、その雨水を再利用する試み
などが工夫されていると言う。

ノースゲートビルのこの空間は北向きだ。
淀川の流れも、すぐ、そこに見える。
今の季節は良いが、冬場は、さぞ、寒いことだろう。



街づくりの槌音は今もつづいている。
はたして、この地域の街づくりが完成するのを見届けられるだろうか。
(おわり)