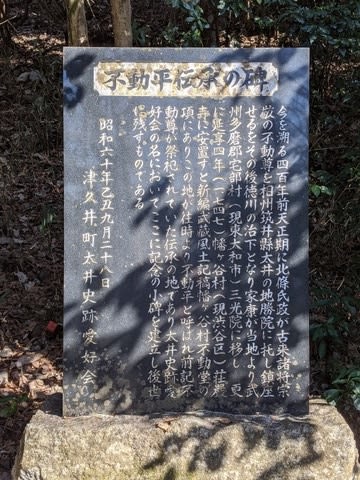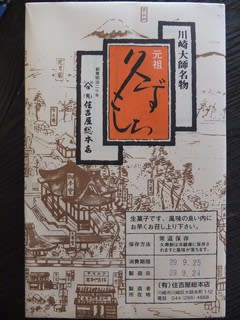川崎大師の駅へ降り立つと、川崎大師へは一旦大師様の敷地をやり過ごし、東側から回り込んで参道に入ることになる。
お大師様の縁起によれば、川崎大師の御本尊は、川崎の沖合いで網に引き揚げられた仏像であるとか。
お堂が海に向いているのは、そのせいなのか。

お約束のくずもち。
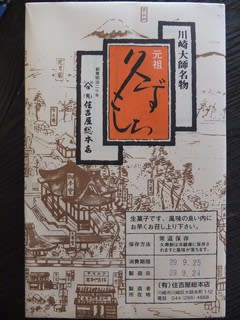
昔はよく親類がお土産などで持ってきてくれた。
物心ついたころにはすでに食べていた。
最近はそうでもないが、昔はたいへんなご馳走だった。
なぜだか渋谷駅でも売っていた。

お大師様から多摩川へ。

広大な芦原が広がっている。
急流な多摩川だが、さすがにこの辺まで来るとほとんど流れもない。

この中途半端に豪華な水門は、ちょっと異様な建造物だ。

上に乗っている彫刻のようなものは、川崎名産のぶどうや梨、桃なのだそうだ。
意外に知られていないかもしれないが、川崎は果物王国だ。
一世を風靡した梨の代表的品種の長十郎は、
川崎の大師河原に住んでいた長十郎さんが発見した品種で、
一時期は市内でも沢山生産されていた。

六郷の渡し跡
多摩川に架かる歩道を歩いて行くと、大きな中洲には芦原が広がっている。
なかなかの規模で圧倒される。


JRの鉄橋下には、蟹が沢山いるのに驚いた。
みんな泥をかぶっていて種類はよくわからないが、昔の川崎のイメージを払拭するかのような光景だ。


今日はここで終了
バスで小杉へ
ちなみに昨日は、田園都市線の鷺沼駅から江田駅まで歩いた。