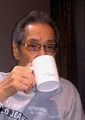|
成長のない社会で、わたしたちはいかに生きていくべきなのか (一般書) |
| 水野和夫,近藤康太郎 | |
| 徳間書店 |
ランキング応援よろしくです
人気ブログランキング
●日経曰く、長命リスクを乗り切る知恵 資産運用、投機に走れ!
日経新聞に、長寿を歓んで謳歌している暇はない。今すぐにでも、投資と云うものに取り組まないと、「長生きリスクの罠にはまる」みたいな解説記事と社説が掲載されていた。何という我田引水なメディアなのだろうか、政権が狂いだせば、メディアが一層狂う典型のような記事である。「資産4000万円でも底をつく 人生90年の備え方」と云う特集記事の詳細は13日の金曜日に、おどろおどろしく本紙に掲載されるようなので、この記事は前宣記事と云うことだろう。先ずは、その記事を読んでいただき、次に期せずして、畳み込むように、社説でも言及する念の入れようだ。このからくりの種明かしは、いずれ日経新聞の全面広告で検証できるのだろうが、あまりにも酷い提灯記事と思われる。
≪ 資産4000万円でも底をつく 人生90年の備え方
「賃貸住宅に住み続けるべきか、思い切って自宅を購入すべきかどちらが得か迷っています」──。頑張って預金8000万円をためたある50代の夫婦。ファイナンシャルプランナー(FP)の小屋洋一氏に相談したが答えは意外なものだった。「持ち家でも借家でも、あなたの人生にとって大きな問題ではありません」
小屋氏が重視したのは、今後30年以上続くこの夫婦の残りの人生のお金の問題。「運用の仕方によっては1億円以上の損得が生じますよ」。預金一辺倒で運用など考えていなかった夫婦はこの日以降、相談内容を老後のマネープランに切り替えた。
■長生きは「リスク」
日本人の平均寿命は2012年で男性79.94歳、女性86.41歳。60歳で退職しても先は長い。2年で2%の物価上昇をうたった日銀の「異次元緩和」から1年たち、物価は上がり始めている。現金を眠らせておくままでは資産価値が目減りする。年金支給の開始年齢も段階的に引き上げられている。老後の備えは今や1人1人の切実な問題だ。
生命保険文化センターによると、老後の通常の生活にかかるお金は夫婦で最低でも月22万円、旅行などゆとりある生活には月35万円が必要。体調を崩し入院すればさらに1日平均2万1000円、介護付き有料老人ホームに入れば入居時に1000万円近くかかる場合もある。
日経ヴェリタスがFPの協力を得て夫の60歳の退職時に4000万円の金融資産がある年金暮らしの夫婦をシミュレーションすると、年金収入に加えて金利の付かない現金の状態のままの資産を取り崩して生活する場合、81歳で完全にお金がなくなってしまった。
「長生きはお金の面から見ればリスクだと認識し、しっかり備えなければいけない」。老後資金を研究する山口大学の城下賢吾教授は警鐘を鳴らす。
老後の必要資金をどのように備えるべきか。専門家は(1)資産運用(2)就労継続(3)資産の有効活用──の3点を助言する。
■70代でも資産形成
フィデリティ退職・投資教育研究所の投資家3000人調査では投資目的について、70代の回答でトップだったのは「老後の資産形成のため」(47%)。70代でも資産形成に励む必要があるという、現実の厳しい一面を示す結果になった。
先のシミュレーションによると年率3%のリターンで4000万円全額を運用した場合、お金が底をつくのは90歳。現金を眠らせる場合と比べて、9年遅らせることができる。
仕事のリタイア時期を延ばし、趣味の夫婦旅行を楽しむのは横浜市在住の72歳男性。60歳で大手メーカーを定年退職後、ビル管理技術者資格を生かし62歳 から大型ビル管理の仕事を始めた。週4日ほどの勤務で月10万円稼ぐ。「生活費は年金、趣味は仕事の収入から。資産は取り崩さない」。金融資産の8割を株 式投資に配分し、資産運用にも励む。「仕事と趣味、投資が元気の源」と笑顔だ。
自宅を担保に資金を借り、死後に自宅を売って返済する「リバースモーゲージ」も広がっている。東京スター銀行は2005年のサービス開始以降、利用件数は低迷し続けたが、ここ3年で急速に契約を伸ばし、2月には累計で3200件を超えた。
人生90年。豊かに暮らすにはお金がかかる。あらかじめ老後の負担を正しく把握し、資産を上手に活用することが長生きを謳歌する第一歩と言えそうだ。 ≫(日経新聞電子版:詳細は13日付紙面に)
≪ 年金の安定へ即座に改革着手を 〈社説〉
少子高齢化の中、厚生年金や国民年金は将来どうなるのか。厚生労働省はこのほど、おおむね100年先までの公的年金の財政状況を検証し、結果を発表した。
それを見ると「今のままでは安心できない」と言わざるを得ない。ある程度意味のある年金を支給し続けるには、制度の改革が欠かせない。改革は国民や企業の痛みを伴うが、放置していては将来世代へのしわ寄せがひどくなるばかり。早急に着手すべきだ。
■楽観できない検証結果
公的年金は人口構成や経済環境に大きな影響を受けるが、それらは時代とともに変化する。そこで厚労省は5年ごとに、人口や経済の新たな前提を置いて将来を検証している。今回は経済について、中長期的に高成長が続くケースからマイナス成長となるケースまで、8通りの前提で試算した。
公的年金の支給水準は、モデル年金額が現役男性会社員の平均手取り収入に対してどの程度あるかという割合で示す。これを「所得代替率」という。モデル年金とは、平均収入で40年会社に勤めた夫と専業主婦の妻からなる世帯がもらう額をいう。
現時点での所得代替率は62.7%。検証結果によると、8通りの経済前提のうちの中間で標準的とみられるケースの場合、所得代替率は約30年かけて50.6%にまで下がって安定する。年金は約2割の目減りだ。 政府は所得代替率50%以上の維持を目標としているから、このシナリオなら目的を達することになる。しかし、ひと安心とはいかない。前提が楽観的なのだ。
今後10年で日本経済は急速に回復し、中長期的に物価は毎年1.2%、賃金は2.5%伸びるとする。年金積立金の運用利回りの見通しも5年前の検証の標準ケースよりわずかだが引き上げている。女性や高齢者の労働参加も大幅に増えると仮定する。
後で「あの通りにはいきませんでした」では信頼を損なう。より堅実な前提に重きを置くべきだとわたしたちは主張してきた。
女性らの労働参加も進まず中長期的にマイナス成長が続く最悪ケースでは、40年後の所得代替率は39%にまで下がりかねない。年金は今より4割ほど目減りすることになる。アベノミクスが功を奏すことを期待したくもなるが、厳しい未来も視野に入れ、改革を実施していく必要がある。
公的年金は2004年、現役世代の負担ばかりが増えるという批判を踏まえて、保険料に上限を設け、その範囲内で年金を支給する制度に変更した。厚生年金の場合で給料にかかる保険料率は現在約17%だが、3年後には18.3%まで上がって固定される。
ただ、そのときに導入した「マクロ経済スライド」はまだ一度も発動されていない。年金水準を毎年小刻みに下げる仕組みだが、デフレ経済下では機能しにくい立て付けになっているためだ。
制度を見直し、即座に着実に実施していくべきだ。早いうちに年金の水準を切り詰めておけば、将来の水準低下をある程度抑えることができる。
年金制度の支え手を増やすことは、年金財政健全化に役立ち支給水準も上げる。
■支え手を増やそう
女性を中心とするパート労働者の厚生年金加入を進め、保険料を負担してもらうようにしていきたい。現在、パートの中には夫に扶養される立場として、保険料を負担していない人も多い。
現在は原則65歳である年金の受給開始年齢を引き上げることも、検討に値する。この場合、高齢者が働きやすい環境を整えていくことが必要だ。
年金財政が厳しいと公的年金積立金の運用に期待したくなる。だが、高い利回りを前提に制度を考えるべきではない。運用の目的は将来の年金受給者のため長期的に年金資産の価値を高めることだ。運用力の強化は進めるべきだが、目先の利回りを最優先するような運用体制にしてはならない。
年金制度に関連した様々な制度改革も進めたい。現役世代に比べ優遇されている高齢者に対する税制は見直し、世代間格差の是正につなげてほしい。収入や資産が多い高齢者には相応の負担を求め、世代間だけでなく世代内の助け合いも強化していくべきだ。
女性や高齢者の社会参加を進めて担い手を増やすだけでなく、将来の担い手である子供の数も増やしたい。夫婦共働きでも子育てがしやすい社会をつくるなど、年金の安定に向けて社会全体を変えていく必要もある。 ≫(日経新聞6月8日付社説)
ご無理ごもっとものような社説だが、昨日の伊藤元重のコラム同様、根っこの前提の議論が抜け落ちている。つまり、現状のまま、どのような改革に着手しようと、“目くそ鼻くそ”の類の議論になるだけだ。定年退職しした人々の何%が、4000万の金融資産を有しているか、非常に恵まれた類の人を前提にしているのも気に入らん。 ≪生命保険文化センターによると、老後の通常の生活にかかるお金は夫婦で最低でも月22万円、旅行などゆとりある生活には月35万円が必要。≫とあるが、通常の生活費が22万円で、ゆとりある生活なら35万円と跳ね上がる。月額13万円も浪費するゆとりってのは、なんじゃい!月10万程度で若いお姉さんでもサポートするアイデアなのだろうか?(笑)
今のままのシステム(中央集権体制)では、どのようなシミュレーションをしても、多くが捕らぬ狸の議論になるわけで、時間の無駄、金の無駄である。いまの統治システムを変えたくない連中が考える限り、永遠に答えは得られない。地方主権と地産地消的な生活観念の変革。そして、そもそも、幸福感とは何なのか、この難しい哲学的論争を経ないことには、納得な答えは出てこない。うんざりするほど気の遠くなる議論だが、いずれ、この議論の場に座らないことには、物事が前に進まない事実を国民は認めざるを得なくなるのだ。その為に、早く、現在の体制の日本と云う国が亡びるのは良いことかもしれない。亡んでしまえば、考えると云う行為が行える人間であることに気づくだろうから。
人間には知恵がある。援けあう心もある。他人との距離感を適度に保つバランス感覚もある。しかし、人間の感性を超えた大きさに拡がった世界で置き去りになると、この持って生まれた人間の基本的感性が眠りにつく。ここが中央集権体制の国家の嵌りやすい落とし穴なのだ。知っている顔、知っている町や村を歩いている限り、落とし穴がどこにあり、どこそこの沼は底なし沼だと伝えてくれる伝承が残る。ここなんだよね、地方分権と共同体自治が成立する肝は。地域ごとに個性的に生きる面であれば、日本人は異様に優秀な民族になる。あまりに広過ぎ、早すぎると、日本人は感性を失い、民族の有能度を発揮する場を失う。
≪投資家3000人調査では投資目的について、70代の回答でトップだったのは「老後の資産形成のため」(47%)。70代でも資産形成に励む必要があるという、現実の厳しい一面を示す結果になった。≫こんなことも書いてある。つまり、ない金を増やそうと投資するわけだが、ない金がゼロになる話をしていないのが奇妙だ。投資は投機である。根こそぎ無くなるばかりか、借金まで抱えるリスクもあるわけだ。そのような事態が起きたら、日経は、投資・投機は自己責任の範囲で、と口を拭うのであろう。亡き邱永漢氏が言っていた。「金を貯めるコツは金を使わないことだ」貧乏な人ほど、この言葉の意味を充分理解してほしいものだ。
 |
年金は本当にもらえるのか? (ちくま新書) |
| 鈴木 亘 | |
| 筑摩書房 |
ランキング応援よろしくです
人気ブログランキング