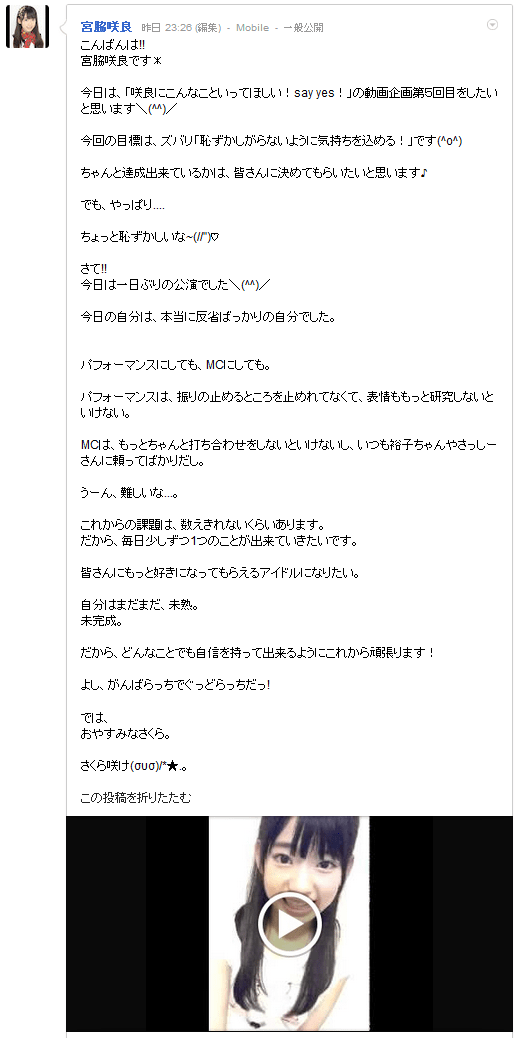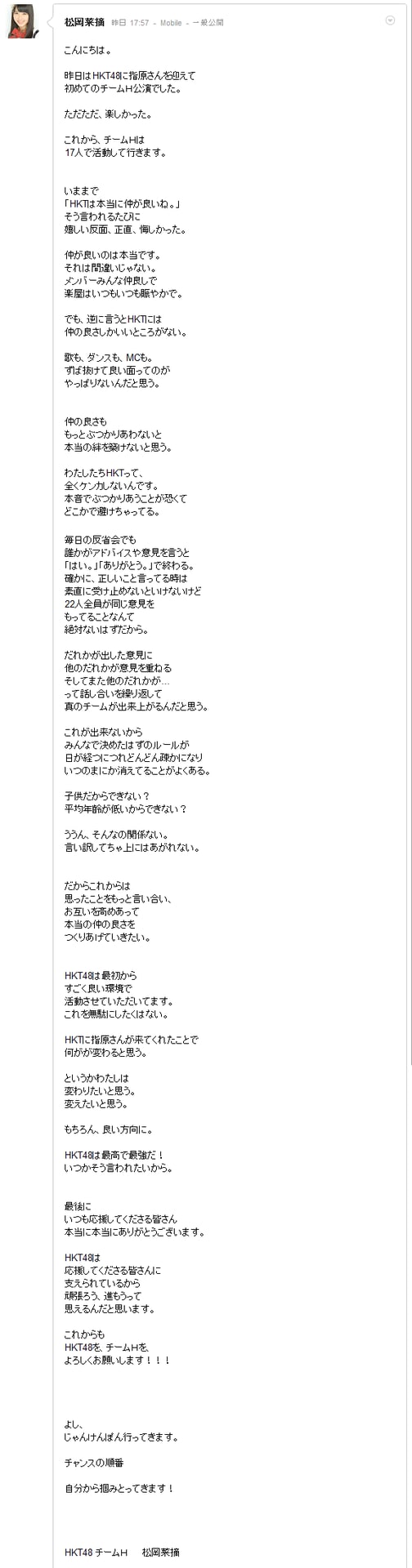広く読まれることに当Blogの価値があると思うので、前提知識なくても読めるVersionの文章も付け加えました。
チーム4について語りたいのだが・・今は我慢してこの話題を。
先に語るのにも、それなりに意味があると思う。
アンチに悩む人へ ~記憶に残る「幕の内弁当」はない~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/618ed3aee1b857694cbeb5370df658b3
↑の補足の
ググタスはコーヒーだ!
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/c42cdcc973803e5025345771e9de7bb6
↑の補足。
「
コアコンピタンス」という話題が出てきたので、関連でさらに補足したいと思います。
コアコンピタンスそのものの説明ではなく、関連する話です。
◆◆◆◆◆◆
戦略を考える上で
「コアコンピタンス(競争優位の源泉となる中核的な能力)」は非常に使いやすい概念です。
(軍事の方の戦略論ではストロング・ポイントと言ったりするそうです。)
組織の「強み」を表現するのに適した言葉だからです。
コアコンピタンスの概念を広めたのは↓でも紹介した
ゲイリー・ハメルの『コアコンピタンス経営』です。
経営の未来 ~未来を変えるための話をしよう~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/328d1744aabb082fb4f42d8b04296071
しかし、使いやすい言葉なだけに、様々な使われ方をすることになり、誤解を生みやすい言葉にもなりました。
もともとは、企業の中核的な能力を構成する有形/無形あわせた経営資源全体を指す概念だったのですが、単純に「強み」の意味で使われることが多くなったのです。
(細かい話だが、SWOT分析だけ使うと嵌りやすいとは思う。)
このことについて、
クレイトン・クリステンセンは
『イノベーションへの解』の中で警鐘を鳴らしています。
(不朽の名作『イノベーションのジレンマ』の次作が『イノベーションへの解』です)

日本の製造業メーカーと台湾EMSを思い浮かべながら、次の話題を読んでみてください。
■コア・コンピタンスとROA最大化のデス・スパイラル (コア・コンピタンス経営の罠)
コモディティ化の餌食となる企業は、すぐ下の階層のサブシステムまたは隣接するプロセスで、コモディティ化と同時に起こる、脱コモディティ化という補完的プロセスを見落とすことが多い。そのため彼らは、これから金が向かう場所に移動する機会を逸し、他社が脱コモディティ化の生み出した成長を捉えるうちに押しつぶされ、時には破滅に追い込まれることすらある。実際、総資産収益率(ROA:Retum on Asset)の改善を迫る投資家からの強く執拗な圧力は、組立て業者にとって、これから金が向かう場所から遠ざかる強い動機になる。そして、モジュール方式によるコモディティ化という状況を認識し損なった彼らは、属性に基づくコア・コンピタンス理論に救いを求め、のちに後悔することになる決定を下すのだ。
企業の株主はROA(どのくらい効率的に利益を上げることができているかを示す指標の一つ)を使って「もっと効率よく利益を上げろ!」と圧力をかけてくる。利益をうまく上げることができず悩む企業は「コアコンピタンス理論」に救いを求めるが、これが失敗の原因になることが多い。
モジュール型製品の組立企業は、総資産収益率(ROA)や使用総資本利益率(ROCE)の改善を求める投資家の要求に、どうすれば応えられるのだろうか。ROAの分子を改善することはできない。製品を差別化したり競争相手よりも低いコストで生産したりすることは、ほとんど不可能だからだ。唯一の選択肢は、資産を処分してROAの分母を圧縮することだ。これは統合が求められる相互依存的な世界では困難だが、製品アーキテクチャがモジュール型であるような状況では、実際、非統合化が促される。そこで、これから架空の部品供給業者とモジュール型パソコン組立企業とのやりとりを通して、これがどのように起こるかを説明してみよう。この2つの企業を、それぞれ、コンポーネンツ社とテキサス・コンピュータ社(TCC)と呼ぶ。
「ROA = (利益/総資産) 」なので、ROAを上げるためには「利益を上げる」か「総資産を減らす」かどちらかだ。競争の激しい状態で「利益を上げる」ことは難しいので、企業は「総資産を減らす」方を選択しがちである。では、総資産の減らし方について例を使って説明する。
コンポーネンツは手始めに、TCCに単純なサーキットボードを供給する。TCCがROA改善を迫る投資家からの圧力に苦しんでいると、コンポーネンツが興味深い提案を持ってやって来る。
「御社にはこれまでサーキットボードを提供させていただいてきましたが、コンピュータのマザーボード全体を納入させていただけませんか?社内で製造されるよりずっとお安いですよ?」
「おお、それは素晴らしいアイディアだ」とTCCの経営者は答える。
「サーキットボード製造業務はいずれにしてもうちのコア・コンピタンスではないし、きわめて資産集約的だからね。君たちに頼めれば、うちにとってはコスト削減になる上、バランスシートからあれだけの資産を取り除ける」
そこでコンポーネンツは、新たな付加価値活動を請け負う。同社の売り上げは急増し、製造試算の稼働率が高まったことから収益性も向上する。株価もそれに合わせて上昇する。一方、TCCがこれらの資産を処分しても、収入線は影響を受けないが、純利益と資産収益率は改善し、株価もそれ相応に上昇する。
製品のすべて(部品から最終製品まで)を自前で開発すると、どこかに非効率的な部分が入り込んでしまう。たいてい企業には得意な分野と、不得意な分野があるからだ。不得意な分野は他に任せて、自分は得意な分野に集中するのが合理的である。そうすることで、収益性(利益率)が改善し、株価も上がり、ROAは上昇する。
------ [ 余談 ] ----------------------------------
たいていこんな計算を頭の中でしているからだ。
(営業利益:企業の取り分の総数)
= G
= (売り上げ) - (コスト)
= P・Q - C
= P・Q - V・Q - F
= ( P - V )・Q - F
= CM・Q - F
P:価格、Q:販売数量、C:総コスト
V:変動費、F:固定費、
CM:販売1単位当たりの貢献利益
G = 0:損益分岐点 (BEP:Break Even Point)
営業利益を上げるための単純な方法は、売り上げを上げることだが、販売数量(Q)が伸びずに価格(P)が小さくなっているので、コスト(C)を下げないといけない。コストは変動費(V)と固定費(F)からなるので、基本的戦略は変動費を下げて貢献利益(CM:P-V)を大きくしつつ、固定費を下げることを考えることにになる。
しかし、この式で考えると、人の頭は次のように自然と脳内変換してしまう。
「"利益"を上げるには"売り上げ"を上げるか、"コスト"を下げるしかない。」
「"売り上げ"を上げる(下げない)ために、"価格"を上げるか、"数量"を伸ばすか、しかない。」
これはちょっと古い考え方で、今は「顧客価値」という観点で「WTP(Willingness to Pay)」を使う(べきだ)。
(顧客との取引によって創造される価値)
= Value
= ( 顧客価値:顧客の取り分 ) + ( 利益:企業の取り分 )
= ( 顧客の支払い意欲 - 価格 ) + ( 価格 - コスト )
= ( WTP - Price ) + ( Price -Cost )
= WTP - Cost
※Value >= 0
「Value」がマイナスになるということは、その取引に価値がないということなので、その取引自体が存在できない。
よって、Value がマイナスになる場合は、Valueが"0"に近づくよう力が働く。
式を見たら一目瞭然だが、
「利益を上げたければ、WTPを上げるか、Costを下げるか、またはどちらも」の3択しかない。
注目すべきは、
上げなければならないのは「WTP」であって「価格」ではない。
価格を上げるためには、WTPを上げないといけない。でないと左辺(WTP-Price)がマイナスになってしまうからだ。
参考:
川上 昌直『ビジネスモデルのグランドデザイン―顧客価値と利益の共創』

----------------------------------------
ほどなくしてコンポーネンツは、TCCの経営者に再び話を持ちかける。
「ご承知のように、マザーボードは実際、コンピュータの心臓部なんです。御社のためにコンピュータ全体を組み立てさせてください。製品組立業務はどのみち御社のコア・コンピタンスではないのですし、社内で組み立てられるよりずっとお安いですよ」
「ふむ、それは素晴らしいアイディアだ」とTCCの経営者は答える。
「どっちみち組立業務はわが社のコア・コンピタンスではないのだし、君たちが製品組立をやってくれれば、あれだけの製造資産をバランスシートから取り除ける」
コンポーネンツがまたもや新たな付加価値活動を請け負うと、売り上げは急増し、製造資産の稼働率が高まるために収益性も改善する。株価もそれ相応に上昇する。TCCは製造資産を排除しても、収入線は影響を被らない。だが、純利益と資産収益率は改善し、株価もそれに応じて上昇する。
しばらくしてコンポーネンツは、TCCの経営者に再び申し入れる。
「あのですね、わたしどもが御社のコンピュータを組立させていただいている以上、どうして御社が厄介な物流のインバウンド、アウトバウンド業務を処理される必要があるのでしょう?業者との交渉やお客様への完成品のお届けは、お任せください。サプライ・チェーンの管理はどのみち御社の本当のコア・コンピタンスではないんですから。それに御社が管理されるよりずっとお安くできますよ」
「うーむ、それはいい考えだ」TCCの経営者は答える。
「そうすればあれだけの流動資産をバランスシートから除ける」
コンポーネンツは新たな付加価値活動を請け負い、売り上げは急増する。また、ビジネスモデルに高付加価値活動を引き入れたために、収益性も改善する。一方、TCCは流動資産を処分しても収入線に影響を受けない。だが、収益性は改善し、株価ももうひと跳ねする。
しばらくするとコンポーネンツがTCCの経営者にまた話を持ってくる。
「えーとですね、御社のサプライヤーと取引させていただいていることですし、今度は御社のためにコンピュータの設計をやらせていただけませんか?モジュール化された製品の設計は、実際には業者の選定に毛の生えたようなものですし、わたしどもの方が御社よりも業者と密な関係がありますので、設計サイクルの最初から彼らと手を組めば、価格と納期についてよい条件を引き出せますよ」
「いやは、それはいい考えだ」とTCCの経営者は答える。
「そうすれば固定費と変動費まで削減できる。それにうちの本当の強みはブランドと顧客管理にあるのであって、製品設計ではないからね」
コンポーネンツがさらなる付加価値活動を請け負うと、売り上げはさらに増え、高付加価値活動をビジネスモデルに引き入れるために、収益性も改善する。株価もそれに応じて上昇する。一方TCCがコストを削減しても収入線は影響されない。だが収益性は改善し、そして株価もまたポンと跳ね上がる~
株主からの圧力に従ってROA(効率的に利益を上げる)を最大化しようとし、自社に「強み」の部分だけを残して「弱み」の部分を外に出すようにすることは合理的な行動であり、やればやるほど効果が出る。しかし・・
しかしそれも、アナリストがゲームが終わったことに気づくまでのことだ。
皮肉にもこの悲劇の中で、コンポーネンツは最終的に、悪循環が始まる前のTCCよりも高度に統合されたバリューチェーンを持つことになる。だが、バリューチェーンの各構成要素が再構成されているため、コンポーネンツは新しい競争基盤にうまく対処できる。この場合の競争基盤とは、製品化のスピードと、はるかに小さな市場分野の顧客向けに製品を機敏に構成する能力である。
TCCは資産やプロセスをコンポーネンツに押し付けるたびに、その決定を彼らの「コア・コンピタンス」という観点から正当化した。問題となっている業務が、コンポーネンツにとってもコア・コンピタンスではない、ということは、彼らの思いもよらないことだった。ある業務がコア・コンピタンスか否かといことは、これから金が向かう場所に滑走していく能力の決定要因ではないのである。
他社の「弱み」を引き受ける企業は、引き受ける際に、応用できる形で引き受けるために、他社の「弱み」を自社の「強み」に変換する形になる。一方は、コアコンピタンス理論に従って「強み」ではないものを外に出したわけだが、もう一方の引き受ける側にとっても、それは「強み」ではない。だが、引き受けた側は「弱み」を引き受けていき続ける中で、「弱み」を「強み」に変換することができる。「強み」「弱み」という基準だけで、判断すると、利益を上げる能力を掴み損ねる可能性が高い。
この話は、非対称的なモチベーションをよく表す例でもある。モジュール組立企業が手を引きたがっていた、まさにその付加価値活動を、部品供給業者は前方統合する意欲を持っていたのだ。
これは無能力を表す話ではない。収益最大化のための、完璧に合理的な決定に関する話なのだ。だからこそ、モジュール製品を「十分に良い」世界で組み立てる企業の多くが、ROA最大化のデス・スパイラルという罠にかかるのである。
「弱み」を吐き出す企業は「弱み」に対してモチベーションが低いが、「弱み」を引き受ける企業は「弱み」を引き受ける活動に対してモチベーションが高い。どちらかの能力が低いということではなく、お互いに合理的に行動した結果、こうなるという話だ。競争が激しく、製品そのものの差異化が難しい状況下でROAを最大化しようと合理的に行動すると、このような問題に遭遇しやすいのだ。
■デススパイラルにはまらないために
ROA最大化のデス・スパイラルはわかった。
では、我々はどう考えるべきなのか。クリステンセンはこう言う。
「コア・コンピタンスは、多くの経営者が用いる用法において、危険なまでに内向き思考の概念だ。競争力とは、単に得意だと自負する業務を行うことではなく、むしろ顧客が高く評価する業務を行うことから生まれる。」
そう、さきほども出てきた
「顧客価値」である。
自分が得意かどうかではなく、顧客価値の高いかどうかで判断することから競争力は生まれるという意味である。
(クリステンセン自身は「顧客価値」という言葉ではなく「用事」という言葉を使っているが、ここでは気にしないことにする。)
田野しいやつらが引き起こす創造的摩擦 ~イノベーションのジレンマを超えるバリュープロポジション~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/cfdd89f383a05dfda9d5ac8a934d4b7c
クレイトン・クリステンセンは、既存の枠組みの中でWTPを上げることは不可能に近く、ゆえにコストを下げるしかないが、その時、コアコンピタンスの名の下に「ROA最大化のデススパイラル」に嵌ることに注意すべきだと述べている。
■やすす先生が作詞をアウトソースしない理由
(前にも書いたことがある話題&一部メンバーに投げているのは知っています。)
なぜ忙しいのに、やすす先生は作詞活動を他の人に任せないのか?
第一義的には「作詞家」だからだと思う。
しかし、それとは別に「ROA最大化のデススパイラル」に嵌ったしまうことのリスクに感づいているからだ。
作詞は楽曲全体のコンセプトを決める作業でもあるため、作詞だけをモジュール化して水平分離することはできない。
まさにそれこそが「コアコンピタンス」だからだ。