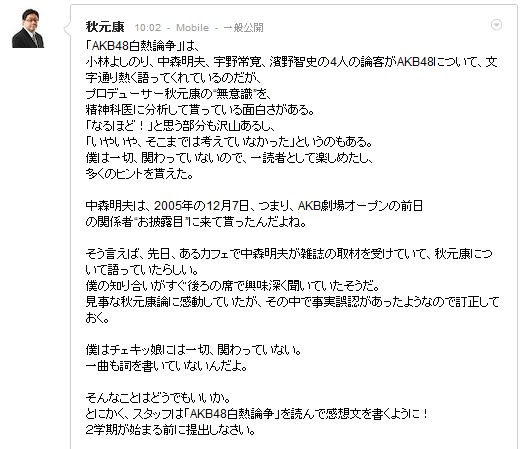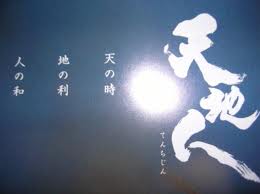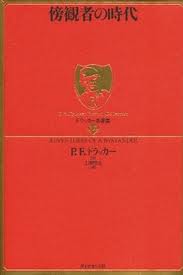語れと言われたので語ることにします。
またSKE48ファンの人々から怒られそうだけど、大事なことだから語ろうと思います。
人それぞれ目指すものは違うと思います。
ただ、私がここで主張したいのは、SKE48の大矢さんがいう「SKE48単独」での活躍の場を広げるためにどういうことを考えるべきかという話です。
まとめんばーのコメント欄を見ていたら、私の言いたいことの半分くらい説明してくれてる素晴らしいコメントがあったので、これを補足する形で私も少し語らせてもらいたい。
【G+まとめ】昇格を逃した松村香織の今夜も1コメダが切ない(AKB48まとめんばー)
http://akb48matome.com/archives/51839641.html

制限しないとどこまでもダラダラと語るのが癖なので、わかりやすくしますね。
私は、いま追いつめられているのはBBQではなく、SKE48運営だと思います。
どういうことか、端的に言い表します。
今のSKE48の「正規生」にどれだけの価値があるのか?
この問いに対して、SKE48運営はどういう回答を用意しているのでしょうか。
この価値を高めるために、SKE48としては、どういう努力をしていくのか。
今日よりも、明日のSKE48の「正規生」の価値が向上するために、どういう道へ進むべきなのかを、常日頃から考えなければなりません。
BBQ松村の昇格見送りの件で、様々な意見があるのは知っています。
それはそれで議論すればよいと思います。
しかし、私は本件を松村の話題で終わらせてはいけないと思います。
本件が投げかけている本質的な問題は、SKE48全体の問題だからです。
もう少しだけ踏み込んでみます。
SKE48がどういう道を進むかを考えるにあたって重要なことは、SKE48が何を善しとするかということです。
それは、つまりSKE48が組織として、どういう評価基準を持つことができるかという問題になります。
公演なのか、握手会なのか、選挙なのか、ダンスなのか、歌なのか、ググタスなのか、人気なのか、新しい何かなのか・・・
もし、SKE48がAKB48からの独立性を高めて、単独での評価を高めたいと考えるなら、新しい価値基準が必要になると私は思います。
まとめんばーから引用したコメントにあるように、公演パフォーマンスにこだわるのは結局「AKB48」との差異化を意識する結果ですから、単独での評価を高めたいのであれば、AKB48に引けを取らない独自性や競争優位を獲得する必要があります。
そのために、SKE48は、これまでにない価値基準を常に生み出していく成長エンジンを組織として獲得する必要があるということです。
以上を考慮に入れると、BBQ松村がどうあるべきかの前に、SKE48運営はBBQ松村の生み出している価値観を、SKE48のために活用することを考えるべきだし、そのための手を打つべきだったと思います。
たとえば、BBQ松村を研究生のまま留めておくとしても、何らかの役割をSKE48として公式に与えるなどが考えられました。
(それが、これまでにない価値基準を認めるということだからです)
SKE48独自のクロスファンクショナルな活動を立ち上げて、そのキャプテンに任命するなどです。
(たとえばのはなしで、考えればいろいろあると思います。)
(それと、松村を高評価し過ぎという意見があるようですが、これは松村の話ではなくSKE48の話です。)
(SKE48を変える必要はなく、このまま行けばいいのだという意見の人もいると思いますが、SKE48運営がそう考えているなら、もはや多くを望むべくもない組織として危機的な状況だと思いますね。私は。)
今回、ひょっとしたらSKE48運営は、機会費用ばかりを考えて機会損失を考えることが不足していたのかもしれません。
何かをした時に失うものを考えるのは容易ですが、何もしなかった時に失うものを考えるのはなかなか大変です。
しかし、後者の方が失うものが大きいことがあることを、よくよく考えてみるべきでしょう。
言うは易く、行うは難しいのはよく理解しているつもりですが。
本エントリをより深く理解するための基本的なエッセンスは過去に述べているので、それをまるごと引用しておきます。
-----------------------------------
なぜAKB48は予定調和を壊し続けることをモットーとするのか? ~多様性とイノベーション~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/a6c037c1f0413c59b507b4c0357c8227
よく使われる言葉「化学反応」とは何なのか?
これをいつもより真面目に(出来る限り)簡単に説明しよう。
参考文献として用いるのはこれだ。
『多様性とイノベーション 価値体系のマネジメントと組織のネットワークダイナミズム』
(デヴィット・スターク著、中野勉/中野真澄訳)

組織生態学が専門である社会学者デヴィット・スタークがイノベーションについて語ったもの。
イノベーション論や組織論にある程度の興味がないと読むのがつらい本だが、内容はさすがに世界屈指の社会学者らしい広範で深遠な洞察がそこかしこに散りばめられており、一読の価値はあると自信をもっておススメできる。
(当Blogの内容では物足りないと思っている方には是非読んで頂ければと思う。)
■検索(サーチ)とイノベーション
「検索(サーチ)」のテクノロジーは、我々の働き方だけではなく、買い物の仕方、社会の中での自分の位置づけなど、多くのものを変えてきたが、現代組織が抱える課題は検索では解決できない。
サーチのテクノロジーは、組織の知識管理上きわめて貴重だが、それが生み出す結果は今日の組織が直面する、より根本的な問題には答えてくれないのだ。
そのような根本的な問題を解決するためのサーチとは、あらかじめて特定されている物やカテゴリーを結びつけるサーチでもなければ、明確に定義された問題の解決方法を探すことでもない。
探している間は何を探しているかわからず、答えが見つかった時に初めてそれがわかるという類のサーチなのである。
そのようなプロセスと、単純なサーチを区別するために「リサーチ(Re-Search)」という用語がある。
(リサーチは「研究」と訳されることが多い。アメリカの哲学者ジョン・デューイは「探求(inquiry)」といった。)
また、リチャード・レスターとマイケル・ピオーリによる研究によれば、イノベーションの最も大切な要素は、きちんと定義された問題を解決する過程をとらないことだと結論づけた。
過去の事例を精査する限り、いずれのイノベーション事例も異種分野の結合を伴うことを明らかにしたのである。
「異分野の境界を横断した統合なしに、新製品が生まれることはない」のだ。
多くの産業においてイノベーションは、少なくとも初期においては特定の必要性や問題への対応として生まれてくるものではなく、製品が使われるようになってから問題が明らかになるものである。このような場合、製品開発者はしばしば何を創ろうとしているのかはっきりわからないまま着手していることが多い。
既にカテゴリー化されているものをパターンとして認識することと、新たな関連性を見出すことは全く別次元のことである。
未知なるものを認識する、つまりカテゴリーとして認知されていないものを認識する興味深い認知機能を含むイノベーション過程は、矛盾をはらんだものになるのだ。
このような過程については、「リサーチ」「イノベーション」「探求」「探索」と様々な表現方法があるが、それは単に情報をうまく管理することではなくて、何度もいろいろな思考を巡らせ解釈を通じて機能する「熟考型の認知(reflective cognition)」を必要とするサーチなのである。
ジョセフ・シュンペーターは、イノベーションとは組み換えなのであり、それは文化として、当然のことと思われていることや組織的な認知のルーティンを根底から破壊するものだと主張した。
(創造的破壊)
逆説的に言えば、「リサーチ」や「イノベーション」は「問題を抱えた複雑で耐え難い状況」によって必要性にかられて引き起こされるということだ。
つまり、複雑な状況が創発的な探求を生むのであれば、イノベーションを求める組織は、複雑な状況を避けるのではなく、受け入れることが必要だ。
もっと基本的なレベルでいえることは、何が重要かについての評価原理に関する相違がある時に、我々を困惑させる状況が生まれるのであるから、生産性の高い複雑な状況を模索するのであれば、ある一つの評価原理を組織が認める正統なフレームワークとして強制するのではなく、何が重要か、何に価値があるか、何を重視すべきかについて、別の考えをはっきり主張することが合理的であると気づくべきである。
序列化された指揮命令系統があり、モノを認知するカテゴリーに概念的な序列がある形態とは異なるガバナンスが必要だ。
イノベーションを喚起する状況を積極的に生み出す「熟考型の認知」が働くことを可能とする「認知環境」である。
■創造的摩擦
そうした組織に摩擦や軋轢が無いはずがない。
しかし、摩擦はどんな代償を払っても回避しなければならないものではない。
複数のパフォーマンス基準が、機知に富んだ不協和を創りだすことが重要である。
組織が置かれた環境が騒然としており、変化する状況の下で何が組織の資源になるかが不透明な場合、価値について論争する枠組みが、組織の貴重な財産になるのである。
不確実性を徹底的に活用する起業家精神に富む活動とは、個人の資質ではなく組織形態の機能のことであり、「複数の評価原理」が機能する状態を維持しつつ、生産性の高い摩擦から利益を享受する能力のことである。
(複数の評価原理を用いながら、その結果、相互作用によって生じる摩擦を徹底的に活用する能力ともいえる)
ここでの不確実性とは、経済学者フランク・ナイトによって定式化された「リスクと不確実性」のことである。
ナイトによれば、この2つはともに将来がわからないことによって生まれるが、リスクはある環境においてチャンスは計算可能、結果の分布は確率で表現できるとするが、不確実性は計算不能である。
不確実性の問題は、人間の計算能力の限界によるものではなく、予測できない状況によるもの、我々が知ることができない何かなのである。
どの価値基準が使われているのかよくわからない状況を徹底的に活用するために、所有する資産の多義性や意味の曖昧さが必要だ。
起業家は曖昧なものから資産を創り出す。
複数のパフォーマンス基準による競い合いが、多義的で意味の曖昧な資産を定義し直し、組み換え、再配置を促すのだ。
(複数の評価原理の曖昧さは、合意を形成するのではなく、結果が読めない状況をつくりだす。)
複数の価値観の作用を維持する組織では、創発力のある摩擦が育まれ、それが受け入れられるビジネスの分類を混乱させ、継続的な資源の組み換えが可能になるのだ。
■ブローカーモデルと創造的摩擦モデル
「創造的摩擦」は、どういうところで起きるのだろうか。
少なくとも「媒介」ではない。
「媒介」とは、ノードとノードが繋がっていないネットワーク構造上の穴、つまり自分が橋渡しをしなければ結びつかない自分以外の二者の間にある隙間(ギャップ)を、仲介者として戦略的に利用し、利益を得ることである。
媒介は、しばしば起業家精神に富む活動と取り違えられるが、両者の役割と社会的プロセスははっきりと異なる。
媒介者は「当事者」ではなく情報の流れに料金を課す者である。
一方、起業家とは、いくつものゲームの当事者であり、組み換えによって価値あるものを生み出す者である。
イノベーションの元となるアイディアは、集団の環境の中に漂いながら存在しているのではない。
アイディアは見つけてもらうのを待っているのではなく、意図的に創り出さなければならない。
情報へのアクセスではなく、新しい知識を創造することが求められいているのであれば、仲介による関係の橋渡しでは不十分である。
イノベーションには、互いに影響し合うようなやりとりをしながら相互に交流することが必要なのである。
ネットワーク分析の用語を用いれば、まとまりが強く凝集性の高いネットワーク構造の重複部分、つまり凝集性の高い結びつきとして定義された幾つもの異なるコミュニティが、それぞれの個性的な集団のアイデンティティを崩壊させることなく、メンバーが重なり合った部分でイノベーションは生まれるのである。
言葉で説明しても理解し難い部分だと思うので、図を添付する。

図の右「創造的摩擦モデル」の重複部分に注目してもらいたい。
たとえ同一組織内であっても、多様なパフォーマンス基準がぶつかり合い、競い合う。
ここではパフォーマンスを評価するために、複数のコード化された規則としての体系を抱えることになり、体系化された知識が壊され、再びコード化される可能性が高くなる。
遺伝学に模して、競い合う基準同士の摩擦が高いほど、突然変異が生じる確率が高まると考えてみればよい。
多様な評価のフレームワークによる不協和は、単に目新しいものを生み出すスピードを高めるだけではない。
いくつもの原理に基づいた立場が併存することは、自然な帰結として、どの立場も当たり前のものとして受け入れられなくなることを意味する。
創造的摩擦が、基準の多様性による様々な可能性について、柔軟な思考をめぐらす状況を組織として作り出すのである。
組織としてイノベーションを育むために有効なのは、情報の円滑な伝達や固定化されたアイデンティティの確認を通じてではなく、生産的な摩擦を育み、組織的に当然と思われてきたことを混乱させ、新しい知識を生み出し、経営資源の定義の見直し、再配置、組み換えを可能にすることを通じてであることがわかるだろう。
思慮の浅い組織への固定化を阻止することが可能となるかは、変化し続ける状況において、基準や原理の曖昧さや多義性、深く再帰的に思考をめぐらせる「再帰的認知」能力を備えるかどうかが非常に重要なのだ。
(あまり長くなっても読みにくくなるので、ここで切り上げます。)
◆◆◆◆◆◆
■参考
本エントリは、松井珠理奈と渡辺美優紀の兼務問題について語っているわけではありませんが、適応できる話だとは思います。
過去のエントリにリンクをはっておきます。
本当のところ、松井珠理奈に限界を与えているのは誰なのか?
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/c6f70e7179b2ba0c3ecad170f021c492
松井珠理奈がチームK、渡辺美優紀がチームBを兼任へ ~AKB48の成長戦略~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/45c9b642fd1b6d0f5b97244ed0fee051
松井珠理奈と渡辺美優紀はなぜ「移籍」ではなく「兼務」なのか 説明しよう ~分化と統合の物語~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/9366d66554175d8acae2c098f7cd4fb3
やすす先生! 鬼になれ! そして前へ進み、河を渡るのです!
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/e757f5634174d9975a4874bed4b2e24e
サプライズ手法に対する疑問に回答します(1) ~直接的な情報発信~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/2b073e5db2ac14c7c2f3d4756030801e
サプライズ手法に対する疑問に回答します(2) ~「マクロ vs. ミクロ」の構図~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/fb8016295797abd4e6befdce2b362718
サプライズ手法に対する疑問に回答します(3) ~采配~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/825893f0f01429761f0656144c1061a3
サプライズ手法に対する疑問に回答します(4) ~顧客と共に成長する関係~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/be0378157c58eb812530701d02da5d32
またSKE48ファンの人々から怒られそうだけど、大事なことだから語ろうと思います。
人それぞれ目指すものは違うと思います。
ただ、私がここで主張したいのは、SKE48の大矢さんがいう「SKE48単独」での活躍の場を広げるためにどういうことを考えるべきかという話です。
まとめんばーのコメント欄を見ていたら、私の言いたいことの半分くらい説明してくれてる素晴らしいコメントがあったので、これを補足する形で私も少し語らせてもらいたい。
【G+まとめ】昇格を逃した松村香織の今夜も1コメダが切ない(AKB48まとめんばー)
http://akb48matome.com/archives/51839641.html

制限しないとどこまでもダラダラと語るのが癖なので、わかりやすくしますね。
私は、いま追いつめられているのはBBQではなく、SKE48運営だと思います。
どういうことか、端的に言い表します。
今のSKE48の「正規生」にどれだけの価値があるのか?
この問いに対して、SKE48運営はどういう回答を用意しているのでしょうか。
この価値を高めるために、SKE48としては、どういう努力をしていくのか。
今日よりも、明日のSKE48の「正規生」の価値が向上するために、どういう道へ進むべきなのかを、常日頃から考えなければなりません。
BBQ松村の昇格見送りの件で、様々な意見があるのは知っています。
それはそれで議論すればよいと思います。
しかし、私は本件を松村の話題で終わらせてはいけないと思います。
本件が投げかけている本質的な問題は、SKE48全体の問題だからです。
もう少しだけ踏み込んでみます。
SKE48がどういう道を進むかを考えるにあたって重要なことは、SKE48が何を善しとするかということです。
それは、つまりSKE48が組織として、どういう評価基準を持つことができるかという問題になります。
公演なのか、握手会なのか、選挙なのか、ダンスなのか、歌なのか、ググタスなのか、人気なのか、新しい何かなのか・・・
もし、SKE48がAKB48からの独立性を高めて、単独での評価を高めたいと考えるなら、新しい価値基準が必要になると私は思います。
まとめんばーから引用したコメントにあるように、公演パフォーマンスにこだわるのは結局「AKB48」との差異化を意識する結果ですから、単独での評価を高めたいのであれば、AKB48に引けを取らない独自性や競争優位を獲得する必要があります。
そのために、SKE48は、これまでにない価値基準を常に生み出していく成長エンジンを組織として獲得する必要があるということです。
以上を考慮に入れると、BBQ松村がどうあるべきかの前に、SKE48運営はBBQ松村の生み出している価値観を、SKE48のために活用することを考えるべきだし、そのための手を打つべきだったと思います。
たとえば、BBQ松村を研究生のまま留めておくとしても、何らかの役割をSKE48として公式に与えるなどが考えられました。
(それが、これまでにない価値基準を認めるということだからです)
SKE48独自のクロスファンクショナルな活動を立ち上げて、そのキャプテンに任命するなどです。
(たとえばのはなしで、考えればいろいろあると思います。)
(それと、松村を高評価し過ぎという意見があるようですが、これは松村の話ではなくSKE48の話です。)
(SKE48を変える必要はなく、このまま行けばいいのだという意見の人もいると思いますが、SKE48運営がそう考えているなら、もはや多くを望むべくもない組織として危機的な状況だと思いますね。私は。)
今回、ひょっとしたらSKE48運営は、機会費用ばかりを考えて機会損失を考えることが不足していたのかもしれません。
何かをした時に失うものを考えるのは容易ですが、何もしなかった時に失うものを考えるのはなかなか大変です。
しかし、後者の方が失うものが大きいことがあることを、よくよく考えてみるべきでしょう。
言うは易く、行うは難しいのはよく理解しているつもりですが。
本エントリをより深く理解するための基本的なエッセンスは過去に述べているので、それをまるごと引用しておきます。
-----------------------------------
なぜAKB48は予定調和を壊し続けることをモットーとするのか? ~多様性とイノベーション~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/a6c037c1f0413c59b507b4c0357c8227
よく使われる言葉「化学反応」とは何なのか?
これをいつもより真面目に(出来る限り)簡単に説明しよう。
参考文献として用いるのはこれだ。
『多様性とイノベーション 価値体系のマネジメントと組織のネットワークダイナミズム』
(デヴィット・スターク著、中野勉/中野真澄訳)

組織生態学が専門である社会学者デヴィット・スタークがイノベーションについて語ったもの。
イノベーション論や組織論にある程度の興味がないと読むのがつらい本だが、内容はさすがに世界屈指の社会学者らしい広範で深遠な洞察がそこかしこに散りばめられており、一読の価値はあると自信をもっておススメできる。
(当Blogの内容では物足りないと思っている方には是非読んで頂ければと思う。)
■検索(サーチ)とイノベーション
「検索(サーチ)」のテクノロジーは、我々の働き方だけではなく、買い物の仕方、社会の中での自分の位置づけなど、多くのものを変えてきたが、現代組織が抱える課題は検索では解決できない。
サーチのテクノロジーは、組織の知識管理上きわめて貴重だが、それが生み出す結果は今日の組織が直面する、より根本的な問題には答えてくれないのだ。
そのような根本的な問題を解決するためのサーチとは、あらかじめて特定されている物やカテゴリーを結びつけるサーチでもなければ、明確に定義された問題の解決方法を探すことでもない。
探している間は何を探しているかわからず、答えが見つかった時に初めてそれがわかるという類のサーチなのである。
そのようなプロセスと、単純なサーチを区別するために「リサーチ(Re-Search)」という用語がある。
(リサーチは「研究」と訳されることが多い。アメリカの哲学者ジョン・デューイは「探求(inquiry)」といった。)
また、リチャード・レスターとマイケル・ピオーリによる研究によれば、イノベーションの最も大切な要素は、きちんと定義された問題を解決する過程をとらないことだと結論づけた。
過去の事例を精査する限り、いずれのイノベーション事例も異種分野の結合を伴うことを明らかにしたのである。
「異分野の境界を横断した統合なしに、新製品が生まれることはない」のだ。
多くの産業においてイノベーションは、少なくとも初期においては特定の必要性や問題への対応として生まれてくるものではなく、製品が使われるようになってから問題が明らかになるものである。このような場合、製品開発者はしばしば何を創ろうとしているのかはっきりわからないまま着手していることが多い。
既にカテゴリー化されているものをパターンとして認識することと、新たな関連性を見出すことは全く別次元のことである。
未知なるものを認識する、つまりカテゴリーとして認知されていないものを認識する興味深い認知機能を含むイノベーション過程は、矛盾をはらんだものになるのだ。
このような過程については、「リサーチ」「イノベーション」「探求」「探索」と様々な表現方法があるが、それは単に情報をうまく管理することではなくて、何度もいろいろな思考を巡らせ解釈を通じて機能する「熟考型の認知(reflective cognition)」を必要とするサーチなのである。
ジョセフ・シュンペーターは、イノベーションとは組み換えなのであり、それは文化として、当然のことと思われていることや組織的な認知のルーティンを根底から破壊するものだと主張した。
(創造的破壊)
逆説的に言えば、「リサーチ」や「イノベーション」は「問題を抱えた複雑で耐え難い状況」によって必要性にかられて引き起こされるということだ。
つまり、複雑な状況が創発的な探求を生むのであれば、イノベーションを求める組織は、複雑な状況を避けるのではなく、受け入れることが必要だ。
もっと基本的なレベルでいえることは、何が重要かについての評価原理に関する相違がある時に、我々を困惑させる状況が生まれるのであるから、生産性の高い複雑な状況を模索するのであれば、ある一つの評価原理を組織が認める正統なフレームワークとして強制するのではなく、何が重要か、何に価値があるか、何を重視すべきかについて、別の考えをはっきり主張することが合理的であると気づくべきである。
序列化された指揮命令系統があり、モノを認知するカテゴリーに概念的な序列がある形態とは異なるガバナンスが必要だ。
イノベーションを喚起する状況を積極的に生み出す「熟考型の認知」が働くことを可能とする「認知環境」である。
■創造的摩擦
そうした組織に摩擦や軋轢が無いはずがない。
しかし、摩擦はどんな代償を払っても回避しなければならないものではない。
複数のパフォーマンス基準が、機知に富んだ不協和を創りだすことが重要である。
組織が置かれた環境が騒然としており、変化する状況の下で何が組織の資源になるかが不透明な場合、価値について論争する枠組みが、組織の貴重な財産になるのである。
不確実性を徹底的に活用する起業家精神に富む活動とは、個人の資質ではなく組織形態の機能のことであり、「複数の評価原理」が機能する状態を維持しつつ、生産性の高い摩擦から利益を享受する能力のことである。
(複数の評価原理を用いながら、その結果、相互作用によって生じる摩擦を徹底的に活用する能力ともいえる)
ここでの不確実性とは、経済学者フランク・ナイトによって定式化された「リスクと不確実性」のことである。
ナイトによれば、この2つはともに将来がわからないことによって生まれるが、リスクはある環境においてチャンスは計算可能、結果の分布は確率で表現できるとするが、不確実性は計算不能である。
不確実性の問題は、人間の計算能力の限界によるものではなく、予測できない状況によるもの、我々が知ることができない何かなのである。
どの価値基準が使われているのかよくわからない状況を徹底的に活用するために、所有する資産の多義性や意味の曖昧さが必要だ。
起業家は曖昧なものから資産を創り出す。
複数のパフォーマンス基準による競い合いが、多義的で意味の曖昧な資産を定義し直し、組み換え、再配置を促すのだ。
(複数の評価原理の曖昧さは、合意を形成するのではなく、結果が読めない状況をつくりだす。)
複数の価値観の作用を維持する組織では、創発力のある摩擦が育まれ、それが受け入れられるビジネスの分類を混乱させ、継続的な資源の組み換えが可能になるのだ。
■ブローカーモデルと創造的摩擦モデル
「創造的摩擦」は、どういうところで起きるのだろうか。
少なくとも「媒介」ではない。
「媒介」とは、ノードとノードが繋がっていないネットワーク構造上の穴、つまり自分が橋渡しをしなければ結びつかない自分以外の二者の間にある隙間(ギャップ)を、仲介者として戦略的に利用し、利益を得ることである。
媒介は、しばしば起業家精神に富む活動と取り違えられるが、両者の役割と社会的プロセスははっきりと異なる。
媒介者は「当事者」ではなく情報の流れに料金を課す者である。
一方、起業家とは、いくつものゲームの当事者であり、組み換えによって価値あるものを生み出す者である。
イノベーションの元となるアイディアは、集団の環境の中に漂いながら存在しているのではない。
アイディアは見つけてもらうのを待っているのではなく、意図的に創り出さなければならない。
情報へのアクセスではなく、新しい知識を創造することが求められいているのであれば、仲介による関係の橋渡しでは不十分である。
イノベーションには、互いに影響し合うようなやりとりをしながら相互に交流することが必要なのである。
ネットワーク分析の用語を用いれば、まとまりが強く凝集性の高いネットワーク構造の重複部分、つまり凝集性の高い結びつきとして定義された幾つもの異なるコミュニティが、それぞれの個性的な集団のアイデンティティを崩壊させることなく、メンバーが重なり合った部分でイノベーションは生まれるのである。
言葉で説明しても理解し難い部分だと思うので、図を添付する。

図の右「創造的摩擦モデル」の重複部分に注目してもらいたい。
たとえ同一組織内であっても、多様なパフォーマンス基準がぶつかり合い、競い合う。
ここではパフォーマンスを評価するために、複数のコード化された規則としての体系を抱えることになり、体系化された知識が壊され、再びコード化される可能性が高くなる。
遺伝学に模して、競い合う基準同士の摩擦が高いほど、突然変異が生じる確率が高まると考えてみればよい。
多様な評価のフレームワークによる不協和は、単に目新しいものを生み出すスピードを高めるだけではない。
いくつもの原理に基づいた立場が併存することは、自然な帰結として、どの立場も当たり前のものとして受け入れられなくなることを意味する。
創造的摩擦が、基準の多様性による様々な可能性について、柔軟な思考をめぐらす状況を組織として作り出すのである。
組織としてイノベーションを育むために有効なのは、情報の円滑な伝達や固定化されたアイデンティティの確認を通じてではなく、生産的な摩擦を育み、組織的に当然と思われてきたことを混乱させ、新しい知識を生み出し、経営資源の定義の見直し、再配置、組み換えを可能にすることを通じてであることがわかるだろう。
思慮の浅い組織への固定化を阻止することが可能となるかは、変化し続ける状況において、基準や原理の曖昧さや多義性、深く再帰的に思考をめぐらせる「再帰的認知」能力を備えるかどうかが非常に重要なのだ。
(あまり長くなっても読みにくくなるので、ここで切り上げます。)
◆◆◆◆◆◆
■参考
本エントリは、松井珠理奈と渡辺美優紀の兼務問題について語っているわけではありませんが、適応できる話だとは思います。
過去のエントリにリンクをはっておきます。
本当のところ、松井珠理奈に限界を与えているのは誰なのか?
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/c6f70e7179b2ba0c3ecad170f021c492
松井珠理奈がチームK、渡辺美優紀がチームBを兼任へ ~AKB48の成長戦略~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/45c9b642fd1b6d0f5b97244ed0fee051
松井珠理奈と渡辺美優紀はなぜ「移籍」ではなく「兼務」なのか 説明しよう ~分化と統合の物語~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/9366d66554175d8acae2c098f7cd4fb3
やすす先生! 鬼になれ! そして前へ進み、河を渡るのです!
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/e757f5634174d9975a4874bed4b2e24e
サプライズ手法に対する疑問に回答します(1) ~直接的な情報発信~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/2b073e5db2ac14c7c2f3d4756030801e
サプライズ手法に対する疑問に回答します(2) ~「マクロ vs. ミクロ」の構図~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/fb8016295797abd4e6befdce2b362718
サプライズ手法に対する疑問に回答します(3) ~采配~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/825893f0f01429761f0656144c1061a3
サプライズ手法に対する疑問に回答します(4) ~顧客と共に成長する関係~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/be0378157c58eb812530701d02da5d32