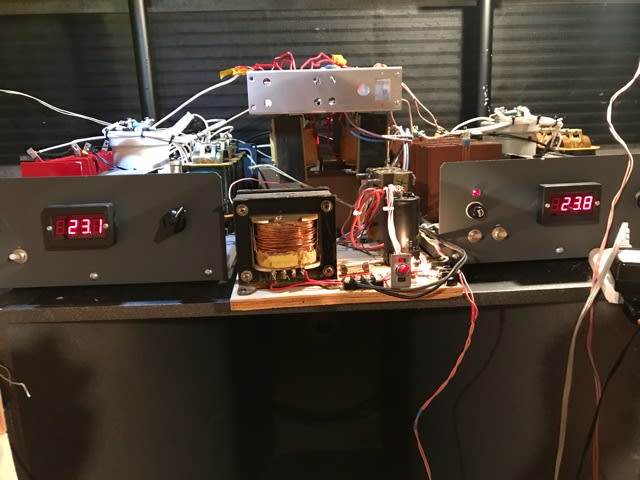先日のブログでM3Dはクラシックに合わない!
と、
軽々しく言ってしまい申し訳ありませんでした
ろくに試していなかったので、今回いろいろ聴き比べやってみました
選んだのはMoNoのレコードで
カラヤンの魔笛、1950年の録音のほうです
これはMoNoでありながら録音は最高音質、演奏も素晴らしいです
しかもセリフ抜きで、序曲、アリアのいいとこ取りの一枚、
この大好きなレコードの1面片面を聞き比べてみました
最初はガラード301に取り付けた3本のアームから

SPU-AE アームはオルトフォンRF297、昇圧トランスはJs6600
この組み合わせが標準となるだろう
ちょっと渋めの重厚な低音に支えられた、派手さの無い音
まさに標準とする音だと思う
ちょっと高域が暴れて聞きにくく、潰れて煩いと感じるいところがあるが
モノレコードだから仕方ないかな?
美味しいかどうかと聞かれれば、普通〜〜
お次はRS212に取り付けられたモノカートリッジ、CG25D+WE 618Bの600Ω受け

あっ、
ぜんぜん世界が違う、これは素晴らしい
先ほどAEでは煩いと感じたところが全くうるさくない、
艶やかに煌びやかに、バイオリンが鳴り響く
えー!、
こんないちがったけっけ?音の艶が全く違う、力が全く違う
MONOレコードをmonoカートリッジだから相性がいいのは当たり前なのか
力があるから音の張り出し方、
細いニアンスまで潰れないでハッキリ奏でている
アリアの歌声も生々しさたっぷりに飛び出して響く、軽やかに華やかに、これはいい!
素材の良さを最大限に引き出した、
旬の素材を最高の手法で料理した、最高に美味しい料理です
でもこの華やかさは、もしかしたらWE618B?のせい

普通の料理のSPUも 618Bなら華やかになるかな?と
もう一度SPU‐AEでトランスを618Bに変えてみる、入力は30Ωで
あっやっぱり派手だ、でも高域の暴れはさっきと同じだが、潰れは少ないかな?
艶やかなSPUサウンドになったが・・・、
立体感や奥行感はCG25Dには全くかなわない、そこはMONO同士が一番相性がいいかな?
CG25Dを聞いた後なので、正直いい音だとは思うが、
やはり比べると面白くない、普通の料理
やはりMONOレコードは、SPUではダメだと思うが一応SPU-GTも聞いてみる

SPU-GTは我が家では一番高額なアームRMG‐309に取り付けてある
あれ?以外にいい、
バランスがいいというか
音楽的にいいと言ったらいいのかな?これはこれで不満がない
角の立たない料理で、目立たないが美味しかった
ここまではクラシックは鳴るのが当たり前の組み合わせ
お次は問題の組み合わせに入る、18インチ大型ターンテーブルが盛大に鳴く

マイクロトラックに取り付けられた二つのアーム
まずはグレースのロングアームに取り付けてあるシュアーM3D
やっぱりあわない~
何と言ったらいいか幻想的とか、わびさびなんて全くないあっけらか〜〜んの世界
奥行とか臨場感とか、謙虚さの欠片もなく
グイグイずいずいと前に遠慮なく押し出してくる
明も暗も無い、全て明るい
オーディオ的に聞いてると、これはこれでありかな〜?と、思えば
・・・思えるのかな〜〜
まあ、聴き方によっては、SPU-AE+JS6600の組み合わせより、
明るく楽しい?
いや、
楽しいという表現が正しいかどうかは分からないが・・・・、
これがフィガロだったらM3Dもありかもしれない、という楽しさというか・・・、
魔笛だからあまり楽しい演奏って・・・
夜の女王のアリアもなかなか明るく元気で良かった・・・・、?
やはり調味料とが素材を生かしていない料理だと思います
お次はRCAのSP用の超ロングアームに無理やり取り付けた、バリレラ

これは音が凄い!
オーディオ的に凄い!
迫力満点の演奏、若いカラヤンの力強演奏がよく伝わって来る
CG25Dに比べるとこちらのほうが味付けがチョー濃い、厚い
☆注、当たり前だが、音楽的に声の張りや音の緊張感、音楽としてのバランスはCG25Dの方がだんぜん上です
あくまでオーディオ的に悪くないとういか、これはこれで聞いてて楽しいが・・・、
が、とても疲れる、音が重い〜〜
胃が重くなり、胃もたれしそうな料理です
夜の女王も、官能的とか美声とかそんな表現はできない、
ただ力強く歌っているとしか言えない
これもほかのレコードであれば、
いいかもしれないが、このレコードはちょっと違う?気がします
最後はトーレンスTD150に、SME3009S2で取り付けた、デッカV

いやーホッとするね〜〜
クラシックは、
魔笛は、こうでなくちゃね〜〜
バリレラで沸騰していた部屋の空気が、す〜と冷めて、正常な温度になってきた
ちょっと冷やかな空気の中、重々しく緊張感のある演奏が鳴り響きました
楽器と楽器の間の無音の静寂もいいですねー
音がいいとか悪いだけじゃない、
楽しい、が、楽しの質が違う、音楽を聞く歓びというか
魔笛の重厚な序曲、夜の女王のアリアも声が滲まず、派手にもならない
デッカのレコードのような、相性のピントの良さは感じませんが
この魔笛らしさは十分楽しめる演奏
結局、今回このレコード聴き比べでは新しい発見には至りませんでした
どれを選ぶと言われれば、迷わずオルトフォンCG25Dモノラルカートリッジ+WE 618B–600Ω受け
デッカ、SPU–GT
・・・、
Monoレコードをstereoカートリッジで掛けたのでは、
曲は痩せてしまい、音潰れもおきてしまうようで、当然ですがモノカートリッジが相性が良いですね
アメリカンカートリッジとアメリカンターンテーブルの組み合わせをためしてみましたが
オーディオ的におもしろいと書きましたが、この魔笛レコードをもう一度聞きたいとは、今は思えません
レコードと入力装置の組み合わせ、好みの問題もあると思いますが
曲のジャンルや、音楽的な音の傾向?、個人的な概念かもしれませんが、
そのレコードの持っている演奏の雰囲気を壊してはいけないと思います
年代、ジャンル、雰囲気そんなものを大切にしながら
新しい、おいしい組み合わせをこれからも探して行こうと思います