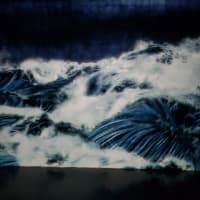音楽療法について話を聞く機会がありました。
患者さんに合わせて計画をたてて、音楽を使って持てる機能を伸ばしていく。病気の程度や好みの音楽的傾向、苦手な音、子どもさんだったら保護者の要望をとりいれて実施する。
楽器を演奏することで、手を動かすことが目的の場合もあるし、じっと座っておくことが難しいので、出来るだけ長く座れるようになることが目的の場合もあるそうです。
理学療法士や看護師と協力しながら音楽療法をするそうです。
計画たてて、目標を設定し期間を区切って評価する。看護と似たようなステップを踏むんだなと感じた。
お話し頂いた例では、最後に演奏会を
開かれたということで、タイミングをはかりながら楽器に触れて音を出すことが出来てとても感動されたそうです。
ほとんど体を動かせない患者さんの為にいろんな楽器が開発されていて、シンセサイザーのように音色が自由に選べて、タッチパネルに触れるだけで音が出る楽器がありました。大きさもかさばらなくて、枕元にも置けちゃいます。
お話し頂いた方は、子どもを対象に働いておられる方で、その子の持ってる力を出来るだけ活かしたいという思いがすごく伝わってきました。すごく素敵な人でした。人間的魅力に溢れてる。
他に印象に残ったのは、患者さんを主体としているというかとても尊重しているということを話の中で感じました。そんなの当たり前といってしまえば当たり前だけど、それぞれの患者さんのコミュニケーションのレベルに寄り添って意思疏通したり、あくまでも患者さんのペースを尊重する。
普段の生活では、自分を優先したり、相手のペースが遅ければ急かしたり自分でやってしまったりすることがある。逆に追いつけないくらい早いと諦めて自分のペースでいったり。
相手を主体とし、
相手のペースに合わせるって慣れてないと難しいと思う。相手が出来るまで待ったり、出来るように手助けしたり、自分でやったら早いけどそれをしないで待つ。
スリッパの話を思い出しました。リハビリ中の患者さんがいたとして、時間はかかるけど、自分でスリッパを履ける患者さんに自分が親切心からスリッパを履かせてあげればすぐに履けるけど、それは看護なの?という話。何でも良かれと思ってこちらがしていては、患者さんの回復を遅らせたり阻害する。常々、出来ることは患者さんにしてもらいましょう。患者さんの協力を得ましょうということを授業で聞く。
一人で出来ることではない(相手が必ず存在する)し、音楽を間に置きながら心を通わせてしているんだなと思いました。
音楽療法士は国家資格ではないらしく、資格を得るためには、大学などで学んだり、講習会に通って試験を受けるそうです。2年くらいはかかるみたいで、なかなかとりにくい資格だなと感じました。ピアノの実技試験もあり、それはそんなに高いレベルは求められてないそうです。
人数も外国に比べたら少ないらしい。
音楽を通して、出来るっていうことや楽しいってことを感じてもらいながらリハビリ的な効果で機能を維持したり、伸ばしたり出来るのは素晴らしいことなんだなと感じました。
音楽療法の認知度はそんなに高くないと思うので、もっとたくさんの人に知ってほしいです。
患者さんに合わせて計画をたてて、音楽を使って持てる機能を伸ばしていく。病気の程度や好みの音楽的傾向、苦手な音、子どもさんだったら保護者の要望をとりいれて実施する。
楽器を演奏することで、手を動かすことが目的の場合もあるし、じっと座っておくことが難しいので、出来るだけ長く座れるようになることが目的の場合もあるそうです。
理学療法士や看護師と協力しながら音楽療法をするそうです。
計画たてて、目標を設定し期間を区切って評価する。看護と似たようなステップを踏むんだなと感じた。
お話し頂いた例では、最後に演奏会を
開かれたということで、タイミングをはかりながら楽器に触れて音を出すことが出来てとても感動されたそうです。
ほとんど体を動かせない患者さんの為にいろんな楽器が開発されていて、シンセサイザーのように音色が自由に選べて、タッチパネルに触れるだけで音が出る楽器がありました。大きさもかさばらなくて、枕元にも置けちゃいます。
お話し頂いた方は、子どもを対象に働いておられる方で、その子の持ってる力を出来るだけ活かしたいという思いがすごく伝わってきました。すごく素敵な人でした。人間的魅力に溢れてる。
他に印象に残ったのは、患者さんを主体としているというかとても尊重しているということを話の中で感じました。そんなの当たり前といってしまえば当たり前だけど、それぞれの患者さんのコミュニケーションのレベルに寄り添って意思疏通したり、あくまでも患者さんのペースを尊重する。
普段の生活では、自分を優先したり、相手のペースが遅ければ急かしたり自分でやってしまったりすることがある。逆に追いつけないくらい早いと諦めて自分のペースでいったり。
相手を主体とし、
相手のペースに合わせるって慣れてないと難しいと思う。相手が出来るまで待ったり、出来るように手助けしたり、自分でやったら早いけどそれをしないで待つ。
スリッパの話を思い出しました。リハビリ中の患者さんがいたとして、時間はかかるけど、自分でスリッパを履ける患者さんに自分が親切心からスリッパを履かせてあげればすぐに履けるけど、それは看護なの?という話。何でも良かれと思ってこちらがしていては、患者さんの回復を遅らせたり阻害する。常々、出来ることは患者さんにしてもらいましょう。患者さんの協力を得ましょうということを授業で聞く。
一人で出来ることではない(相手が必ず存在する)し、音楽を間に置きながら心を通わせてしているんだなと思いました。
音楽療法士は国家資格ではないらしく、資格を得るためには、大学などで学んだり、講習会に通って試験を受けるそうです。2年くらいはかかるみたいで、なかなかとりにくい資格だなと感じました。ピアノの実技試験もあり、それはそんなに高いレベルは求められてないそうです。
人数も外国に比べたら少ないらしい。
音楽を通して、出来るっていうことや楽しいってことを感じてもらいながらリハビリ的な効果で機能を維持したり、伸ばしたり出来るのは素晴らしいことなんだなと感じました。
音楽療法の認知度はそんなに高くないと思うので、もっとたくさんの人に知ってほしいです。