夫のギムナジウム時代のクラス会がメルヘン街道にある町ハン・ミュンデンで開かれました。
メルヘン街道はグリム兄弟の生地ハーナウからブレーメンの音楽隊の港町ブレーメンまでの600KMの長い街道です。
街道沿いには「ハーメルンの笛吹き男」で有名な町ハーメルンなどがありますが、今回訪れた町ハン・ミュンデンはそれほど有名ではありません。
でも木組みの家が建ち並ぶ美しい町です。


ここは「ドクター・アイゼンバート(鉄ひげ医者)」の町としても知られています。
このお医者さんは目立ちたがり屋でドイツ各地の広場で群衆の前で派手な治療をしたり、
東部ドイツのマグデブルクの町では(怪しい?)薬を製造したりしていたらしいです。
ハン・ミュンデンには彼のお墓があり、市庁舎のホールにはペンチで歯を抜く「荒療治」のアイゼンバート先生の像なども置かれています。


ハン・ミュンデンの帰りにはグリム童話の「いばら姫」の舞台になったザバブルク城と「ラプンツェル」のトレンデルブルク城を訪れました。
どちらも古城ホテルになっていて日本からも宿泊客がやってくるそうです。


その日は冷たい雨が降る「花冷え」でしたが、小雨の中、名もない小さな古い塔なども見かけ、やはり「メルヘン街道」は幻想的だなぁと思ったことでした。

メルヘン街道はグリム兄弟の生地ハーナウからブレーメンの音楽隊の港町ブレーメンまでの600KMの長い街道です。
街道沿いには「ハーメルンの笛吹き男」で有名な町ハーメルンなどがありますが、今回訪れた町ハン・ミュンデンはそれほど有名ではありません。
でも木組みの家が建ち並ぶ美しい町です。


ここは「ドクター・アイゼンバート(鉄ひげ医者)」の町としても知られています。
このお医者さんは目立ちたがり屋でドイツ各地の広場で群衆の前で派手な治療をしたり、
東部ドイツのマグデブルクの町では(怪しい?)薬を製造したりしていたらしいです。
ハン・ミュンデンには彼のお墓があり、市庁舎のホールにはペンチで歯を抜く「荒療治」のアイゼンバート先生の像なども置かれています。


ハン・ミュンデンの帰りにはグリム童話の「いばら姫」の舞台になったザバブルク城と「ラプンツェル」のトレンデルブルク城を訪れました。
どちらも古城ホテルになっていて日本からも宿泊客がやってくるそうです。


その日は冷たい雨が降る「花冷え」でしたが、小雨の中、名もない小さな古い塔なども見かけ、やはり「メルヘン街道」は幻想的だなぁと思ったことでした。













 。
。

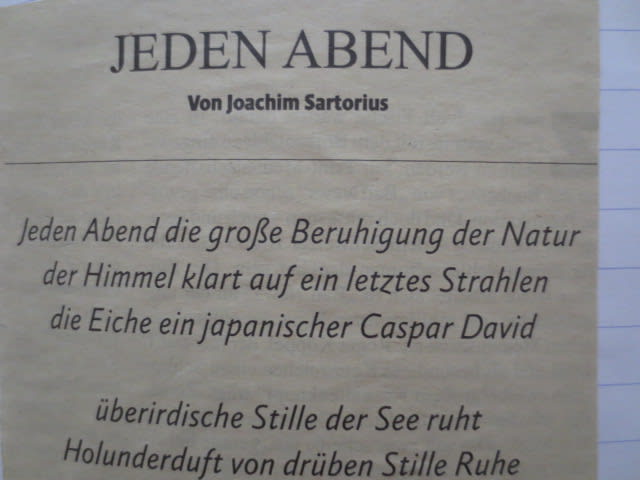
 )、
)、







 。
。





