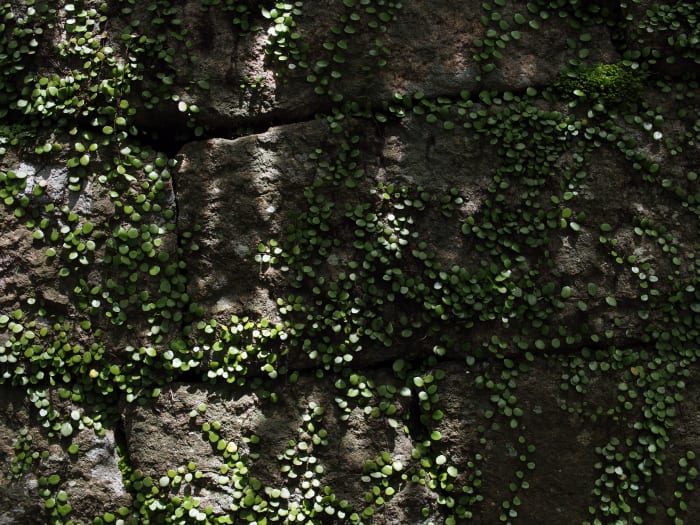8月初め、年休を土日にプラスしてプチ夏休みをいただいた。
夏山に行こう、夏山に。
夏山でイメージするのは日本アルプスの稜線歩きだが、いろいろいろいろいろいろある理由から、日帰り登山になった。
あー、正確には前夜泊の一泊一日登山。
山は山梨県にある瑞牆山(みずがきやま)。
標高2230mである。

当然天気のいい日を狙って行った。
前夜泊した登山口の瑞牆山荘奥の駐車場は真っ暗で、ヘッドライトを消すと夜空に満天の星が輝いて見えた。
写真を撮ろうかと思ったが、広い駐車場には結構な数の先客が車を止めていて、シンと静か。
ガチャガチャやっては迷惑かと見るだけにとどめておいた。

翌朝は5時半に歩き出した。
上空は青空だが南西斜面を登るので朝日は差し込まず、青みを帯びた山道をゆく。
最初のうちは傾斜もなだらかで、サクサクと歩を進める。
程なく富士見平小屋を通過。
小屋前の広場は、ベンチで朝食を摂ったり、出発の準備を進める方でいっぱい。
奥に金峰山もあるからか、登山口からすぐのとこなのに人気の小屋みたいだ。

小屋を過ぎてしばらく行くと、道は下り坂となる。
降り切った天鳥川から再び上り。
ここからの上りは急斜面で、膝に手をついて登らねばいけない段差が頻出。
花崗岩の巨岩の横や下をヒーコラいいながら登る。

なかなかに体力を削がれる道だ。
登山道は幅が広く、急斜面で岩がちだからか一本の道は形作られにくいようで、網目状に直登するルート、回り込むルートが入り乱れていた。
上り下りのすれ違いのやり易い登山道と言える。

なんのマジないだか、花崗岩の大きな岩に木の枝を立てかけてあるのをたくさん見た。
太い丸太や細い小枝まで、いっぱい立てかけてある。
登山に来た巡礼者がお供えしているみたい。
あれだな、石を積んでケルンを作るような感覚なんだろうか。
急斜面を岩が転がり落ちないよう支えているように見えて面白い。

山頂到着は8時15分。
今回はお天気よく迎えてくれた。
左から金峰山、富士山、南アルプスに北アルプス、八ヶ岳と、真っ青な空の下、近く遠く峰々の稜線がくっきりと望めた。
こりゃあいい。
周りの上り終えた皆さんも一様にごきげんである。
山頂は巨大な岩上で、片側は垂直に切れ落ちて、下を覗くとあな恐ろしや。
すぐ隣にも巨石が屹立し、なかなか特徴的な山上だ。

八ヶ岳側に斜めに平らな場所があり、横になってしばし眠った。
日がさんさんと差していたが、標高のせいか暑くは感じず、上りの疲れも手伝って気持ちよく眠った。
いびきをかいてなかったろうか。
程よく眠って起き出し、お昼にした。
眠ってる間に雲が少し出て来て、富士山は見えなくなっていた。
新たに山頂に到着した方は少し残念そう。
でもまだまだ他の山々は青くくっきりと眺められた。
結局山頂には2時間もいた。
最長記録だな。
それだけ居心地が良かったということか。

下りは上りと同じ道を引き返した。
花はさほど多くなく、キノコの方がよく見かけた。
花の密度が一番濃かったのは富士見平小屋の周り。
マルバダケブキの黄色い花が咲き始めていた。
トンボが蕾に止まっていたので逃げないよう遠くから撮影。
しかしこのトンボ、結構近づいても一向に逃げようとしない。
調子に乗ってどんどん近づいて、大きく撮ってやった。
そして下山。
駐車場着は13:00だった。

今回の登山口は中央道から結構離れている。
途中山中の温泉地を抜けてさらに奥に入らねばいけない。
行きは夜で真っ暗だったから様子がよく分からなかったが、帰りに明るい中走ったらある事に気付いた。
林道は渓流の横を走り、駐車スペースも結構ある。
夏場の涼を得るのに日がな一日過ごすのに良さげな所だ。
なにも高度を稼がなくても涼しく過ごせる場所があるのではと思ったのだ。
問題は水辺でヤブ蚊がいるかどうかだな。
夏山に行こう、夏山に。

夏山でイメージするのは日本アルプスの稜線歩きだが、いろいろいろいろいろいろある理由から、日帰り登山になった。
あー、正確には前夜泊の一泊一日登山。
山は山梨県にある瑞牆山(みずがきやま)。
標高2230mである。

当然天気のいい日を狙って行った。
前夜泊した登山口の瑞牆山荘奥の駐車場は真っ暗で、ヘッドライトを消すと夜空に満天の星が輝いて見えた。

写真を撮ろうかと思ったが、広い駐車場には結構な数の先客が車を止めていて、シンと静か。
ガチャガチャやっては迷惑かと見るだけにとどめておいた。

翌朝は5時半に歩き出した。
上空は青空だが南西斜面を登るので朝日は差し込まず、青みを帯びた山道をゆく。
最初のうちは傾斜もなだらかで、サクサクと歩を進める。
程なく富士見平小屋を通過。
小屋前の広場は、ベンチで朝食を摂ったり、出発の準備を進める方でいっぱい。
奥に金峰山もあるからか、登山口からすぐのとこなのに人気の小屋みたいだ。

小屋を過ぎてしばらく行くと、道は下り坂となる。
降り切った天鳥川から再び上り。
ここからの上りは急斜面で、膝に手をついて登らねばいけない段差が頻出。
花崗岩の巨岩の横や下をヒーコラいいながら登る。


なかなかに体力を削がれる道だ。
登山道は幅が広く、急斜面で岩がちだからか一本の道は形作られにくいようで、網目状に直登するルート、回り込むルートが入り乱れていた。
上り下りのすれ違いのやり易い登山道と言える。

なんのマジないだか、花崗岩の大きな岩に木の枝を立てかけてあるのをたくさん見た。
太い丸太や細い小枝まで、いっぱい立てかけてある。
登山に来た巡礼者がお供えしているみたい。
あれだな、石を積んでケルンを作るような感覚なんだろうか。
急斜面を岩が転がり落ちないよう支えているように見えて面白い。


山頂到着は8時15分。
今回はお天気よく迎えてくれた。
左から金峰山、富士山、南アルプスに北アルプス、八ヶ岳と、真っ青な空の下、近く遠く峰々の稜線がくっきりと望めた。

こりゃあいい。
周りの上り終えた皆さんも一様にごきげんである。
山頂は巨大な岩上で、片側は垂直に切れ落ちて、下を覗くとあな恐ろしや。
すぐ隣にも巨石が屹立し、なかなか特徴的な山上だ。

八ヶ岳側に斜めに平らな場所があり、横になってしばし眠った。
日がさんさんと差していたが、標高のせいか暑くは感じず、上りの疲れも手伝って気持ちよく眠った。
いびきをかいてなかったろうか。

程よく眠って起き出し、お昼にした。
眠ってる間に雲が少し出て来て、富士山は見えなくなっていた。
新たに山頂に到着した方は少し残念そう。
でもまだまだ他の山々は青くくっきりと眺められた。
結局山頂には2時間もいた。

最長記録だな。
それだけ居心地が良かったということか。

下りは上りと同じ道を引き返した。
花はさほど多くなく、キノコの方がよく見かけた。
花の密度が一番濃かったのは富士見平小屋の周り。
マルバダケブキの黄色い花が咲き始めていた。
トンボが蕾に止まっていたので逃げないよう遠くから撮影。
しかしこのトンボ、結構近づいても一向に逃げようとしない。
調子に乗ってどんどん近づいて、大きく撮ってやった。

そして下山。
駐車場着は13:00だった。

今回の登山口は中央道から結構離れている。
途中山中の温泉地を抜けてさらに奥に入らねばいけない。
行きは夜で真っ暗だったから様子がよく分からなかったが、帰りに明るい中走ったらある事に気付いた。
林道は渓流の横を走り、駐車スペースも結構ある。
夏場の涼を得るのに日がな一日過ごすのに良さげな所だ。
なにも高度を稼がなくても涼しく過ごせる場所があるのではと思ったのだ。
問題は水辺でヤブ蚊がいるかどうかだな。











 )
)