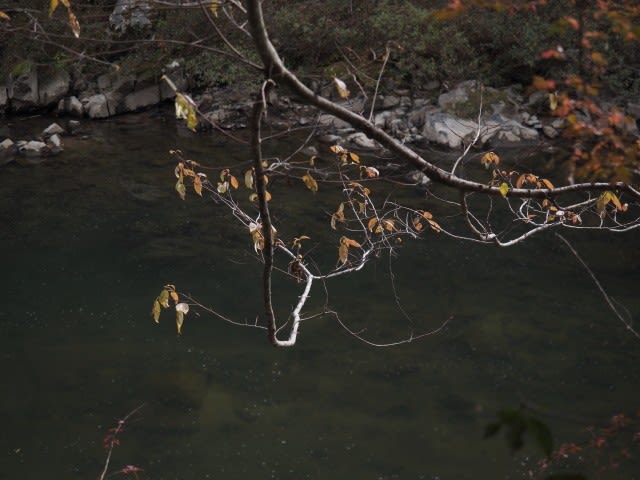常滑での昼食はやきもの散歩道を巡る途中、コース内側に少し入ったところのお店に入った。
そろそろお腹が空いてきたなという頃合い。
狭い道を歩いていると、植物が壁を覆った建物の門の所に小さな看板が置いてあるのを見つけた。
看板が無ければ古民家にしか見えない外観。

敷地への入口の小さな門扉はなかなかの年代物で、どんな店かと恐る恐る入ってみた。
中は周りを家と壁が囲む中庭で、いろんな植物に溢れていた。
パラソル付きのテーブルと椅子がいくつかあり、新しいものだったので少し安心。

玄関の扉を開けると、中は古民家を改装したいい雰囲気のお店だった。
店員さんのエプロンがかわいい。
黒板のメニューを見ると食事もできるのでここで食べる事にした。
おにぎり(天むすだったと思う)と豚汁のセットを注文。

店内も古びていて良かったが、まずまず席が埋まっていたので、誰もいない中庭のパラソル下で食べる事に。
料理ができるまで中庭の様子を撮影させてもらった。
わさわさといろんな植物が生えており、鉢植えもたくさん置かれている。

きれいに整えられた庭ではなく雑多な感じなのだが、手入れはするものの自由に枝葉を伸ばさせている感じ。
居心地良し。
二人で独占していたかったが他のお客さんが前の席に座ってしまった。
まあ致し方なし。

おにぎりと豚汁のセットが運ばれてきた。
小さく切り揃えられた豚汁の具材は程よく煮込まれコクはあるが上品な味付け。
おにぎりもふんわりと握られていて美味しかった。
若い人には量が物足りないだろう。
きっとこのあと何処かでお茶するだろうから、お腹の隙間はそこで埋めよう。

寒くなると言われていた日だったのに、お天気よく暖かくなった。
食後もしばしベンチに座り、日の光あふれる庭を眺めていた。
最前写真を撮っている時、お客さんとは思えぬ男の人がやってきて、また食事をしている時子供が二人やってきて、中庭に面する奥の建物に入っていった。
住居の隣をお店にしたようだ。
お店がお休みの時はこの中庭でコーヒーを飲む時間を過ごしたりするのだろうか。
うらやましい事である。

そろそろお腹が空いてきたなという頃合い。
狭い道を歩いていると、植物が壁を覆った建物の門の所に小さな看板が置いてあるのを見つけた。
看板が無ければ古民家にしか見えない外観。

敷地への入口の小さな門扉はなかなかの年代物で、どんな店かと恐る恐る入ってみた。
中は周りを家と壁が囲む中庭で、いろんな植物に溢れていた。
パラソル付きのテーブルと椅子がいくつかあり、新しいものだったので少し安心。

玄関の扉を開けると、中は古民家を改装したいい雰囲気のお店だった。
店員さんのエプロンがかわいい。
黒板のメニューを見ると食事もできるのでここで食べる事にした。
おにぎり(天むすだったと思う)と豚汁のセットを注文。

店内も古びていて良かったが、まずまず席が埋まっていたので、誰もいない中庭のパラソル下で食べる事に。
料理ができるまで中庭の様子を撮影させてもらった。
わさわさといろんな植物が生えており、鉢植えもたくさん置かれている。

きれいに整えられた庭ではなく雑多な感じなのだが、手入れはするものの自由に枝葉を伸ばさせている感じ。
居心地良し。
二人で独占していたかったが他のお客さんが前の席に座ってしまった。
まあ致し方なし。

おにぎりと豚汁のセットが運ばれてきた。
小さく切り揃えられた豚汁の具材は程よく煮込まれコクはあるが上品な味付け。
おにぎりもふんわりと握られていて美味しかった。
若い人には量が物足りないだろう。
きっとこのあと何処かでお茶するだろうから、お腹の隙間はそこで埋めよう。

寒くなると言われていた日だったのに、お天気よく暖かくなった。
食後もしばしベンチに座り、日の光あふれる庭を眺めていた。
最前写真を撮っている時、お客さんとは思えぬ男の人がやってきて、また食事をしている時子供が二人やってきて、中庭に面する奥の建物に入っていった。
住居の隣をお店にしたようだ。
お店がお休みの時はこの中庭でコーヒーを飲む時間を過ごしたりするのだろうか。
うらやましい事である。