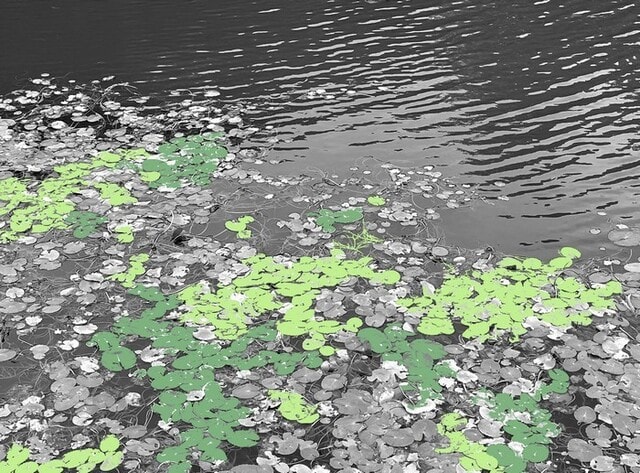
息をすると 鼻の奥にツンとくる この風の味が懐かしい 騒がしかった夏が終わり 季節が変わろうとして 静かに寄せてくる 周りの澄んだ静寂が 広い空間に感じられて その隙間にいろいろなものが 水のように沁み込んでくる 今まで聞こえなかった 微かな物音であったり 天井のしみや障子の破れなどが 急に見えてきたりして 夏の間にできてしまった 感覚のずれや反応のずれなど 小さなものかもしれないが 見詰めすぎると些細なずれが 亀裂になってしまうこともあったり ずれたままで重ならないままでも あえて心地のいい方へ動いていく ずれた感覚に浸ってみるのも ときには快いものだったりもして そのうち季節の方でも 少しずつずれながら 秋もしだいに深まってゆくようで 今はそんな季節だろうか 久しぶりに本を読みたくなって そうしていつのまにか 川上弘美の短編小説の 不思議な世界にずれこんでいく 熊の神様のご利益とは…『神様』 恋をする河童たちの…『河童玉』 壺の中で生きる若い女の…『クリスマス』 人魚への奇妙な偏愛…『離さない』など 日常生活から少し ずれた非現実なところに かなしい真実があったりする
「このところ、夜になると何かがずれるようになったのである。何がずれるのか、時間がずれていくような気もしたし、空気のずれていくような気もしたし、音がずれていくような気もしたし、全部ひっくるめてずれていくのかもしれなかった。それで、昼間梨畑で働かせてもらうことにした。」
これは川上弘美の短編『夏休み』の一節 ある日「わたし」は 梨畑で白い毛の生えた 3匹の生き物を見つけ 家に連れて帰る 2匹はすこぶる元気だが 1匹は臆病で引っ込み思案 「ぼくいろいろだめなの」と言葉も喋る 「ぼくが入ってもぼくが抜けても、その場所が変わっちゃうのがだめ」と言う この1匹は仲間とずれている それが「わたし」は 気になって仕方ない 梨の収穫も 終わりに近くなって 最後の日 主人の原田さんから あの3匹は シーズンが終ると消えてしまうよ と奇妙な話をされ その日の夜になって 「わたし」に激しいずれがやってくる
「空気や地軸がずれる感じではなく、からだ全体がすっぽり抜けてしまうようなずれだった。」
寝ている自分と 立ちあがった自分の ふたりがいる 横たわっている自分の からだを残したまま さかんに梨畑に行きたがる3匹を 肩に乗せて梨畑に向かう 活発な2匹は 木のてっぺんに登って 木守りの梨をかじりはじめるが 引っ込み思案の1匹は 「こわい」と言いながら 「わたし」の肩の上で震えている
「震えが伝わる部分があたたまって、ゆるんでくる。肩から胸から腹から腕から足まで、次第にゆるみはじめる。湯に入っているようだった。」
やっと弱虫の1匹も 幹にとびうつって 木守りの梨を食べはじめる そのうちに3匹は 梨の木の白い瘤になってしまう 「わたし」も同じように 瘤に引き込まれそうになるのを 必死で振り払ったら 重さというものをなくして 軽くなった体でとんで帰る 翌日「わたし」は原田さんを訪ね 雇ってもらった礼を言い 帰りがけにもういちど 梨畑に寄ってみるが どの木に白い瘤がついているのか 既にわからなくなっている そこで梨の木の1本を 思わずとんとんと叩いて いろいろとありがとうと呟く 読んだあとに すじ雲が高く残った 秋空のような爽やかさが残る


























