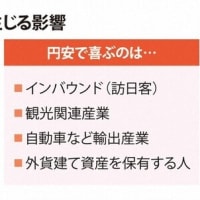国際捕鯨委員会脱退―メリットとデメリット―
日本は1951年に国際捕鯨委員会(IWC)に加盟しました。当時、日本は戦後の食料不足、
とりわけタンパク不足を補うため、乱獲と言われても仕方がないほど、商業捕鯨を活発に行っ
ていました。
しかしIWCは1988年4月にクジラの資源枯渇を理由に商業捕鯨の「一時停止」を決めま
した。それ以来、日本も商業捕鯨を中断し、南極海と北西大西洋での「調査捕鯨」に切り替え
ました。
「調査捕鯨」の名目で南極海では年間、クロミンククジラ331頭、北西太平洋ではミンクク
ジラ170頭、イワシクジラ134頭を獲ってきました。
ところが今年の9月10~14、ブラジル・フロリアポリスで開かれたIWC総会で、日本は
商業捕鯨を一部解禁する提案を行いました。
しかし、この提案は賛成41、反対48の反対多数で否決されました。
日本政府は、これまで日本のクジラを食べる食文化を維持するために適切な規模の商業捕鯨は
正当であり、30年に及ぶ調査で、鯨の数はかなり復活している、との主張をしてきましたが
受け入れられませんでした。
他方、今総会においては、今後6年間の先住民捕獲枠を認める提案が4分の3以上の賛成で可
決されました。谷合副大臣は「持続的利用という観点に立てば、先住民であれ商業捕鯨であれ
根底にあるものは一緒であり、認められるべきだと主張してきた。だが、商業捕鯨になった途
端、理屈がなく一切ダメになる。その理由が分からないので今日に到っている」と隔靴掻痒の
感を表明しました(注1)。
総会で日本の主張が退けられたため、政府は12月20日、「捕鯨の是非をめぐってこう着状
態に陥っているIWCでの議論に見切りをつけ脱退する方針を固めました(『東京新聞』2018
年12月21日;『毎日新聞』2018年12月20日)。
そして、12月25日にIWC脱退を閣議決定し、翌26日には本部へ公式に脱退の通告をし
ました。ただし、日本政府はIWCから脱退しても、オブザーバー(監視役)としてクジラの
資源管理には貢献する、としています。
菅官房長官は27日、脱退に関する談話を発表しました。その趣旨は、異なる意見を持つ国と
共存する可能性がないこと、日本はクジラを食料としてだけでなくさまざまな用途に利用し文
化や生活を築いてきたこと、科学的な根拠に基づき持続的に利用する考え方が各国に理解され
ることを期待する、というものです(『東京新聞』)2018年12月27日)。
今回の決定に関しては、なぜ今、敢えて脱退するのか、脱退により何が変わり、日本にとって
どんな影響が具体的にあるのかを検討し、その後で、果たして今回の脱退に合理性と正当性が
あるのかどうかを検討したいと思います。
その前に、この脱退によってこれから捕鯨がどうなるかを押えておきましょう。
まず、来年の7月から、①公海である南極海と南半球での調査捕鯨ができなくなり、②日本の
捕鯨は排他的経済水域(EEZ)や近海でのミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ツ
チクジラなどを対象とした商業捕鯨に限定することになりました。
その代わり、IWCに加盟しているから子ど認められてきた南極海と北西太平洋での「調査捕
鯨は認められなくなります。
さらに、EEZ内においても商業捕鯨は無条件ではなく、海洋法条約によって、鯨類の捕獲は
しかるべき国際機関の監視の下で行う必要があるのです。
ちなみに、現在日本で捕鯨を行っている捕鯨基地は、網走、釧路、八戸、石巻、南房総、太地
(和歌山)、下関の七カ所です。これらの場所では脱退大歓迎のようですが、果たしてこれで
産業として、地域おこしになるでしょうか。
EEZ内での捕獲頭数実績は、年間の上限でツチクジラ66頭、マゴンドウ72頭、ハナゴン
ドウ20頭です。
日本の脱退の通告に対して、オーストラリアやニュージーランドをはじめ、反捕鯨の立場をと
ってきた国々や団体から批判が寄せられました。
また、国内においても、さまざまな反応と幾つもの疑問が出されています。
第一の反応は、国際機関からの脱退というのは、戦前の国際連盟からの脱退し、戦争に突入し
ていった暗い過去を想い起させる、という街の声です。
第二に、鯨の肉の消費量はかつての50分の1に減少しているのに、なぜ、商業捕鯨を再開す
る必要があるのか、せっかく捕っても消費されず無駄になるのでは、という疑問です。
第三に、捕鯨の問題を追いかけてきた共同通信の井田徹治氏がいうよに、EEZ内での商業捕
鯨ということであれば、IWCの枠内の議論でも認められる可能性が十分あるのに、なぜその
ような提案をして粘り強く説得しないのか、それをしないで、いきなりIWCからの脱退とい
うのは短絡的であるという批判です(テレビ朝日『モーニングショー』2018年12月27日)。
第四に、たとえEEZ内での商業捕鯨を行ったとしても、鯨の供給量は増えない、むしろ南極
海での調査捕鯨が無くなった分、実際には供給量は減ってしまう、という現実です。
第五に、国内手続き的に憲法上の問題があると、早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏は指
摘しています。
水島氏によれば、「国際機関への加盟の根拠となる条約の締結について、憲法第七三条には、
事前もしくは事後の国会承認が必要としている。その趣旨からすれば、条約や国際機関からの
脱退も国政の重大な変更であり、国会での議論抜きにはありえない」ということになります。
ここは非常に大切なことで、国際機関からの脱退という、国にとって重大な問題を閣議決定だ
けで実行してしまうのは、「国会無視」、「憲法無視」という安倍政権の一貫した姿勢で、法
治国家としては大いに問題だと思います。
実際、この決定と通告がなされた時には、国会はすでに閉会となっており、国会での議論はで
きないタイミングでした。
9月には決まっていたのに、このタイミングで脱退を公に通告したのは、国会での議論を避け
る目的があったのではないか、とさえ勘繰りたくなります。
最後に水島氏は、IWCからの一方的な脱退は、憲法九八条が掲げる「国際協調主義」を捨て
去る最初の一歩になりかねない、と警鐘を鳴らしています(『東京新聞』2018年12月27日)。
以上の手続きや憲法だけでなく、日本の外交との関連でも、今回の一方的な離脱には大きな問
題がありあす。
まず、国際機関からの脱退は、これまで日本がとってきた国際協調主義や国際ルールの順守と
いった基本方針と整合性に疑義は生ずる懸念が残ります。安倍政権は11月のAPEC(アジ
ア太平洋経済協力会議)では、貿易をめぐる米中対立の激化にたいして多国間の枠組みでの自
由貿易推進を呼び掛けましたから、一層、整合性を欠くことになります。
また中国の南シナ海への進出や韓国の徴用工に関する韓国最高裁の判決にたいして日本政府は、
国際ルールの尊重を訴えて相手国に抗議していますので、この点でも矛盾しているとみなされ
る可能性があります。
こうした状況を踏まえたうえで、日本の要求が受け入れられないからといって、菅官房長官の
談話にあるように、「異なる意見を持つ国と共存する可能性がないこと」を理由にIWCを脱
退することは、他の国からみたら自分勝手であると見えるでしょう。
2020年の東京オリンピック・パッリンピックを控えて、日本への評価が少なからず傷つくので
はないか、と心配されます。
最後に、鯨と食文化との関連で捕鯨の問題を考えてみたいと思います。
日本人は、すくなくとも江戸時代には捕鯨が行われ、クジラ肉は食文化の一角を占めていたし、
以来、日本の食文化にはクジラが根付いてきました。
この点に関しては、私も捕鯨とクジラの肉を食べる食文化を維持するためにも、捕鯨はある程
度、認められて欲しいと思います。
そのためなら、井田氏が言うようにIWCに留まって、日本のEEZ内での一定の頭数の捕鯨
を認めてもらうよう粘り強い説得を続けるべきだと思います。
現在のクジラ肉にたいする需要を現実的に考えるなら、捕鯨が今後、大きな産業に成長すると
は思えません。しかも、IWCが禁じているのは大型のクジラの商業捕鯨で、日本近海の小型
のツチクジラは対象になっていません。小型クジラに限れば、現状と変わらないのです。
一方、IWCの目的は、国際捕鯨取締条約に基づき鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展
を図ることであったはずなのに、今では捕鯨産業の秩序ある発展という目的は消えてしまい、
クジラ資源の保護という自然保護が前面に出てきてしまっていることも事実です。
もし、そのように変わったのなら、IWCの目的を改訂した方が混乱が少なくなるでしょう。
今回の脱退の決断は、合理的・現実的に考え貫いてだした結論というより、日本の食文化に口
を出すな、という感情論、あるいはナショナリズム的な感じさえします。
こうした事情を考慮しても私は、総合的に考えて私は、今回の脱退は、得られるメリットより
も失うデメリットの方が大きいと考えています。
この問題に関して、元IWC日本代表の小松正之氏は、「今回のIWCからの脱退で説得力が
なくなってしまう。交渉の場から離れず主張をつづけることが重要」であるとし、結局、脱退
によって一つでも利益があるのか、と政府の決定を批判しています(12月30日 TBS
「サンデー・モーニング」)。私も、全く同感です。
(注1)『日経新聞』デジタル版 2018年9月20日
https://www.nikkeyshimbun.jp/2018/180929-72colonia.html
日本は1951年に国際捕鯨委員会(IWC)に加盟しました。当時、日本は戦後の食料不足、
とりわけタンパク不足を補うため、乱獲と言われても仕方がないほど、商業捕鯨を活発に行っ
ていました。
しかしIWCは1988年4月にクジラの資源枯渇を理由に商業捕鯨の「一時停止」を決めま
した。それ以来、日本も商業捕鯨を中断し、南極海と北西大西洋での「調査捕鯨」に切り替え
ました。
「調査捕鯨」の名目で南極海では年間、クロミンククジラ331頭、北西太平洋ではミンクク
ジラ170頭、イワシクジラ134頭を獲ってきました。
ところが今年の9月10~14、ブラジル・フロリアポリスで開かれたIWC総会で、日本は
商業捕鯨を一部解禁する提案を行いました。
しかし、この提案は賛成41、反対48の反対多数で否決されました。
日本政府は、これまで日本のクジラを食べる食文化を維持するために適切な規模の商業捕鯨は
正当であり、30年に及ぶ調査で、鯨の数はかなり復活している、との主張をしてきましたが
受け入れられませんでした。
他方、今総会においては、今後6年間の先住民捕獲枠を認める提案が4分の3以上の賛成で可
決されました。谷合副大臣は「持続的利用という観点に立てば、先住民であれ商業捕鯨であれ
根底にあるものは一緒であり、認められるべきだと主張してきた。だが、商業捕鯨になった途
端、理屈がなく一切ダメになる。その理由が分からないので今日に到っている」と隔靴掻痒の
感を表明しました(注1)。
総会で日本の主張が退けられたため、政府は12月20日、「捕鯨の是非をめぐってこう着状
態に陥っているIWCでの議論に見切りをつけ脱退する方針を固めました(『東京新聞』2018
年12月21日;『毎日新聞』2018年12月20日)。
そして、12月25日にIWC脱退を閣議決定し、翌26日には本部へ公式に脱退の通告をし
ました。ただし、日本政府はIWCから脱退しても、オブザーバー(監視役)としてクジラの
資源管理には貢献する、としています。
菅官房長官は27日、脱退に関する談話を発表しました。その趣旨は、異なる意見を持つ国と
共存する可能性がないこと、日本はクジラを食料としてだけでなくさまざまな用途に利用し文
化や生活を築いてきたこと、科学的な根拠に基づき持続的に利用する考え方が各国に理解され
ることを期待する、というものです(『東京新聞』)2018年12月27日)。
今回の決定に関しては、なぜ今、敢えて脱退するのか、脱退により何が変わり、日本にとって
どんな影響が具体的にあるのかを検討し、その後で、果たして今回の脱退に合理性と正当性が
あるのかどうかを検討したいと思います。
その前に、この脱退によってこれから捕鯨がどうなるかを押えておきましょう。
まず、来年の7月から、①公海である南極海と南半球での調査捕鯨ができなくなり、②日本の
捕鯨は排他的経済水域(EEZ)や近海でのミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ツ
チクジラなどを対象とした商業捕鯨に限定することになりました。
その代わり、IWCに加盟しているから子ど認められてきた南極海と北西太平洋での「調査捕
鯨は認められなくなります。
さらに、EEZ内においても商業捕鯨は無条件ではなく、海洋法条約によって、鯨類の捕獲は
しかるべき国際機関の監視の下で行う必要があるのです。
ちなみに、現在日本で捕鯨を行っている捕鯨基地は、網走、釧路、八戸、石巻、南房総、太地
(和歌山)、下関の七カ所です。これらの場所では脱退大歓迎のようですが、果たしてこれで
産業として、地域おこしになるでしょうか。
EEZ内での捕獲頭数実績は、年間の上限でツチクジラ66頭、マゴンドウ72頭、ハナゴン
ドウ20頭です。
日本の脱退の通告に対して、オーストラリアやニュージーランドをはじめ、反捕鯨の立場をと
ってきた国々や団体から批判が寄せられました。
また、国内においても、さまざまな反応と幾つもの疑問が出されています。
第一の反応は、国際機関からの脱退というのは、戦前の国際連盟からの脱退し、戦争に突入し
ていった暗い過去を想い起させる、という街の声です。
第二に、鯨の肉の消費量はかつての50分の1に減少しているのに、なぜ、商業捕鯨を再開す
る必要があるのか、せっかく捕っても消費されず無駄になるのでは、という疑問です。
第三に、捕鯨の問題を追いかけてきた共同通信の井田徹治氏がいうよに、EEZ内での商業捕
鯨ということであれば、IWCの枠内の議論でも認められる可能性が十分あるのに、なぜその
ような提案をして粘り強く説得しないのか、それをしないで、いきなりIWCからの脱退とい
うのは短絡的であるという批判です(テレビ朝日『モーニングショー』2018年12月27日)。
第四に、たとえEEZ内での商業捕鯨を行ったとしても、鯨の供給量は増えない、むしろ南極
海での調査捕鯨が無くなった分、実際には供給量は減ってしまう、という現実です。
第五に、国内手続き的に憲法上の問題があると、早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏は指
摘しています。
水島氏によれば、「国際機関への加盟の根拠となる条約の締結について、憲法第七三条には、
事前もしくは事後の国会承認が必要としている。その趣旨からすれば、条約や国際機関からの
脱退も国政の重大な変更であり、国会での議論抜きにはありえない」ということになります。
ここは非常に大切なことで、国際機関からの脱退という、国にとって重大な問題を閣議決定だ
けで実行してしまうのは、「国会無視」、「憲法無視」という安倍政権の一貫した姿勢で、法
治国家としては大いに問題だと思います。
実際、この決定と通告がなされた時には、国会はすでに閉会となっており、国会での議論はで
きないタイミングでした。
9月には決まっていたのに、このタイミングで脱退を公に通告したのは、国会での議論を避け
る目的があったのではないか、とさえ勘繰りたくなります。
最後に水島氏は、IWCからの一方的な脱退は、憲法九八条が掲げる「国際協調主義」を捨て
去る最初の一歩になりかねない、と警鐘を鳴らしています(『東京新聞』2018年12月27日)。
以上の手続きや憲法だけでなく、日本の外交との関連でも、今回の一方的な離脱には大きな問
題がありあす。
まず、国際機関からの脱退は、これまで日本がとってきた国際協調主義や国際ルールの順守と
いった基本方針と整合性に疑義は生ずる懸念が残ります。安倍政権は11月のAPEC(アジ
ア太平洋経済協力会議)では、貿易をめぐる米中対立の激化にたいして多国間の枠組みでの自
由貿易推進を呼び掛けましたから、一層、整合性を欠くことになります。
また中国の南シナ海への進出や韓国の徴用工に関する韓国最高裁の判決にたいして日本政府は、
国際ルールの尊重を訴えて相手国に抗議していますので、この点でも矛盾しているとみなされ
る可能性があります。
こうした状況を踏まえたうえで、日本の要求が受け入れられないからといって、菅官房長官の
談話にあるように、「異なる意見を持つ国と共存する可能性がないこと」を理由にIWCを脱
退することは、他の国からみたら自分勝手であると見えるでしょう。
2020年の東京オリンピック・パッリンピックを控えて、日本への評価が少なからず傷つくので
はないか、と心配されます。
最後に、鯨と食文化との関連で捕鯨の問題を考えてみたいと思います。
日本人は、すくなくとも江戸時代には捕鯨が行われ、クジラ肉は食文化の一角を占めていたし、
以来、日本の食文化にはクジラが根付いてきました。
この点に関しては、私も捕鯨とクジラの肉を食べる食文化を維持するためにも、捕鯨はある程
度、認められて欲しいと思います。
そのためなら、井田氏が言うようにIWCに留まって、日本のEEZ内での一定の頭数の捕鯨
を認めてもらうよう粘り強い説得を続けるべきだと思います。
現在のクジラ肉にたいする需要を現実的に考えるなら、捕鯨が今後、大きな産業に成長すると
は思えません。しかも、IWCが禁じているのは大型のクジラの商業捕鯨で、日本近海の小型
のツチクジラは対象になっていません。小型クジラに限れば、現状と変わらないのです。
一方、IWCの目的は、国際捕鯨取締条約に基づき鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展
を図ることであったはずなのに、今では捕鯨産業の秩序ある発展という目的は消えてしまい、
クジラ資源の保護という自然保護が前面に出てきてしまっていることも事実です。
もし、そのように変わったのなら、IWCの目的を改訂した方が混乱が少なくなるでしょう。
今回の脱退の決断は、合理的・現実的に考え貫いてだした結論というより、日本の食文化に口
を出すな、という感情論、あるいはナショナリズム的な感じさえします。
こうした事情を考慮しても私は、総合的に考えて私は、今回の脱退は、得られるメリットより
も失うデメリットの方が大きいと考えています。
この問題に関して、元IWC日本代表の小松正之氏は、「今回のIWCからの脱退で説得力が
なくなってしまう。交渉の場から離れず主張をつづけることが重要」であるとし、結局、脱退
によって一つでも利益があるのか、と政府の決定を批判しています(12月30日 TBS
「サンデー・モーニング」)。私も、全く同感です。
(注1)『日経新聞』デジタル版 2018年9月20日
https://www.nikkeyshimbun.jp/2018/180929-72colonia.html