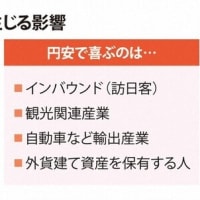本の紹介 鈴木宣弘『農業消滅―農政の失敗がまねく国家存亡の危機―』(1)
―危機の本質―
ウクライナ戦争は、思いもかけなかった余波を世界の各地域に引き起こしています。
石油と天然ガスのエネルギー価格が急騰しています。メディアではエネルギー問題ほど大きく
報じていませんが、食料及び食料生産にも大きな影響を与えています。
これまで日本は、工業製品を輸出して、食料は輸入すればよい、という大雑把な方針の下で、
食料価格について、まったく危機感を持っていませんでした。
しかし、ここで紹介する『農業消滅』(平凡社新書、2021、239ページ)の著者、鈴木宣弘
(東京大学大学院農学科)は、これまでも一貫して日本の農業と食料の危機について、さま
ざまな場所で警告してきました。
実際、本書に書かれている内容を正面から受け止めると、現在日本が抱えている危機の実態
がみえてきます。
著者の鈴木氏は東大農学部を卒業後の農林水産省に入省し、そこで15年勤務した後、九州
大学と経て現職に就き現在に至ります。経歴からも分かるように、農業に関するプロ中のプ
ロです。
まず本書の構成を示しておきます。
はじめに
序章 飢餓は他人事ではない
第1章 2008年の教訓は生かされない
第2章 種を制するものは世界を制す
第3章 自由化と買い叩きにあう日本の農業
第4章 危ない食料は日本向け
第5章 安全保障の要としての国家戦略の欠如
終章 日本の未来は守れるか
おわりに
「はじめに」と第1章からみてみよう。ここは本書全体を見通す問題が提示されています。
それは、食料自給率の低下の問題です。現在食料自給率がカロリーベースで38%、農水省
の試算によれば、2035年には、実質的な自給率は酪農では12%、コメで11%、青果物や
畜産では1~4%に落ちてしまう。
ここで注意しなければならないのは、日本の場合、飼料や種を輸入している場合、たとえ生
産物が日本産であっても純粋に国産物とは言えない、という点である。
たとえば、鶏卵の場合、鶏のヒナはすでに100%に近いので、厳密に言えば自給率は0%
です。
自給率80%の野菜も、その種の90%は輸入なのです。
なお、コメも生産高でみる限り自給率は106%ですが、これも種が全て国産の場合です。
最近の政府の政策(種子法の廃止など)により、今後は種籾も輸入品が多くなることが想定
されるので(農水省では自給率は10%と想定)実質的にはコメの自給率は11%になって
しまいます。
政府は際限ない貿易自由化を進めており、国産の農産物が買いたたかれています。
たとえば、主食であるコメにいてみると、2022年にコメ農家に支払われる農協の概算金
は、1俵(60キログラム)が1万円を切る可能性が指摘されています。
しかし、実際の生産費はどんなに頑張っても1俵当たり1万円以上かかっているのです。これ
では農家の存続さえ危うくなり、農業を続ける意欲を失わせます。
アメリカなどでは、政府が農産物を直接買い上げて、コロナ禍で生活が苦しくなった人々や
子供たちに配給するという人道支援をおこなっています。
鈴木氏は日本でもフードバンクや子供食堂などの支援のため政府買い入れをしないのか、と
政府に注文をつけています。しかし、一旦、備蓄米以上のコメを買わないと決めて以上、断
固として買わない、という政府に対して次のように手厳しく批判しています。
すなわち、「上から目線で『コメを作付けするな』と言っている場合ではないのだ。政府の
メンツを保つためだけのために、苦しんでいる国民や農家を放置する政府・行政の存在意義
が厳しく問われている、と。
農家の高齢化による生産者数の減少に加えて、生産意欲を失わせるような政府・行政の農政
のため、耕作放棄地が増え、主食のコメでさえ将来は自給できなくなる可能性が大いにあり
ます。
もし、種や家畜飼料が何らかの理由で輸入できなかったり価格が暴騰していたり(今日のト
ウモロコシや大豆のように)、2008年に起こった旱魃や、あるいは水害などで生産が大
きな打撃を受けると、本当に飢餓が発生しかねません。
この意味で、農業は国家の存亡にかかわる問題ですが、政府はこれまで本格的に農業を保護
育成する政策を採ってきませんでした。
それは、日本は工業立国で生きてゆくべきで製造業中心の国造りをしてきたからです。実は、
この方針が日本の食料問題を危うくする一つの大きな原因となっているのです。
第2章は、現実に日本が食料危機に陥る脅威について説明しています。
食料の3分の2を輸入に依存している日本にとっての脅威は自然災害だけではありません。世
界市場における食料の供給不足につけ込んで国を背景に持つ巨大企業が価格を吊り上げること
も脅威です。
アメリカは、自国の農業保護(輸出補助金)制度は残したまま、他国には「安く売ってあげる
から非効率な農業はやめたほうがいいよ」と言って、世界の農産物資の自由化と農業保護の削
減を進めてきました。
国による補助金で安く農産物を売り、他国の農業を縮小させてきたのです。
こうして、基礎食料(コメ、小麦、トウモロコシなどの穀物)の生産国が減り、アメリカ、カ
ナダ、オーストラリアなどの少数の農業大国に依存する市場構造になってしまったのです。
実際、2007年のオーストラリアなどの旱魃に加えて、アメリカのトウモロコシをバイオ燃
料にするため、2008年には世界的な品不足となり、価格は急騰し、カネを出しても買えな
い状況が発生しました。
鈴木氏は、この背景にはアメリカ政府の戦略があったとしています。すなわち、アメリカ政府
は輸出補助金の財政負担を軽減する方法を模索する中で、トウモロコシを国内でバイオ燃料と
して使えば輸出補助金は要らないし、価格は暴騰します。
アメリカ政府の目論見通り、2008年にはトウモロコシ価格は暴騰し、アメリカの生産者や
巨大企業は巨額の利益を得る一方、トウモロコシを重要な食料としている中南米諸国や、家畜
飼料として100%近く輸入に依存していた日本のような国は、大パニックに陥りました。
鈴木氏は、この苦い経験から日本政府は、主要農作物は自給する政策を推進すべきであったの
に、2008年の教訓は生かされず、今も危険な状態が続いていると警告しています。
トウモロコシとは別に、アメリカ政府は自国の農畜産物だけ輸出補助金を付けて安く輸出し、
他の国の生産を縮小させて(もっと露骨に言えば「潰して」)、アメリカへの依存を高めさせ、
やがて価格の高騰を待って利益を回収するという政策をずっと取り続けています。
言い換えるとアメリカは、自国だけは補助金で輸出価格を低くし、世界市場では他の国に自由
貿易を受け入れさせて市場を支配し、利益を得るという世界戦略で行動しています。
鈴木氏はこれを「節操なき貿易自由化」と呼んでいます。
日本もこれまで、半ばアメリカの圧力でかつて農水産物の自由化を飲まされてきました。農水
省官僚として仕事をしてきた鈴木氏は、こうしたアメリカのやり方に強い憤りをもっていると
同時に、日本は主要食料に関しては、一時的にコスト高になっても自給する方向を採るべきだ、
と主張しています。
鈴木氏には、日本国民が生き残るためには3つの安全保障が必要だ、と考えが基本にあります。
すなわち、軍事的安全保障、エネルギーの安全保障、そして、食料の安全保障(通称「食料安
保」)です。
ところが、食料の安全保障を根底から脅かす事態が静かに、しかし着実に進行しています。そ
れが、第3章で検討する、外部の巨大アグリビジネス企業(種、農産物の売買、肥料、農薬な
ど一括して扱う企業)による種の支配です。
―危機の本質―
ウクライナ戦争は、思いもかけなかった余波を世界の各地域に引き起こしています。
石油と天然ガスのエネルギー価格が急騰しています。メディアではエネルギー問題ほど大きく
報じていませんが、食料及び食料生産にも大きな影響を与えています。
これまで日本は、工業製品を輸出して、食料は輸入すればよい、という大雑把な方針の下で、
食料価格について、まったく危機感を持っていませんでした。
しかし、ここで紹介する『農業消滅』(平凡社新書、2021、239ページ)の著者、鈴木宣弘
(東京大学大学院農学科)は、これまでも一貫して日本の農業と食料の危機について、さま
ざまな場所で警告してきました。
実際、本書に書かれている内容を正面から受け止めると、現在日本が抱えている危機の実態
がみえてきます。
著者の鈴木氏は東大農学部を卒業後の農林水産省に入省し、そこで15年勤務した後、九州
大学と経て現職に就き現在に至ります。経歴からも分かるように、農業に関するプロ中のプ
ロです。
まず本書の構成を示しておきます。
はじめに
序章 飢餓は他人事ではない
第1章 2008年の教訓は生かされない
第2章 種を制するものは世界を制す
第3章 自由化と買い叩きにあう日本の農業
第4章 危ない食料は日本向け
第5章 安全保障の要としての国家戦略の欠如
終章 日本の未来は守れるか
おわりに
「はじめに」と第1章からみてみよう。ここは本書全体を見通す問題が提示されています。
それは、食料自給率の低下の問題です。現在食料自給率がカロリーベースで38%、農水省
の試算によれば、2035年には、実質的な自給率は酪農では12%、コメで11%、青果物や
畜産では1~4%に落ちてしまう。
ここで注意しなければならないのは、日本の場合、飼料や種を輸入している場合、たとえ生
産物が日本産であっても純粋に国産物とは言えない、という点である。
たとえば、鶏卵の場合、鶏のヒナはすでに100%に近いので、厳密に言えば自給率は0%
です。
自給率80%の野菜も、その種の90%は輸入なのです。
なお、コメも生産高でみる限り自給率は106%ですが、これも種が全て国産の場合です。
最近の政府の政策(種子法の廃止など)により、今後は種籾も輸入品が多くなることが想定
されるので(農水省では自給率は10%と想定)実質的にはコメの自給率は11%になって
しまいます。
政府は際限ない貿易自由化を進めており、国産の農産物が買いたたかれています。
たとえば、主食であるコメにいてみると、2022年にコメ農家に支払われる農協の概算金
は、1俵(60キログラム)が1万円を切る可能性が指摘されています。
しかし、実際の生産費はどんなに頑張っても1俵当たり1万円以上かかっているのです。これ
では農家の存続さえ危うくなり、農業を続ける意欲を失わせます。
アメリカなどでは、政府が農産物を直接買い上げて、コロナ禍で生活が苦しくなった人々や
子供たちに配給するという人道支援をおこなっています。
鈴木氏は日本でもフードバンクや子供食堂などの支援のため政府買い入れをしないのか、と
政府に注文をつけています。しかし、一旦、備蓄米以上のコメを買わないと決めて以上、断
固として買わない、という政府に対して次のように手厳しく批判しています。
すなわち、「上から目線で『コメを作付けするな』と言っている場合ではないのだ。政府の
メンツを保つためだけのために、苦しんでいる国民や農家を放置する政府・行政の存在意義
が厳しく問われている、と。
農家の高齢化による生産者数の減少に加えて、生産意欲を失わせるような政府・行政の農政
のため、耕作放棄地が増え、主食のコメでさえ将来は自給できなくなる可能性が大いにあり
ます。
もし、種や家畜飼料が何らかの理由で輸入できなかったり価格が暴騰していたり(今日のト
ウモロコシや大豆のように)、2008年に起こった旱魃や、あるいは水害などで生産が大
きな打撃を受けると、本当に飢餓が発生しかねません。
この意味で、農業は国家の存亡にかかわる問題ですが、政府はこれまで本格的に農業を保護
育成する政策を採ってきませんでした。
それは、日本は工業立国で生きてゆくべきで製造業中心の国造りをしてきたからです。実は、
この方針が日本の食料問題を危うくする一つの大きな原因となっているのです。
第2章は、現実に日本が食料危機に陥る脅威について説明しています。
食料の3分の2を輸入に依存している日本にとっての脅威は自然災害だけではありません。世
界市場における食料の供給不足につけ込んで国を背景に持つ巨大企業が価格を吊り上げること
も脅威です。
アメリカは、自国の農業保護(輸出補助金)制度は残したまま、他国には「安く売ってあげる
から非効率な農業はやめたほうがいいよ」と言って、世界の農産物資の自由化と農業保護の削
減を進めてきました。
国による補助金で安く農産物を売り、他国の農業を縮小させてきたのです。
こうして、基礎食料(コメ、小麦、トウモロコシなどの穀物)の生産国が減り、アメリカ、カ
ナダ、オーストラリアなどの少数の農業大国に依存する市場構造になってしまったのです。
実際、2007年のオーストラリアなどの旱魃に加えて、アメリカのトウモロコシをバイオ燃
料にするため、2008年には世界的な品不足となり、価格は急騰し、カネを出しても買えな
い状況が発生しました。
鈴木氏は、この背景にはアメリカ政府の戦略があったとしています。すなわち、アメリカ政府
は輸出補助金の財政負担を軽減する方法を模索する中で、トウモロコシを国内でバイオ燃料と
して使えば輸出補助金は要らないし、価格は暴騰します。
アメリカ政府の目論見通り、2008年にはトウモロコシ価格は暴騰し、アメリカの生産者や
巨大企業は巨額の利益を得る一方、トウモロコシを重要な食料としている中南米諸国や、家畜
飼料として100%近く輸入に依存していた日本のような国は、大パニックに陥りました。
鈴木氏は、この苦い経験から日本政府は、主要農作物は自給する政策を推進すべきであったの
に、2008年の教訓は生かされず、今も危険な状態が続いていると警告しています。
トウモロコシとは別に、アメリカ政府は自国の農畜産物だけ輸出補助金を付けて安く輸出し、
他の国の生産を縮小させて(もっと露骨に言えば「潰して」)、アメリカへの依存を高めさせ、
やがて価格の高騰を待って利益を回収するという政策をずっと取り続けています。
言い換えるとアメリカは、自国だけは補助金で輸出価格を低くし、世界市場では他の国に自由
貿易を受け入れさせて市場を支配し、利益を得るという世界戦略で行動しています。
鈴木氏はこれを「節操なき貿易自由化」と呼んでいます。
日本もこれまで、半ばアメリカの圧力でかつて農水産物の自由化を飲まされてきました。農水
省官僚として仕事をしてきた鈴木氏は、こうしたアメリカのやり方に強い憤りをもっていると
同時に、日本は主要食料に関しては、一時的にコスト高になっても自給する方向を採るべきだ、
と主張しています。
鈴木氏には、日本国民が生き残るためには3つの安全保障が必要だ、と考えが基本にあります。
すなわち、軍事的安全保障、エネルギーの安全保障、そして、食料の安全保障(通称「食料安
保」)です。
ところが、食料の安全保障を根底から脅かす事態が静かに、しかし着実に進行しています。そ
れが、第3章で検討する、外部の巨大アグリビジネス企業(種、農産物の売買、肥料、農薬な
ど一括して扱う企業)による種の支配です。