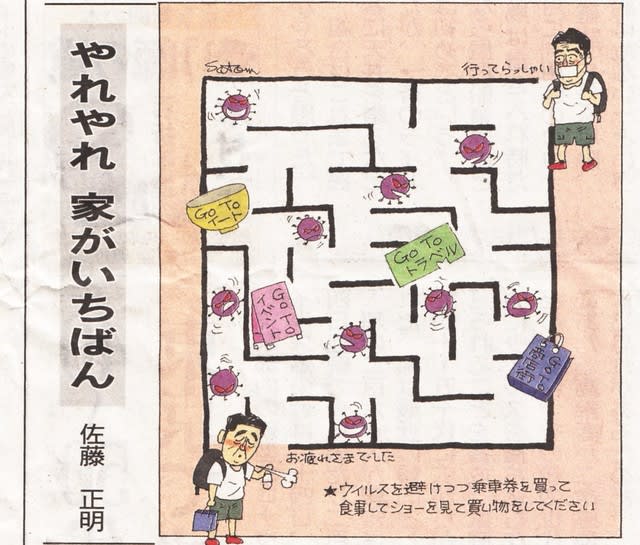新型コロナウイルス禍の意味論―「コロナと共に」とは?―
現在の新型コロナウイルス禍に関して、ずっと一つの疑問をもってきました。
それは、なぜ、今、世界中で新型コロナウイルスの感染者と死者が日々増え続けるコロナ禍
が発生しているのか、という疑問です。
もちろん、今回の新型コロナウイルスは、未知の新型ウイルスであるといえばそれまでです。
つまり、サーズやマーズのようにすぐに症状がでたり、エボラ出血熱のように感染者を直ち
に重症化させたり死に至らしめるタイプのウイルスならば、発症した患者とその周辺の人び
とを隔離してしまえば、比較的簡単に抑え込むことができます。
しかし新型コロナの場合、感染したばかりの数日は発症せず、したがって本人も周囲も無症
状のままで歩きまわり人と接触することで、ウイルスをまき散らしてしまいます。
そして、このウイルスの死亡率はそれほど高くはありません。このため、ヒトは少しみくび
って警戒心をゆるめてしまいます。
こうして時間を稼いでいる間に、ウイルスは、思う存分子孫を拡散することができることに
なります。
この意味で、新型ウイルスはヒトにとって、非常に皮肉で意地悪な性格の持ち主です。
ところで、武漢で大規模な新型コロナウイルスの大規模な発症が生じて1年経ちました。
この間、医者や科学者は総力を挙げてその正体を解明してきました。その結果、今では変異
したタイプも含めて、この新型ウイルスの遺伝子構造は完全ではないにしても、かなり解明
されつつあります。
しかし、問題は、正体は分かったが、ではコロナに感染した場合、どのように治療すればよ
いのか、その方法は今のところ見つかっていないことです。
すでにワクチンもいくつか開発され、緊急避難的に接種が始められていますが、その有効性
も安全性も十分に検証されていません。
もう一つの頼みは、治療薬です。今のところ有効かも知れないという程度の治療薬の候補は
いくつかありますが、まだ特効薬と言える決定打は出ていません。
そこで、「コロナと共に」あるいは「コロナとの共生・共存」(with corona)といった言葉が
時々メディアなどで見られます。
こういった言葉は、コロナウイルスは簡単に消滅することはないから、コロナとの共存を覚
悟しなければならない、という意味で使われる場合が多いと思います。
あるいは、「自然との共存」と同じ文脈で「コロナとの共存」という表現を使っているのか
もしれません。
コロナも人間も「自然」の一部ですから、「コロナとの共存」は間違いではないでしょう。
しかも、ウイルスという生物は、人類が登場するはるか昔からこの地球上に存在している、
いわば人類の大先輩、それに比べると人類は新参者です。
コロナウイルスに限らず、そもそもウイルスという生物がこの地球上に存在し続けていると
いうことは、そこで何らかの役割を果たしているからに違いありません。
たとえば、人間との関係でいえば、母体の中の胎児は父親の遺伝形質を半分もっており、母
親の免疫システム(リンパ球)はそれを“異物”と認識して攻撃してしまいます。そこで、こ
のリンパ球が胎児の血管に入り込むのを防いでいるのがウイルスでることが分かっています。
この他にも、このような例は無数にあるでしょう。もし、ウイルスが他の生物を攻撃し傷つ
けるだけなら、今日のように、無数の種類のウイルスは存在できないでしょう。
ここで、新型コロナウイルスを例に、ウイルスの立場に立って、彼らがどのようにして生き
残り、場合によっては増殖してきたのかを考えてみましょう。
まず、新型コロナウイルスも、生物として一定の環境の中で生存しています。この際、ウイ
ルスは、その生存を脅かす幾つもの“敵”との生存競争に勝たなければなりません。
その“敵”の一つは、同類のウイルスです。
コロナウイルスにはサーズ、マーズ、インフルエンザなどいくつかの種類があり、それらの
間での生存競争があります。今年はインフルエンザが例年の0.3%しか発生していません。こ
れは、新型コロナウイルスとの“闘い”でインフルエンザのウイルスが抑えられたからだと考
えられています。
さらに、新型コロナウイルスも、時間が経つにしたがって次々と変異してゆきます。しかし、
その中でも、環境に最も適応したタイプの変異種のウイルスだけが生存競争の“勝者”となっ
て、他のウイルスを駆逐してゆき、その時、その場所における支配的なウイルスとなってゆ
きます。
この「環境」の中には気温、湿度などの自然条件だけでなく、後に述べるように感染相手の
ヒトの免疫、医療(ウイルスに対する攻撃)、社会状況などあらゆる外部条件が含まれます。
以上を念頭に置いて、「コロナとの共存」という言葉の意味内容をもう一度考えてみたいと
思います。
ここまで見てきたように、ある生物が生き残るには、食うか食われるかの熾烈な自然界の闘
争に打ち勝たなければなりません。
今回の新型コロナウイルスも、一方でウイルス同士の戦いのほか、ヒトとの闘いにも勝たな
ければなりません。
ウイルスは自己増殖できないので、さまざまな障害を乗り越えてなんとかうまくヒトの体内
(細胞内)に入り込み、子孫の増殖を図らなければなりません。
まず、ウイルスがヒトの体内に入ると、免疫システムをすり抜けるために、細胞の入り口と
なる突起と自らの突起(いずれもタンパク質)を合わせてまんまと細胞内に入り込んでしま
います。
一旦、ヒトの細胞内に入り込むと、直ちに暴れまわるのではなく、しばらく無症状の状態を
続けるので、その間にヒトは感染に気が付かず動き回っている間に増殖します。
宿主となったヒトをすぐに死なせてしまうのは、そこで増殖が止まってしまうという意味で、
ウイルスの増殖戦略としては“失敗”なのです。
私は、かつて感染症の問題に関わっていたとき、エイズの専門家が、エイズ・ウイルスはヒ
トに感染してもすぐに殺さず、できる限り多くの人にウイルスを増殖させるという、とても
ずる賢い戦略で子孫を増やしている、と言った言葉を思い出します。
今回の新型コロナウイルスの場合、感染したヒトの多くは死なないまでも、さまざまな症状
に苦しめられます。その中で、体力や免疫力が弱まっている高齢者や基礎疾患を持っている
人が亡くなってしまいます。
今回の新型コロナウイルスの場合、まだ未知の部分があり、これまで人間はこれとの闘いで
絶対に打ち勝つ武器や方法を見出していません。
これからは、人間がワクチンとい武器を使ってウイルス退治に乗り出し始めているので、こ
れからがヒトとウイルスとの、もう一段階進んだ命を懸けた闘争となります。
その闘いがどれほどの期間続き、その結末がどうなるかは全く分かりません。ただ、結末の
一つの形は「共生」です。
たとえば、私たちの腸の中には無数の腸内細菌、たとえば大腸菌、がいます。今でこそ、こ
れらの細菌はヒトの体の一つのパーツとして、ヒトの生体を維持する上で一定の役割を果た
すようになっています。
しかし、ここに至るまでは、やはりヒトと大腸菌との間で食うか食われるかの闘争の歴史が
あって、長い時間をかけて徐々に妥協点を見つけ、お互いに殺すことなく共存する、共生関
係に落ち着いたのではないかと思われます。
私は「コロナとの共存」というのは、それほど簡単ではないと覚悟しています。
さて新型コロナウイルス禍の意味論という意味では、「なぜ、今?」という問いも重要です。
先ほど、ウイルスは生き残りをかけて、可能なら最大限の子孫繁栄のために与えられた環境
の中で最善の適応をする、と書きました。
その環境の中で、人間の側の変化も重要な要素です。たとえば、グローバリズムの中で人の
移動が地球規模で激しくなっていること、人口の増加、貧富の格差拡大、温暖化に表れる自
然環境の悪化、精神的な状況(特にストレス増加)、心臓病・糖尿病・脳・血管疾患・高血
圧など基礎疾患の増加、人間関係の変化、さらにヒトの基礎的な免疫力や抵抗力の変化(特
に低下)、などなど、さまざまな要因が関与しています。
現在、世界を覆っている暗い影、新型コロナウイルス禍の意味論を総合的に解読しようとす
るなら、これら人間社会のあらゆる場面を考える必要があるでしょう。
政府は、”人類がコロナに打ち勝った証として」オリンピックを何が何でも開催する勢いで、
無観客の競技も想定しているといいます。
しかし、もしコロナが消えていない場合には、”人類がコロナに敗北した証として無観客で
行う”、というブラック。ユーモアになってしまいます。
現在の新型コロナウイルス禍に関して、ずっと一つの疑問をもってきました。
それは、なぜ、今、世界中で新型コロナウイルスの感染者と死者が日々増え続けるコロナ禍
が発生しているのか、という疑問です。
もちろん、今回の新型コロナウイルスは、未知の新型ウイルスであるといえばそれまでです。
つまり、サーズやマーズのようにすぐに症状がでたり、エボラ出血熱のように感染者を直ち
に重症化させたり死に至らしめるタイプのウイルスならば、発症した患者とその周辺の人び
とを隔離してしまえば、比較的簡単に抑え込むことができます。
しかし新型コロナの場合、感染したばかりの数日は発症せず、したがって本人も周囲も無症
状のままで歩きまわり人と接触することで、ウイルスをまき散らしてしまいます。
そして、このウイルスの死亡率はそれほど高くはありません。このため、ヒトは少しみくび
って警戒心をゆるめてしまいます。
こうして時間を稼いでいる間に、ウイルスは、思う存分子孫を拡散することができることに
なります。
この意味で、新型ウイルスはヒトにとって、非常に皮肉で意地悪な性格の持ち主です。
ところで、武漢で大規模な新型コロナウイルスの大規模な発症が生じて1年経ちました。
この間、医者や科学者は総力を挙げてその正体を解明してきました。その結果、今では変異
したタイプも含めて、この新型ウイルスの遺伝子構造は完全ではないにしても、かなり解明
されつつあります。
しかし、問題は、正体は分かったが、ではコロナに感染した場合、どのように治療すればよ
いのか、その方法は今のところ見つかっていないことです。
すでにワクチンもいくつか開発され、緊急避難的に接種が始められていますが、その有効性
も安全性も十分に検証されていません。
もう一つの頼みは、治療薬です。今のところ有効かも知れないという程度の治療薬の候補は
いくつかありますが、まだ特効薬と言える決定打は出ていません。
そこで、「コロナと共に」あるいは「コロナとの共生・共存」(with corona)といった言葉が
時々メディアなどで見られます。
こういった言葉は、コロナウイルスは簡単に消滅することはないから、コロナとの共存を覚
悟しなければならない、という意味で使われる場合が多いと思います。
あるいは、「自然との共存」と同じ文脈で「コロナとの共存」という表現を使っているのか
もしれません。
コロナも人間も「自然」の一部ですから、「コロナとの共存」は間違いではないでしょう。
しかも、ウイルスという生物は、人類が登場するはるか昔からこの地球上に存在している、
いわば人類の大先輩、それに比べると人類は新参者です。
コロナウイルスに限らず、そもそもウイルスという生物がこの地球上に存在し続けていると
いうことは、そこで何らかの役割を果たしているからに違いありません。
たとえば、人間との関係でいえば、母体の中の胎児は父親の遺伝形質を半分もっており、母
親の免疫システム(リンパ球)はそれを“異物”と認識して攻撃してしまいます。そこで、こ
のリンパ球が胎児の血管に入り込むのを防いでいるのがウイルスでることが分かっています。
この他にも、このような例は無数にあるでしょう。もし、ウイルスが他の生物を攻撃し傷つ
けるだけなら、今日のように、無数の種類のウイルスは存在できないでしょう。
ここで、新型コロナウイルスを例に、ウイルスの立場に立って、彼らがどのようにして生き
残り、場合によっては増殖してきたのかを考えてみましょう。
まず、新型コロナウイルスも、生物として一定の環境の中で生存しています。この際、ウイ
ルスは、その生存を脅かす幾つもの“敵”との生存競争に勝たなければなりません。
その“敵”の一つは、同類のウイルスです。
コロナウイルスにはサーズ、マーズ、インフルエンザなどいくつかの種類があり、それらの
間での生存競争があります。今年はインフルエンザが例年の0.3%しか発生していません。こ
れは、新型コロナウイルスとの“闘い”でインフルエンザのウイルスが抑えられたからだと考
えられています。
さらに、新型コロナウイルスも、時間が経つにしたがって次々と変異してゆきます。しかし、
その中でも、環境に最も適応したタイプの変異種のウイルスだけが生存競争の“勝者”となっ
て、他のウイルスを駆逐してゆき、その時、その場所における支配的なウイルスとなってゆ
きます。
この「環境」の中には気温、湿度などの自然条件だけでなく、後に述べるように感染相手の
ヒトの免疫、医療(ウイルスに対する攻撃)、社会状況などあらゆる外部条件が含まれます。
以上を念頭に置いて、「コロナとの共存」という言葉の意味内容をもう一度考えてみたいと
思います。
ここまで見てきたように、ある生物が生き残るには、食うか食われるかの熾烈な自然界の闘
争に打ち勝たなければなりません。
今回の新型コロナウイルスも、一方でウイルス同士の戦いのほか、ヒトとの闘いにも勝たな
ければなりません。
ウイルスは自己増殖できないので、さまざまな障害を乗り越えてなんとかうまくヒトの体内
(細胞内)に入り込み、子孫の増殖を図らなければなりません。
まず、ウイルスがヒトの体内に入ると、免疫システムをすり抜けるために、細胞の入り口と
なる突起と自らの突起(いずれもタンパク質)を合わせてまんまと細胞内に入り込んでしま
います。
一旦、ヒトの細胞内に入り込むと、直ちに暴れまわるのではなく、しばらく無症状の状態を
続けるので、その間にヒトは感染に気が付かず動き回っている間に増殖します。
宿主となったヒトをすぐに死なせてしまうのは、そこで増殖が止まってしまうという意味で、
ウイルスの増殖戦略としては“失敗”なのです。
私は、かつて感染症の問題に関わっていたとき、エイズの専門家が、エイズ・ウイルスはヒ
トに感染してもすぐに殺さず、できる限り多くの人にウイルスを増殖させるという、とても
ずる賢い戦略で子孫を増やしている、と言った言葉を思い出します。
今回の新型コロナウイルスの場合、感染したヒトの多くは死なないまでも、さまざまな症状
に苦しめられます。その中で、体力や免疫力が弱まっている高齢者や基礎疾患を持っている
人が亡くなってしまいます。
今回の新型コロナウイルスの場合、まだ未知の部分があり、これまで人間はこれとの闘いで
絶対に打ち勝つ武器や方法を見出していません。
これからは、人間がワクチンとい武器を使ってウイルス退治に乗り出し始めているので、こ
れからがヒトとウイルスとの、もう一段階進んだ命を懸けた闘争となります。
その闘いがどれほどの期間続き、その結末がどうなるかは全く分かりません。ただ、結末の
一つの形は「共生」です。
たとえば、私たちの腸の中には無数の腸内細菌、たとえば大腸菌、がいます。今でこそ、こ
れらの細菌はヒトの体の一つのパーツとして、ヒトの生体を維持する上で一定の役割を果た
すようになっています。
しかし、ここに至るまでは、やはりヒトと大腸菌との間で食うか食われるかの闘争の歴史が
あって、長い時間をかけて徐々に妥協点を見つけ、お互いに殺すことなく共存する、共生関
係に落ち着いたのではないかと思われます。
私は「コロナとの共存」というのは、それほど簡単ではないと覚悟しています。
さて新型コロナウイルス禍の意味論という意味では、「なぜ、今?」という問いも重要です。
先ほど、ウイルスは生き残りをかけて、可能なら最大限の子孫繁栄のために与えられた環境
の中で最善の適応をする、と書きました。
その環境の中で、人間の側の変化も重要な要素です。たとえば、グローバリズムの中で人の
移動が地球規模で激しくなっていること、人口の増加、貧富の格差拡大、温暖化に表れる自
然環境の悪化、精神的な状況(特にストレス増加)、心臓病・糖尿病・脳・血管疾患・高血
圧など基礎疾患の増加、人間関係の変化、さらにヒトの基礎的な免疫力や抵抗力の変化(特
に低下)、などなど、さまざまな要因が関与しています。
現在、世界を覆っている暗い影、新型コロナウイルス禍の意味論を総合的に解読しようとす
るなら、これら人間社会のあらゆる場面を考える必要があるでしょう。
政府は、”人類がコロナに打ち勝った証として」オリンピックを何が何でも開催する勢いで、
無観客の競技も想定しているといいます。
しかし、もしコロナが消えていない場合には、”人類がコロナに敗北した証として無観客で
行う”、というブラック。ユーモアになってしまいます。