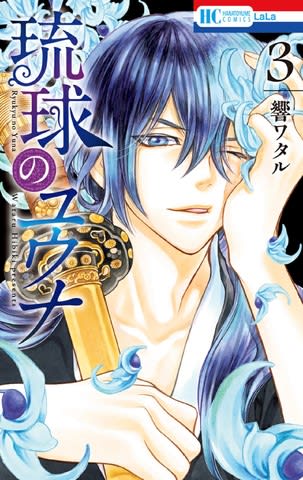Twitterではすでに発表していたのですが、
お知らせです。
本日、
『新装改訂版 琉球戦国列伝』
が発売になりました!!
本日県内書店配本、順次店頭販売(店舗によって多少時差があると思います)。
Amazonや楽天などへは、もう少し後になるようです。
どこの本屋さんでで買えますか!?って結構きかれるけど、
沖縄県内の主要本屋(TSUTAYA含む)なら大抵取り扱っています。
沖縄本(郷土本)コーナーに行ってみてね!
追記:
Amazon掲載されました!
https://amzn.to/37I8tV0
楽天ブックス、hontoなど主要書籍通販サイトも対応済み。
(旧)琉球戦国列伝が発売されてちょうど10年。
この10年の間に蓄積された最新の研究成果なども踏まえて
古琉球史 最新バージョンの
新装改訂版として出版することとなりました!
本の内容・構成は基本同じですが、
上里さんのコラムを複数追加!
そして全イラストが今回の改訂版に合わせた描きおろしです。
使いまわしのイラストはちびキャラも含めてゼロ。
新キャラ2名を含む63キャラ、74体を
完全リニューアルしております。
新キャラ、さーて誰でしょう!?
(始めてキャラ化した人と、お馴染みのアノ人ですよ)
前回のイラストでは敢えて「盛った」り、
ちょっと無理めなフィクション設定があったり、
阿麻和利も組踊衣装で描いたりしていましたが、
(もちろんそれには断り書きをいれていましたが)
今回は服飾やアイテムに関しては可能な限り「当時の姿」を追及。
(顔つきや体格はさすがに想像ですけどね)
シンプルだからと装飾を盛ったりせず、
”舞台衣装”である組踊衣装も一掃!
実際の発掘出土物も前回以上に盛り込んでいます♪
前作がフィクションビジュアル満載の『琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑』だったので
我ながら極端だなぁと思います(^^;)
最新の研究成果を元にを踏まえた結果、
キャラクターが旧作と180度変わった人物もいるんですよ(ふふふ)。
なので、旧作を持っている人も持っていない人も
どちらも楽しめる1冊だと思います♪
そして、もう一つの目玉は
15世紀の首里城イメージ図を掲載!
志魯・布里の乱後に建てられたとされている
首里城正殿イメージ図をプロローグに使っています。
首里城正殿がずっと同じ姿ではなかったことが
お分かりいただけるかなと思います。

ただ、この首里城イメージ図、
本では演出のための画像加工がされており
解説も少ししかありません。
そ・こ・で、お知らせPart2!
何がどう違うのか、その解説を付けた元図(画像加工前)と、
上里さんの15世紀首里城(城郭)概念図をセットにした
「15世紀首里城イメージ図(解説付き)」シートが
予約特典としてもらえます!
え?発売になったからもう遅いのでは?
と思われた方、ご安心下さい。
予約特典がもらえるのは2022. 3/11申し込み分まで有効。
ただし、
ボーダーインクのサイトから申し込んだ方に限ります
(書店ではできませんよ~)
送料無料です。
支払いが郵便振り込み(後払い)のみなので
少しお手間を取らせますが、
「15世紀首里城解説図がほしい!」
という方はこの機会をお見逃しなく!
 特典期間は終了しました
特典期間は終了しました
ボーダーインクからの購入リンクは
https://bit.ly/3pqFYkC
こちらからページプレビューや前書き、
目次などもチェックできます。
Amazon派の方はこちらから
https://amzn.to/37I8tV0
『新装改訂版 琉球戦国列伝』
A5判 オールカラー120ページ
定価1870円(本体1700円+税)
上里隆史[著・監修] 和々 [イラスト]
よろしくお願いします
なお、今回は本の「紙」を変えているので
印刷の発色がより原画に近くなりました!
ページ数は旧作と同じですが、
少し薄くなっているのは紙のせい。
量は変わらず、よりコンパクトになっていますよ~。











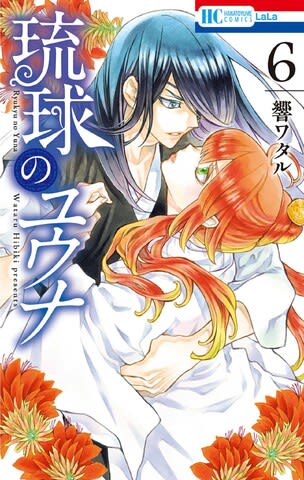
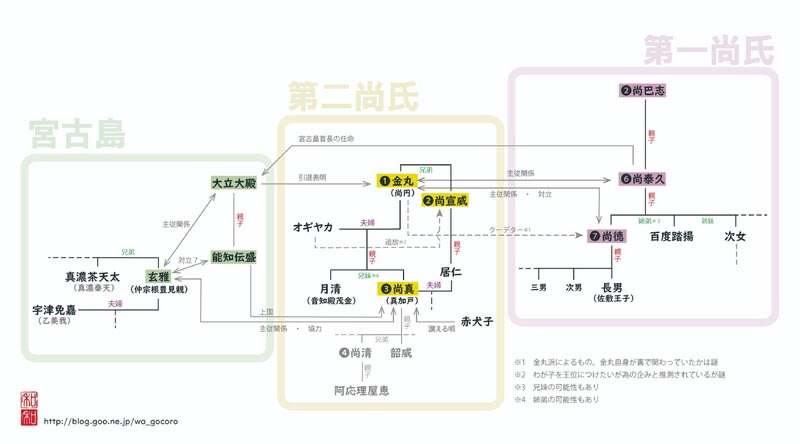
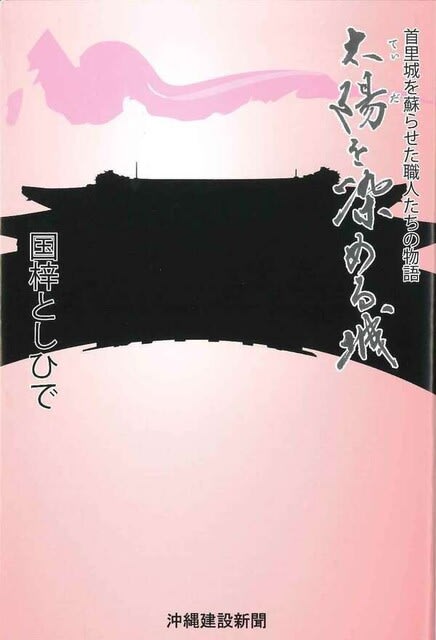




















 )
)

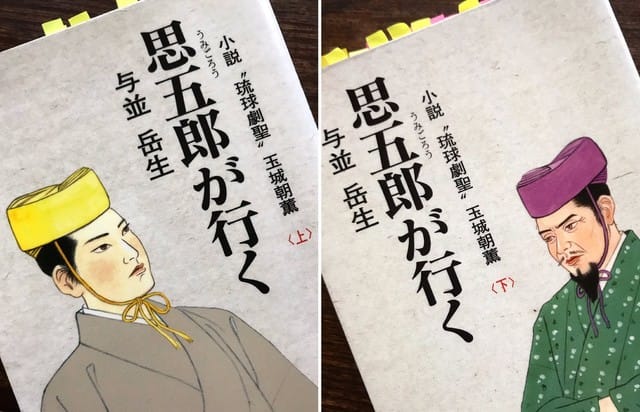
 (後悔)。
(後悔)。