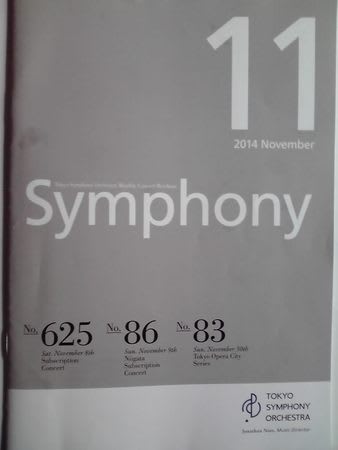10日(月)。土曜日に娘がモコタロの1カ月検診に行った時に、段ボール箱に代えて木製の”小屋”を買ってきました。わが家に来てから44日目を迎えたモコタロです 

段ボール箱の小屋で ホームレスも顔負けの姿でくつろぐモコタロ

新しいワンルーム・マンションで ちょっときゅうくつそうに暮らすモコタロ

 閑話休題
閑話休題 

昨日、息子の通う大学の就職進学懇談会が金町の新校舎で開かれたので参加しました 懇談会は4回に分けて実施していますが、これまでの2回で約1,000人が参加、今回の第3回目も約400人の参加とのことで、子どもの進路に対する父母の関心の高さが窺われます
懇談会は4回に分けて実施していますが、これまでの2回で約1,000人が参加、今回の第3回目も約400人の参加とのことで、子どもの進路に対する父母の関心の高さが窺われます
思えば息子は大学1年生の時は北海道長万部で学生寮に缶詰になって学生生活を送り、2年生になって千葉県の野田校舎に約2時間かけて通いました 3年生になってからは東京の金町に出来た新校舎まで1時間弱かけて通っています
3年生になってからは東京の金町に出来た新校舎まで1時間弱かけて通っています
息子の通う大学は夏目漱石の「坊ちゃん」の中に「東京物理学校」という名前で出てくる理科系の大学ですが、全体的に大学院への進学率が高く、また就職率も高いことがあらためて分かりました。とくに女子学生は引っ張りだこのようです
どういう方向に進むにしても、目標を定め、それを達成するため日々頑張ってほしいと思います

 閑話休題
閑話休題 

8日(土)に新日本フィルの定期演奏会と東京交響楽団の第625回定期演奏会を聴きましたが、昨日新日本フィルの模様を書いたので、今日は東響のコンサートの模様を書きます プログラムは①バルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」、②ベルリオーズ「幻想交響曲」で、①のヴァイオリン独奏は第5回仙台国際音楽コンクールヴァイオリン部門優勝者のリチャード・リン、指揮は飯森範親です
プログラムは①バルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」、②ベルリオーズ「幻想交響曲」で、①のヴァイオリン独奏は第5回仙台国際音楽コンクールヴァイオリン部門優勝者のリチャード・リン、指揮は飯森範親です

オケの配置は左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置ですが、コントラバスは後方に横並びに配置し、左サイドに打楽器陣、右サイドにハープがスタンバイします。コンマスは大谷康子です
1曲目のバルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」を聴くのは生演奏、CDを問わず初めてです CDを持っていないので予習が出来ない・・・これは最悪です
CDを持っていないので予習が出来ない・・・これは最悪です 4000枚のCDを持っているのにこの曲のCDは1枚もない。いかに好みが偏っているかの証拠です
4000枚のCDを持っているのにこの曲のCDは1枚もない。いかに好みが偏っているかの証拠です 今度タワーレコードに行く機会があったら買い求めようと思います。どれにしようか迷ったら”クラシック音楽の百科事典”NAXOSを買えば無難でしょう
今度タワーレコードに行く機会があったら買い求めようと思います。どれにしようか迷ったら”クラシック音楽の百科事典”NAXOSを買えば無難でしょう
この曲はハンガリーのヴァイオリニスト、ゾルターン・セーケイの依頼により作曲され1939年3月に初演されました
ソリストのリンが飯森とともに登場します。第1楽章はハープから入り、弦のピツィカートが加わり、ヴァイオリン・ソロが入ってきますが、なかなか抒情的で良い曲です 第2楽章はメロディーが美しい曲です。第3楽章を聴いていたら、何となく曲想がコルンゴルトのヴァイオリン協奏曲に似ているな、と思いました
第2楽章はメロディーが美しい曲です。第3楽章を聴いていたら、何となく曲想がコルンゴルトのヴァイオリン協奏曲に似ているな、と思いました 実はこれは逆で、バルトークの方が早く活躍していたのでコルンゴルトの方がバルトークに似ていると言うべきでしょう
実はこれは逆で、バルトークの方が早く活躍していたのでコルンゴルトの方がバルトークに似ていると言うべきでしょう 全体を通して、繰り返して聴くに堪える名曲だと思いました。バルトークというと敬遠しがちですが、この曲は聴きやすいと思います
全体を通して、繰り返して聴くに堪える名曲だと思いました。バルトークというと敬遠しがちですが、この曲は聴きやすいと思います
演奏後、何度もステージに呼び戻されたリンは拍手を制して、日本語で「みなさま、今夜はお越しいただき ありがとうございました( ) このあと、アンコールしますか?(
) このあと、アンコールしますか?( )少し休んでください(
)少し休んでください( )バッハ
)バッハ 」と言って調弦し、バッハの無伴奏ソナタ第2番から「アンダンテ」を演奏し静かな感動を呼びました
」と言って調弦し、バッハの無伴奏ソナタ第2番から「アンダンテ」を演奏し静かな感動を呼びました

休憩後はベルリオーズの「幻想交響曲」です。バルトークの100年前の曲です この曲は周知のように、ある芸術家の夢想を綴った物語です。ある芸術家というのはベルリオーズ自身で、夢想の相手はベルリオーズの最初の妻になった女優ハリエット・スミッソンという女性です
この曲は周知のように、ある芸術家の夢想を綴った物語です。ある芸術家というのはベルリオーズ自身で、夢想の相手はベルリオーズの最初の妻になった女優ハリエット・スミッソンという女性です
私はこの曲の中では第2楽章の「舞踏会」が一番好きです 優雅なワルツのメロディーが心地よく響きます。第3楽章「田園の風景」では、ステージ上のイングリッシュ・ホルンと舞台の右袖裏のオーボエとの対話が何とも言えない郷愁を誘います
優雅なワルツのメロディーが心地よく響きます。第3楽章「田園の風景」では、ステージ上のイングリッシュ・ホルンと舞台の右袖裏のオーボエとの対話が何とも言えない郷愁を誘います そして第4楽章「断頭台への行進」の勇ましい音楽に突入します。弦のピッツィカートに乗って奏でられるファゴットの軽快な演奏が忘れられません
そして第4楽章「断頭台への行進」の勇ましい音楽に突入します。弦のピッツィカートに乗って奏でられるファゴットの軽快な演奏が忘れられません アイ・ハブ・ネバー・ファゴットン
アイ・ハブ・ネバー・ファゴットン
そして第5楽章「魔女たちの夜宴」では舞台左袖裏で鳴らされる教会の鐘の音が印象的に響きます フルオーケストラによるフィナーレは圧巻でした
フルオーケストラによるフィナーレは圧巻でした