「築地」はもともと埋立地という意味で、東京築地は1658(万治元)年、木挽町(こびきちょう)の海側を埋め立てて土地を築いたことに由来する。この埋め立ては1657(明暦3)年の明暦の大火で焼失した浅草の江戸浅草御坊(現在の築地本願寺)の移転のために、佃島の住人によって造成された。
まだ機械のない時代の埋め立て作業は難しく、波も荒くなかなか堤防を築くことができなかった。そんな時、海から稲荷大神の御神体が流れてきてこれを祀ったところ、波は静まり、作業は順調に進んだという。御神体を祀った神社は「波除(なみよけ)稲荷神社」で、現在も築地市場の脇で静かに土地を守っている。
その後、浄土真宗の寺院や墓地が次々と建立され、周辺は寺町のようになった。ほかの地域は土佐藩山内家、松井松平家、白河藩松平家などの武家屋敷が立ち並んだ。
江戸時代末期、江戸幕府は軍事力増強を目的として築地に講武所を設け、後に海軍部門の軍艦操練所を設置、勝海舟らが教授として赴任した。
明治維新の後、大名屋敷や講武所跡は明治政府に接収され、太平洋戦争後に日本海軍が解散されるまで、主に海軍用地として使用された。過去に築地にあった帝国海軍関係施設は海軍本省、海軍兵学校、海軍軍医学校、海軍経理学校などがある。
1923年に発生した関東大震災では、築地一帯は焼け野原となった。帝都復興計画に基づいて晴海通りや新大橋通りなどの大規模な道路の建設と区画整理が行われ、それに伴い多くの寺院が移転していった。復興が一段落した1935(昭和10)年には、日本橋の魚河岸が築地の海軍用地に移転され、場外にも市場が形成された。
外国人居留地があった隣町、明石町から続けて築地を歩く。
●シーボルト胸像(あかつき公園) 住所:築地7-19-1
フィリップ・F・フォン・シーボルト(1796~1866)は、オランダの商館医として1823(文政6)年、長崎に到着、診療の傍ら長崎の鳴滝に塾を開くなどして活躍。1826(文政9)年、商館長と共に江戸へ向かい、日本橋の長崎屋に止宿し、出発するまでの間、江戸の蘭学者に面接指導し大きな影響を与えた。しかし、1828(文政11)年シーボルト事件が発生し、追放された。後に1859(安政6)年幕府顧問として再来日したが、2年後帰国しミュンヘンで没した。



北斎が描いた「長崎屋」甘酒横町界隈を歩いた際に写す
●濱野家住宅 住所:築地7-10-8
海産物を扱う商家として、1930(昭和5)年現在地に建てられた。
入口には、人見梁(はり)という背の高い梁がかけられ、軒は出桁造 という形式になっている。また、以前は、家に入ってすぐの場所が広い土間になっていて、鰹節 を入れた樽が山のように積まれていたという。



中央区の文化財に指定されているの売り物件になっている。家を間違えたかと確認したが、間違えなかった
●海運所跡東京税関発祥の地 住所:明石町14-19
江戸築地鉄砲洲(現明石町周辺)一帯の外国人居留地に税関業務を行う運上所を設置した。

碑は洒落た店の前にあった
●月島の渡し跡 所在地 中央区築地7-18
「月島の渡し」は、1892(明治25)年、南飯田町(現在の築地7-18)から月島(現、月島3-24)へ、手漕ぎの船で私設の有料渡船を開始したことに始まる。その後、月島への交通の重要性を考慮した東京市が渡船の市営化を決め、汽船曳舟2隻で交互運転を開始し、 渡賃も無料となった。
月島の渡しの渡船場は、当初、明石橋橋詰の南飯田町にあったが、東京市に移管された以降は、明石町(現在の明石町14)に渡船場を移設し、1940(昭和15)年に勝鬨橋が架橋されるまで、住民や工場へ通う人々の重要な交通機関として活躍した。

●勝鬨の渡し碑 住所:築地6-20(勝鬨橋橋畔)
1892(明治25)年、銀座・築地方面と月島との間には「月島の渡し」が開設されたが、月島側の発展に伴い、両地の交通はこれのみではさばけない状態であった。
1905(明治38)年、日露戦争の旅順要塞(中国北東部)陥落を契機に、京橋区民の有志が「勝鬨の渡し」と名付け渡船場を設置し、東京市に寄付した。当地にある石碑は、この時にたてられた。

●勝鬨橋とかちどき橋資料館 住所:築地6-19~勝どき1-13 、築地6-20
全長246m、中央部80mが上方へ70度はねあがる可動橋。当初は1日5回20分間づつ開いていたが、橋上の交通の激化と、東京港の整備により大型船の通過もなくなったため、1970(昭和45)年点検開橋以来、開閉は行っていない。


資料館は、橋を開くために使用していた変電所を改修し、この勝鬨橋をはじめ隅田川の橋についての資料や関連情報等を展示・公開している。
また、橋脚内見学ツアーを毎週木曜日に行っており、予約によって橋を開くための装置を見学できる。


●海軍経理学校跡 住所: 築地6-20
1874(明治7)年海軍会計学舎が芝山内天神谷に設けられたが、のちに幾変遷を経て1907(明治40)年ここが海軍経理学校となった。
その間1888(明治21)年校舎は築地に移されたが、その敷地は松平定信邸の浴恩園の跡地であたった。その付近は、明治時代は海軍の施設が多く、その一帯が海軍発祥の地とも称されている。戦後の海軍解体に伴い1945(昭和20)年9月におよそ70年の歴史を閉じた。

●本願寺の路地裏
築地6~7丁目は昭和期の面影ある建物が存在する。


●軍艦操練所跡 住所:築地6-20(築地市場駐車場)
現在、中央卸市場となっている一帯は、かつて江戸幕府の軍艦操練所があった。1857(安政4)年頭取(向井将監・勝海舟等が就任)以下、教授方出役・取調方等を任命。1864(元和元)年に焼失して、南隣りの松平安芸守の屋敷に仮移転し、1866(慶応2)年、海軍所と改めた。同年再び類焼して現在の浜離宮に移り、跡地には、日本最初の洋式ホテルである築地ホテル館が建った。

●築地ホテル館 住所:築地6-20(築地市場駐車場)
軍艦操練所跡に日本初のホテルが建設されたのは1868(明治元)年のことである。築地鉄砲洲に外国人居留地があったためである。
しかしながら、築地居留地はあまり発展しなかったため、次第にホテル館の経営も厳しくなり、1872(明治5)年、ホテル館は海軍の手に渡った。それから間もない1872(明治5)年に発生した銀座大火で類焼し、焼失した。わずか4年足らずの寿命だった。
設計者は横浜~新橋の停車場を設計した米国人ブリジェンヌ。施工には現清水建設の祖、二代目清水喜助氏があたった。外国人からは「江戸ホテル」と呼ばれた。
建物は、木造2階建て、かわら屋根になまこ壁、ベランダのある接客室には鎧戸(よろいど)付きの窓を設け、海に面した中庭には日本庭園を築く和洋折衷様式であった。この姿は錦絵に残っている。

●波除稲荷 住所:築地6-20-37
このブログの冒頭にも書いたように、海中に漂う稲荷神の像をみつけ、祀ったという。
起立は万治年間(1658~61)といわれている。「波除」の尊称もこの伝説に由来。



獅子殿に厄除天井大獅子が、反対側にはお羽黒獅子が祀られている
●魚河岸水神社遥拝堂 住所:築地5-2-1
1590(天正18)年徳川家康の江戸入城とともに、移住した日本橋魚河岸市場の開祖・森孫右衛門ら摂津国佃村、大和田村の漁師たちが、大漁・海上安全を祈願して「弥都波能売命(みずはのめのみこと)」を祀った「大市場交易神」がそのはじまりという。1901(明治34)年には神田明神の境内に「水神社」が建立され、日本橋市場は関東大震災以後築地に移転、現在地に遥拝堂が建立。以来築地市場の守護神として守られている。本殿は神田明神境内に祀られている。


魚河岸水神社関連 : 江戸総鎮守 神田明神
●海軍発祥の地 住所:築地5-2-1
魚河岸水神社遥拝堂の境内に、向かって左手前に「旗山」と刻まれた自然石の石碑が建っている。1872(明治5)年、ここに海軍省が置かれ, 浴恩園内の築山に海軍卿の旗が掲揚されたため旗山と呼ばれた。ここが、日本海軍発祥の地である。
旗山の碑は、1933(昭和8)年に築地市場が移転してきた時、元の位置から少し動かして現在の場所に移ったといわれる。

●築地魚市場 住所:築地5-2-1
もともとこの地は、江戸時代中期の陸奥白川藩主松平定信は、老中の職にあって寛政の改革(1787~93)で幕政の建て直しを行ったが、老後に将軍からこの土地を拝領した。
当時この地は東京湾に臨み風光明媚で林泉の美に富み、「浴恩園」と名付けて定信は、好んだという。

松平定信関連 : 松平定信の墓所 霊願寺
また、この地は、築地本願寺を中心に58ヶ寺もが並ぶ寺町でもあった。
関東大震災で焼失してからは、寺の維持も困難になり、大半が郊外へ移転。
さらに、日本橋の魚河岸が海軍用地だったところに移転して築地市場ができると、それに付随して商店が続々と入り込んで、現在の場外市場ができた。

●築地川南支川 門跡橋 住所:築地3(晴海通り善林寺山門付近)
江戸時代、この界隈の土地が造成され、海から陸になった際に埋め残された部分が築地川となったと考えられる。
銀座から隅田川にいたる一帯には、かつて水路(運河)が縦横に走っていた。築地市場周囲にも築地川東支川と築地川南支川などが流れていたが、この2つの水路は1960(昭和35)年から徐々に埋め立てられ、1995(平成7)年までに完全に姿を消し、その一部は築地川公園となっている。
当時の遺構のひとつ「門跡橋」の橋柱。門跡とは本願寺に因んだ名前と思われる。ほかにも「小田原橋」などの橋柱が残っている。


門跡橋 備前橋


築地川公園
●築地本願寺 住所: 築地3-15-1
京都の浄土真宗西本願寺の東京別院。 1617(元和3)年に第十二世准如上人が横山町に創建したが、明暦の大火で焼失、現在地に移った。
境内には、森孫右衛門供養塔が本堂に向かって左手の道路沿いにある。
この供養塔は1861(文久元)年森孫右衛門の二百年忌に建てられており、供養塔の右側面には、佃島の漁師と徳川家との係わりが、また左側面には、1644(正保元)年に築かれた佃島の成り立ちなどが刻まれている。
森孫右衛門は摂津国西成郡佃村(現大阪市西淀川区佃)から江戸に下り、徳川家の食膳に供する白魚御用を務めたといわれている。
また、江戸時代以来、佃島を築き、日本橋魚河岸のもととなる店を開いた人物とも、伝えられている。
そのほか、九条武子歌碑、赤穂義士間新六供養塔、画僧酒井抱一の墓、芭蕉句碑などがある。
その日は丁度、講堂でパイプオルガンによるコンサートが行われていて、参拝客で一杯であった。結婚式も行われるという。
建物は、関東大震災後、1934(昭和9)年古代インド様式となった。


森孫右衛門(左)と間新六の供養塔
●築地小劇場跡 築地2-11(築地NTTビル)
1924(大正13)年、歌舞伎の伝統から離れた写実的演劇を目指す小山内薫、土方与志らにより建てられた近代演劇史上記念すべき劇場あった。
劇場の面積は100坪弱、平屋建てで、客席は400~500席。電気を用いた世界初の照明室を備えていた。天井が高く、可動舞台を備えていた。
高度な照明設備と優れた舞台を備えていたため、演劇の実験室としての役割を果たした。


●桂川甫周屋敷跡 住所: 築地1-10-5
桂川家は代々、幕府の奥医師としてこの地に住んだ。四代目甫周(ほしゅう)は杉田玄白らと「解体新書」の翻訳に参加。後に外科術を学んで幕府医官となった。また、外国事情にも精通し、「魯志亜志」などの著者もある。

●活字発祥の地 住所:築地1-12
1873(明治6)年平野富二(1846年~92)がこの地に長崎新塾出張活版製作所(後の東京築地活版製造所)を興し、活字だけでなく活版印刷機械やその付属器具をも制作販売した。

●采女ヶ原(万年橋西交差点の北西一角 国立ガンセンターの北)
采女橋のあたりに采女ヶ原馬場があった。
ここは、1724(享保9)年までは伊予今治藩主松平采女正定基(うねめのしょうさだもと)の屋敷があったところで、焼失し、のち火除地も兼ねて馬場となり、明治まで残っていた。
幕府の軍役規定では、200石以上の旗本などは、太平の世になっても、馬術の訓練が義務づけられていた。しかしながら生活にも困窮し、馬など飼うことができぬ貧困武士に馬をレンタルする馬場が采女ヶ原にあったと最近読んだ本に書かれていた。馬場周辺には茶屋や見世物小屋まで出来て賑やかだったという。そんな情景は鬼平犯科帳にも登場しているようだ。
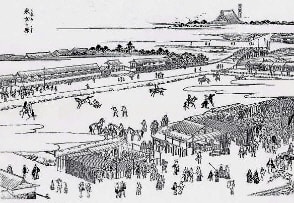

●采女橋 住所:築地4/銀座5・銀座6(みゆき通り)
江戸時代にこの辺りに屋敷を構えていた、紀伊徳川家筋の旗本 松平采女正 に由来するという。
なお、「釆女橋」は別名「二之橋」とか「矢の橋」とも呼ばれていた。
現在の采女橋は、銀座五丁目と六丁目の境を走るみゆき通りが、築地四丁目との間で首都高速道路を渡る橋である。


●新橋演舞場 住所:銀座6-18(釆女橋公園となり)
1925(大正14)年に新橋芸者衆のための演舞場として開場したもので、その年の4月に京都祇園の「都おどり」に対抗して演じられた「東おどり」が、その柿落し(こけらおとし・初舞台)であったという。
現在は「歌舞伎」や「松竹新喜劇」なども興行されている。
その以前は、松井松平家上屋敷(三河松井家)があった。

●海軍兵学寮跡 住所:築地5-1-1
海軍士官の養成校だった海軍兵学寮は、1872(明治2)年築地の藩邸跡に海軍操練所として誕生した。翌年海軍兵学寮と改め1879(明治9)年海軍兵学校と改称し、明治21年広島県江田島に移転。1934(昭和9)年旧地を記念するためこの碑を建立。

海軍軍医学校は、1873(明治6)年海軍病院付属学舎として創立。1880(明治13)年に廃校となるが、1882(明治15)年に海軍医務局学舎として芝に再興され、1889(明治22年)に海軍軍医学校と改称された。さらに1908(明治41)年に築地に移転され、1929(昭和4)年に築地五丁目に新築移転され、現在敷地は国立がん研究センター中央病院となっている。
この碑は、がん研究センターの首都高側の敷地に置かれている。
その他ここは、「運動会発祥の地」や「サッカー発祥の地」でもある。
何もない海から、寺町、海軍関係施設地へ、そして築地市場へと様々な顔に、「築地」は変化して行った。そして現在の築地市場も豊洲への平成27年度移転計画があって、またまた新しい顔に変化して行くようだ。どんな顔になるのだろう。これからも時代がデザインしていく。
まだまだ散策は続き、次は浜離宮恩賜公園に向かう。
関連 : 外国人居留地・明石町を歩く
将軍様のお鷹場だった浜離宮
まだ機械のない時代の埋め立て作業は難しく、波も荒くなかなか堤防を築くことができなかった。そんな時、海から稲荷大神の御神体が流れてきてこれを祀ったところ、波は静まり、作業は順調に進んだという。御神体を祀った神社は「波除(なみよけ)稲荷神社」で、現在も築地市場の脇で静かに土地を守っている。
その後、浄土真宗の寺院や墓地が次々と建立され、周辺は寺町のようになった。ほかの地域は土佐藩山内家、松井松平家、白河藩松平家などの武家屋敷が立ち並んだ。
江戸時代末期、江戸幕府は軍事力増強を目的として築地に講武所を設け、後に海軍部門の軍艦操練所を設置、勝海舟らが教授として赴任した。
明治維新の後、大名屋敷や講武所跡は明治政府に接収され、太平洋戦争後に日本海軍が解散されるまで、主に海軍用地として使用された。過去に築地にあった帝国海軍関係施設は海軍本省、海軍兵学校、海軍軍医学校、海軍経理学校などがある。
1923年に発生した関東大震災では、築地一帯は焼け野原となった。帝都復興計画に基づいて晴海通りや新大橋通りなどの大規模な道路の建設と区画整理が行われ、それに伴い多くの寺院が移転していった。復興が一段落した1935(昭和10)年には、日本橋の魚河岸が築地の海軍用地に移転され、場外にも市場が形成された。
外国人居留地があった隣町、明石町から続けて築地を歩く。
●シーボルト胸像(あかつき公園) 住所:築地7-19-1
フィリップ・F・フォン・シーボルト(1796~1866)は、オランダの商館医として1823(文政6)年、長崎に到着、診療の傍ら長崎の鳴滝に塾を開くなどして活躍。1826(文政9)年、商館長と共に江戸へ向かい、日本橋の長崎屋に止宿し、出発するまでの間、江戸の蘭学者に面接指導し大きな影響を与えた。しかし、1828(文政11)年シーボルト事件が発生し、追放された。後に1859(安政6)年幕府顧問として再来日したが、2年後帰国しミュンヘンで没した。



北斎が描いた「長崎屋」甘酒横町界隈を歩いた際に写す
●濱野家住宅 住所:築地7-10-8
海産物を扱う商家として、1930(昭和5)年現在地に建てられた。
入口には、人見梁(はり)という背の高い梁がかけられ、軒は出桁造 という形式になっている。また、以前は、家に入ってすぐの場所が広い土間になっていて、鰹節 を入れた樽が山のように積まれていたという。



中央区の文化財に指定されているの売り物件になっている。家を間違えたかと確認したが、間違えなかった
●海運所跡東京税関発祥の地 住所:明石町14-19
江戸築地鉄砲洲(現明石町周辺)一帯の外国人居留地に税関業務を行う運上所を設置した。

碑は洒落た店の前にあった
●月島の渡し跡 所在地 中央区築地7-18
「月島の渡し」は、1892(明治25)年、南飯田町(現在の築地7-18)から月島(現、月島3-24)へ、手漕ぎの船で私設の有料渡船を開始したことに始まる。その後、月島への交通の重要性を考慮した東京市が渡船の市営化を決め、汽船曳舟2隻で交互運転を開始し、 渡賃も無料となった。
月島の渡しの渡船場は、当初、明石橋橋詰の南飯田町にあったが、東京市に移管された以降は、明石町(現在の明石町14)に渡船場を移設し、1940(昭和15)年に勝鬨橋が架橋されるまで、住民や工場へ通う人々の重要な交通機関として活躍した。

●勝鬨の渡し碑 住所:築地6-20(勝鬨橋橋畔)
1892(明治25)年、銀座・築地方面と月島との間には「月島の渡し」が開設されたが、月島側の発展に伴い、両地の交通はこれのみではさばけない状態であった。
1905(明治38)年、日露戦争の旅順要塞(中国北東部)陥落を契機に、京橋区民の有志が「勝鬨の渡し」と名付け渡船場を設置し、東京市に寄付した。当地にある石碑は、この時にたてられた。

●勝鬨橋とかちどき橋資料館 住所:築地6-19~勝どき1-13 、築地6-20
全長246m、中央部80mが上方へ70度はねあがる可動橋。当初は1日5回20分間づつ開いていたが、橋上の交通の激化と、東京港の整備により大型船の通過もなくなったため、1970(昭和45)年点検開橋以来、開閉は行っていない。


資料館は、橋を開くために使用していた変電所を改修し、この勝鬨橋をはじめ隅田川の橋についての資料や関連情報等を展示・公開している。
また、橋脚内見学ツアーを毎週木曜日に行っており、予約によって橋を開くための装置を見学できる。


●海軍経理学校跡 住所: 築地6-20
1874(明治7)年海軍会計学舎が芝山内天神谷に設けられたが、のちに幾変遷を経て1907(明治40)年ここが海軍経理学校となった。
その間1888(明治21)年校舎は築地に移されたが、その敷地は松平定信邸の浴恩園の跡地であたった。その付近は、明治時代は海軍の施設が多く、その一帯が海軍発祥の地とも称されている。戦後の海軍解体に伴い1945(昭和20)年9月におよそ70年の歴史を閉じた。

●本願寺の路地裏
築地6~7丁目は昭和期の面影ある建物が存在する。


●軍艦操練所跡 住所:築地6-20(築地市場駐車場)
現在、中央卸市場となっている一帯は、かつて江戸幕府の軍艦操練所があった。1857(安政4)年頭取(向井将監・勝海舟等が就任)以下、教授方出役・取調方等を任命。1864(元和元)年に焼失して、南隣りの松平安芸守の屋敷に仮移転し、1866(慶応2)年、海軍所と改めた。同年再び類焼して現在の浜離宮に移り、跡地には、日本最初の洋式ホテルである築地ホテル館が建った。

●築地ホテル館 住所:築地6-20(築地市場駐車場)
軍艦操練所跡に日本初のホテルが建設されたのは1868(明治元)年のことである。築地鉄砲洲に外国人居留地があったためである。
しかしながら、築地居留地はあまり発展しなかったため、次第にホテル館の経営も厳しくなり、1872(明治5)年、ホテル館は海軍の手に渡った。それから間もない1872(明治5)年に発生した銀座大火で類焼し、焼失した。わずか4年足らずの寿命だった。
設計者は横浜~新橋の停車場を設計した米国人ブリジェンヌ。施工には現清水建設の祖、二代目清水喜助氏があたった。外国人からは「江戸ホテル」と呼ばれた。
建物は、木造2階建て、かわら屋根になまこ壁、ベランダのある接客室には鎧戸(よろいど)付きの窓を設け、海に面した中庭には日本庭園を築く和洋折衷様式であった。この姿は錦絵に残っている。

●波除稲荷 住所:築地6-20-37
このブログの冒頭にも書いたように、海中に漂う稲荷神の像をみつけ、祀ったという。
起立は万治年間(1658~61)といわれている。「波除」の尊称もこの伝説に由来。



獅子殿に厄除天井大獅子が、反対側にはお羽黒獅子が祀られている
●魚河岸水神社遥拝堂 住所:築地5-2-1
1590(天正18)年徳川家康の江戸入城とともに、移住した日本橋魚河岸市場の開祖・森孫右衛門ら摂津国佃村、大和田村の漁師たちが、大漁・海上安全を祈願して「弥都波能売命(みずはのめのみこと)」を祀った「大市場交易神」がそのはじまりという。1901(明治34)年には神田明神の境内に「水神社」が建立され、日本橋市場は関東大震災以後築地に移転、現在地に遥拝堂が建立。以来築地市場の守護神として守られている。本殿は神田明神境内に祀られている。


魚河岸水神社関連 : 江戸総鎮守 神田明神
●海軍発祥の地 住所:築地5-2-1
魚河岸水神社遥拝堂の境内に、向かって左手前に「旗山」と刻まれた自然石の石碑が建っている。1872(明治5)年、ここに海軍省が置かれ, 浴恩園内の築山に海軍卿の旗が掲揚されたため旗山と呼ばれた。ここが、日本海軍発祥の地である。
旗山の碑は、1933(昭和8)年に築地市場が移転してきた時、元の位置から少し動かして現在の場所に移ったといわれる。

●築地魚市場 住所:築地5-2-1
もともとこの地は、江戸時代中期の陸奥白川藩主松平定信は、老中の職にあって寛政の改革(1787~93)で幕政の建て直しを行ったが、老後に将軍からこの土地を拝領した。
当時この地は東京湾に臨み風光明媚で林泉の美に富み、「浴恩園」と名付けて定信は、好んだという。

松平定信関連 : 松平定信の墓所 霊願寺
また、この地は、築地本願寺を中心に58ヶ寺もが並ぶ寺町でもあった。
関東大震災で焼失してからは、寺の維持も困難になり、大半が郊外へ移転。
さらに、日本橋の魚河岸が海軍用地だったところに移転して築地市場ができると、それに付随して商店が続々と入り込んで、現在の場外市場ができた。

●築地川南支川 門跡橋 住所:築地3(晴海通り善林寺山門付近)
江戸時代、この界隈の土地が造成され、海から陸になった際に埋め残された部分が築地川となったと考えられる。
銀座から隅田川にいたる一帯には、かつて水路(運河)が縦横に走っていた。築地市場周囲にも築地川東支川と築地川南支川などが流れていたが、この2つの水路は1960(昭和35)年から徐々に埋め立てられ、1995(平成7)年までに完全に姿を消し、その一部は築地川公園となっている。
当時の遺構のひとつ「門跡橋」の橋柱。門跡とは本願寺に因んだ名前と思われる。ほかにも「小田原橋」などの橋柱が残っている。


門跡橋 備前橋


築地川公園
●築地本願寺 住所: 築地3-15-1
京都の浄土真宗西本願寺の東京別院。 1617(元和3)年に第十二世准如上人が横山町に創建したが、明暦の大火で焼失、現在地に移った。
境内には、森孫右衛門供養塔が本堂に向かって左手の道路沿いにある。
この供養塔は1861(文久元)年森孫右衛門の二百年忌に建てられており、供養塔の右側面には、佃島の漁師と徳川家との係わりが、また左側面には、1644(正保元)年に築かれた佃島の成り立ちなどが刻まれている。
森孫右衛門は摂津国西成郡佃村(現大阪市西淀川区佃)から江戸に下り、徳川家の食膳に供する白魚御用を務めたといわれている。
また、江戸時代以来、佃島を築き、日本橋魚河岸のもととなる店を開いた人物とも、伝えられている。
そのほか、九条武子歌碑、赤穂義士間新六供養塔、画僧酒井抱一の墓、芭蕉句碑などがある。
その日は丁度、講堂でパイプオルガンによるコンサートが行われていて、参拝客で一杯であった。結婚式も行われるという。
建物は、関東大震災後、1934(昭和9)年古代インド様式となった。


森孫右衛門(左)と間新六の供養塔
●築地小劇場跡 築地2-11(築地NTTビル)
1924(大正13)年、歌舞伎の伝統から離れた写実的演劇を目指す小山内薫、土方与志らにより建てられた近代演劇史上記念すべき劇場あった。
劇場の面積は100坪弱、平屋建てで、客席は400~500席。電気を用いた世界初の照明室を備えていた。天井が高く、可動舞台を備えていた。
高度な照明設備と優れた舞台を備えていたため、演劇の実験室としての役割を果たした。


●桂川甫周屋敷跡 住所: 築地1-10-5
桂川家は代々、幕府の奥医師としてこの地に住んだ。四代目甫周(ほしゅう)は杉田玄白らと「解体新書」の翻訳に参加。後に外科術を学んで幕府医官となった。また、外国事情にも精通し、「魯志亜志」などの著者もある。

●活字発祥の地 住所:築地1-12
1873(明治6)年平野富二(1846年~92)がこの地に長崎新塾出張活版製作所(後の東京築地活版製造所)を興し、活字だけでなく活版印刷機械やその付属器具をも制作販売した。

●采女ヶ原(万年橋西交差点の北西一角 国立ガンセンターの北)
采女橋のあたりに采女ヶ原馬場があった。
ここは、1724(享保9)年までは伊予今治藩主松平采女正定基(うねめのしょうさだもと)の屋敷があったところで、焼失し、のち火除地も兼ねて馬場となり、明治まで残っていた。
幕府の軍役規定では、200石以上の旗本などは、太平の世になっても、馬術の訓練が義務づけられていた。しかしながら生活にも困窮し、馬など飼うことができぬ貧困武士に馬をレンタルする馬場が采女ヶ原にあったと最近読んだ本に書かれていた。馬場周辺には茶屋や見世物小屋まで出来て賑やかだったという。そんな情景は鬼平犯科帳にも登場しているようだ。
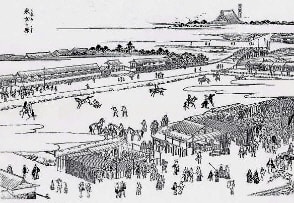

●采女橋 住所:築地4/銀座5・銀座6(みゆき通り)
江戸時代にこの辺りに屋敷を構えていた、紀伊徳川家筋の旗本 松平采女正 に由来するという。
なお、「釆女橋」は別名「二之橋」とか「矢の橋」とも呼ばれていた。
現在の采女橋は、銀座五丁目と六丁目の境を走るみゆき通りが、築地四丁目との間で首都高速道路を渡る橋である。


●新橋演舞場 住所:銀座6-18(釆女橋公園となり)
1925(大正14)年に新橋芸者衆のための演舞場として開場したもので、その年の4月に京都祇園の「都おどり」に対抗して演じられた「東おどり」が、その柿落し(こけらおとし・初舞台)であったという。
現在は「歌舞伎」や「松竹新喜劇」なども興行されている。
その以前は、松井松平家上屋敷(三河松井家)があった。

●海軍兵学寮跡 住所:築地5-1-1
海軍士官の養成校だった海軍兵学寮は、1872(明治2)年築地の藩邸跡に海軍操練所として誕生した。翌年海軍兵学寮と改め1879(明治9)年海軍兵学校と改称し、明治21年広島県江田島に移転。1934(昭和9)年旧地を記念するためこの碑を建立。

海軍軍医学校は、1873(明治6)年海軍病院付属学舎として創立。1880(明治13)年に廃校となるが、1882(明治15)年に海軍医務局学舎として芝に再興され、1889(明治22年)に海軍軍医学校と改称された。さらに1908(明治41)年に築地に移転され、1929(昭和4)年に築地五丁目に新築移転され、現在敷地は国立がん研究センター中央病院となっている。
この碑は、がん研究センターの首都高側の敷地に置かれている。
その他ここは、「運動会発祥の地」や「サッカー発祥の地」でもある。
何もない海から、寺町、海軍関係施設地へ、そして築地市場へと様々な顔に、「築地」は変化して行った。そして現在の築地市場も豊洲への平成27年度移転計画があって、またまた新しい顔に変化して行くようだ。どんな顔になるのだろう。これからも時代がデザインしていく。
まだまだ散策は続き、次は浜離宮恩賜公園に向かう。
関連 : 外国人居留地・明石町を歩く
将軍様のお鷹場だった浜離宮
























