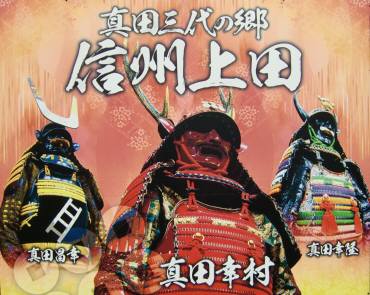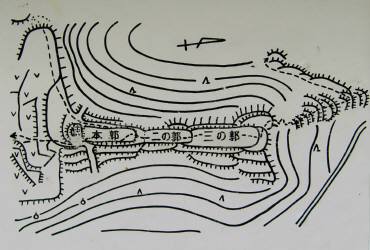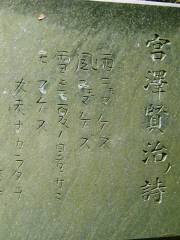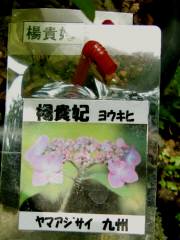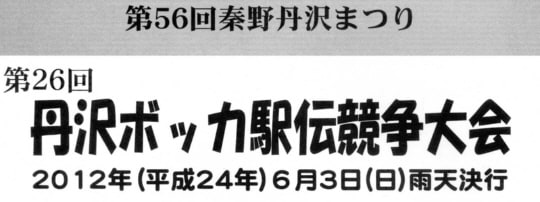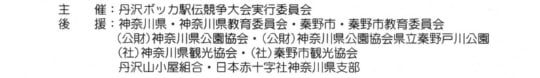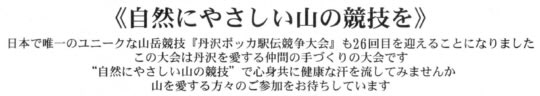地井武雄さんの訃報を聞き、驚きでいっぱいである。
健康を回復して「皆さ~ん! 最近、歩いていますか~!?」とすぐにでも「ちい散歩」に再登場すると思っていたのに残念でならない。
地井さんが体調不良で1月末に検査入院して「ちい散歩」の番組も5月4日に終了してしまった。
地井さんが出演した「ちい散歩」は2006年4月に始まって6年間放送した番組である。
番組が終わる1年ほど前からこの番組と私の散策とがおかしな偶然でつながっていることに気づいた。
それは、「ちい散歩」の番組より数日前に私が先に散歩しているのである。
「人生は偶然の積み重ね」というが、この言葉がこれにあてはまるかは分らぬが、偶然地井さんの放送の先取り散歩をしていた。
その幾つかの「先取り散歩」を紹介して地井武雄さんへの追悼としたい。
始まりは、2011年4月12日放送の「鹿島田」である。
この日、私は二ヶ領用水完成400年を記念して「二ヶ領用水を歩く」2日目で、二ヶ領用水を川崎市の高津から鹿島田まで歩いた。
出がけに偶然TV欄をみて「ちい散歩」で川崎市の鹿島田が紹介されることを知り何処を案内するのか楽しみに録画をセットして家を出たのである。
番組では地井さんも二ヶ領用水を紹介されていて、同じ日に放送と同じ場所に行ったことに驚いた。


鹿島田の二ヶ領用水
二ヶ領用水に関連している中野島(2011.12.6放送)、稲田堤(2011.6.21放送)、宿河原(2011.8.8放送)の散策もあった。

中野島駅

稲田堤

宿河原堰
●ふたつ目の偶然
「鹿島田」の放送から偶然がスタートし、そのあと9月24日に「弘明寺」の放送があったが横浜市南区の弘明寺は放送の10日ほど前の9月13日に訪れていた。

弘明寺の三門
●3つ目と4つ目の偶然
それから、御嶽山(2011.10.21放送、訪れた日8.29)もあるが、11月末から今年にかけて偶然が度重なった。


奥多摩・御岳山のケーブル駅と御嶽神社 参道のみやげ店には地井さんのスナップもあった
11月25日放送「特選ちい散歩、方南町・環七通りの住宅街」に建築業のお店の屋上に石膏でつくられた龍が出てきたのだが、その龍を偶然散策中に見つけたのである。それは放送の5日後、11月30日であった。
その日は「赤穂浪士のゆかりの地散策」で数カ所の街を歩いたのだが、最初の目的地である通称「釜寺」に向かった途中にこの石膏龍を見つけたのである。テレビを見ていた時には街の名すら気に留めず、コテでつくられた見事な龍の姿だけが印象に残っていたのであるが、まさか赤穂浪士のゆかりの地に行く前に見つけるなんて驚きで、「なんじゃ、こりゃ」と叫びたい心境だった。

その偶然のお陰でか、この日は目的地すべてがスムーズに行くことが出来た。
●5つ目の偶然
その次が大磯町(2011.12.12放送)である。私も「東海道の宿場を歩く」で平塚宿まで巡りBlogに掲載している。大磯宿も近々にと下調べも終え、コースを決定し、あとは天候と相談して日程を決めるだけの状態であった時に放送があった。そこで、残念ながら今回は後追いになったが3日後の12月15日に大磯宿を探訪した。


大磯宿の鴫立庵と今日の一枚の絵で描いた大ケヤキ
●6つ目の偶然
その次は、ひと駅散歩「雪谷大塚駅――石川台駅」(2011.12.16)の放送である。放送が始まって、石川台駅って何処かで聞いた駅名だなと思った。それはその時にまとめていたBlog、「大御所様の道・中原街道を行く」に出てくる駅名だと思い出す。
池上線は池上・鎌田間を15駅で結ぶ住宅地の中を走る電車であるが池上・雪谷大塚間は中原街道と並行して走っている。
池上線といえば西島三枝子が歌って大ヒットした曲があるので、是非とも中原街道のBlogに池上線を書き添えたいと考えていた。ただ今回、「東急池上線・石川台駅」をBlogに載せたのは偶然出会った駅であったし、池上線の駅だったら戸越銀座駅もカメラに収めてあったが、何故に名の知れていない石川台駅を選んだのかは神のみぞ知るである。

●7つ目の偶然
つぎは、「京都散歩(2011.12.25)」。
「ちい散歩」初の全国放送だそうである。萬田久子と合流した「哲学の道」を2ヶ月ほど前の10月31日の雨の中を歩いた。私の京都旅行は目的地変更の旅であった。本来は宮城・岩手の海岸線を歩く予定だったが大震災のために目的地を変更したことで、京都の旅自体が偶然の産物であった。

哲学の道と疏水
●8つ目の偶然
年が明けて2012年1月6日、ひと駅散歩「北品川駅――新馬場駅」の放送。
20日ほど前の2011年12年13日に「東海七福神散策」ということで新馬場駅に団体で降り、この駅から京急大森海岸駅までの旧品川宿を歩いた。



新馬場駅近くの品川神社にある地井さんも上った「富士塚」と頂上から眺める「ひと駅散歩」の京浜急行線
今年2月2日放送の、ひと駅散歩「青物横丁駅――鮫洲駅」に地井さんが回った千骵荒神がある海雲寺もその時参拝している。


「青物横丁駅」への道標と地井さんが参詣した海運寺
「ちい散歩」の番組で地井さんは独特のキャラクター相まって「散歩の達人」として有名になり、地井さんのライフワークともなっていたようだ。謹んで冥福をお祈りします。

「皆さ~ん! 最近、歩いていますか~!? 散歩っていいですよ! さぁ、散歩に出かけましょう!!」
健康を回復して「皆さ~ん! 最近、歩いていますか~!?」とすぐにでも「ちい散歩」に再登場すると思っていたのに残念でならない。
地井さんが体調不良で1月末に検査入院して「ちい散歩」の番組も5月4日に終了してしまった。
地井さんが出演した「ちい散歩」は2006年4月に始まって6年間放送した番組である。
番組が終わる1年ほど前からこの番組と私の散策とがおかしな偶然でつながっていることに気づいた。
それは、「ちい散歩」の番組より数日前に私が先に散歩しているのである。
「人生は偶然の積み重ね」というが、この言葉がこれにあてはまるかは分らぬが、偶然地井さんの放送の先取り散歩をしていた。
その幾つかの「先取り散歩」を紹介して地井武雄さんへの追悼としたい。
始まりは、2011年4月12日放送の「鹿島田」である。
この日、私は二ヶ領用水完成400年を記念して「二ヶ領用水を歩く」2日目で、二ヶ領用水を川崎市の高津から鹿島田まで歩いた。
出がけに偶然TV欄をみて「ちい散歩」で川崎市の鹿島田が紹介されることを知り何処を案内するのか楽しみに録画をセットして家を出たのである。
番組では地井さんも二ヶ領用水を紹介されていて、同じ日に放送と同じ場所に行ったことに驚いた。


鹿島田の二ヶ領用水
二ヶ領用水に関連している中野島(2011.12.6放送)、稲田堤(2011.6.21放送)、宿河原(2011.8.8放送)の散策もあった。

中野島駅

稲田堤

宿河原堰
●ふたつ目の偶然
「鹿島田」の放送から偶然がスタートし、そのあと9月24日に「弘明寺」の放送があったが横浜市南区の弘明寺は放送の10日ほど前の9月13日に訪れていた。

弘明寺の三門
●3つ目と4つ目の偶然
それから、御嶽山(2011.10.21放送、訪れた日8.29)もあるが、11月末から今年にかけて偶然が度重なった。


奥多摩・御岳山のケーブル駅と御嶽神社 参道のみやげ店には地井さんのスナップもあった
11月25日放送「特選ちい散歩、方南町・環七通りの住宅街」に建築業のお店の屋上に石膏でつくられた龍が出てきたのだが、その龍を偶然散策中に見つけたのである。それは放送の5日後、11月30日であった。
その日は「赤穂浪士のゆかりの地散策」で数カ所の街を歩いたのだが、最初の目的地である通称「釜寺」に向かった途中にこの石膏龍を見つけたのである。テレビを見ていた時には街の名すら気に留めず、コテでつくられた見事な龍の姿だけが印象に残っていたのであるが、まさか赤穂浪士のゆかりの地に行く前に見つけるなんて驚きで、「なんじゃ、こりゃ」と叫びたい心境だった。

その偶然のお陰でか、この日は目的地すべてがスムーズに行くことが出来た。
●5つ目の偶然
その次が大磯町(2011.12.12放送)である。私も「東海道の宿場を歩く」で平塚宿まで巡りBlogに掲載している。大磯宿も近々にと下調べも終え、コースを決定し、あとは天候と相談して日程を決めるだけの状態であった時に放送があった。そこで、残念ながら今回は後追いになったが3日後の12月15日に大磯宿を探訪した。


大磯宿の鴫立庵と今日の一枚の絵で描いた大ケヤキ
●6つ目の偶然
その次は、ひと駅散歩「雪谷大塚駅――石川台駅」(2011.12.16)の放送である。放送が始まって、石川台駅って何処かで聞いた駅名だなと思った。それはその時にまとめていたBlog、「大御所様の道・中原街道を行く」に出てくる駅名だと思い出す。
池上線は池上・鎌田間を15駅で結ぶ住宅地の中を走る電車であるが池上・雪谷大塚間は中原街道と並行して走っている。
池上線といえば西島三枝子が歌って大ヒットした曲があるので、是非とも中原街道のBlogに池上線を書き添えたいと考えていた。ただ今回、「東急池上線・石川台駅」をBlogに載せたのは偶然出会った駅であったし、池上線の駅だったら戸越銀座駅もカメラに収めてあったが、何故に名の知れていない石川台駅を選んだのかは神のみぞ知るである。

●7つ目の偶然
つぎは、「京都散歩(2011.12.25)」。
「ちい散歩」初の全国放送だそうである。萬田久子と合流した「哲学の道」を2ヶ月ほど前の10月31日の雨の中を歩いた。私の京都旅行は目的地変更の旅であった。本来は宮城・岩手の海岸線を歩く予定だったが大震災のために目的地を変更したことで、京都の旅自体が偶然の産物であった。

哲学の道と疏水
●8つ目の偶然
年が明けて2012年1月6日、ひと駅散歩「北品川駅――新馬場駅」の放送。
20日ほど前の2011年12年13日に「東海七福神散策」ということで新馬場駅に団体で降り、この駅から京急大森海岸駅までの旧品川宿を歩いた。



新馬場駅近くの品川神社にある地井さんも上った「富士塚」と頂上から眺める「ひと駅散歩」の京浜急行線
今年2月2日放送の、ひと駅散歩「青物横丁駅――鮫洲駅」に地井さんが回った千骵荒神がある海雲寺もその時参拝している。


「青物横丁駅」への道標と地井さんが参詣した海運寺
「ちい散歩」の番組で地井さんは独特のキャラクター相まって「散歩の達人」として有名になり、地井さんのライフワークともなっていたようだ。謹んで冥福をお祈りします。

「皆さ~ん! 最近、歩いていますか~!? 散歩っていいですよ! さぁ、散歩に出かけましょう!!」