大磯宿を歩く
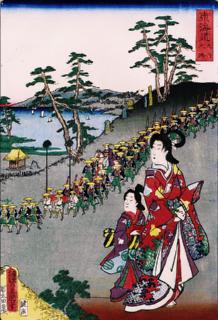
大磯宿は1601(慶長6)年、東海道に宿駅伝馬制度が制定された時に設置された初期の宿場のひとつで、江戸から八番目の宿場、日本橋からの距離は66m(16里27町)に位置する。
この道は、源頼朝が鎌倉に幕府を開いて以来の鎌倉と京都を結ぶ上洛道として発展した。これが東海道の始まりと伝えられている。
鎌倉時代、大磯の中心は化粧坂の付近にあったと思われる。
「大磯宿を歩く」は化粧坂にある一里塚からスタートする。
化粧坂は、東海道の旧道として残され、松並木に覆われている。

●化粧坂一里塚跡
化粧坂の中ほどに日本橋より16里の一里塚跡がある。海側には榎、山側にはせんだんが植栽されていた。


●大磯八景碑
大磯八景は1907(明治40)年ころ、大磯町町長が、大磯八景を選んで絵葉書にしたことが始まり。


JR東海道線のガードを潜ると、いよいよ大磯宿の中心地に入る。

●江戸見附
宿場の出入り口につくられた構造物で、本来簡易な防御施設として設置されたものである。また、宿場の範囲を示しており、江戸側にあるものを江戸見附と呼ぶ。




●日枝神社の庚申塔群

青面(しょうめん)金剛像が庚申塔群の右手に含まれている。

●神明神社
明治天皇が1868(明治元)年、京都から東京に行幸途中、大磯宿小島本陣に宿泊した際に、内侍所御羽車(賢所 天照大神の御霊代のヤカタノカガミを祭ってある腰輿)を神明神社に奉安されたという記念碑がある。


●火除土手跡
江戸時代、大磯宿はたびたび大きな火災に見舞われている。
なかでも宿内450軒が消失した1836(天保7)年9月の大火や1853(嘉永6)年8月の漁師町家数380軒余のうち、312軒を焼きつくした大火などがある。そのために火除土手が1855(安政2)年に築かれる。
火除土手の場所が分からず大磯駅前の観光案内所で教えていただく。現在は土手といえるほどの高低差はなく、道として利用されている。

●延台寺
日本三大仇討ちのひとつ、曽我兄弟の仇討ちにゆかりの深い鎌倉時代の舞の名手、伝説の美女虎御前(虎女)が兄弟を偲んで庵を結んだ跡とも伝えられる(延台寺案内)。
曽我十郎身代わり石と称する「虎御石」がある。
虎御前のもとに通う曽我十郎が工藤祐経に矢を射かけられた時、この石が防いだとされ、長さ二尺一寸(約60cm)幅一尺(約30cm)重さ三十六貫(約135kg)ほどの大きさがある。


狭い境内の中には大磯遊女の墓、虎御前供養塔などの史跡がある。


●秋葉神社
1762(宝暦12)1月年の大火で宿場の大半が焼き尽くされた。そこで遠州秋葉山から秋葉大権現を勧請し、祀った。

●北組問屋場跡
大磯宿の問屋場は北本町、南本町に一カ所ずつあり、地福寺の門前通りを境として北組と南組に分かれていた。それぞれに問屋年寄1人、帳付4人、人足指2人、馬指2人が置かれ交互に役を勤めていた。
北組問屋場は間口6m余(3間半)であった。


●小島本陣跡
東海道五十三次のうち、日本橋から8番目にあたる大磯宿の本陣跡。
大磯宿には、小島家、尾上家、石井家の3軒の本陣があった。小島本陣跡には、1870(明治3)年創業の蕎麦屋「古伊勢屋」が建つ。


●地福寺・島崎藤村の墓
837(承和4)年創建という古義真言宗京都東寺末の古刹で、かつて家康が利用した「御茶屋」があったところといわれる。境内には梅が立ち並び、名所として知られる。

境内に島崎藤村夫妻の墓がある(下画像)。島崎藤村は、代々中山道馬籠宿の本陣、庄屋を務めた家に生まれ、のちに郷里において牢死した国学者の父をモデルに『夜明け前』を執筆した。

●尾上本陣跡
小嶋、尾上、石井の三箇所に本陣がありその建坪は夫々 246、238、235坪であった。本陣の建物は平屋造りで多くの座敷、板の間、土間などがあり、奥には大名の寝所となる床の間と違い棚のある書院造りの御上段の間がある。
南本町東側にあった石井本陣は早く幕を下ろすが、尾上、小島本陣は幕末まで続いた。

小島本陣は北本町に、尾上本陣は南本町地福寺入り口付近一帯にあり、石井本陣は東海道を挟んで、尾上本陣の斜向かいにあった。

●南組問屋場跡


●アロエの花
「海水浴場発祥の地碑」に向かう道筋に咲いていた。その後も時折みごとに咲くアロエの花を見かける。

●海水浴場発祥の地碑
1885(明治18)年、当時の軍医総監・松本順が国民の健康増進と体力向上をはかるため海水浴が良いと説き、有名歌舞伎役者を大磯照ヶ浜海岸に大勢連れて来て海水浴をさせ、大磯町を日本で最初の海水浴場として日本中に広めた。


●新島襄終焉の地(旅館百足屋の跡地)
早稲田大学の大隈重信、慶応の福沢諭吉とともに明治時代の三代教育者である、後の同志社大学創始者・新島襄が療養先の大磯の旅館百足屋で47歳の生涯を閉じた。かつての百足屋跡地に石碑がたてられている。


●新杵

●湘南発祥の地碑
「湘南」は、もともと現在の中国湖南省を流れる湘江の南部のことで、大磯がこの地に似ているとことから江戸期に湘南の発祥の地と命名された。

●鴫立庵(しぎたつあん)
鎌倉時代の有名な歌人・西行法師が、「こころなき身にもあわれは しられけり 鴫立つ沢の 秋の夕暮れ」という和歌をこの地で詠んだ。
江戸時代初期に、崇雪という俳人が、西行を慕って大磯・鴫立沢のほとりに草庵を建て、その後これが鴫立庵と呼ばれた。崇雪は鴫立庵の脇に「著盡湘南清絶地」という標柱(1664年建立)を建てたことから、この付近を湘南と呼ぶ様になったとの説もある。庵はなかなか瀟洒な作りで、風情にあふれている。歴代俳諧重鎮が江戸時代より現在に到るまで、この庵に在住してここを守ってきている。



●法虎堂(鴫立庵)
鴫立庵庭内の沢を背にして法虎堂がある。堂内には有髪僧体の虎御前19歳の姿を写した木造が安置されている。堂の前には1701(元禄14)年に建立した虎御前碑(東鑑碑)がある。



●高札場跡
通常、土台部分を石垣で固め、その上を柵で囲んで、高札が掲げられる部分には屋根がついていたという。現在、民家の庭の中となっている。

●島崎藤村旧宅~静の草屋~
藤村邸は大正後期から昭和初期にかけて建築された町屋園と呼ばれる貸別荘の1軒。
萬事閑居簡不自由なし
藤村が最晩年の2年余りを過ごした邸宅。1941(昭和16)年2月、東京市麹町区(現千代田区)より大磯町に疎開した藤村は、1943(昭和18)年8月21日、「東方の門」の朗読中に倒れ、翌未明に亡くなった。享年71歳。



ガラス戸の板ガラスは大正製
●東海道松並木
松並木は、今から400年前に諸街道の改修時に植えられたもので、幕府や領主に保護され、150年前ころから厳しい管理の下、たち枯れした樹は村ごとに植え継がれて大切に育てられた。


●蹌踉(そうろう)閣(伊藤博文邸跡)
1890(明治23)年に、足柄下郡小田原町(現:神奈川県 小田原市)に建てられた、政治家・伊藤博文の別邸。
1897(明治30)年に中郡大磯町に 同名の邸宅を建てて移転し、本籍も同町に移したことから、本邸となった。
また、邸内に、明治の元勲である三条実美、岩倉具視、大久保利通、木戸孝允を祀った四賢堂を造り、日々の戒めとしたとされる(伊藤の死後、夫人が伊藤博文を加えて五賢堂となった)。滄浪閣は、長年大磯プリンスホテル別館となっていたが、2007年3月末をもって終了した。いずれは老人ホームとなる計画があるようだ。
また、この辺一帯は、山形、陸奥、西園寺等の明治の元老旧邸が点在している。

●上方見附跡
「上方見附」は東小磯村加宿のはずれにあり、現在の「統監道」バス停の付近に案内板がたっている。この見附は平和な江戸時代になっては、防御施設としての役目はなくなり旅人に宿場の出人口を示す目印となった。

●大磯城山(じょうやま)公園・旧三井財閥別邸

元は三井財閥総本家の別荘地で、三井家は小磯別邸城山荘と呼んでいた。
1933(昭和8)年、三井家の当主・三井八郎右衛門高棟は第一線を退き隠居し、大磯に城山荘新館を新築。


公園となった現在、ここからの眺望は「関東の富士見百景」(国土交通省)に選定されているが、訪れた時はカメラに収めたものの残念ながらぼやけていた。なんとか露出調整をして富士を眺められた。

●国府本郷・一里塚
大磯宿付近には日本橋から16里目の一里塚が大磯宿地内に、そして国府本郷村地内に17番目の一里塚があった。国府本郷の一里塚は実際にはここより200mほど江戸よりに位置していた。塚の規模は不明だが、東海道をはさんで左右一対の塚の上には、それぞれ榎が植えられていたようである。


●東海道の道祖神



●六所神社
1192(建久3)年、北条政子の安産祈願として神馬が奉納された。



●宝積院
741(天平13)年、創建された真言宗の寺。
宝積院(ほうしゃくいん)入口付近には1631(寛永8)年の銘がある梵鐘があり、大磯に現存する鐘としては、最古のもの。


宿内の家並みは、長さ11町52間(1.3km)、江戸方より街道に沿って、山王町・神明町・北本町・南本町・茶屋町(石船町)・南台町の6町で構成されていた。江戸後期の人口は3,056人、家数は676軒で、三つの本陣と66軒の旅龍は北本町・南本町・茶屋町に集中し、問屋場は北本町と南本町の2ヵ所にあった
江戸寄りの平塚宿との間はわずか27町(2.9km)と短く、一方、小田原宿との間は、4里(15.7km)で比較的長く、その間に徒歩渡しで有名な酒匂川がある。南側の海と北側の山に挟まれた細長い町並みで、宿場としてはどちらかといえば、寂れた宿場のひとつであったようである。その主な理由は、江戸からの旅人は翌日の箱根越えに備え小田原にまで足を伸ばしてしまい、又、箱根を下ってきた人は、酒匂川の渡しを前に、その疲れを休めるために小田原に宿泊してしまうことが多かったからと思われる。
大磯と小田原との間宿(あいのしゅく)二宮
●二宮駅前ガラスのうさぎ
「ガラスのうさぎ」は、児童文学作家・高木敏子によるノンフィクション文学である。作者自身の経験をもとに執筆され、戦争で家族を失った少女を描いている。
三度の映画化、NHKでのドラマ化、アニメ化と多彩に作品化されている。

二度と戦争があってはならないと、永遠の平和を願う人々の浄財によって1981(昭和56)年、二宮駅前に建てられた。

【別ブログを閉鎖・編集し掲載:2011.12.15散策】
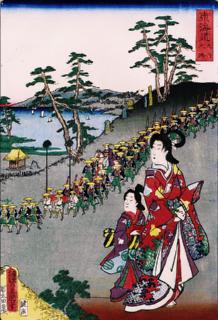
大磯宿は1601(慶長6)年、東海道に宿駅伝馬制度が制定された時に設置された初期の宿場のひとつで、江戸から八番目の宿場、日本橋からの距離は66m(16里27町)に位置する。
この道は、源頼朝が鎌倉に幕府を開いて以来の鎌倉と京都を結ぶ上洛道として発展した。これが東海道の始まりと伝えられている。
鎌倉時代、大磯の中心は化粧坂の付近にあったと思われる。
「大磯宿を歩く」は化粧坂にある一里塚からスタートする。
化粧坂は、東海道の旧道として残され、松並木に覆われている。

●化粧坂一里塚跡
化粧坂の中ほどに日本橋より16里の一里塚跡がある。海側には榎、山側にはせんだんが植栽されていた。


●大磯八景碑
大磯八景は1907(明治40)年ころ、大磯町町長が、大磯八景を選んで絵葉書にしたことが始まり。


JR東海道線のガードを潜ると、いよいよ大磯宿の中心地に入る。

●江戸見附
宿場の出入り口につくられた構造物で、本来簡易な防御施設として設置されたものである。また、宿場の範囲を示しており、江戸側にあるものを江戸見附と呼ぶ。




●日枝神社の庚申塔群

青面(しょうめん)金剛像が庚申塔群の右手に含まれている。

●神明神社
明治天皇が1868(明治元)年、京都から東京に行幸途中、大磯宿小島本陣に宿泊した際に、内侍所御羽車(賢所 天照大神の御霊代のヤカタノカガミを祭ってある腰輿)を神明神社に奉安されたという記念碑がある。


●火除土手跡
江戸時代、大磯宿はたびたび大きな火災に見舞われている。
なかでも宿内450軒が消失した1836(天保7)年9月の大火や1853(嘉永6)年8月の漁師町家数380軒余のうち、312軒を焼きつくした大火などがある。そのために火除土手が1855(安政2)年に築かれる。
火除土手の場所が分からず大磯駅前の観光案内所で教えていただく。現在は土手といえるほどの高低差はなく、道として利用されている。

●延台寺
日本三大仇討ちのひとつ、曽我兄弟の仇討ちにゆかりの深い鎌倉時代の舞の名手、伝説の美女虎御前(虎女)が兄弟を偲んで庵を結んだ跡とも伝えられる(延台寺案内)。
曽我十郎身代わり石と称する「虎御石」がある。
虎御前のもとに通う曽我十郎が工藤祐経に矢を射かけられた時、この石が防いだとされ、長さ二尺一寸(約60cm)幅一尺(約30cm)重さ三十六貫(約135kg)ほどの大きさがある。


狭い境内の中には大磯遊女の墓、虎御前供養塔などの史跡がある。


●秋葉神社
1762(宝暦12)1月年の大火で宿場の大半が焼き尽くされた。そこで遠州秋葉山から秋葉大権現を勧請し、祀った。

●北組問屋場跡
大磯宿の問屋場は北本町、南本町に一カ所ずつあり、地福寺の門前通りを境として北組と南組に分かれていた。それぞれに問屋年寄1人、帳付4人、人足指2人、馬指2人が置かれ交互に役を勤めていた。
北組問屋場は間口6m余(3間半)であった。


●小島本陣跡
東海道五十三次のうち、日本橋から8番目にあたる大磯宿の本陣跡。
大磯宿には、小島家、尾上家、石井家の3軒の本陣があった。小島本陣跡には、1870(明治3)年創業の蕎麦屋「古伊勢屋」が建つ。


●地福寺・島崎藤村の墓
837(承和4)年創建という古義真言宗京都東寺末の古刹で、かつて家康が利用した「御茶屋」があったところといわれる。境内には梅が立ち並び、名所として知られる。

境内に島崎藤村夫妻の墓がある(下画像)。島崎藤村は、代々中山道馬籠宿の本陣、庄屋を務めた家に生まれ、のちに郷里において牢死した国学者の父をモデルに『夜明け前』を執筆した。

●尾上本陣跡
小嶋、尾上、石井の三箇所に本陣がありその建坪は夫々 246、238、235坪であった。本陣の建物は平屋造りで多くの座敷、板の間、土間などがあり、奥には大名の寝所となる床の間と違い棚のある書院造りの御上段の間がある。
南本町東側にあった石井本陣は早く幕を下ろすが、尾上、小島本陣は幕末まで続いた。

小島本陣は北本町に、尾上本陣は南本町地福寺入り口付近一帯にあり、石井本陣は東海道を挟んで、尾上本陣の斜向かいにあった。

●南組問屋場跡


●アロエの花
「海水浴場発祥の地碑」に向かう道筋に咲いていた。その後も時折みごとに咲くアロエの花を見かける。

●海水浴場発祥の地碑
1885(明治18)年、当時の軍医総監・松本順が国民の健康増進と体力向上をはかるため海水浴が良いと説き、有名歌舞伎役者を大磯照ヶ浜海岸に大勢連れて来て海水浴をさせ、大磯町を日本で最初の海水浴場として日本中に広めた。


●新島襄終焉の地(旅館百足屋の跡地)
早稲田大学の大隈重信、慶応の福沢諭吉とともに明治時代の三代教育者である、後の同志社大学創始者・新島襄が療養先の大磯の旅館百足屋で47歳の生涯を閉じた。かつての百足屋跡地に石碑がたてられている。


●新杵

●湘南発祥の地碑
「湘南」は、もともと現在の中国湖南省を流れる湘江の南部のことで、大磯がこの地に似ているとことから江戸期に湘南の発祥の地と命名された。

●鴫立庵(しぎたつあん)
鎌倉時代の有名な歌人・西行法師が、「こころなき身にもあわれは しられけり 鴫立つ沢の 秋の夕暮れ」という和歌をこの地で詠んだ。
江戸時代初期に、崇雪という俳人が、西行を慕って大磯・鴫立沢のほとりに草庵を建て、その後これが鴫立庵と呼ばれた。崇雪は鴫立庵の脇に「著盡湘南清絶地」という標柱(1664年建立)を建てたことから、この付近を湘南と呼ぶ様になったとの説もある。庵はなかなか瀟洒な作りで、風情にあふれている。歴代俳諧重鎮が江戸時代より現在に到るまで、この庵に在住してここを守ってきている。



●法虎堂(鴫立庵)
鴫立庵庭内の沢を背にして法虎堂がある。堂内には有髪僧体の虎御前19歳の姿を写した木造が安置されている。堂の前には1701(元禄14)年に建立した虎御前碑(東鑑碑)がある。



●高札場跡
通常、土台部分を石垣で固め、その上を柵で囲んで、高札が掲げられる部分には屋根がついていたという。現在、民家の庭の中となっている。

●島崎藤村旧宅~静の草屋~
藤村邸は大正後期から昭和初期にかけて建築された町屋園と呼ばれる貸別荘の1軒。
萬事閑居簡不自由なし
藤村が最晩年の2年余りを過ごした邸宅。1941(昭和16)年2月、東京市麹町区(現千代田区)より大磯町に疎開した藤村は、1943(昭和18)年8月21日、「東方の門」の朗読中に倒れ、翌未明に亡くなった。享年71歳。



ガラス戸の板ガラスは大正製
●東海道松並木
松並木は、今から400年前に諸街道の改修時に植えられたもので、幕府や領主に保護され、150年前ころから厳しい管理の下、たち枯れした樹は村ごとに植え継がれて大切に育てられた。


●蹌踉(そうろう)閣(伊藤博文邸跡)
1890(明治23)年に、足柄下郡小田原町(現:神奈川県 小田原市)に建てられた、政治家・伊藤博文の別邸。
1897(明治30)年に中郡大磯町に 同名の邸宅を建てて移転し、本籍も同町に移したことから、本邸となった。
また、邸内に、明治の元勲である三条実美、岩倉具視、大久保利通、木戸孝允を祀った四賢堂を造り、日々の戒めとしたとされる(伊藤の死後、夫人が伊藤博文を加えて五賢堂となった)。滄浪閣は、長年大磯プリンスホテル別館となっていたが、2007年3月末をもって終了した。いずれは老人ホームとなる計画があるようだ。
また、この辺一帯は、山形、陸奥、西園寺等の明治の元老旧邸が点在している。

●上方見附跡
「上方見附」は東小磯村加宿のはずれにあり、現在の「統監道」バス停の付近に案内板がたっている。この見附は平和な江戸時代になっては、防御施設としての役目はなくなり旅人に宿場の出人口を示す目印となった。

●大磯城山(じょうやま)公園・旧三井財閥別邸

元は三井財閥総本家の別荘地で、三井家は小磯別邸城山荘と呼んでいた。
1933(昭和8)年、三井家の当主・三井八郎右衛門高棟は第一線を退き隠居し、大磯に城山荘新館を新築。


公園となった現在、ここからの眺望は「関東の富士見百景」(国土交通省)に選定されているが、訪れた時はカメラに収めたものの残念ながらぼやけていた。なんとか露出調整をして富士を眺められた。

●国府本郷・一里塚
大磯宿付近には日本橋から16里目の一里塚が大磯宿地内に、そして国府本郷村地内に17番目の一里塚があった。国府本郷の一里塚は実際にはここより200mほど江戸よりに位置していた。塚の規模は不明だが、東海道をはさんで左右一対の塚の上には、それぞれ榎が植えられていたようである。


●東海道の道祖神



●六所神社
1192(建久3)年、北条政子の安産祈願として神馬が奉納された。



●宝積院
741(天平13)年、創建された真言宗の寺。
宝積院(ほうしゃくいん)入口付近には1631(寛永8)年の銘がある梵鐘があり、大磯に現存する鐘としては、最古のもの。


宿内の家並みは、長さ11町52間(1.3km)、江戸方より街道に沿って、山王町・神明町・北本町・南本町・茶屋町(石船町)・南台町の6町で構成されていた。江戸後期の人口は3,056人、家数は676軒で、三つの本陣と66軒の旅龍は北本町・南本町・茶屋町に集中し、問屋場は北本町と南本町の2ヵ所にあった
江戸寄りの平塚宿との間はわずか27町(2.9km)と短く、一方、小田原宿との間は、4里(15.7km)で比較的長く、その間に徒歩渡しで有名な酒匂川がある。南側の海と北側の山に挟まれた細長い町並みで、宿場としてはどちらかといえば、寂れた宿場のひとつであったようである。その主な理由は、江戸からの旅人は翌日の箱根越えに備え小田原にまで足を伸ばしてしまい、又、箱根を下ってきた人は、酒匂川の渡しを前に、その疲れを休めるために小田原に宿泊してしまうことが多かったからと思われる。
大磯と小田原との間宿(あいのしゅく)二宮
●二宮駅前ガラスのうさぎ
「ガラスのうさぎ」は、児童文学作家・高木敏子によるノンフィクション文学である。作者自身の経験をもとに執筆され、戦争で家族を失った少女を描いている。
三度の映画化、NHKでのドラマ化、アニメ化と多彩に作品化されている。

二度と戦争があってはならないと、永遠の平和を願う人々の浄財によって1981(昭和56)年、二宮駅前に建てられた。

【別ブログを閉鎖・編集し掲載:2011.12.15散策】






















 晴雲寺
晴雲寺































 明治当時の見附
明治当時の見附



 西組問屋場跡
西組問屋場跡











 高麗山
高麗山 

 かつての上宮
かつての上宮













 正宗殿
正宗殿


























