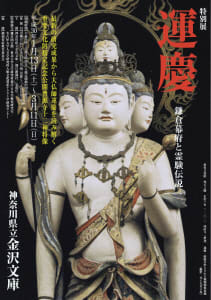「まァ綺麗な野菊、政夫さん。」
「私にも半分おくれったら、私ほんとうに野菊が好き」
「僕はもとから野菊がだいすき。民さんも野菊が好き・・・・・・」
「私なんでも野菊の生まれ返りよ。
野菊の花をみると身振が出るほど好もしいの。
どうしてこんなかと、自分でも思う位」
「民さんはそんなに野菊が好き・・・・・・
道理でどうやら民さんは野菊のような人だ」
民子は分けてやった半分の野菊を顔に押しあてて嬉しがった。 (野菊の墓碑「野菊の人」より)
15歳の少年。斉藤政夫と2歳年上の従姉、民子との淡い恋物語である。
舞台は明治時代の千葉県松戸市矢切付近であり、矢切りの渡しは政夫と民子の最後の別れの場となったところである。
船で河から市川へ出るつもりだから、十七日の朝、小雨の降るのに、一切の持物をカバン一個(ひとつ)につめ込み民子とお増に送られて矢切の渡へ降りた。村の者の荷船に便乗する訣でもう船は来て居る。僕は民さんそれじゃ……と言うつもりでも咽がつまって声が出ない。民子は僕に包を渡してからは、自分の手のやりばに困って胸を撫でたり襟えりを撫でたりして、下ばかり向いている。眼にもつ涙をお増に見られまいとして、体を脇へそらしている、民子があわれな姿を見ては僕も涙が抑え切れなかった。民子は今日を別れと思ってか、髪はさっぱりとした銀杏返しに薄く化粧をしている。煤色(すすいろ)と紺の細かい弁慶縞で、羽織も長着も同じ米沢紬(よねざわつむぎ)に、品のよい友禅縮緬(ゆうぜんちりめん)の帯をしめていた。襷(たすき)を掛けた民子もよかったけれど今日の民子はまた一層引立って見えた。(青空文庫『野菊の墓』より)
その後、民子は他家に嫁に行き、流産で命を落とす。死んだ民子の手には紅絹(もみ・女ものの薄手の絹地)のきれに包んだ政夫の写真と手紙が握られていた。
政夫は民子の墓の周りに、好きだった野菊を一面に植えた。
原作は、伊藤左千夫で、百恵さんや聖子さんがTVや映画で民子を演じている。
矢切の渡しで江戸川を渡って20分、「野菊のこみち」をたどって野菊の墓の記念碑が建つ西蓮寺(千葉県松戸市下矢切261)に向かった。
●矢切の渡し
徳川幕府は、戦略上、江戸城を守るために、交通の要衝となる川には橋を架けなかった。そのかわり、川を渡るために「渡し」を設けた。柴又と対岸の矢切を結ぶ「矢切の渡し」は江戸時代初期に地元民専用として、耕作、日用品購入、社寺詣などの目的で利用を許されていた。一般の通行は、上流の金町~松戸関所の渡しを利用しなければならなかった。
現在は、柴又に来る観光客のための渡船として楽しまれている。大人片道200円。
「矢切の渡し」と云えば、細川たかしさんがレコード大賞を受賞した歌謡曲として知られているが、TBS-TVで「寂しいのはおまえだけじゃない」というドラマがあったが、その中でちあきなおみさんの「矢切の渡し」が流れていたことが印象にある。そのドラマでセリフ回しが一本調子だと思った旅役者芸人役で登場していた人物がいたが、後に誰もが知る下町の玉三郎こと梅沢富雄さんであった。今から35年も前のことである。
●野菊のこみち
渡しを降りてからは西蓮寺までをスマホの地図頼りに歩く予定で住所を控えておいたのだが、その住所が誤っていたようで、行き先不明になってしまった。あとで調べたら松戸市には西蓮寺が2寺あることが分かった。
しかし、江戸川の堤に上がると、目の前に矢切の渡しの大きな看板や地図も備えられていた。
しかも「野菊のこみち」のネーミングも付けられて要所には道標が建つ親切な案内が備えれているコースなので、迷わずに目的地にたどりつけた。
●矢切のネギ
「野菊のこみち」はネギ畑の中を歩いて行くので、ネギの匂いがたっぷりだ。
この辺りは川砂地で、江戸川の氾濫によって大地ができたようだ
で、その土壌がネギの栽培に適しているようで、ネギの品種名にもなっている。ただし品種は一説に2万種もあるようだ。この矢切ネギは明治時代から「焼いてよし、鍋によし」で松戸の名産品(地域ブランド)にもなっている。
●大井戸之碑
坂の改修で井戸を埋めることとなり、記念に碑が建てられた。
ここにあった井戸は徳川時代からあって、いかなる時も枯れることなく、生活用水に田畑への往復の際に喉を潤す水であったことが刻まれている。1958(昭和33)年に建てられる。
●伊藤佐千夫文学碑
西蓮寺(松戸市松戸1900-1)境内に『野菊の墓』の記念碑がある。
文学碑は、左千夫の門人である土屋文明の筆になるものであり、小説『野菊の墓』の一節が刻まれている。
「僕の家というのは、松戸から二里ばかり下って、矢切の渡を東へ渡り、小高い丘の上でやはり矢切村と云ってる所。・・・・・・」
●八幡山西蓮寺(はちまんざんさいれんじ)
境内には「伊藤佐千夫文学」の碑が建てられている。
また、この地は北条氏と里見氏の国府台合戦の主戦場でもあり、その合戦の模様が本堂裏に掲示されている。
それによると今から400年程前、二度ほどの大戦争があって、敵味方千人以上の死者が出たという。また、当地に庚申板碑が出ている。板碑は1543(天文12)年と室町時代の作品である。板碑としては比較的に新しいようだ。
●野菊苑
西蓮寺の向かい側の崖上の小さな公園で「野菊の墓」の舞台とされるところ。政夫が民子を待った大きな銀杏の木は西蓮寺の入口にかつてはあったと云う。
ここからは江戸川方向が望める。
●矢喰村庚申塚
矢喰村庚申塚の由来によると、この地は下総の国の重要な地点であったことで、北条氏と里見氏の国府台合戦の主戦場となり、戦没者がこちらの解説では1万人余を数えた(西蓮寺の解説と大きな隔たりがある)。家は焼かれ、田畑は荒らされ、女子供年寄りは逃げまどい、男どもは人足に狩り出され、一家離散。この塗炭の苦しみから弓矢を呪うあまり、「矢切り」「矢切れ」「矢喰い」の名が生まれた。
江戸中期に二度と戦乱のないよう、やすらぎと健康を願い、庚申仏や地蔵尊に矢喰村と刻み朝夕祈ってきた。
庚申塚は角地に青面金剛像、馬頭観世音像、地蔵尊像などが鎮座している。
●矢切神社
1704(宝永元)年、長雨により、江戸川が大洪水を起こし、水高が地面より3m近く(8尺余り)に及んだ。当時は江戸川沿岸に民家があったため、多数の死者を出し、産業も甚大な被害を受けた。そのため村民が台地上に移住し、鎮守として京都より稲荷を勧請して祀った。かつては稲荷神社と呼ばれていたが、現在は第六天神、稲荷、天神(菅原道真)を祭神として祀っており、矢切神社に名を変えている。
扁額には「葛飾郷」と記されている。葛飾「郡」は現在の東京都、千葉県、埼玉県にまたがった地域だが、「郷」となると狭い地域であり、それが葛飾区内ではなく、千葉県側にあるとは驚きだ。
対岸の柴又に向け帰路につく。
帰りの船はエンジンで少々上流に上がり、川の流れに任せて柴又の船着場に着岸した。
訪れた日は11月29日で、今年の営業終了前日であった。