全長360m、全国でも4番目の大きさを誇る巨大な前方後円墳・造山(ぞうざん)
古墳は古墳時代中期(5世紀頃?)に築造されたもので、この地を治めた豪族の
墓と言われている。
また、墳丘の大きさや形が大阪の石津丘古墳(履中天皇陵と言われている)とほ
ぼ一致することから、国を治めた王の墓だとの見方もある。

然しこの古墳は埋葬者が未だに比定されていないため、天皇陵などとされた古
墳と違い、立ち入りの規制は無く、だれでも気軽に築山に登り立ち入ることが出来、
そのことが全国的に見ても貴重な存在となっている。


古墳の裾には人家が建ち、既に田畑となっているところも見受けられる。
宮内庁管理の古墳とは、えらく趣が違うが、そんな古墳だからこそ、地元には愛着
も深く、ボランテァや小学生が課外学習の一環でクリーン活動を行っていると言う。

県下にはそれに次ぎ、全国的に見ても9番目と言う規模の作山(さくざん)古墳も
ある。それは全長286m、高さ24mの前方後円墳だが、盗掘された痕跡がなく、未
だ発掘調査は行われていない。
もしかすればこの足もとにまだ埋葬者が眠っている・・などと考えると、なんだか
ワクワクするような、そんな楽しみを秘めた墳丘である。


近年、造山古墳にようやく県教委の調査メスが入ることに成った。
かつては古墳の外周に有ったとされる、墳丘を囲む周濠の本格的な調査に着手し
たのだ。作山古墳などにも、本格的な調査が入り、どんな秘密が眠っているのか
その謎が解き明かされる日が待ち遠しい。(続)
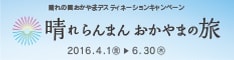

 にほんブログ村
にほんブログ村
古墳は古墳時代中期(5世紀頃?)に築造されたもので、この地を治めた豪族の
墓と言われている。
また、墳丘の大きさや形が大阪の石津丘古墳(履中天皇陵と言われている)とほ
ぼ一致することから、国を治めた王の墓だとの見方もある。

然しこの古墳は埋葬者が未だに比定されていないため、天皇陵などとされた古
墳と違い、立ち入りの規制は無く、だれでも気軽に築山に登り立ち入ることが出来、
そのことが全国的に見ても貴重な存在となっている。


古墳の裾には人家が建ち、既に田畑となっているところも見受けられる。
宮内庁管理の古墳とは、えらく趣が違うが、そんな古墳だからこそ、地元には愛着
も深く、ボランテァや小学生が課外学習の一環でクリーン活動を行っていると言う。

県下にはそれに次ぎ、全国的に見ても9番目と言う規模の作山(さくざん)古墳も
ある。それは全長286m、高さ24mの前方後円墳だが、盗掘された痕跡がなく、未
だ発掘調査は行われていない。
もしかすればこの足もとにまだ埋葬者が眠っている・・などと考えると、なんだか
ワクワクするような、そんな楽しみを秘めた墳丘である。


近年、造山古墳にようやく県教委の調査メスが入ることに成った。
かつては古墳の外周に有ったとされる、墳丘を囲む周濠の本格的な調査に着手し
たのだ。作山古墳などにも、本格的な調査が入り、どんな秘密が眠っているのか
その謎が解き明かされる日が待ち遠しい。(続)
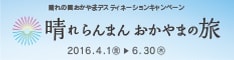



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます