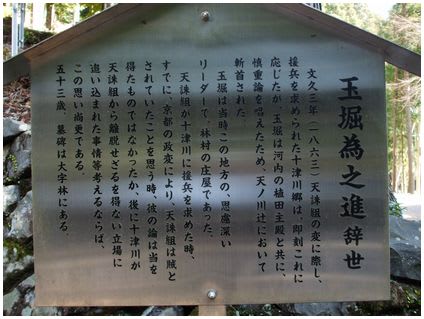<大日川の戦い>
忠光公は、8月30日の朝まで吉村総裁らが合流するのを待った。
ところが吉村は、『新宮に向かうには10数日かかり、途中で要所を固められると脱出は無理だ。それよりも敵中突破で五條から河内に出たほうがいい』と言う水郡善之祐の進言に従っていたのだ。
一方、忠光本隊も、新宮には向かうものの、ゆっくり進み、風屋村には2泊もしている。吉村たちを待ってのことなのか・・・?
その頃、京の孝明天皇は、なかなか討伐に動かない各藩に痺れを切らし、再度の「触れ書」を出している。
『政変は天皇の意思に基づくものであり、忠光は国家の乱賊である』・・・と。
<o:p></o:p>
各藩もこのお達しによって、天辻峠を三方から囲む布陣を張ることになり、新宮藩は、熊野川筋の船着場を押さえたとの情報も届く。
9月2日、忠光本隊は、風屋から更に南12kmの武蔵村(168号線沿いにある、現・十津川町役場、歴史民族資料館や道の駅から更に山の上で、かなり不便な場所だ。元・武蔵小学校跡で楠木正勝の墓がある「長盛山光明寺跡」)に移動。ここに3日間留まることになる。
忠光は、どうも、この武蔵の地を最後の砦とし、死に場所と決めていたのでは・・・とも言われている。
▲大日川~和田(賀名生)辺りの山路。向こうから槍を持った兵士たちが出てきそうなところです。
9月4日、本隊は、吉村からの具申により五條~河内を突破することとし、北に引き返すことになる。
天誅組を追う各藩も、戦い慣れないため、乱れがあったり恐れたり討伐にしり込みしているようだ。
その例が、各藩の偵察のため那須信吾らが恋野村(現・和歌山県橋本市)に陣を張っていた和歌山藩に夜襲を掛けたところ、簡単に勝って陣地を焼き払っているのだ。
このように和歌山藩には戦意がないと分かると、一気に北に向けて戻ることが出来る。
9月6日、忠光本隊は、天辻の本陣に戻ってきた。
軍議により本隊の多くを西吉野村・北曽木(賀名生村の南隣)まで出し、そこに砦を築き五條からの敵軍と戦うことを決める。
この行動は、下市方面に向かうと見せかけて五條を突破し、堺に脱出する作戦だった。
北曽木の陣が準備出来たため忠光一行は出発するが、大日川辺りで伊賀上野の藤堂新七郎軍600名と遭遇、前進できず3時間近くの戦闘となる。
▲大日川辺りの風景。この辺りで藤堂藩600人と戦闘が繰り広げられたのだろう。
<o:p> </o:p>
闘った後、天誅組は北曽木の東北にある銀峯山(白銀岳 611m)にある波宝神社に本陣を構える。これは当初の作戦通りだったのかもしれない。<o:p></o:p>
この波宝神社は神宮皇后が祈願したところであり、また吉野将軍宮が城砦を築き勝利したのもこの神社で、由緒ある神社だったのです。
▲西吉野村十日市辺りの県道20号・下市宗檜線の道端に「波宝神社」の案内看板があった。 <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
▲「波宝神社」は、この山の頂辺りなのだろうか? 見晴らしの良い山頂からは五條や下市方面が眺められるらしい。
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>