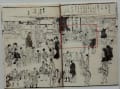江戸には各地に神社仏閣があり、様々な祭礼が催されていた。山王(日
枝神社)や神田明神、三社(浅草神社)のような大きな規模のものだけでな
く、町内の小さな神社の祭礼もあり、これに出向くことは庶民の愉しみ
でもあった。
おもちゃ絵にも、そんな祭礼に関するものがあり、灯籠や山車を描い
たものも、神輿を作るものなどもあった。
次は、「とうろうのゑ」(文化~文正年間・1804~30頃、歌川国長画、
版元未詳)は、絵の上部に作品のタイトルが書かれ、同じタイプの絵に
“あんどん” と記されたものもあり、祭の飾り行灯を作るための絵と判
明。
祭の時には大行灯が飾られ、そこには神話や武者などが描かれてい
ることが多く、この絵には天岩戸と土蜘蛛退治が判る。

参考図として「江戸と東京 風俗野史」8伊藤晴雨画)より。
tabashio-museum(墨田区横川1-16-3)
枝神社)や神田明神、三社(浅草神社)のような大きな規模のものだけでな
く、町内の小さな神社の祭礼もあり、これに出向くことは庶民の愉しみ
でもあった。
おもちゃ絵にも、そんな祭礼に関するものがあり、灯籠や山車を描い
たものも、神輿を作るものなどもあった。
次は、「とうろうのゑ」(文化~文正年間・1804~30頃、歌川国長画、
版元未詳)は、絵の上部に作品のタイトルが書かれ、同じタイプの絵に
“あんどん” と記されたものもあり、祭の飾り行灯を作るための絵と判
明。
祭の時には大行灯が飾られ、そこには神話や武者などが描かれてい
ることが多く、この絵には天岩戸と土蜘蛛退治が判る。

参考図として「江戸と東京 風俗野史」8伊藤晴雨画)より。
tabashio-museum(墨田区横川1-16-3)