
私は彼の斜め前に腰を降ろし、歩道の縁に座った彼を少し見上げる形で話しを聞いた。
彼の話しは終始、支離滅裂ではあったが、その内容の主な趣旨は自分のこの現状はほんとうの自分ではない、自分には名誉、誇りをあり、乞食ではないとひたすら伝えたがっていた。
私は思った、彼の語るそれは彼の生きる術であり、生きる証しであり、生きる気力である、自分は誰にとやかく言われるのことのない人間であると言うことを伝えたがっていた。
私には十分にそれが伝わった。
かなり長い時間、彼の話しを聞いた、その間、私の近く通る炊き出しのカレーを食べ終えたおじさんたちは私にお辞儀をしたり、手を振ったり、挨拶をして通り過ぎて行った。
だが、きっとその誰一人、彼の目には映らなかったのかも知れない、彼は私を自分自身を証明するものとして捉えて、決して離さそうとはしなかったからだ。
話すことで彼は彼の脳裏の中で理想の彼になって近づこうとしていたのかも知れなかった。
ただ何度も「オレは乞食ではない」と言って鼻で笑い飛ばしていた、そうしなくて今を生きて行けないのだろうと私は思った。
気が付けば、辺りには私たち二人の他、誰も居なくなっていた。
私は切りの良いところで、いや、そんなところはなかったが、彼のところから離れ、自転車を取りに行った。
そして、まだまだ話したらないだろう、彼に声を掛けて帰ろうとすると、彼は持っていたビニール袋から、おもむろに何かのチラシを出し、ポケットに入っていたのかも知れない赤のボールペンをいつの間にかに持ち、私の名前を聞いていた。
私が苗字を教えると、そのチラシに私の名前をなぐり書き、「詩を書いてあげる」と私に有無も言わせぬ、そのチャンスすらを与えぬスピードで言った。
最初に彼は素早くこう声に出しながら殴り書いた。
「みんな同じ色をしている 何の色 サラリーマン」
彼のサラリーマンに対する明らかなコンプレックスと羨望を私は感じた。
彼は言葉にした詩に物足りなかった様子で次の詩をすぐ殴り書き始めた。
「人と人の出会いは 神の気まぐれなり」
そして、そのチラシを私の方に履き捨てるように差し出した。
彼は私の感想などは何一つ求めず、すべて彼のなかで完了完結されたもののようだった。
私はただ「そうだね、ありがとう」と言い、「また炊き出しに顔を見せに来てね」と言うと、もごもごと何かを言うようにして頷いた。
彼のこの現状は彼が考えるに、ただ神の気まぐれだとし、そうすることで自らの境遇を無意識にどうにかしても売れ容れようとしたものが詩として現れたのか。
私には何も分からなかった。
ただ彼は必死に詩人として生きていた。
私に残されたものは胸の痛みと祈りだけだった。
いや、違う、弱い人間の強さもであった。
















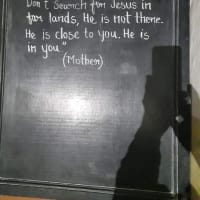



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます