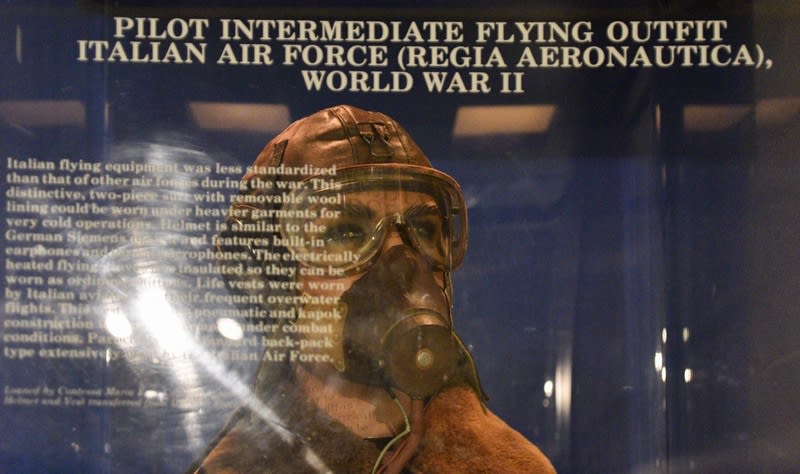フライング・レザーネックの展示機を紹介してきましたが、
今日はその中の回転翼、ヘリコプターを取り上げます。
ヘリコプターという乗りものが軍事に導入されるようになったのは
第二次世界大戦後で、特にベトナム戦争では
ヘリコプターはその象徴のようになっていました。
年代の古い順に機体を紹介していくことにすると、
■ シコルスキー HUS-1(UH-34D)シーホース

とわたしはいつもこれを見ると思うのですが、
独特な形をしているのでほぼ間違えようがないのはありがたいところです。
【攻撃ヘリコプターとは】
H-34は、1962年から海兵隊の突撃ヘリとしてベトナム戦争で活躍しました。
ほとんどのヘリと同じく、デビューは「ポストウォー」と言われる朝鮮戦争後です。
「アタックヘリ」ということもありますが、そもそも
「攻撃ヘリコプター」とは何かということを考えてみましょう。
飛行機と同じように、当初ヘリコプターはマルチロール機、
複数の役割を果たすように設計されました。
具体的には外部の荷物を運んだり、負傷者を避難させたり、
銃やミサイル、兵器を搭載したガンシップとして運用されたりといったところです。
しかし、「ガンシップヘリ」は「攻撃ヘリ」とは別物になり、
決してイコールではありません。
攻撃ヘリとは本来、戦闘機として設計されたものを言います。
低空を定速度で飛ぶという飛行特性を生かして、
歩兵、軍用車両、要塞などを主な目標とし、搭載される標準的な武装は、
機関銃、ロケット弾、対戦車ミサイルなどです。
現代の攻撃ヘリには、大まかに言って2つの主要な任務があります。
ひとつは、当たり前のようですが、敵の戦車や車両、地上施設を破壊すること。
2つ目は、地上部隊のための近接航空支援を行うことです。
もちろん場合によっては、輸送ヘリの護衛を行うこともあります。
攻撃用ヘリコプターの歴史は、第二次世界大戦の初期、ロシアとアメリカが
低速の固定翼機を使って夜間のステルス攻撃を試みたことに遡ります。
もちろんのこと、この時はまだ回転翼ではないのですが、
攻撃用ヘリの運用を戦略と捉えた場合の歴史とお考えください。
有名なのは、アメリカの使用したパイパーJ-3カブを改造した機体です。

バズーカのロケットランチャーを3〜4本、支柱に外付けし、
ドイツの戦車や大砲を見事にやっつけてしまったことがあります。

ロシア移民の技術者、イーゴリ・シコルスキはヘリコプターを設計し、
シコルスキーR-4を最初のモデルとして発表しました。

シコルスキーR-4は、世界初の量産ヘリコプターであり、
アメリカ空軍に就役した最初のヘリコプターでとなりました。
陸軍航空隊の司令官だったフィリップ・コクラン大佐は、このことを手紙に
このいまいましいヤツは理性を持つかのように動いた。」
と書いて知らせています。
泡立て器・・・誰が上手いこと言えと。
陸軍はすぐにこのデザインの有用性を認め、戦闘用に改造し始めました。
ただし第二次戦時中に使用されたのはほんのわずかで、
その使用方法は、戦闘地域からの救助や避難にとどまりました。
ともあれR-4は成功し、第二次世界大戦後の技術開発に多大な影響を与えました。
滑走路を必要とせず、過酷な地形でも活動でき、
固定翼機では危険な場所でも低空でゆっくりと飛行することができ、
どこにでも着陸して、人員をせたり降ろしたりすることができます。
今では当たり前のこととして周知されているこれらヘリの実用性は、
他のどんな固定翼機にも持てない利点となりました。
1950年代がヘリコプターの全盛期となったのも当然のことだったでしょう。
朝鮮戦争やベトナム戦争を舞台にした映画や物語で、
ヘリコプターが出てこないものはないと100%断言できるくらいです。
その他、シコルスキーの設計で最も成功したものの1つがS-55です。
S-55はここにある海軍用のHUS-1シーホースになりました。
このほか、やはり海軍用にHSS-1シーバットというのもありました。

シコルスキー社が個人的に始めたものでした。
なぜなら、このヘリコプターは当初、いくつかの斬新な設計コンセプトの
「テストベッド」(実験用機体)として設計されたからでした。
1年足らずでモックアップが設計・製作されています。
最初に納入したのはアメリカ空軍で、評価のために5機のYH-19を発注し、
プログラム開始から1年も経たない1949年に初飛行させ、
1950年には海軍に初号機が納入されています。
海兵隊に1号機が納入されたのは翌年の1951年でした。
朝鮮戦争では、全軍がH-19を貨物輸送、兵員輸送、死傷者の避難、
撃墜されたパイロットや航空機の回収などに使用しました。
H-19は、8人または10人の乗員、1,000ポンド以上の貨物、
または6台の担架を運ぶことができました。
また、エンジンを機首に搭載することで、船倉内のスペースを確保し、
メンテナンス時のエンジンへのアクセスを容易にしたのもユニークな点です。
海兵隊のHRS-1は、戦時中の2つの軍事作戦で重要な役割を果たしています。
まず、1951年9月のウィンドミルI作戦。
HRS-1が74名の海兵隊員と18,848ポンドの装備を運搬した作戦で、
1953年のヘイリフトII作戦では、同じ部隊が
160万ポンドの貨物を輸送し、2つの連隊に補給を行いました。

知っている俳優がひとりもいないという
ただし、こちらはネバダの旱魃に対処するため、空軍が出動して
上空から干し草を落として住民を救った、という実話をベースにしています。
米軍はなんでも「作戦」にしてしまいますが、
この作戦によって命を救われたのは、人ではなく牧場の牛と馬だった、
(まあ間接的に人命も救えた事になるわけですが)というストーリーです。
使用されているのはフェアチャイルド社のC-82のようです。
ヘリコプターは、負傷者を野戦病院に迅速に運ぶことができたため、
朝鮮戦争では死亡した負傷者の数を史上最少に抑えることができたと言われますが、
ヘリがもっと投入されたベトナム戦争でなぜ効果が取り沙汰されないかというと、
おそらヘリくらいでは『焼け石に水』状態だったってことなんでしょう。
H-19以降、ヘリコプターは現代の戦争には欠かせないものとなっていきます。
海兵隊はヘリコプターを突撃輸送機として使用する先駆者となり、
自ら編み出した垂直突撃や包囲戦術を実践しました。
また海兵隊のヘリコプターは、敵陣の背後にある、
アクセスできない場所(たいていは山の上)に兵員を輸送しています。
しかし、朝鮮戦争でヘリコプターを使った攻撃が一貫して行われなかったため、
ヘリコプターは敵からの攻撃を受けるという経験をしないまま終戦を迎えます。
これは、ヘリコプターにとって不幸なことでした。
ヘリコプターは地上からの攻撃に弱い、という致命的な弱点に
誰も気づかずにベトナム戦争に投入されて、すぐにそれを敵に見抜かれ、
甚大な人的被害を被るという最悪の結果を招くことになったのです。
海兵隊は最終的に89機のHRS-3を購入していました。
これは海軍のより強力な、700馬力のライトR-1300-3を搭載していました。
HRS-3のBuNo.130252は、1953年3月31日に
コネチカットのシコルスキー工場で海兵隊に受け入れられました。
HMR-162の "ゴールデンイーグルス "に譲渡され、
1953年8月19日にUSS 「バターン」(CVL-29)に搭載されて日本に到着し、
その後、改修されるまで日本に駐在していたそうです。
1957年1月4日には、MCASサンタアナのヘリコプター輸送部隊
「フライングタイガース」に送られました。
1958年2月ハードタック核実験作戦を支援するため、
USS「ボクサー」(CVS-21)に搭載されてビキニ環礁に向けて出発。
その後1964年10月には、MCAS岩国の海兵隊航空機整備隊17に所属。
1966年に空軍軍用機保管処分センターに移され、引退しました。
総飛行時間は3,608時間でした。
【ソ連の回転翼機】
やっぱりこちらも同様に、回転翼機の技術を開発していたのです。
最初に成功した輸送用ヘリコプターはMil Mi-4で、
シコルスキーとほぼ同様の性能を持っていたそうです。

ミル・ミィ4 気のせいかHUSにそっくり
すぐに武装したシコルスキーH-34やミルMi-4が戦闘行為を行います。
その後、次世代のヘリコプターが開発されるにつれ、
各モデルに武装オプションが追加されていきました。
ベトナム戦争におけるベルUH-1ヒューイやミルMi-8のように。
本当の意味の攻撃ヘリは、ベトナム戦争の真っ最中に、
アメリカ陸軍の切実なニーズから生まれました。
基本的な設計要件は、輸送用ヘリよりも高速で機動性が高く、
かつ重装甲で火力が強いことです。
その要望に応え、ロッキード社の「AH-56シャイアン」始め、
シコルスキー、カマン、ベルからも続々と試作品が提出されました。
シャイアンは設計が複雑すぎて、予算もスケジュールも大幅にオーバーし、
採用に至ることはありませんでしたが、
代わりに出てきたHSS-1は、海軍の対潜戦用ヘリとして1952年に就役しました。
【H-34シーホース】
話をシコルスキーH-34に戻しましょう。
H-34はアメリカ海軍の対潜水艦戦(ASW)機として設計された
ピストンエンジン搭載のヘリコプターで、対潜哨戒機以外にも
実用機、捜索救難機、VIP輸送機などの役割を担いました。
輸送機としては12〜16人の兵員を、医療救護のためには
8つの担架を運ぶことができ、VIP輸送機としても乗り心地は良かったようです。
その後、UH-1ヒューイやCH-46シーナイトなど、
タービンエンジンを搭載した機種に置き換えられていったので、
これがアメリカ海兵隊で運用された最後のピストンエンジン搭載機になりました。
H-34は1953年から1970年までに2,108機が製造されました。
シンプルであるがゆえに信頼性が高く、ベトナム戦争で
海兵隊員たちはこれを名指しで要求したとされます。
いかに彼らに必要とされていたかは、海兵隊独特のスラングとして、
同機がもう使われなくなって久しい現在でも、
"Give me a HUS!"
"Get me a HUS!"
"Cut me a HUS! "
「助けてくれ!」
という意味で使われていることからも窺い知れるというものです。
H-34は、最初に戦場に投入されたヘリコプター・ガンシップの一つでもあり、
M60C機関銃2挺とロケット弾ポッド2個からなる
TK-1(Temporary Kit-1)でゴリゴリに武装されていましたが、
「スティンガー」という武装したH-34は賛否両論あり、すぐに廃止されました。
【マリーン・ワン第1号機】
1957年9月7日、ドワイト・D・アイゼンハワー大統領は、
ロードアイランド州ニューポートの別荘で休暇を過ごしていましたが、
ある出来事が起こり、ホワイトハウスで彼の身柄が早急に必要となりました。
そこで、マリーン・ヘリコプター・スクワッドロン・ワン(HMX-1)の
バージル・D・オルソン大佐らは、HUS-1に乗ってナラガンセット湾を渡り、
待機しているエアフォース・ワンまで大統領を飛ばすよう命じられました。
HMX-1は1962年にVH-3Aシーキングに切り替わるまで、
HUS-1で大統領を輸送し続けました。
アメリカ陸軍とアメリカ海兵隊の共同運行管理であったため、
この時期の専用ヘリコプターのコールサイン・名称には
「アーミー・ワン」が用いられていました。
現在の「マリーン・ワン」のコールサイン・名称となるのは、
運行管理がアメリカ海兵隊単独となった1976年以降のことになります。
「FLAMのシーホース」
UH-34D(BuNo 150219)は、1962年12月21日、
やはりコネチカットのシコルスキー工場で海兵隊に納入され、
HMM-364の「パープルフォックス」に配属されました。
1963年9月、HMM-364機として沖縄のMCAS普天間基地に配備されています。
1963年12月にはHMM-361の「フライング・タイガース」に移され、
ベトナム沖での戦闘活動のためにUSS「バレーフォージ」(LPH-8)に乗組。
その後USS 「イオージマ」(LPH-2)でベトナムでの戦闘活動を続けました。
1964年12月には、HMM-163「リッジランナー」に移され、
もういちどMCAS普天間に戻されました。
その後、日本のNAS厚木のデポでメンテナンスを受け、
1964年12月、「リッジランナー」とともに普天間基地に戻り、
ベトナムのダナンに派遣され、HMM-162(ゴールデンイーグルス)、
HMM-365(ブルーナイツ)、HMM-161(グレイホーク)と一緒に活動しました。
何度もNAS厚木での整備期間を経て、1968年5月、
ベトナムのフーバイが最後の戦闘任務となりました。
帰国してからはサンフランシスコのアラメダ基地の倉庫にいましたが、
1972年2月に退役しました。
当機は6年半の間に12の飛行隊で合計4,124時間飛行し、
その生涯のほとんどが戦闘状態にありました。
























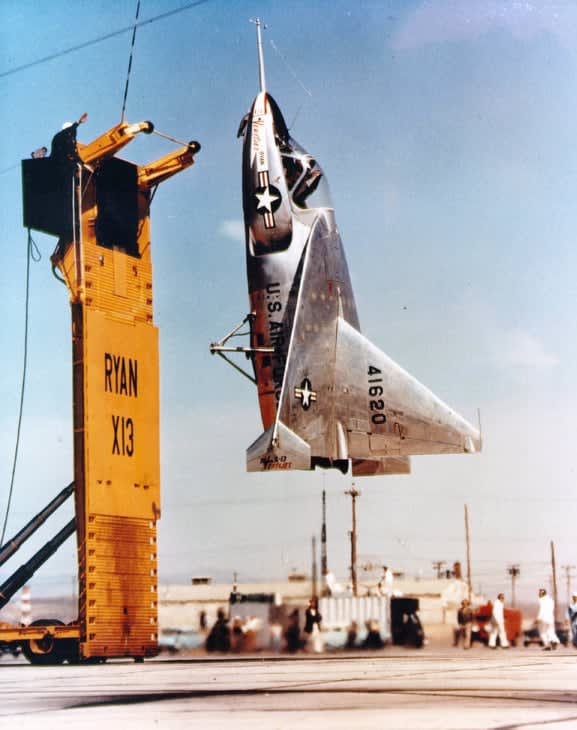





































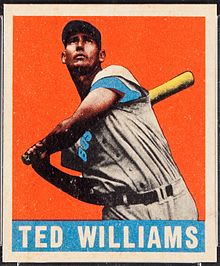



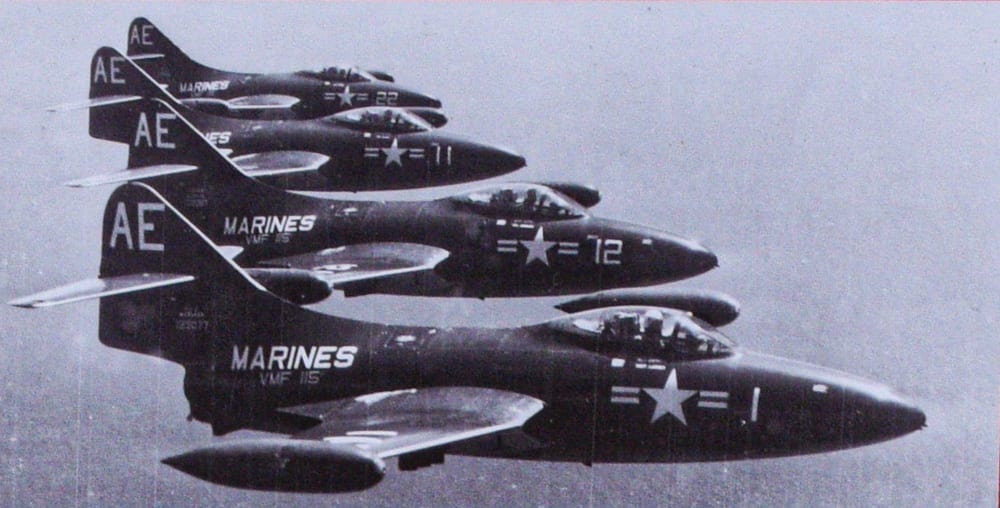

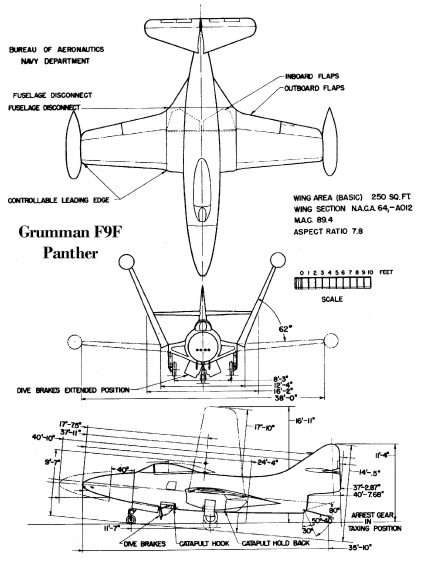
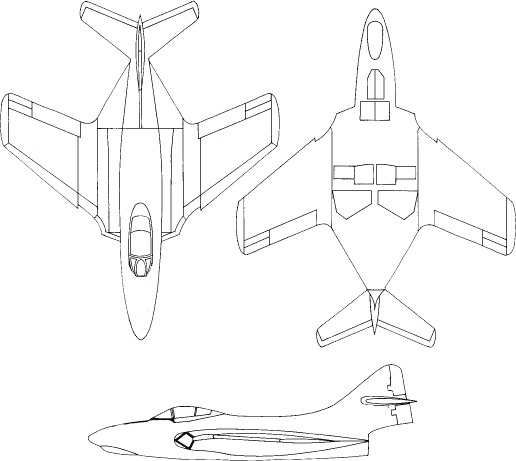




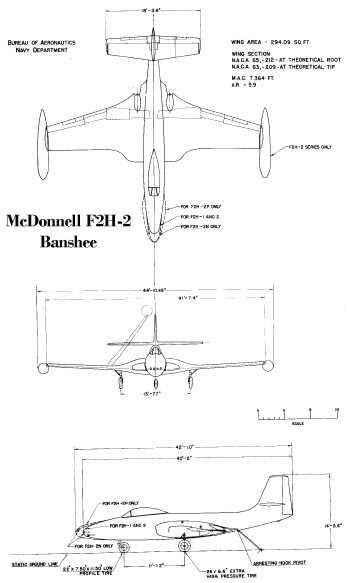

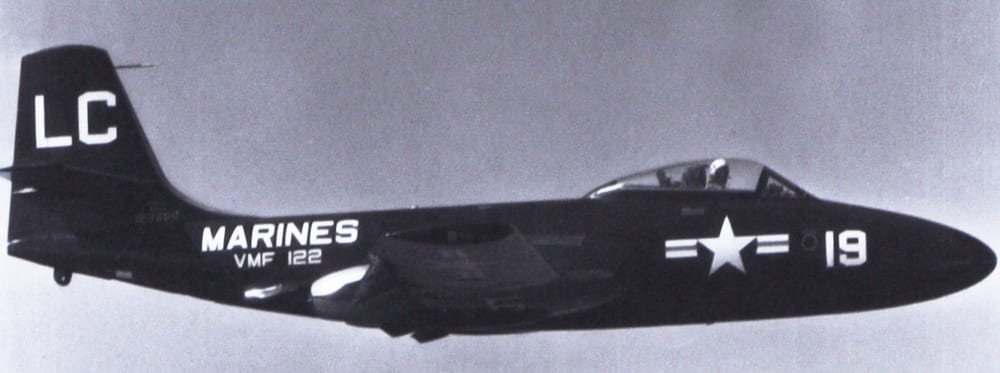
























































 Maj. Gen.Alberto Briganti
Maj. Gen.Alberto Briganti