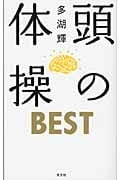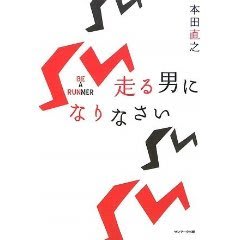★「社長の教科書/小宮一慶(ダイヤモンド社1500円)」
紹介が遅くなりましたが、小宮一慶氏の近刊「社長の教科書」です。タイトルに偽りなし。中小企業経営者に最低限知ってもらいたい、心がけてもらいたい、やめてもらいたいことが「原理原則50」としてまとめられています。
まずは「経営とは何か」という経営者が身につけるべき基本から入ります。注目は、よくある落とし穴「社長のアイデアを絶対と思うな。仮説と思え」、そして同族企業にありがちな「公私混同の禁止」。前者は社長の思いつきには部下は大抵反論しないが故の落とし穴です。後者は、オーナー企業と言えども、法人格を持つ会社は公のものですから、「部下がやっても許せるかが自分の行動の基準」と実にうまい線引きをしています。部下が「妻は会社に通う自分の世話をしてくれているのだから、会社に来ない妻にも給与を払って欲しい」と言ったら、社長は「ふざけるな!」と言いますよね。すなわち、社長も会社に無関係な自分の家族に形式給与を払うのは社員から見たら「ふざけるな!」であって、それが公私混同ということなのです。この考え方こそ社員が経営者についてくるための「帝王学」であると著者は言っています。なるほどですね。本章の一節が、私は他の経営指南書にない本書の素晴らしい部分であると思いました。
以降は、「ビジョン・理念」「戦略立案」「マーケティング」「会計・財務」「ヒューマン・リソース」「リーダーシップ」について、コンパクトにポイントをまとめてくれています。計数データの扱いがお得意の小宮氏が「ビジョン」とか「シナリオ」とか概念的な分野を説くのは少し珍しい感じがしますが、逆に専門分野でないからこそ仔細に入り込み過ぎないほどよい内容にまとまっているようにも思います。「会計・財務」はその得意分野をあえて約30ページに凝縮してまとめてくれています。ポイントはいつもどおり、貸借対照表の重要性(経営素人は損益計算書で「いくら儲かった」「いくら経費がかかった」ばかりに気を取られがちです)とキャッシュフロー重視の経営のすすめです。この点は、何冊もの同じようなビジネス書で繰り返し読んででも、しっかりと身につけるべきポイントですね。
と言う訳で、全般的にこの手の本は“浅く広く”になりがちなので、ガツンと手ごたえを感じる内容ではないのですが、よくある経営全般領域の指南書としてはかなりバランスが良い部類かと思います。中身は常識的かつ教科書的な内容であるので、全体を通しての印象はこの手の本の宿命として10点満点で7点といった感じですが、先にもお話ししたように冒頭の「経営という仕事と経営に対する考え方」のくだりが他にないなかなか良い事を言っていますので、十分8点でよろしいかと思いました。本の帯に「この危機のときに、リーダーは何を学ぶべきなのか?」とありますが、まさしくこの時代だからこそ必要な“経営のこころ”を丁寧に説いている1冊であると言っていいのではないでしょうか。
最近小宮氏の「日経新聞の本当の読み方がわかる本」が大変売れているようです(「日経新聞の数字がわかる本」の続編です)。こちらの方が小宮氏らしい著作かなとは思います。時間があればこちらも取り上げます。
紹介が遅くなりましたが、小宮一慶氏の近刊「社長の教科書」です。タイトルに偽りなし。中小企業経営者に最低限知ってもらいたい、心がけてもらいたい、やめてもらいたいことが「原理原則50」としてまとめられています。
まずは「経営とは何か」という経営者が身につけるべき基本から入ります。注目は、よくある落とし穴「社長のアイデアを絶対と思うな。仮説と思え」、そして同族企業にありがちな「公私混同の禁止」。前者は社長の思いつきには部下は大抵反論しないが故の落とし穴です。後者は、オーナー企業と言えども、法人格を持つ会社は公のものですから、「部下がやっても許せるかが自分の行動の基準」と実にうまい線引きをしています。部下が「妻は会社に通う自分の世話をしてくれているのだから、会社に来ない妻にも給与を払って欲しい」と言ったら、社長は「ふざけるな!」と言いますよね。すなわち、社長も会社に無関係な自分の家族に形式給与を払うのは社員から見たら「ふざけるな!」であって、それが公私混同ということなのです。この考え方こそ社員が経営者についてくるための「帝王学」であると著者は言っています。なるほどですね。本章の一節が、私は他の経営指南書にない本書の素晴らしい部分であると思いました。
以降は、「ビジョン・理念」「戦略立案」「マーケティング」「会計・財務」「ヒューマン・リソース」「リーダーシップ」について、コンパクトにポイントをまとめてくれています。計数データの扱いがお得意の小宮氏が「ビジョン」とか「シナリオ」とか概念的な分野を説くのは少し珍しい感じがしますが、逆に専門分野でないからこそ仔細に入り込み過ぎないほどよい内容にまとまっているようにも思います。「会計・財務」はその得意分野をあえて約30ページに凝縮してまとめてくれています。ポイントはいつもどおり、貸借対照表の重要性(経営素人は損益計算書で「いくら儲かった」「いくら経費がかかった」ばかりに気を取られがちです)とキャッシュフロー重視の経営のすすめです。この点は、何冊もの同じようなビジネス書で繰り返し読んででも、しっかりと身につけるべきポイントですね。
と言う訳で、全般的にこの手の本は“浅く広く”になりがちなので、ガツンと手ごたえを感じる内容ではないのですが、よくある経営全般領域の指南書としてはかなりバランスが良い部類かと思います。中身は常識的かつ教科書的な内容であるので、全体を通しての印象はこの手の本の宿命として10点満点で7点といった感じですが、先にもお話ししたように冒頭の「経営という仕事と経営に対する考え方」のくだりが他にないなかなか良い事を言っていますので、十分8点でよろしいかと思いました。本の帯に「この危機のときに、リーダーは何を学ぶべきなのか?」とありますが、まさしくこの時代だからこそ必要な“経営のこころ”を丁寧に説いている1冊であると言っていいのではないでしょうか。
最近小宮氏の「日経新聞の本当の読み方がわかる本」が大変売れているようです(「日経新聞の数字がわかる本」の続編です)。こちらの方が小宮氏らしい著作かなとは思います。時間があればこちらも取り上げます。