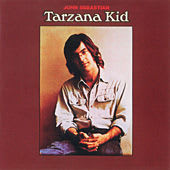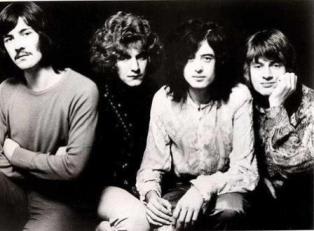ジョニ・ミッチェルの紙ジャケットがようやく発売されました。それにちなんで、彼女のアルバムの中で最高にお気に入りの1枚を取り上げます。
★ Hejira / Joni Mitchell
1. Coyote
2. Amelia
3. Furry Sings The Blues
4. A Strange Boy
5. Hejira
6. Song For Sharon
7. Black Crow
8. Blue Motel Room
9. Refuge Of The Roads
ジョニ・ミッチェルの音楽はアートです。彼女の音楽は内面をすべてさらけ出すかのような繊細さを常に感じさせ、その時々の心模様を非常にストレートに表現しようとしているように思えます。その軸になっているのが彼女独自の変則なオープンチューニングであり、そのチューニングの結果として得られる不思議な旋律もまた、微妙に揺れ動く彼女の内面を赤裸々に表わしているかのようで、一度はまると聞く者の心の耳を捉えて離さない不思議な魅力に満ち溢れているのです。決して美人とは言い難い彼女が、デビッド・ブルーやジェームス・テイラー、グラハム・ナッシュ、ジャコ・パストリアスといった音楽界の錚々たるイケ面たちと恋仲にあったという事実は、その繊細で謎めいた女性としての魅力に引きつけられた結果であろうと、彼女の音楽を聞いているだけでその人間的魅力が分かるような気がするのです。
彼女の音楽キャリアの中で、一般的な名盤と言えば初期のシンガーソングライター的告白アルバム「ブルー」や、ジャズメンとの美しすぎる融合作であった「コート・アンド・スパーク」あたりが常に上げられるのでしょうが、私のイチオシは76年の作品「逃避行」です。先に記した彼女の繊細さや謎めいた印象が最も強く表れた作品であり、このアルバムで初めて共演した、ジャズ界の鬼才ベーシストであるジャコ・パストリアスのベース・ラインがあまりにジョニの音楽性にマッチして、恐ろしいほどに深く、しかしながら恐ろしいほどに澄んだジョニ・ミッチェルの世界へと誘ってくれるのです。
アルバム全9曲は捨て曲なしの素晴らしい楽曲水準にあることはもちろんですが、やはり特筆すべきはジャコとの共演である①⑤⑦⑨が圧巻の出来栄えであると思います。まず①「コヨーテ」は軽快なジョニのギターとアンニュイなニュアンスのジャコのベースにボビー・ホールのパーカッションがアクセントに入る程度でありながら、冒頭からこの雰囲気はなんなのだという実に不思議な世界へといきなり引きずり込まれる思いがします。⑤「逃避行」は歌うジャコのベースがさながらジョニのボーカルとデュオを奏でている、そんな印象の1曲です。さすがにタイトルナンバー、アルバム全体を覆う言うに言われぬ独自のムードが最も強く感じられる名演であると思います。
⑦「黒いカラス」は、アルバムの内ジャケットでジョニ自身が翼を広げたカラスを模したアクションをとっており、アルバムのもう一つの主題と言っていい楽曲でしょう。ジョニのアコーステックのコードカッティングにジャコのエフェクティブなコーラス・ベースとラリー・カールトンの不思議なリード・ギター、3者の演奏だけで構成されるカラスの羽ばたきはまるで絵画を見ているかのような演奏です。音楽家であり画家・写真家でもある彼女の作品はどれもみな絵画的な表現が多いのが特徴でもあるのですが、この曲における写実性は他のどの作品よりもすさまじいものがあると思います。
このアルバムの共演を機にジャコとの蜜月が始まり、次作では芸術家同士の競演がやや一般リスナーとなかけ離れた芸術の領域に入り込む嫌いも出てきます。それは言ってみれば、出会って間もなくの舞い上がっていたジョンとヨーコとも相通じる、芸術家故の嵯峨であるのかもしれません。そういった意味からも、出会いがしらのギリギリの緊張感の中で、作られたこのアルバムこそが奇跡の1枚であり、ジャケット・アートとの統一感も含め長いジョニの音楽キャリアを通じての最高傑作と呼ぶにふさわしいアルバムであると、私は信じて止まないのです。
★ Hejira / Joni Mitchell
1. Coyote
2. Amelia
3. Furry Sings The Blues
4. A Strange Boy
5. Hejira
6. Song For Sharon
7. Black Crow
8. Blue Motel Room
9. Refuge Of The Roads
ジョニ・ミッチェルの音楽はアートです。彼女の音楽は内面をすべてさらけ出すかのような繊細さを常に感じさせ、その時々の心模様を非常にストレートに表現しようとしているように思えます。その軸になっているのが彼女独自の変則なオープンチューニングであり、そのチューニングの結果として得られる不思議な旋律もまた、微妙に揺れ動く彼女の内面を赤裸々に表わしているかのようで、一度はまると聞く者の心の耳を捉えて離さない不思議な魅力に満ち溢れているのです。決して美人とは言い難い彼女が、デビッド・ブルーやジェームス・テイラー、グラハム・ナッシュ、ジャコ・パストリアスといった音楽界の錚々たるイケ面たちと恋仲にあったという事実は、その繊細で謎めいた女性としての魅力に引きつけられた結果であろうと、彼女の音楽を聞いているだけでその人間的魅力が分かるような気がするのです。
彼女の音楽キャリアの中で、一般的な名盤と言えば初期のシンガーソングライター的告白アルバム「ブルー」や、ジャズメンとの美しすぎる融合作であった「コート・アンド・スパーク」あたりが常に上げられるのでしょうが、私のイチオシは76年の作品「逃避行」です。先に記した彼女の繊細さや謎めいた印象が最も強く表れた作品であり、このアルバムで初めて共演した、ジャズ界の鬼才ベーシストであるジャコ・パストリアスのベース・ラインがあまりにジョニの音楽性にマッチして、恐ろしいほどに深く、しかしながら恐ろしいほどに澄んだジョニ・ミッチェルの世界へと誘ってくれるのです。
アルバム全9曲は捨て曲なしの素晴らしい楽曲水準にあることはもちろんですが、やはり特筆すべきはジャコとの共演である①⑤⑦⑨が圧巻の出来栄えであると思います。まず①「コヨーテ」は軽快なジョニのギターとアンニュイなニュアンスのジャコのベースにボビー・ホールのパーカッションがアクセントに入る程度でありながら、冒頭からこの雰囲気はなんなのだという実に不思議な世界へといきなり引きずり込まれる思いがします。⑤「逃避行」は歌うジャコのベースがさながらジョニのボーカルとデュオを奏でている、そんな印象の1曲です。さすがにタイトルナンバー、アルバム全体を覆う言うに言われぬ独自のムードが最も強く感じられる名演であると思います。
⑦「黒いカラス」は、アルバムの内ジャケットでジョニ自身が翼を広げたカラスを模したアクションをとっており、アルバムのもう一つの主題と言っていい楽曲でしょう。ジョニのアコーステックのコードカッティングにジャコのエフェクティブなコーラス・ベースとラリー・カールトンの不思議なリード・ギター、3者の演奏だけで構成されるカラスの羽ばたきはまるで絵画を見ているかのような演奏です。音楽家であり画家・写真家でもある彼女の作品はどれもみな絵画的な表現が多いのが特徴でもあるのですが、この曲における写実性は他のどの作品よりもすさまじいものがあると思います。
このアルバムの共演を機にジャコとの蜜月が始まり、次作では芸術家同士の競演がやや一般リスナーとなかけ離れた芸術の領域に入り込む嫌いも出てきます。それは言ってみれば、出会って間もなくの舞い上がっていたジョンとヨーコとも相通じる、芸術家故の嵯峨であるのかもしれません。そういった意味からも、出会いがしらのギリギリの緊張感の中で、作られたこのアルバムこそが奇跡の1枚であり、ジャケット・アートとの統一感も含め長いジョニの音楽キャリアを通じての最高傑作と呼ぶにふさわしいアルバムであると、私は信じて止まないのです。