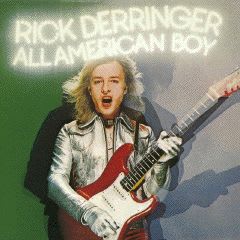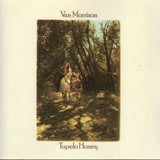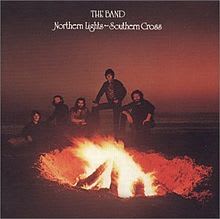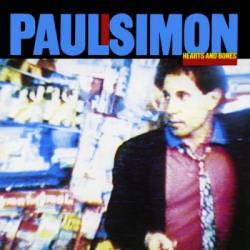今回は、私のブラコン初体験時期のお気に入り3曲を紹介します。
7.「夜汽車よ!ジョージアへ…/グラディス・ナイト&ザ・ピップス」
★YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=C4Vfxq7Hs_I&feature=related

中坊の私がラジオで聞いて「うーん、名曲だぁ」と染み入ってしまったのがこの曲。楽曲のよさもさることながら、はじめはゆるゆるスタートしながら徐々に盛り上げて、しまいにはぐいぐい引き込んでしまうグラディス・ナイトのボーカルの素晴らしさにノックアウト状態でした。人生で初めて買ったブラコンのシングル盤です。雑誌で写真を見て驚いたのは、てっきり太っちょのオバさんだとばかり思っていたのが、小柄なグラディスの風貌。こんな体のどこからこんなにソウルフルでパンチの効いた歌唱が出てくるのか、本当に不思議でなりませんでした。今だに彼女の代表曲として、またほかのシンガーにも歌い継がれる名曲として燦然と光り輝いています。中坊時代の私の眼力もたいしたものです。それと、邦題も素晴らしいですね。「!」と「…」の使い方は、その後パクらせていただいてます。
8.「ロッキンロール・ベイビー/スタイリスティックス」
★YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=0vrVGzDmIm4

一転してこちらはノリの良いソウルナンバーというより、タイトルのとおりロックンロールのソウル版?曲調は確かに3コードのロックンロールですが、ファルセット・ボーカルが確実にブラコンを感じさせる実に不思議なナンバーです。同名タイトルのアルバムからのファースト・シングルでした。当時はスタイリスティックスは日本の一般ピープルレベルではまだまだ無名状態。この後、同アルバムからの第二弾シングル「誓い」が大ヒットして日本でも一躍人気ソウル・ボーカル・グループにのし上がるわけです。「誓い」後はご存知のとおり、ラッセル・トンプキンスJRのファルセット・ボーカルを前面に押し立てたバラード一辺倒の展開に。彼らのバラード路線、どれも代わり映えしない暑苦しい感じが個人的には興味がわきません。たまにはこの手のノリのいい楽しいやつとバランス良くやったらいいと思うのですが…。ちなみに当時、ラッセルのボーカルは絶対に女性だと思っていました。
9.「1000億光年の彼方/スティーヴィー・ワンダー」
★YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=yIE6unjkXmc&feature=fvsr

おなじみスティーヴィー・ワンダーです。スティーヴィーはこの当時すでに日本で人気アーティストで、「迷信」「サンシャイン」が特に大ヒットしました。その後は「ハイヤー・グラウンド」とか「悪夢」とか「迷信」パターンの曲が主流だったのですが、アルバム「ファースト・フィナーレ」からの「悪夢」に続く第二弾シングルがこの曲でした。忘れもしない試験勉強中の深夜、FMから流れてきたのこのバラードの旋律の美しさとスティヴィーのボーカルの素晴らしさに本当に感動して聞き入ってしまいました。先のグラディス・ナイトもマイケル・ジャクソンもそしてこのスティーヴィーもそうですが、いかにもブラコンチックなリズミカルなナンバーもちろんいいのですが、黒人の極めつけはやはりバラードですね。アメリカでは「レゲ・ウーマン」(レゲエじゃなくて“レゲ”って言うのが時代を感じさせます)がA面でしたが、日本のみこちらがA面。バラード好きな国民性を読んだ、当時のレコード会社のファインプレーだと思います。
7.「夜汽車よ!ジョージアへ…/グラディス・ナイト&ザ・ピップス」
★YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=C4Vfxq7Hs_I&feature=related

中坊の私がラジオで聞いて「うーん、名曲だぁ」と染み入ってしまったのがこの曲。楽曲のよさもさることながら、はじめはゆるゆるスタートしながら徐々に盛り上げて、しまいにはぐいぐい引き込んでしまうグラディス・ナイトのボーカルの素晴らしさにノックアウト状態でした。人生で初めて買ったブラコンのシングル盤です。雑誌で写真を見て驚いたのは、てっきり太っちょのオバさんだとばかり思っていたのが、小柄なグラディスの風貌。こんな体のどこからこんなにソウルフルでパンチの効いた歌唱が出てくるのか、本当に不思議でなりませんでした。今だに彼女の代表曲として、またほかのシンガーにも歌い継がれる名曲として燦然と光り輝いています。中坊時代の私の眼力もたいしたものです。それと、邦題も素晴らしいですね。「!」と「…」の使い方は、その後パクらせていただいてます。
8.「ロッキンロール・ベイビー/スタイリスティックス」
★YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=0vrVGzDmIm4

一転してこちらはノリの良いソウルナンバーというより、タイトルのとおりロックンロールのソウル版?曲調は確かに3コードのロックンロールですが、ファルセット・ボーカルが確実にブラコンを感じさせる実に不思議なナンバーです。同名タイトルのアルバムからのファースト・シングルでした。当時はスタイリスティックスは日本の一般ピープルレベルではまだまだ無名状態。この後、同アルバムからの第二弾シングル「誓い」が大ヒットして日本でも一躍人気ソウル・ボーカル・グループにのし上がるわけです。「誓い」後はご存知のとおり、ラッセル・トンプキンスJRのファルセット・ボーカルを前面に押し立てたバラード一辺倒の展開に。彼らのバラード路線、どれも代わり映えしない暑苦しい感じが個人的には興味がわきません。たまにはこの手のノリのいい楽しいやつとバランス良くやったらいいと思うのですが…。ちなみに当時、ラッセルのボーカルは絶対に女性だと思っていました。
9.「1000億光年の彼方/スティーヴィー・ワンダー」
★YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=yIE6unjkXmc&feature=fvsr

おなじみスティーヴィー・ワンダーです。スティーヴィーはこの当時すでに日本で人気アーティストで、「迷信」「サンシャイン」が特に大ヒットしました。その後は「ハイヤー・グラウンド」とか「悪夢」とか「迷信」パターンの曲が主流だったのですが、アルバム「ファースト・フィナーレ」からの「悪夢」に続く第二弾シングルがこの曲でした。忘れもしない試験勉強中の深夜、FMから流れてきたのこのバラードの旋律の美しさとスティヴィーのボーカルの素晴らしさに本当に感動して聞き入ってしまいました。先のグラディス・ナイトもマイケル・ジャクソンもそしてこのスティーヴィーもそうですが、いかにもブラコンチックなリズミカルなナンバーもちろんいいのですが、黒人の極めつけはやはりバラードですね。アメリカでは「レゲ・ウーマン」(レゲエじゃなくて“レゲ”って言うのが時代を感じさせます)がA面でしたが、日本のみこちらがA面。バラード好きな国民性を読んだ、当時のレコード会社のファインプレーだと思います。