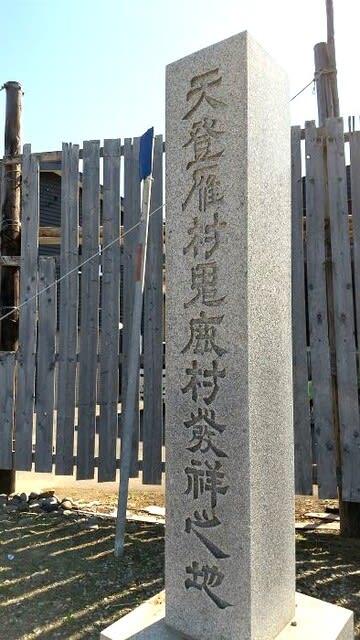稚内のお宿事情は5月~10月のオンシーズンとそれ以外のオフシーズンでは全く違います。
オンシーズンとオフシーズン、月の境の1日で宿泊料金が全く違ってしまい、混雑状況もこれまた段違い。
オンシーズンの半年で1年分の稼ぎをしなければいけないのでこれは仕方ないのは承知しています。
私が最近、稚内で定宿にしていたお宿もオフシーズンの倍以上したしな。
そのシーズンの境目、私が稚内に宿をとったのは5月2日でした。
今年の曜日の配列のこの微妙な一日、その隙をついてお宿を予約しました。
いろいろな要素がありこのお宿に決めたのですが、それを書いていくとキリがないので省略。
お宿の場所は稚内駅から徒歩10分ほど、要は街中の便利な場所にあるということ。
私は車なので立地は関係ないのですが、街中の便利なところにあるのは何かと助かります。
お宿は2階建て、1階はフロントや食堂、浴室などがあります。
2階はアウトバス・トイレの10部屋が廊下の両側に並んでいます。
普段は商用客で賑わっているのであろう、観光シーズンも混みあっているに違いない。
その隙をついてこの日に予約した私、その選択眼は間違いなかったらしい。
細かいことは申し上げませんが、ゆっくりと過ごすことができました。
これはひたすら、お宿の主の人柄にもよります。
ちょっとした会話の中に、人柄がにじんでいました。
このお宿、個人的には馴染むなぁ…。