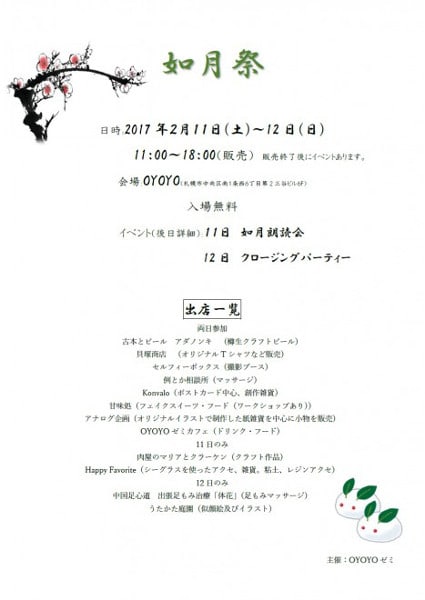場所は下雄柏10号、道路脇の畑の中にありますが、
草むらの向こうにあり草の背が伸びるころには発見が難しいかもしれません。
濁川から行くと道道の左側になります。
明治44年、オシラネップ特別教授場として開校しました。
40平方メートル、柾葺掘立小屋を校舎にし、児童数20数名とのこと。
開拓が奥地に進んだ事により大正9年、15号に移転し雄柏尋常小学校に、
更に開拓が進んだことにより昭和10年、12号に移転しています。
おや、学校が少し手前に戻ってきた。
これは昭和7年、24号に上雄柏特別教授場ができたため、
オシラネップ原野全体で学校のバランスをとるための移転です。
それでは年表です。
明治44年 渚滑第二教育所(後の滝下小学校)所属「オシラネップ特別教授場」として開校
大正 9年 15号に移転、「雄柏尋常小学校」と改称、独立
昭和10年 12号に移転
昭和16年 「雄柏国民学校」となる
昭和19年 高等科併置
昭和22年 「雄柏小中学校」となる
昭和48年 閉校