ラモン・ビラロ『侍とキリスト』(平凡社、2011年)
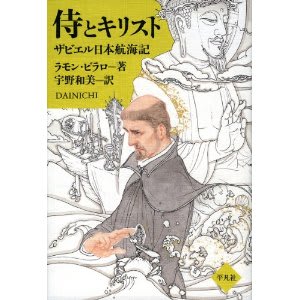 図書館でたまたま見つけた。日本へのキリスト教布教の先陣を飾ったことで、つとに有名な、あのフランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着してから、平戸、山口、堺、京都、山口と回って、平戸から中国へ向かって旅立って行くまでを描いた小説。
図書館でたまたま見つけた。日本へのキリスト教布教の先陣を飾ったことで、つとに有名な、あのフランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着してから、平戸、山口、堺、京都、山口と回って、平戸から中国へ向かって旅立って行くまでを描いた小説。
ゴアにいるときにキリスト教の洗礼を受けた弥治郎という鹿児島出身の若者がいたことが、ザビエルの日本での布教を決心させたということだが、通訳をしてくれる者がいなかったら、とても布教などできないだろう。この小説の主題となっていることはいくつかあるが、その一つに唯一神の概念を理解させることが難しいということがある。
日本人はあらゆるところに存在するヤオロズの神々を信仰し、さらには多数存在する仏の手本である阿弥陀、如来などを信仰する多神教である。キリスト教とユダヤ教、そしてイスラム教以外は、ほとんどの宗教が多神教だと思うのだが、その意味では一神教のほうが珍しい。現代の日本人なら、信仰するかどうかは別として、概念的は理解できるだろうが、イエスのような人の姿をしているわけでもなく、まったく実体をもたず、どんな姿形もしていない唯一存在としての神というようなものが、理解できなかったのはよく分かる。
その上、上に挙げた一神教がすべてそうだが、これらは排他的な宗教である。ここで排他的というのは、敵対的という意味ではなくて、この小説でも問題になっていたが、キリスト教を信仰したら、他の宗教を信仰してはいけないという意味である。仏教にせよ神道にせよ、どちらも同時に信仰してもかまわない。思うに、こうした排他性は結局、敵対性になる。
だから、仏僧のトップたちが、キリスト教を排除しようとした理由もここにある。とくにこの小説でしっかり描かれているが、鹿児島の福昌寺の忍室との対談で、忍室は互いを認め合っていくのなら何も問題ない、仏教には仏教の真理への近づき方があり、キリスト教にもそれ固有の道がある、だから互いを尊重しあっていこうと主張しているのにたいして、ザビエルはそれを頑なに拒んでいる。そういう排他的な宗教を仏教の指導者たちが受け入れられないのは当然だろう。
もう一つ不思議なのは、庶民にキリスト教が広まっていったことだ。もちろん庶民は虐げられ、貧しい暮らしを余儀なくされていた時代だ。だからといって、訳の分からない宗教に救いを求めるというのが私には理解できない。もちろんあくまでも少数派には違いないが、キリスト教の何が彼らを動かしたのか、知りたいものだが、残念ながら、そこまで立ち入った書き方にはなっていない。
原題はDAINICHIという。これは大日如来のことで、神を日本人に理解させることが難しく、彼らの心のなかにストンと入るものを探した結果、「大日」と呼ぶようにしたということから来ている。だが、京都ではまったく布教の手がかりをつかむことができず、山口への帰還を余儀なくされたため、ザビエルはそれが神を勝手に大日などと言い換えたことへの天罰だと思い込む。
ザビエルは日本を出て、中国への布教に行くが、それも果たさないうちに亡くなっている
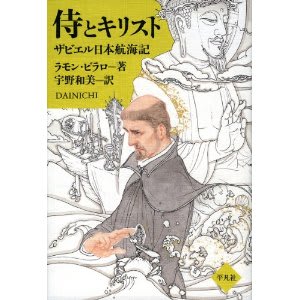 図書館でたまたま見つけた。日本へのキリスト教布教の先陣を飾ったことで、つとに有名な、あのフランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着してから、平戸、山口、堺、京都、山口と回って、平戸から中国へ向かって旅立って行くまでを描いた小説。
図書館でたまたま見つけた。日本へのキリスト教布教の先陣を飾ったことで、つとに有名な、あのフランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着してから、平戸、山口、堺、京都、山口と回って、平戸から中国へ向かって旅立って行くまでを描いた小説。ゴアにいるときにキリスト教の洗礼を受けた弥治郎という鹿児島出身の若者がいたことが、ザビエルの日本での布教を決心させたということだが、通訳をしてくれる者がいなかったら、とても布教などできないだろう。この小説の主題となっていることはいくつかあるが、その一つに唯一神の概念を理解させることが難しいということがある。
日本人はあらゆるところに存在するヤオロズの神々を信仰し、さらには多数存在する仏の手本である阿弥陀、如来などを信仰する多神教である。キリスト教とユダヤ教、そしてイスラム教以外は、ほとんどの宗教が多神教だと思うのだが、その意味では一神教のほうが珍しい。現代の日本人なら、信仰するかどうかは別として、概念的は理解できるだろうが、イエスのような人の姿をしているわけでもなく、まったく実体をもたず、どんな姿形もしていない唯一存在としての神というようなものが、理解できなかったのはよく分かる。
その上、上に挙げた一神教がすべてそうだが、これらは排他的な宗教である。ここで排他的というのは、敵対的という意味ではなくて、この小説でも問題になっていたが、キリスト教を信仰したら、他の宗教を信仰してはいけないという意味である。仏教にせよ神道にせよ、どちらも同時に信仰してもかまわない。思うに、こうした排他性は結局、敵対性になる。
だから、仏僧のトップたちが、キリスト教を排除しようとした理由もここにある。とくにこの小説でしっかり描かれているが、鹿児島の福昌寺の忍室との対談で、忍室は互いを認め合っていくのなら何も問題ない、仏教には仏教の真理への近づき方があり、キリスト教にもそれ固有の道がある、だから互いを尊重しあっていこうと主張しているのにたいして、ザビエルはそれを頑なに拒んでいる。そういう排他的な宗教を仏教の指導者たちが受け入れられないのは当然だろう。
もう一つ不思議なのは、庶民にキリスト教が広まっていったことだ。もちろん庶民は虐げられ、貧しい暮らしを余儀なくされていた時代だ。だからといって、訳の分からない宗教に救いを求めるというのが私には理解できない。もちろんあくまでも少数派には違いないが、キリスト教の何が彼らを動かしたのか、知りたいものだが、残念ながら、そこまで立ち入った書き方にはなっていない。
原題はDAINICHIという。これは大日如来のことで、神を日本人に理解させることが難しく、彼らの心のなかにストンと入るものを探した結果、「大日」と呼ぶようにしたということから来ている。だが、京都ではまったく布教の手がかりをつかむことができず、山口への帰還を余儀なくされたため、ザビエルはそれが神を勝手に大日などと言い換えたことへの天罰だと思い込む。
ザビエルは日本を出て、中国への布教に行くが、それも果たさないうちに亡くなっている
























