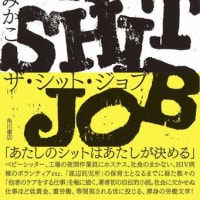NHKBS「蝶々夫人は悲劇か?」
 23日のBSで岡村喬生さんが夏にイタリアでおこなった改訂版の「蝶々夫人」上演にいたる紆余曲折を放送していた。プッチーニが1904年にミラノ・スカラ座で初演した「蝶々夫人」には、日本の文化にたいする無理解が原因になっているおかしな部分がたくさんあるということはよく知られている。その極めつけが、ピンカートンと結婚するときに誠意を示すためにキリスト教に改宗した蝶々に、彼女の叔父である僧侶のボンゾーが「カミサルンダシーコ」と訳の分からない言葉を投げつけるところである。
23日のBSで岡村喬生さんが夏にイタリアでおこなった改訂版の「蝶々夫人」上演にいたる紆余曲折を放送していた。プッチーニが1904年にミラノ・スカラ座で初演した「蝶々夫人」には、日本の文化にたいする無理解が原因になっているおかしな部分がたくさんあるということはよく知られている。その極めつけが、ピンカートンと結婚するときに誠意を示すためにキリスト教に改宗した蝶々に、彼女の叔父である僧侶のボンゾーが「カミサルンダシーコ」と訳の分からない言葉を投げつけるところである。
岡村さんはこれを「天罰が下る」というように歌詞を換えたり、結婚式に参列した芸者たちに歌を歌いながら踊らせたりなどなど、色々な変更を加えたものをもって、夏のプッチーニ演劇祭に参加するために、日本でオーディションをして、練習して、イタリアに乗り込んだのだが、プッチーニの孫が勝手な変更は許されないと言い出して、ほとんど通常の形で上演されることになった。おまけにスズキ役の女性も野外上演に向かないということで、三回のうちの最後の上演だけになってしまったり、岡村さんとしては散々な結果になった一部始終をカメラで追っている。
私もこれを見ながら、日本の文化の実際に合わせて変更可能なところを変えて、できるだけ真実に近いバージョンを創り上げようとしてきた岡村さんの無念の思いに共感した。たしかにプッチーニの孫が言うところの、あらゆる作品は誤解の上に成り立っているのであって、それを全部修正することは不可能であり、そういうものとして後世に伝えるしかないということも分からぬでもないなと思いながら番組を見ていた。だが、後になって調べてみると、1904年の初演では散々な結果に終わり、その後も何度か修正を加えてパリ版が一般的に使われるものだが、その後もプッチーニ以外の人間が勝手に修正を加えたものが上演されてきたのだということを知った。そうであるのならば、日本人が主人公で日本を舞台にしたオペラであるのだから、音楽を変えようというわけではなし、せめても訳のわからない歌詞をまともなものに変えることくらい許されてしかるべきだろうと思う。
いつも書くことだが、モーツァルトでさえも、繰り返しが多くて退屈になる。時間も長い。繰り返しは端折ってもっとスピーディに展開するようにすれば、上演時間も2時間程度に収まって現代人の時間感覚にマッチしたものになるはずだ。私はそういうことをしてもいいと思う。そういう改変をすることで古典と言われるものが現代に蘇るはずであり、同時に元の形の意味もまた問い直されるのだという気がする。いくらモーツァルトだからといって、金科玉条のように扱っていては、腐れてしまう。
以前見た「蝶々夫人」についてはこちら
プッチーニ『蝶々夫人』(第12回河内長野マイタウンオペラ)
新国際版『蝶々夫人』
プッチーニ『蝶々夫人』(大阪音楽大学第13回コンサート・オペラ)
 23日のBSで岡村喬生さんが夏にイタリアでおこなった改訂版の「蝶々夫人」上演にいたる紆余曲折を放送していた。プッチーニが1904年にミラノ・スカラ座で初演した「蝶々夫人」には、日本の文化にたいする無理解が原因になっているおかしな部分がたくさんあるということはよく知られている。その極めつけが、ピンカートンと結婚するときに誠意を示すためにキリスト教に改宗した蝶々に、彼女の叔父である僧侶のボンゾーが「カミサルンダシーコ」と訳の分からない言葉を投げつけるところである。
23日のBSで岡村喬生さんが夏にイタリアでおこなった改訂版の「蝶々夫人」上演にいたる紆余曲折を放送していた。プッチーニが1904年にミラノ・スカラ座で初演した「蝶々夫人」には、日本の文化にたいする無理解が原因になっているおかしな部分がたくさんあるということはよく知られている。その極めつけが、ピンカートンと結婚するときに誠意を示すためにキリスト教に改宗した蝶々に、彼女の叔父である僧侶のボンゾーが「カミサルンダシーコ」と訳の分からない言葉を投げつけるところである。岡村さんはこれを「天罰が下る」というように歌詞を換えたり、結婚式に参列した芸者たちに歌を歌いながら踊らせたりなどなど、色々な変更を加えたものをもって、夏のプッチーニ演劇祭に参加するために、日本でオーディションをして、練習して、イタリアに乗り込んだのだが、プッチーニの孫が勝手な変更は許されないと言い出して、ほとんど通常の形で上演されることになった。おまけにスズキ役の女性も野外上演に向かないということで、三回のうちの最後の上演だけになってしまったり、岡村さんとしては散々な結果になった一部始終をカメラで追っている。
私もこれを見ながら、日本の文化の実際に合わせて変更可能なところを変えて、できるだけ真実に近いバージョンを創り上げようとしてきた岡村さんの無念の思いに共感した。たしかにプッチーニの孫が言うところの、あらゆる作品は誤解の上に成り立っているのであって、それを全部修正することは不可能であり、そういうものとして後世に伝えるしかないということも分からぬでもないなと思いながら番組を見ていた。だが、後になって調べてみると、1904年の初演では散々な結果に終わり、その後も何度か修正を加えてパリ版が一般的に使われるものだが、その後もプッチーニ以外の人間が勝手に修正を加えたものが上演されてきたのだということを知った。そうであるのならば、日本人が主人公で日本を舞台にしたオペラであるのだから、音楽を変えようというわけではなし、せめても訳のわからない歌詞をまともなものに変えることくらい許されてしかるべきだろうと思う。
いつも書くことだが、モーツァルトでさえも、繰り返しが多くて退屈になる。時間も長い。繰り返しは端折ってもっとスピーディに展開するようにすれば、上演時間も2時間程度に収まって現代人の時間感覚にマッチしたものになるはずだ。私はそういうことをしてもいいと思う。そういう改変をすることで古典と言われるものが現代に蘇るはずであり、同時に元の形の意味もまた問い直されるのだという気がする。いくらモーツァルトだからといって、金科玉条のように扱っていては、腐れてしまう。
以前見た「蝶々夫人」についてはこちら
プッチーニ『蝶々夫人』(第12回河内長野マイタウンオペラ)
新国際版『蝶々夫人』
プッチーニ『蝶々夫人』(大阪音楽大学第13回コンサート・オペラ)
 | プッチーニ:歌劇《蝶々夫人》アレーナ・ディ・ヴェローナ2004年 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 日本コロムビア |