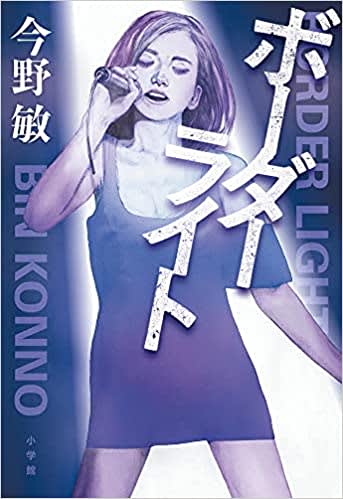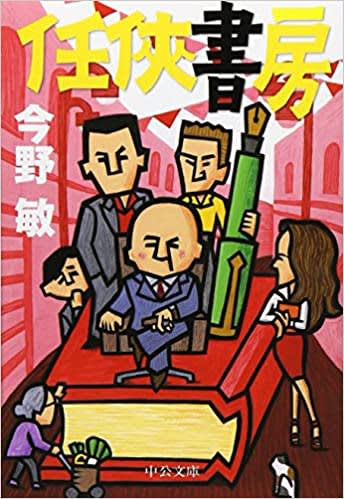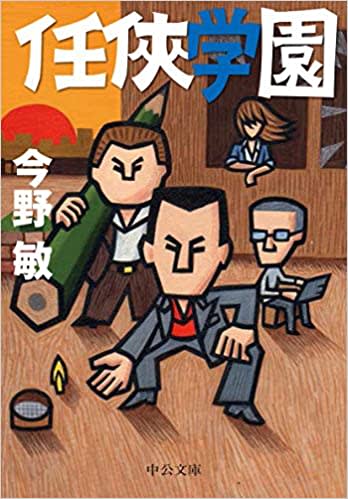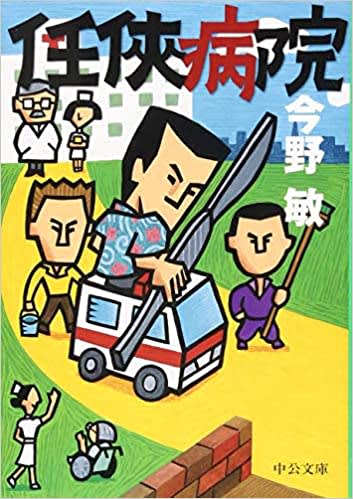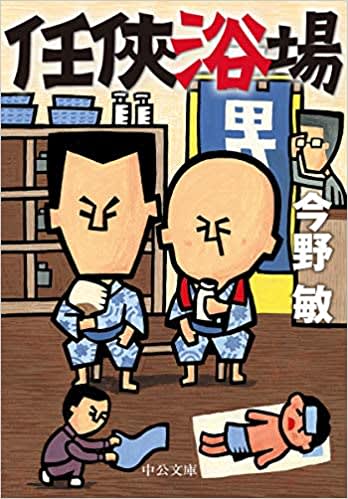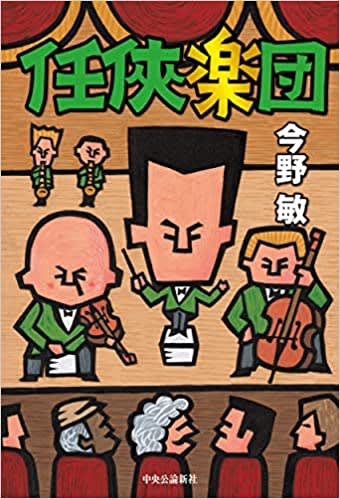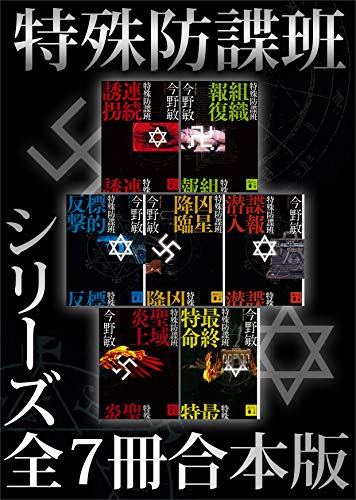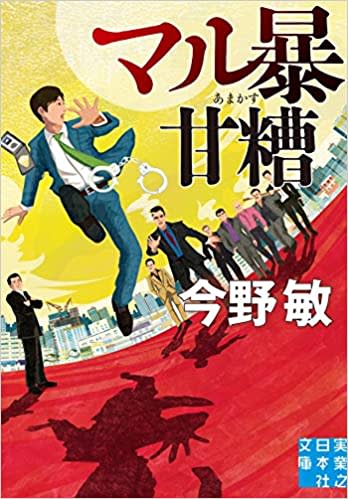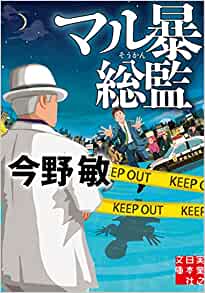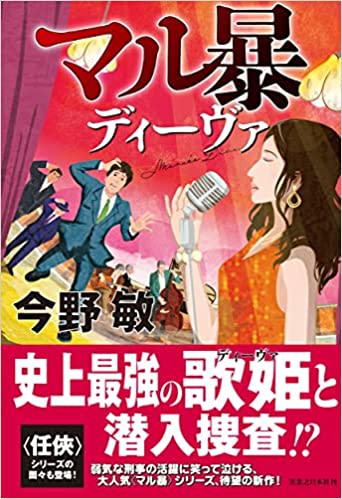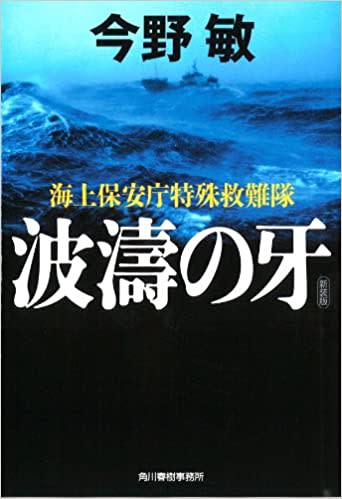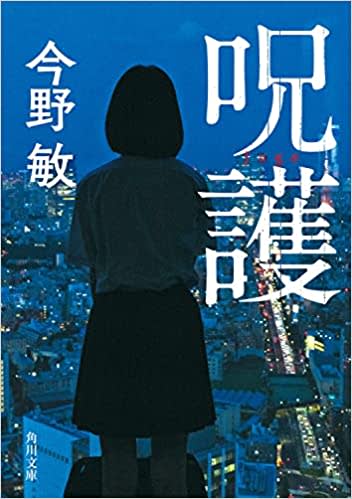最近読んだ『マル暴甘糟』シリーズの甘糟がちょい役で登場しているという任侠シリーズ既刊6巻を一気読みしました。
語り手は日村誠二。30代半ばで、今時珍しい任侠道をわきまえたヤクザ・阿岐本組の代貸です。組は組長を含めて総勢6名ですが、阿岐本組長が異様に顔が広く、全国のヤクザの組長に収まっている人たちと若い時分に兄弟の盃を交わしているため、大きな指定暴力団の傘下に入らないまま独立で生き残っています。
甘糟はこの阿岐本組の様子見に来ており、時には阿岐本組に対する警察側の理不尽な扱いがあった際に助けてくれたりするので、「ちょい役」というほど小さな役割ではありません。
さて、甘糟刑事のことはともかく、この任侠シリーズの面白いところは、組長が損得ではなく人情で様々な面倒ごとの解決を引き受け、そのたびに振り回されている心配性の日村の人間性と、組長のヤクザらしからぬ行動の手伝いを嬉しそうにする若い衆の意外な可愛さでしょうか。
とにかく、阿岐本組長の弟分の神永が毎回処理に困った旨味のない債権などを持ち込み、阿岐本組長がお人よしなのか道楽なのか理由はともかく、それを引き受けるのがこのシリーズのお約束です。
最初に持ち込まれるのが、倒産寸前の出版社です。(任侠書房)
潰してしまえばそれなりに処分できる財産はなくはないものの、それそれで面倒なことも起こるということで、阿岐本組長が経営を引き受けて出版社を立て直すというストーリーです。
阿岐本組がどのように出版社の問題点を見極めて解決していくかが見ものです。
問題自体は極めて現実的で生臭いのですが、それらを阿岐本組長の体現する理想論でスカッと解決し、解決後は見事に身を引くところに大きなカタルシス効果があります。
次に持ち込まれるのは廃坑寸前の学校法人・井の頭学院高校で、絵に描いたような「荒れた学校」です。
窓ガラスは割れ放題、校庭も花壇も荒れ放題、生徒はやりたい放題という状態で、先生方はとにかく「生徒たちが卒業してくれさえすればいい」というスタンスで生徒を教育する気がなく、校長も生徒たちをお客さん扱いし、とにかく親から苦情が来るようなことをしないのが第一と考えているところに阿岐本組長たちが理事長と理事として乗り込んでいくわけです。
まずは掃除から、というのがとてもシンプルですが、効き目が絶大なのが読んでいて気持ちがいいです。
ロクに学校に通ったことがなく高校中退の日村が、花壇の手入れや割れたガラスの始末などをしながら、少しずつ生徒たちと交流して、彼らの心を掴んでいくのがいいですね。擦れて全然大人の言うことなんか聞かないような子たちでも、真剣に向き合ってくれる大人にはだんだん心を開くようになるというメッセージが強く込められているように感じました。
学校に対して発言力を持つモンスターペアレンツの問題にも切り込んでいて、本当にこんなふうにうまく解決出来たらどんなにいいだろうという夢が語られています。
3つ目のエピソードで持ち込まれるのは、倒産寸前の病院です。
こちらは「地域の病院を失くしてはいけない」という信念のもと、医療法人の理事として阿岐本組が乗り込むことになります。
この巻では最初から病院内の清掃を始めとするあらゆるサービスをまとめて受けている業者ときな臭いことになります。このサービス業者がヤクザのフロント企業で、割高な料金を請求し、病院の経営を悪化させてたので、あわや抗争か?という緊張があります。
ここでは病院が抱える人手不足や医療制度のしわ寄せなどの問題も扱われてはいますが、制度的なことはどうにもできないので、問題のサービス業者を切ることと、病院長を始めとするスタッフの気持ちを向上させることに尽力しています。
出版社、学校、病院と続けて見事に立て直した後、阿岐本組はその実績を見込まれて?今度は赤坂にある銭湯の立て直しの相談に乗ることになります。
現代の日本人にはゆっくり風呂に入ることが重要だ!という強いメッセージが込められているようです。
同時に、「子どもには子どもの人生がある」という建前の元に家業を手伝わせようとせず、話し合いも持たなかった経営者と家族の問題も描かれており、親に聞かれないから言わないだけで、子どもは子どもで結構自分なりに考えていることが明らかになるのがいいですね。
銭湯の次に持ち込まれたのは街の小さな映画館。娯楽が多様化し、映画も家で見れる時代、わざわざ映画館で映画を見る人たちは激減し、大きな映画館は次々閉館の憂き目にあっているものの、小さなミニシアターのような映画館は細々と生き残っています。「千住シネマ」もその一つで、閉鎖の噂に対して存続を願う「ファンの会」 がクラウドファンディングで資金を募ってなんとかしようという動きもあり、千住興行の社長も迷っている状態のところに阿岐本組が乗り込みます。
この「ファンの会」は嫌がらせを受けているため、最初阿岐本たちは嫌がらせの犯人と勘違いされるのですが、実は阿岐本組長自身も映画、特に任侠映画が好きで、高倉健のファンということで、本当に映画館存続の相談に乗るつもりであることが理解してもらえます。
この嫌がらせの犯人と、社長が悩む理由がこのエピソードのメインテーマです。
最新刊『任侠楽団』で持ち込まれる相談事は、タイトルの通りオーケストラなのですが、今回は経営危機ではなく、大切な公演を控えているのに内部対立が激化しているのをなんとかするという話です。
阿岐本組長たちはコンサルティング会社の人間として招待を隠して事態に当たることになります。
お門違いもいいところではないかと思わなくもないですが、その辺りが阿岐本組長のおおらかさというか、モノ好きというか、面白いところです。
ここでは乗り込んで早々に常任指揮者に任じられたばかりのエルンスト・ハーンがオーケストラ内でいきなり殴られて気絶させられるという事件が起き、所轄が事件で済ませたがっているのに、ハーンは「殴られたんだから絶対に犯人を見つけろ」と言ってきかなかったため、捜査一課の碓氷弘一が1人で捜査に乗り出してきます。
この碓氷という刑事は『警視庁捜査一課・碓氷弘一』というシリーズの主人公で、こちらに客演した形です。こちらのシリーズは読んだことがないので、次に読むものはこれで決まりましたね(笑)
ここで、ハーンを殴った犯人を捜すことは、オーケストラ内の対立問題を解決することに繋がるだろうということで、碓氷と阿岐本が手を組み協力するところが、また味があって面白いです。
またここで、阿岐本が実はジャズも好きという事実が判明します。
つくづく奥の深い人ですね。
このシリーズで阿岐本組が解決していく問題は、本当に現実にありそうなものでリアルである一方、そこに乗り込んでいく阿岐本組は「そんなヤクザが実際にいるのか?いや、いないでしょ」というようなフィクションが交錯しており、それでいて彼らはやはり蛇の道は蛇という彼らにしかできない解決の糸口を持っているところが妙に説得力があるのも魅力の一つだと思います。
また、「オヤジの言うことは絶対」とほぼ盲目的に従う心配性・苦労性の日村もいろんな事案に関わるうちに学んで成長して行く物語であることもシリーズの大事な要素ですね。
今野敏の作品はどれもそうですが、キャラクターたちが非常に魅力的です。
安積班シリーズ
隠蔽捜査シリーズ
警視庁強行犯係・樋口顕シリーズ
ST 警視庁科学特捜班シリーズ
「同期」シリーズ
横浜みなとみらい署 暴対係シリーズ
鬼龍光一シリーズ
奏者水滸伝
マル暴甘糟シリーズ
その他