夏ですね。川そのものよりも川の流れに、氷よりもガラスを触った時の物足りない皮膚の冷覚に夏を感じます。都会であれ、公園へと足を運べば青葉若葉に蝉の声でございます。やはり夏ですね。
「真夏の宿場は空虚であった。」
挨拶もほどほどに、少し遅れてしまいました、7月17日に行われた横光利一『蠅』の研究発表についてご報告いたします。発表は3年鷹觜さん、1年古瀬さん、同じく1年坂さんでした。司会はわたくし2年望月が担当しました。『蠅』は上の一節から始まるわけですが、発表の副題は〈空虚さの受容〉、ということで本文全体に一貫する、或いは底流する〈空虚〉というもの読み解こうという発表者側の試みでした。
『蠅』は【初出】「文芸春秋」大正12年5月、【初刊】『文芸春秋叢書 日輪』大正13年5月(春陽堂)、研究史においては初期の頃から既に映画技法としての〈カメラ・アイ〉が指摘されています。所謂モンタージュという映画技法に則ったもので、様々な視点から、複数のカット、映像の断片を組み合わせることによって、相互のシーンに新たな意味を産出せしめるという方法論でございます。モンタージュ技法の旗手としてエイゼンシュテインが挙げられますが、『蠅』で論じられる〈カメラ・アイ〉という用語も言語論的、又は記号論的映画論とも言えるモンタージュ技法と密接に繋がってるというのが早くから指摘されていました。それからは横光の、主に初期作品との関連、テクストの構図性、登場人物の意義或いは意味、人物と一直線上に語られる物等々、多角的に論じられてきましたが、やはり視点というのがキータームになっているようです。短い作品なので読むとすぐ分かるように、本文の一、九、十節で語られる「蠅」については一つの焦点となっていました。人馬もろともに崖から落下し、その後に空を悠々と飛ぶ「蠅」が語れるとは如何なることか、「馭者」や「饅頭」、その他人物が末尾に描かれる惨劇の当然たる論理的帰結の先取りとして描かれているのではないか、等々述べられてきました。横光の言葉を引いた上で、「饅頭」とは「馭者」にとっての欲望、充たされぬ性欲の対象、権化なのだという論も示唆に富みます。また『蠅』は教材としても扱われることがあるようです。そのような研究史の中で、〈空虚〉性は『蠅」テクストを構成する重要概念として多く取り沙汰され、発表者の方々もその点について今一度証左明証するという意気込みでございました。
もう少し具体的に申しますと、発表者側の指摘は次のようになります。つまり、テクスト末尾の事故の必然性は、人馬の無意味化、物の意味化はテクストに一貫する〈空虚〉に因り、その〈空虚〉とは実は語り手の、或る種の恣意性が介在しているのだ、と。そして物と等価な人間はディスコミュニケーション、ナンセンスかつ〈空虚〉な会話が描写され、必然的に「人と馬と板片との塊り」となって、「沈黙した」のだと指摘する。その上飛翔していく「蠅」が描かれることによって読者は〈空虚〉な時空間に存在するしかないのだ、とここまでが発表者の見解のあらましでございます。
はてさて、議論の中心はまず、馬車上での「目匿し」をされたような人物たちをどのように扱うか、に注目、岡崎先生から、先行研究でも言及されている通り馬車は人生の縮図となっていて、集団の中に埋没する人物が描かれることによって「馭者」に目が向かず、それは馬車の異常に気が付かなかった原因でもあり、我々の生活の形象化でもあるとの御意見をいただきました。発表者側は語り手が〈空虚〉を演出しているとし、そこには〈空虚〉への志向がみられると指摘、加えて、章によっては会話が断絶されるようにして次の章に移り、そこに語り手の恣意性がうかがわれるとしました。
先生から自然主義的な一筆書きで描かれた人物たちは即ち「塊り」であるという指摘の後、映画(ここではトーキー映画)の影響が〈空虚〉性の表現に一役買い、モンタージュ技法が映画で実践されるより以前に『蠅』はモンタージュ技法を文学において駆使したものであり、その点この作品の大きな評価点となるという御言葉をもらいました。加えて先行研究でも言及されていたショット・サイズの転換に注目された上で、「眼の大きな一疋の蠅」は、大きくも小さくも写すことができるカメラレンズを、そしてカメラレンズを描くこと自体が近代以降の技術を示すものでもあるとの御指摘をしていただきました。
さて、本文最後の崖からの墜落、「蠅」の飛翔に話題が移りまして、先生の方から、「蠅」が飛んでいく描写があることによって、『蠅』は悲劇や不条理で終始せずむしろ悲劇の否定が描かれ、ある意味爽快でもあるとの御意見をいただきました。最後に描かれるのは「蠅」による皮肉とは言い切れず、それは「塊り」視線が固まることの否定であり、認知言語学や認知心理学で取り沙汰されるような「ルビンの壺」、つまり図地反転図として読み取れるのではないか、という御意見でもありました。
その他にも、擬人化、語られない空白と予感を裏切る語り、登場人物それぞれへの注目した論等、いずれも今回の発表では〈空虚〉を主題とした議論が交わされました。先行研究においては映画イコール文学という構図を否定したものも既にありますが、いやはや忘我恍惚の中でわたくしは議論を聴いておりました。映画論というものにも手を付けてみたいものです。
以上が今回の『蠅』発表でした。語り手、テクストの構造、映画技法との関り、などなど文学研究を志す者には養分の詰まった話し合いでございました。養分と言えば最近ではスーパーに足を運ぶと養分の詰まった、豊穣で水気の多い夏野菜が並んでおります。皆様はくれぐれも馬車に乗る際、「饅頭」よりも先に夏野菜を摂るようになさってください。ではこれにて失礼します。わたくしがこの文章を作成している現在では既に、7月24日井上靖「猟銃」の読書会が終了しているので悪しからず。ご報告遅れましたことを、この場を借りてお詫び申し上げます。
「真夏の宿場は空虚であった。」
挨拶もほどほどに、少し遅れてしまいました、7月17日に行われた横光利一『蠅』の研究発表についてご報告いたします。発表は3年鷹觜さん、1年古瀬さん、同じく1年坂さんでした。司会はわたくし2年望月が担当しました。『蠅』は上の一節から始まるわけですが、発表の副題は〈空虚さの受容〉、ということで本文全体に一貫する、或いは底流する〈空虚〉というもの読み解こうという発表者側の試みでした。
『蠅』は【初出】「文芸春秋」大正12年5月、【初刊】『文芸春秋叢書 日輪』大正13年5月(春陽堂)、研究史においては初期の頃から既に映画技法としての〈カメラ・アイ〉が指摘されています。所謂モンタージュという映画技法に則ったもので、様々な視点から、複数のカット、映像の断片を組み合わせることによって、相互のシーンに新たな意味を産出せしめるという方法論でございます。モンタージュ技法の旗手としてエイゼンシュテインが挙げられますが、『蠅』で論じられる〈カメラ・アイ〉という用語も言語論的、又は記号論的映画論とも言えるモンタージュ技法と密接に繋がってるというのが早くから指摘されていました。それからは横光の、主に初期作品との関連、テクストの構図性、登場人物の意義或いは意味、人物と一直線上に語られる物等々、多角的に論じられてきましたが、やはり視点というのがキータームになっているようです。短い作品なので読むとすぐ分かるように、本文の一、九、十節で語られる「蠅」については一つの焦点となっていました。人馬もろともに崖から落下し、その後に空を悠々と飛ぶ「蠅」が語れるとは如何なることか、「馭者」や「饅頭」、その他人物が末尾に描かれる惨劇の当然たる論理的帰結の先取りとして描かれているのではないか、等々述べられてきました。横光の言葉を引いた上で、「饅頭」とは「馭者」にとっての欲望、充たされぬ性欲の対象、権化なのだという論も示唆に富みます。また『蠅』は教材としても扱われることがあるようです。そのような研究史の中で、〈空虚〉性は『蠅」テクストを構成する重要概念として多く取り沙汰され、発表者の方々もその点について今一度証左明証するという意気込みでございました。
もう少し具体的に申しますと、発表者側の指摘は次のようになります。つまり、テクスト末尾の事故の必然性は、人馬の無意味化、物の意味化はテクストに一貫する〈空虚〉に因り、その〈空虚〉とは実は語り手の、或る種の恣意性が介在しているのだ、と。そして物と等価な人間はディスコミュニケーション、ナンセンスかつ〈空虚〉な会話が描写され、必然的に「人と馬と板片との塊り」となって、「沈黙した」のだと指摘する。その上飛翔していく「蠅」が描かれることによって読者は〈空虚〉な時空間に存在するしかないのだ、とここまでが発表者の見解のあらましでございます。
はてさて、議論の中心はまず、馬車上での「目匿し」をされたような人物たちをどのように扱うか、に注目、岡崎先生から、先行研究でも言及されている通り馬車は人生の縮図となっていて、集団の中に埋没する人物が描かれることによって「馭者」に目が向かず、それは馬車の異常に気が付かなかった原因でもあり、我々の生活の形象化でもあるとの御意見をいただきました。発表者側は語り手が〈空虚〉を演出しているとし、そこには〈空虚〉への志向がみられると指摘、加えて、章によっては会話が断絶されるようにして次の章に移り、そこに語り手の恣意性がうかがわれるとしました。
先生から自然主義的な一筆書きで描かれた人物たちは即ち「塊り」であるという指摘の後、映画(ここではトーキー映画)の影響が〈空虚〉性の表現に一役買い、モンタージュ技法が映画で実践されるより以前に『蠅』はモンタージュ技法を文学において駆使したものであり、その点この作品の大きな評価点となるという御言葉をもらいました。加えて先行研究でも言及されていたショット・サイズの転換に注目された上で、「眼の大きな一疋の蠅」は、大きくも小さくも写すことができるカメラレンズを、そしてカメラレンズを描くこと自体が近代以降の技術を示すものでもあるとの御指摘をしていただきました。
さて、本文最後の崖からの墜落、「蠅」の飛翔に話題が移りまして、先生の方から、「蠅」が飛んでいく描写があることによって、『蠅』は悲劇や不条理で終始せずむしろ悲劇の否定が描かれ、ある意味爽快でもあるとの御意見をいただきました。最後に描かれるのは「蠅」による皮肉とは言い切れず、それは「塊り」視線が固まることの否定であり、認知言語学や認知心理学で取り沙汰されるような「ルビンの壺」、つまり図地反転図として読み取れるのではないか、という御意見でもありました。
その他にも、擬人化、語られない空白と予感を裏切る語り、登場人物それぞれへの注目した論等、いずれも今回の発表では〈空虚〉を主題とした議論が交わされました。先行研究においては映画イコール文学という構図を否定したものも既にありますが、いやはや忘我恍惚の中でわたくしは議論を聴いておりました。映画論というものにも手を付けてみたいものです。
以上が今回の『蠅』発表でした。語り手、テクストの構造、映画技法との関り、などなど文学研究を志す者には養分の詰まった話し合いでございました。養分と言えば最近ではスーパーに足を運ぶと養分の詰まった、豊穣で水気の多い夏野菜が並んでおります。皆様はくれぐれも馬車に乗る際、「饅頭」よりも先に夏野菜を摂るようになさってください。ではこれにて失礼します。わたくしがこの文章を作成している現在では既に、7月24日井上靖「猟銃」の読書会が終了しているので悪しからず。ご報告遅れましたことを、この場を借りてお詫び申し上げます。















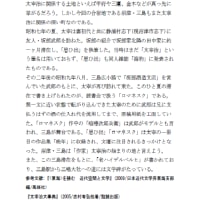

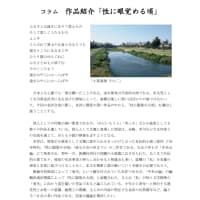
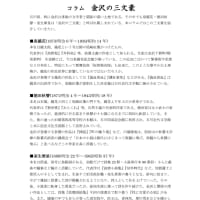
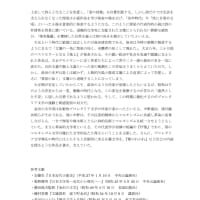
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます