こんにちは。
夏休みが終わり、後期の活動がスタートしました。後期の作品テーマは「嘘と文学」です。
本日は、9月24日に行われた読書会についてご報告致します。扱った作品は太宰治「ダス・ゲマイネ」、司会は私、2年古瀬が務めさせていただきました。
「ダス・ゲマイネ」は、昭和10年10月「文芸春秋」にて発表され、昭和26年6月、新潮社より刊行された『虚構の彷徨・ダスゲマイネ』に収録されました。この作品に対する太宰治の自己評価は高く、書簡の中では特に、表現形式の新しさについて主張しています。
作品の特徴としては、作中人物に作者と同姓同名の〈太宰治〉という作家が登場すること、語り手である〈私〉がいなくなってしまうこと、〈私〉がいなくなった後も物語が続くことなどが挙げられます。これらのことは先行研究でも多く取り上げられており、今回の読書会でも話題になりました。
一章から三章までは、〈私〉=〈佐野次郎〉によって物語が語られていますが、三章の最後に、〈佐野次郎〉は電車にはね飛ばされて死んでしまいます。語り手の死=物語の終わりと思いきや、続きの四章があるのです。四章は〈佐野次郎〉と〈太宰〉以外の作中人物たちの会話文だけで成り立っています。岡崎先生からは、語り手がいなくなっても物語が記述されているということは、語り手よりももう一つ上の概念である、記述者がいることを教えているというご指摘をいただきました。作者の言及にもあった新しい表現形式というのは、非常に挑戦的なものであったと思われます。
時代背景や作者の実生活を絡めた意見や、後期のテーマでもある「嘘」に関する意見も多く挙がりました。
作中人物は知識人を装っているだけで中身がないという指摘から、作中人物たちの生き方についての議論が始まり、先生からは、嘘をつくこと以外に方法がない、何を理想として生きていけばよいか分からない青年たちの姿がコミカルに描かれているものの、悲しく感じるという意見をいただきました。
今回扱った「ダス・ゲマイネ」は難解で読みづらい作品ではありますが、だからこそ研究し甲斐のある作品だと思っています。個人的には特に研究してみたい作品の一つでもあるので、今回の読書会で様々な意見を聞くことができて大変嬉しかったです。
後期第一回目の活動でしたが、良いスタートを切れたのではないでしょうか。
次回の例会は10月8日、国木田独歩「運命論者」の研究発表を行います。
夏休みが終わり、後期の活動がスタートしました。後期の作品テーマは「嘘と文学」です。
本日は、9月24日に行われた読書会についてご報告致します。扱った作品は太宰治「ダス・ゲマイネ」、司会は私、2年古瀬が務めさせていただきました。
「ダス・ゲマイネ」は、昭和10年10月「文芸春秋」にて発表され、昭和26年6月、新潮社より刊行された『虚構の彷徨・ダスゲマイネ』に収録されました。この作品に対する太宰治の自己評価は高く、書簡の中では特に、表現形式の新しさについて主張しています。
作品の特徴としては、作中人物に作者と同姓同名の〈太宰治〉という作家が登場すること、語り手である〈私〉がいなくなってしまうこと、〈私〉がいなくなった後も物語が続くことなどが挙げられます。これらのことは先行研究でも多く取り上げられており、今回の読書会でも話題になりました。
一章から三章までは、〈私〉=〈佐野次郎〉によって物語が語られていますが、三章の最後に、〈佐野次郎〉は電車にはね飛ばされて死んでしまいます。語り手の死=物語の終わりと思いきや、続きの四章があるのです。四章は〈佐野次郎〉と〈太宰〉以外の作中人物たちの会話文だけで成り立っています。岡崎先生からは、語り手がいなくなっても物語が記述されているということは、語り手よりももう一つ上の概念である、記述者がいることを教えているというご指摘をいただきました。作者の言及にもあった新しい表現形式というのは、非常に挑戦的なものであったと思われます。
時代背景や作者の実生活を絡めた意見や、後期のテーマでもある「嘘」に関する意見も多く挙がりました。
作中人物は知識人を装っているだけで中身がないという指摘から、作中人物たちの生き方についての議論が始まり、先生からは、嘘をつくこと以外に方法がない、何を理想として生きていけばよいか分からない青年たちの姿がコミカルに描かれているものの、悲しく感じるという意見をいただきました。
今回扱った「ダス・ゲマイネ」は難解で読みづらい作品ではありますが、だからこそ研究し甲斐のある作品だと思っています。個人的には特に研究してみたい作品の一つでもあるので、今回の読書会で様々な意見を聞くことができて大変嬉しかったです。
後期第一回目の活動でしたが、良いスタートを切れたのではないでしょうか。
次回の例会は10月8日、国木田独歩「運命論者」の研究発表を行います。















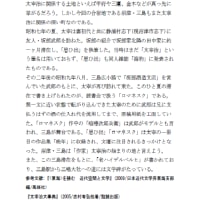

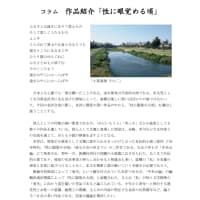
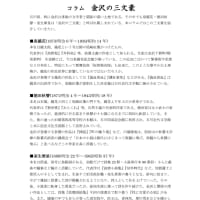
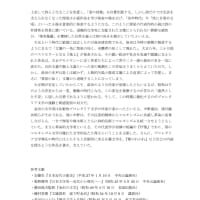
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます