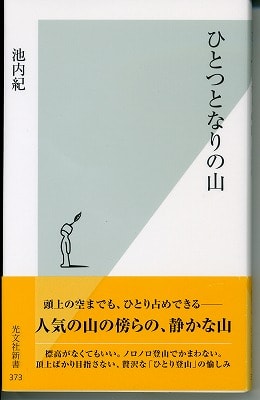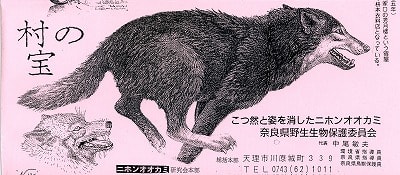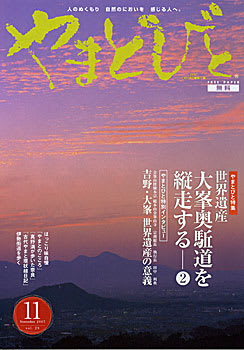これは、まだ現在進行中(つまり読みかけ…)の本です。
「逆説の日本史」は週刊誌連載中(現在も)や単行本、文庫版でも読んだのですが、その後の新しい発掘・発見を踏まえたビジュアル版ということで購入しました。

諸星大二郎の卑弥呼の絵(2ページを使って!)など、「あらずもがな」のイラストや写真もありますが、総じて図版ならではの説得力もあります。
面白かったのは15年前の「古代黎明編」で「箸墓=卑弥呼墓」に「私は賛成しない」と書いていた筆者の考え方が、「可能性が高い」と変わったこと。
つまり邪馬台国九州説から大和説に傾いたわけです。
私・変愚院にとっては、無論、自分の棲み家のある大和説の方が嬉しいのですが…。
「逆説の日本史」は週刊誌連載中(現在も)や単行本、文庫版でも読んだのですが、その後の新しい発掘・発見を踏まえたビジュアル版ということで購入しました。

諸星大二郎の卑弥呼の絵(2ページを使って!)など、「あらずもがな」のイラストや写真もありますが、総じて図版ならではの説得力もあります。
面白かったのは15年前の「古代黎明編」で「箸墓=卑弥呼墓」に「私は賛成しない」と書いていた筆者の考え方が、「可能性が高い」と変わったこと。
つまり邪馬台国九州説から大和説に傾いたわけです。
私・変愚院にとっては、無論、自分の棲み家のある大和説の方が嬉しいのですが…。