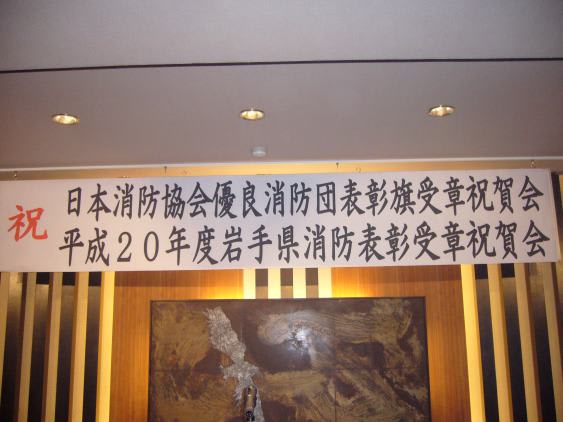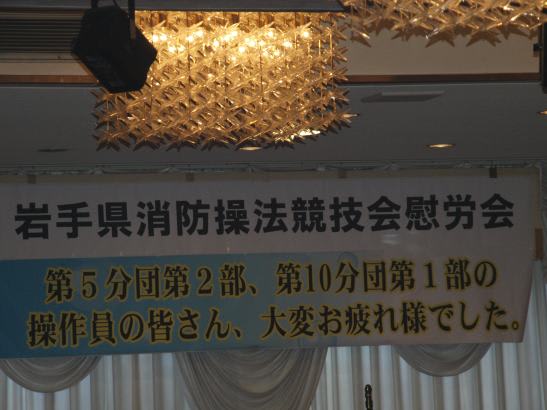宮仕いの定め、年度末は長年職務にあたった方々の退職やら異動での送別の宴が行われる時期でもある。
我職場でも長年勤務され、仕事面はもとより私生活面でもご指導をいただいた上司4名の方々が定年を迎えられ、「旅立ちを祝う会」としての送別の宴に出席いたしました。

我職種的には生え抜きで、まさに陣頭指揮をとった強者といっても過言ではない先輩の方々、現場経験も豊富で、まだまだ現役でご指導やら叱咤激励をいただきたいが本音でもあります。
この先輩方が30歳前後で体力気力が十分満ち溢れていた時代に小生は新人として今の職種に就きました。
先輩方には直接的に指導され、同じ釜の飯を食べ、時には私的部分でもたいへんお世話になった思い出が蘇り、色んなことがついこの間のように思い浮かぶ瞬間でもありました。

長い間、たいへんご苦労さまでした。
そしてお疲れ様でした。
とりあえずは、少しのんびりされまして、第二の人生を楽しまれてください。
たいへんお世話になりました。
ありがとうございました。
ということで、今回退職された先輩方とは、長いお付き合いだったということもあって、色々と昔話的な思い出として、何か語ってくれ・・・とお願いされてましたので、ある上司の方のエピソードなんかをご披露いたしました。
素晴らしい事、凄かったエピソードを語れば良かったのですが、どうしても面白かったことが主となってしまい、その上司には失礼な内容となってしまったことを少し反省しております。
しかし、楽しいエピソードには事欠かない上司でもありましたので、逆にいえば、この方ならでは、この方らしい・・・・そんな場面だったのでは?・・・汗
いずれ、皆さん、個性溢れ、それぞれの得意分野を持ち職務に精通された方々ばかりなので、その別れを皆さん大いに分かち合ったという送別の宴であったと思います。


今が旬、バッケの天婦羅(ふきのとう)

大いに語り、そして食べて飲んで・・・・
そして・・・
二次会は・・・
共に一年間、同じ部として寝食を共にし、汗を流した同僚達との送別の宴を場所を移して行いました。
新年度から部体制の入れ替え、昇進、異動、さらに長期出向となる同僚もいて、それぞれの立場を越えて楽しむことができました。
一年間、ありがとうございました。

ピンボケですが、酒の肴として出た毛ガニのから揚げ・・・。
もちろん、全部食べれます・・・・時折、口の中で何か刺さって痛いのがたまに傷・・・・汗
宴たけなわでしたが、嫁さんも別場所で送別会の宴に参加しており、そちらでも二次会に流れたらしく、そろそろ終わるので帰ろうコール・・・・。
後ろ髪を引かれる思いで同僚達と別れ、嫁さんと合流して帰りました。
しかし、いつもなら皆と〆のラーメンとかを食べるのが常であり、何か物足りない・・・・お腹一杯という嫁さんに何処かでラーメンが食べたいと懇願し、地方都市の街道沿いにチェーン展開されている某外食店のバイパス店、ラストオーダーぎりぎりの時間に飛び込む・・・。

和風ラーメンをいただく。
酔っていたせいもあるかもしれませんが、これが案外美味かった・・・・。
それにしても今月は週に1~2度くらいのペースで飲会に顔を出している。
来週からは新年度、今度は歓迎会等も予定されており懐もかなり寂しくなってきておりますし内臓系も少しお疲れモード・・・涙
いずれ年度末、新年度の恒例ということで、もうひと踏ん張りといったところです。