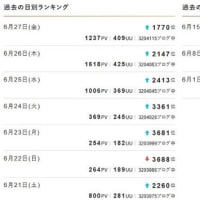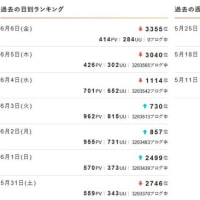▲ 今週のみけちゃん
▼ 新しい街でもぶどう記録;第395週

■ 今週の武相境斜面


■ 今週の草木花実




■ 今週のどうどう

四世同堂/威風堂々 Google[英国のエリザベス女王の歴史的な在位70年「プラチナジュビリー」]
即位は70年前の1952年。戴冠式は、1953年。日本から皇太子(いまの上皇陛下)が参列した。
当時の英国首相はチャーチルであり、出迎えたときの画像がこれなのだろう。
■ 今週(も)貸りて読んだ本

今週(も)貸りて読んだ高橋たか子の本は次の5冊。『亡命者』(1995年)、『霊的な出発』(1985年)、『放射する思い』(1997年)、『この晩年という時』(2002年)、『高橋たか子の「日記」』(2005年)。『亡命者』のみが小説で、他はエッセイと日記。『亡命者』はおいらが読む高橋たか子の2冊目の小説。1冊目は『誘惑者』。これらの本は計4週間貸りている。
◆ なぜ、高橋たか子か? なぜ、高橋たか子の一連の本を読んでいるかの理由。高橋たか子の<創作的現実>に関心がある。高橋たか子は私小説を嫌い、自分の小説から彼女の人間像を探る動きを嫌悪する。おいらは、高橋たか子の人間に興味があるわけではなく、なぜそういう作り話を書くのか?ということ。あるいは、なぜそう(日本は「ダメ」で、ヨーロッパーは「偉い」)考えているのか?を知りたい。
さらに、当時(あるいは今でも)どういう人がどういう動機で高橋たか子の作り話を読んでいるのか?そして、そういう人たちは現実社会でどう生きているのか?に関心がある。もっとも、後者は探るのが難しい。
幸いなことに、高橋たか子は自ら小説、自伝、日記のそれぞれの表現を文学と認識している。そして、小説作品ばかりでなく、自伝、日記も書いている。極めて面白かったのが、自伝・『私が通って来た路』だ。これは、1980年から1988年までのフランス、パリでの修道生活についての記録であり、修道女にはなったが、最後は組織、および「グル」とけんかわかれして帰国する。そのけんか別れのいきさつが、おいらから見て、極めて「俗」で、興味深かった。
特に興味深いのが高橋たか子の脱俗願望とその願望をかなえる修道生活を担保しているのが、おカネであり、高橋たか子はおカネもちに違いないのだ。そして、そのおカネは、高橋たか子が嫌う世俗の読者による彼女の作品の購買に基づくのだ。
高橋たか子はおカネもちに違いないとわかるのは、小説では書かれていないが、自伝『私が通って来た路』では、パリでの生活を可能にできるための身元保証人が必要となった。日本の銀行のパリ支店の日本人銀行員が便宜を図る。理由は、日本の高橋たか子の口座にはおカネがうなるほどあるからである。高橋たか子自らいうに、鎌倉の並んでいる2軒の自宅の1軒は転売価格が一億円であった。著作印税収入も多かったであろう。したがって、修道生活のためパリに行った時、「すべてをすてて」というが、実際は、財産はがっちり保持していた。
そういう金持ちたか子は、パリの加入しているカトリック・セクトで、やって来た気に入らない女性信者の費用を負担することを不満に思い、その気に入らない女性信者をセクトの「グル」が追放しない、厚遇することに不満を抱き、誰がカネ出していると思っているんだといわんばかりの憤懣を自伝『私が通って来た路』で述べる。これは、記録力が、すごい。
要は、俗な言い方で恐縮だが、「承認欲求」の渇きを潤すことができず、セクトを去る。「承認欲求」の渇きを潤すことができないことは、一生続いたようで、その高橋たか子の「宿痾」であり、一連の本に迸(ほとばし)っているのだ。
超俗を目指しながら、極めて俗なところが、おもしろい。
◆ 高橋たか子の小説作品は年代で分けられる。すなわち、1980年以前(前期・高橋たか子)と1990年以降(後期・高橋たか子)。高橋たか子は1980年に小説家を辞めて、修道生活のためパリに行く。修道女にはなったが、加入していたカトリックのセクトを(「けんか」別れして)辞め1988年に56歳で帰国。この時は「死んだも同然」であったと後述。なお、この件について「挫折」とかいう言い方はしていない。今週借りて読んだ本の中で、『霊的な出発』(1985年)のみが「挫折」前の本。いずれにせよ、この4冊は、高橋たか子の8年間のパリ修道生活に言及するもの。その捉え方が興味深い。
1998年の帰国後、1990年代の10年間は痴呆症にもなった母親の面倒のため「最悪の地」京都で暮らす。2003年、京都から神奈川県に移る。
▼『霊的な出発』(1985年)
小説家を辞めて、修道生活に入って、パリでの修道生活の報告記。出版は、発行所 女子パウロ会、港区赤坂8丁目とある。ググると、あった web site。この後、高橋たか子の著作に頻出する「砂漠」、「スプチニア」、「アヴィラの聖テレジア」が、はや、出てくる。これは他の著作でも語られるように、パリでの修道生活の体験に基づく。つまり、ロシアでキリスト者が祈りため小屋を建てる。その小屋をスプチニアという。スプチニアとはロシア語で砂漠の意味。砂漠はキリスト教の聖地のパレスチナの地理的条件だ。そして、砂漠は、世俗的なものを無くした祈りのための極端な状況の象徴でもある。
一九七五年の六月、生まれてはじめて修道院というところに一週間滞在した。北海道のカルメル会女子修道院である。その頃。私はまだキリスト者ではなかった 。
客観的には、新進の小説家として人々から大変羨まれる状態だったのに、世間から私に来るものの一切が嫌だった。そのくせ世間の中に貪欲に何かを探していた 。
回顧
『高橋たか子の「日記」』(2005年)の2004年8月9日の日記に、『霊的な出発』を20年ぶりに読んでのことが記されている;
すると、誰が、自分のことをこういう風に書いたのだろう、と思いに打たれる。いきいきとフレッシュな、神をめぐる歩みが、そこに記録されているのである。誰が書いたのか?誰が、こんなふうにパリで生きていたのか?
一九八〇年代の初めの頃の私であるのだが、もう現在の私がどんなに手を伸ばしても触れることのできない、霊的な出発時の、一歩また一歩と地上を越えて行く女(私)が、そこにいるのである。
その時の、その場所での、その思い。その時にしか感じることのできないその場所での、私というものー というものがある。
そういう私が、あった。
けれども、今、私はそのようではない。
そして、最後に、「でも残念なこと!あの時の私がずっと続いていって天国に突入できればよかったのに。」と云っている。これは1988年に加入していたカトリックのある派から脱退し帰国し、その後修道生活から「還俗」することになったことを踏まえているのだ。
▼小説、『亡命者』1995年
高橋たか子、『亡命者』。1995年の作品。あらすじは、1983年にパリに渡った50歳少し前の日本人女性が主人公。キリスト教信者で、夫と別れ[1]、パリで求道的生活をする。修道院に入るのではなく、パリの安く狭い貸部屋で祈り、教会へ通う。そして、しばしばパリから出て修道院へ小旅行に出かける。この修道院での小修行でやの信者と会い、啓発される。特に、亡命の意味などを再考させられる。この『亡命者』は後半ではこの日本人女性は消え、話が変わる。というか、日本人女性が書く小説がこの小説を構成する。すなわち、この日本人女性が出会ったフランス人夫婦(ダニエルとアニー)の話となる。この夫婦は結婚しているが、二人で修道者となる道を歩む。修道生活をするのはフランスではなく、イスラエルである。さらに、ダニエルの手記が示される。
<理想の人生>この『亡命者』の本人による解説は、「フランス、わが愛」という文章でなされている。このダニエルというフランス人男性が高橋たか子の理想的な男性であり、そういう人物を造形したと書かれている。モデルは4世紀に夫婦で修道生活に入ったイタリア貴族とのこと。この人物こそ、後述するように、高橋たか子がなれなかった人間に違いない。
<日本離脱からフランスへ> この小説の前半の日本人女性がパリに行く話は、高橋たか子の人生と同じである。この小説では離日の理由は明言されておらず、修道への意思も強くは書かれていない。キリスト者と自称し、元小説家であったことは暗示されるが、滞在目的は明言されない。高橋たか子本人の場合のようなカトリックの一セクトの日本導入への活動であるとは書かれていない。ただ、神学校の講義を受ける学生という身分でヴィザを取っている。半年に一度更新しなければいけないヴィザの手続きの困難を冒頭には強く書かれている。つまり、現世の国籍の現実味が書かれている。
<そして、砂漠へ> 高橋たか子は生まれた地を「呪う」。生まれ育った京都を最悪の街という(この世で一番不浄な土地である京都; 『この晩年という時』 2002年刊)。さらに、日本に価値を認めない。だから、フランスに行った。ついには、霊的には日本人からフランス人になったのだと。ところで、当の生粋のフランス人、あるいはヨーロッパ人はキリスト教が広まった4世紀にエジプトなど砂漠の修道院に修道のため赴いた。高橋たか子はこれに着目し、小説『亡命者』ではフランス人のダニエルとアニー(夫婦)をイスラエルに修道のため赴かせる。
<求道の動機> 日本人女性の求道の動機は明確に書かれていないが、後半のダニエルとアニーの物語でダニエルの言葉として求道の動機が書かれている;
君と、こんなに愛し合っているのに決定的に何かが足りない。君に近づけば近づくほど、ますます君は遠ざかる、とみえる。捕まえようとすればするほど、君は、捕まらぬ。アニー、君は、いったい何処にいるのだ?そう思ったよ、ってね。 (『亡命者』)
若い頃から一日たりとも探さない日はなかったもの、それは一対一の男女の熱烈な愛であった。現についているのに、どの相手においても何かがすっぱり欠けている感じがあって、その得ているものの中にいっそう探していた、と。すっぽり欠けていたもの、それは神であったのだ。私はそうとは気づかずに神を探していたのだ。このことを、エルサレム会の枠内で修道者的に生きるようになった頃に気づいた。(高橋たか子、『霊的な出発』 1985年刊行)
<亡命> この小説『亡命者』の亡命は冒頭の日本人女性の日本からフランスへの渡航から、日本人のキリスト教文明への亡命かと思ってします。途中、主人公がフランス人キリスト者との対話で認識を新たにする。亡命とはあの世・神の国からこの世・現世へ来ることだと。生まれ出ることとまでは言っていないが。死ぬこと・召命とは亡命生活の終わりだと。
<夫との別れた状況・事情> この高橋たか子、『亡命者』は先月、新装文庫本として販売され始めた。講談社。1995年に最初に単行本で出た時と同じ出版社。
さて、その新刊の宣伝の文章は;夫と死別し、神とは何かを求めてパリに飛び立った私。極限の信仰を求めてプスチニアと呼ばれる、貧しい小さな部屋に辿り着くが、そこは日常の生活に必要なもの一切を捨て切った荒涼とした砂漠のような部屋。個人としての「亡命」とは、神とは、宗教とは何か。異邦人として暮らし、神の沈黙と深く向きあう魂の巡礼、天路歴程の静謐な旅。 いきなり、「夫と死別し、」とある。おそらく、間違い。むしろ、生き別れたことが暗示されている;
フランスの修道院で大きなマントを着た修道士を見て主人公は想起する;
マントと言っても、昔に日本で着ていたとんびであるから、裾も袖もひらひらして、闇のなかに立っている姿は、誰ともわからぬ。そう、あの十年ほど前の、その瞬間でさえ、影がそこに揺れているのを、走りだしたタクシーの後部の窓から振り返って見て、見間違いかと疑ったほどだから、ふいに記憶から浮かび出たその影法師はなおさら茫漠としていたけれども、それでも、あの時に別れた夫が、タクシーで出ていく私を追って夜の門前へ走り出た姿だ、と、わかってき、思い出すのはやめておこうと思念を切った。そうしたことも、他のたくさんのことも、国境の向こう側へと落としてきたのであったから。
すなわち、主人公は夫を残して、日本からフランスへ渡ったと書いてある。(もちろん、10年前のことなので、その後死んだのかもしれないが、文章には書いていない)したがって、講談社のこの紹介文を書いた人はまともにこの『亡命者』を読んではいないのだ。
もちろん、誤解の原因は容易に推定できる。高橋たか子の夫、高橋和巳が病死し、たか子は夫と死別したという事実に引きずられているのであろう。これこそ、高橋たか子が嫌う小説の主人公の属性と実際の作家の現実の混同である。
わかることは、高橋たか子の『亡命者』の埃を払って文庫として再販した講談社の担当者は作品なぞ読んでいないということだ。講談社の担当者にとって、本は読むものではなく、本は売るもんだからである。なお、作品を読まない担当者は、作品の宣伝者、解説文作文者を選ぶことが、この文庫化の最大の仕事であったらしい。解説文作文者は、芥川賞作家石沢麻依。なお、高橋たか子は芥川賞の候補に4度なったらしい。そして、結局受賞しなかった。『高橋たか子の「日記」』(2005年)には、芥川賞の選定は茶番ではないか?説が披露されている。芥川賞の選定の茶番を暴くには、「内部告発の保護制度」があれば安心と書いている。さらに、なぜこういうことを書くかについてこうかいている;
芥川賞作家という肩書によって書く場を与えられている、実際には評価されていないらしい人々が、文壇・ジャーナリズムを汚してるという印象を受けたからだった。
おいらは、芥川賞作家石沢麻依さんを存じ上げないのだが、芥川賞作家という肩書によって高橋たか子の本のプロモーターをやっているのを見て、にこにこできた。
<この小説を書く動機>
小説という「虚」の中で作者は常に常に生まれ変わりをみずから体験している、という真実がある。亡命者を書き出した瞬間、私自身が、別な姿をとって深みから起き上り、そして、マリ・ダニエルというフランス人男性となって長編の時間を生き抜いていった。今も、そうして私は生きている 。(『この晩年という時』)
つまりは、憧れて、お望みのフランスに行き、8年滞在したが、修道生活をフランスで全うできなかった高橋たか子が帰国後に、修道生活の全うを作り話の登場人物に託したということ。登場人物はフランス人男性であり、「本当に素敵な男性だと自分で作っておきながら思う」と作った本人が云っている。
▼ 『放射する思い』(1997年)
『亡命者』(1995年)のすぐあとに刊行されたエッセイ集。したがって、『亡命者』に関することも多く書かれている。「砂漠・砂漠・砂漠」、「フランスでの、どん底」、「フランス、わが愛」。さらに、この頃、遠藤周作が死んだので、追悼の文章が載っている。遠藤周作は高橋たか子の井上洋治神父による洗礼に立ち会った。
さて、私は、私自身そう望んだわけではないのに、それ以前の私からすれば狂気の沙汰とも思える生活で入っていった。生のどん底へと。
それは無視される私ということ。
さきに日本での過密な状況や意識の事を言ったが、言いかえると、無視されることのない私が日本では異常繁殖しつつあったのであった。そして国境を越えた途端、極か極へと跳ぶように、無視されつづける私を私は生きる羽目になった。
出会うすべての人よりも私が劣っているという状況そのものが、日々、そこにある。それはそうだろう。この世的なものでで自己宣伝しないかぎり、私は誰よりもこの世的には下位にあるから。
こんなどん底へと、私は入っていた。
▼ 『この晩年という時』(2002年)
エッセイ集。10年にわたる母親の介護から解放された頃の本。高橋たか子の人生にまつわるエピソードで興味深いことを抜き書きする;
0. 1999年の日記
七月十八日(雨)日曜
すこし前から、アヴィラの聖テレサの自伝をゆっくり再読し始めている。(再読か、三度目か?)もういちど、彼女を私のそばに立ててみよう。いつも、ずっと。そこから、力が来る。かつて、そうだったように、(以下、略)
7月二十九日(曇)木曜
(中略)
ずっと、蒸し暑い天気が続いている。家中、三台のクーラーをかけて、これが最高のぜいたく。日本ではないところを、少なくとも湿気の除去でつくっている。
1980年からのパリでの修道生活で、アヴィラの聖テレーズが出てくる。そして、禁欲的、苦行的修道で知られるアヴィラの聖テレーズに、勝手に親近感をもつ高橋たか子は、家中、三台のクーラーをかける生活をしていたのだ。
1.
日本を出る少し前に手に入った中央公論社の世界の文学シリーズの『テレーズ・デスケールー』の翻訳料が、何と、当時としてはびっくりする額の百二十万円ほどであり、私はそれを全部使ってしまうつもりだった。
1967年の大卒初任給が26,000円。2022年は22万円。換算すると約1,000万円。ただし、当時は円が安いので(1ドル=360円)、今の価値として330万円(=1000*120/360)ほどか。こうして、計算すると、そうたいしたこともないかな? 今、パリで1年間を300万円では中産階級の程度の暮らしもできそうもないな。
2.
私のまわり ー京大文学部の学生としてその後はかつて学生であった人々ー そこには、一つの強い排他的な潮流があった。それは左翼運動である。運動に参加しないまでも左翼思想がその環境を捲きかえしていた。
左翼でなければバカだ、とでもいった、目に見える平手打ちが来た(同時に、女はバカだという京都という、京都という土地から平手打ちも並行していた。まだ五十人に一人という女子学生のパーセンテージの時代だった)。
私はもともとこの世からずっと後ろに身を退かせている程度のものだったが、この時期に、さらに自分を後退させる姿勢をとるようになった。(私のまわりにあった雰囲気ー昭和三十年前後の頃)
おそらく、こういう状況であったに違いないと思う。それをしっかり文章化してくれて、ありがたい。
▼ 『高橋たか子の「日記」』(2005年)
この頃、小説(『きれいな人』)が賞を受けたとのこと。過去の思い出と現状認識。思い出話は興味深い。一方、現状認識は世俗への否定的見解の列記。
1.
一般的に言って、最近の私は、ドキュメンタリーに興味をもつ。同じ意味で、誰か作家の、作品よりも、その人の自転や日記のほうが、私にはおもしろい。(もっとも、西洋の作家に関してのみ、その人の自伝や日記がおもしろい、ということだが。本当が書いてあるので)
2.
三十三、四歳の頃から、何年もの間、私はどこか精神病院へ入りたい、と夢想していたのだった。
高橋たか子は若い頃から、脱俗意識が強かった。
その他、『霊的な出発』についての回顧も書いてあった(上述)。
3. そして、最後にこれ。これは極めて興味深い。高橋たか子の認識が、他者からはどう見えたのか?示唆される;
私がフランスの会を辞めざるを得なくなったことをー 『私の通った路』の、第三部に書かれていることだがー そのことを、私は日本へ帰国後に、何人もの日本人聖職者にくわしく聞いてもらった。なぜ、そんなことが、神を信じていると言っている人々において起こるのか、教えて欲しかったからである。ところが、それらの日本人聖職者の口から、私が話終わったあと、ほとんど一言の言葉が出なかった。
こんな重大な出来事を1時間以上もかけて聞いてもらっているのに、なぜ?と私は、いっそうわけのわからぬ重くるしい気持ちになって退場したものだった。
なぜ?
彼らが人間としてあまりにも未熟だから、わからなかったのか。きっと、そうだろう。(『私の通った路』の文学読者はわかってくださったらしい反応があったのだから・・・)
■