

1973年受賞。江崎玲於奈 1925- (存命) 三島由紀夫 1925 -1970
[ソース]
三島由紀夫の作品には東京の戦災が出てくる。実際、三島は戦災の東京を生きていた。東京の空襲の大きなもの、すなわち、3月10日の墨東地区の東京大空襲と5月25日の山手空襲のふたつが作品には出てくる。三島自身は、炎に追われるといった経験はしていない。遠くから見た巨視的な視点となる。一番近接した視点としては、罹災者を見ることであった。
一方、三島由紀夫の作品には何度も血と炎が登場する。この血と炎は死を彩る要素だ。血は死へと続くばかりでなく、三島由紀夫にとっては、発情、欲情の因ともなる。『仮面の告白』では若い男の腹に刃を立て血の迸ることを空想して自涜に耽ることが書かれている。一方、炎と死では、既に死んだものではあるが、遺体が火葬される場面を肉体の変化という即物的、そして猟奇的に描写している。いわば、戦災死を、その場で、微視的視点で見れば、見えたはずの状況ともいえる;
屍は次々と火に委ねられていた。縛めの縄は焼き切れ、赤や白の屍衣は焦げ失せて、突然、黒い腕がもたげられたり、屍体が寝返りを打つかのように、火中に身を反らしたりするのが眺められた。先に焼かれたものから、黒い灰墨の色があらわになった。ものの煮えこぼれるような音が水面を伝わった。焼けにくいのは頭蓋であった。たえず竹竿を構えた隠亡が徘徊していて、体は灰になっても頭ばかり燻ぶる屍の、頭蓋をその竿で突き砕いた。(『暁の寺』、8章)
さて、「遠くから見た巨視的な視点での話と、一番近接して罹災者を見ること」の具体的な描写を『仮面の告白』から拾う;
『仮面の告白』で主人公は、3月9日からM市(おそらく前橋市)に行き、泊まる。東京大空襲が始まったのは3月10日午前0時10分。M市から東京の方が真赤にみえたことになっている。現在から見て、この時2-3時間で東京の墨東地区で約10万人が焼き殺された。3月10日に東京に帰る。O駅(おそらく大宮)に着く。そこで、罹災者の群れを見る。その罹災者を見て主人公が考えたことが書かれている;
それにもかかわらず、私の中で何者かが燃え出すのだった。ここに居並んでいる「不幸」の行列が私を勇気づけ私に力を与えた。私は革命がもたらす昂奮を理解した。彼らは自分たちの存在を規定していたもろもろのものが火に包まれるのを見たのだった。人間関係が、愛憎が、理性が、財産が、目の当たり火に包まれるのを見たのである。そのとき彼らは火と戦ったのではなかった。彼らは人間関係と戦い、愛情と戦い、財産と戦ったのである。そのとき彼らは難破船の乗組員同様に、一人が生きるためには一人を殺して良い条件が与えられていたのである。恋人を救おうとして死んだ男は、火に殺されたのではなく、恋人に殺されたのであり、子供を救おうとして死んだ母親は、他ならぬ子供に殺されたのである。そこで戦い 合ったのはおそらく人間のかつてないほど普遍的な、また 根本的な諸条件であった。
私は目覚ましい劇が人間の面に残す 疲労の後を彼らに見た。 私に何らかの 熱い 革新がほとばしった。ほんの行く瞬間ではあるが、 人間の根本的な条件に関する私の不安が、ものの見事に拭い去られたのを私は感じた。叫び 出したい思いが胸に満ちた。
『仮面の告白』は、他の三島の発言により、行動は事実である。心中は創作として、2-3時間で約10万人が焼き殺された状況と上記の想定が整合的であるか理解しがたい。もっとも、『仮面の告白』は何の情報もなく主人公が大宮駅で罹災者を見るので、罹災者を見て、どう思おうが、それは作品の内在的論理に従うのだろう。救おうとした対象に殺されるという論理は、他人を救う暇もなく逃げ、そして死んだ人たちは誰に殺されたことになるのだろうか?よくわからない。
そもそも、三島由紀夫は、空襲は強烈な印象をもたらし、その後の人生でなかなか消えないものであったと昭和37年に云っている;
戦後十七年を経たというのに、未だに私にとって、現実が確固たるものに見えず、仮りの、一時的な姿に見えがちなのも、私の持って生まれた性向だと言えばそれまでだが、明日にでも空襲で壊滅するかもしれず、事実、空襲のおかげで昨日在ったものは今日ないような時代の、強烈な印象は、十七年ぐらいではなかなか消えないものらしい。(三島由紀夫、『私の遍歴時代』)
5月25日の山手空襲を三島は座間の海軍工廠から見た。小田急で家に帰った。家は戦災を免れていた。この山手空襲のあと、主人公が考えたこと;
その晩郊外の家へ落着いて私は生まれてはじめて本気になって自殺を考えた。考えているうちに大そう億劫になって来て、それを 滑稽なことだと思い返した。私には敗北の趣味が先天的に欠けていた。その上 まるで豊かな秋の収穫のように、私のぐるりにある夥しい死、戦災死 、殉職、 戦病死、戦死、 轢死、 病死のどの一群かに、私の名が予定されていない筈はないと思われた。死刑囚は自殺をしない。どう考えても自殺には似合わしからぬ季節であった。私は何ものかが私を殺してくれるのを待っていた。ところがそれは、何ものかが私を生かしてくれるのを待っているのと同じことなのである。
空襲の被害への立ち合いという観点から、三島由紀夫は空襲直後の現場に立ち入った気配はない。一方、晩年の作品で、ある登場人物に5月25日の山手空襲の焼け跡を「経験」させている;
窓からは六月の光の下に、渋谷駅から駅までの間は、ところどころに焼ビルを残した新鮮な焼阯で、ここらを焼いた空襲はわずか一週間前のことである。すなわち昭和二十年五月二十五日の二晩連続して、延五百機のB29が山の手の各所を焼いた。まだその匂いがくすぶり、真昼の光りに阿鼻叫喚が漂っているような気がする。
火葬場の匂いに近く、しかももっと日常的な、たとえば厨房や焚火の匂いもまじり、又、ひどく機械的化学的な、薬品工場の匂いを加味したような、この焼趾の匂いに本多ははや馴れていた。幸い本郷の本多の家はまだ罹災せずにいたけれど。 (三島由紀夫、『暁の寺』)
むかしの町と比べての感慨は、本多は少しもなかった。ただ目はまばゆい廃墟の反射をとらえて、割れた硝子の一片が今目を射るならば、次の刹那にはこの硝子も滅し、焼趾も亦滅して、新たな廃墟を迎えることになるということを、感覚的な確かさで受け入れた。破局に対抗するに破局を以てし、際限もない頽落と破滅に処するに、さらに巨大、さらに全的な一瞬一瞬の滅亡を以てすること、・・・そうだ、刹那刹那の確実で法則的な全的滅却をしっかり心に保持して、なお不確実な未来の滅びに備えること、・・・・本多は唯識から学んだこの考えの、身もおののくような涼しさに酔った。(三島由紀夫、『暁の寺』、第二十章)
興味深いのは、敵、すなわち、アメリカの悪意、無辜を大量死させる悪意には無頓着であること。死ぬまで強烈な印象を残した事象を引き起こした主体とその意図に関心がないのだろうか?不思議だ。これは誰も指摘しないことだ。おいらの感覚がおかしいのかもしれない。おそらく、現在の日本人の主流はこういう考えなのだろう;

https://x.com/CGO23689/status/1898542847609212959
■ 昭和100年
今年は昭和100年である。三島由紀夫は1925年生まれなので、生きていれば、100歳であった。さて、三島由紀夫と云えば?、ノーベル賞である。ノーベル賞候補であった、ノーベル賞を希求していたなどと口さがない京童がうわさする。一方、本当のノーベル賞を獲った江崎玲於奈さんも1925年生まれである。そして、御存命だ。さらには、3月10日の東京大空襲を生き抜いて、その朝、東大で講義を受けている。
- - そして、この朝も、すでになじみになった例の二十五番教室で、田中務教授はいつもと少しも代わらぬ調子で、「物理実験第一」の講義を行った。私は必死になってノートを取った。前夜のことから離れ、物理学の世界に没頭した。東大アカデミズムの存在感が身に伝わったときであった。- - (昭和20年3月10日朝の回顧)
江崎玲於奈・『限界への挑戦 私の履歴書』 (愚記事)
三島は法学部、江崎は理学部の学生だった。理系は兵隊にとられず学業を継続できたのだろう。一方、法学部は兵役、徴用に学生が動員されていた。ただ、病気の学生が学内に残っていた。(あと、特別学生団)。法学部も3月は授業をやったと三島の作品には書いてある。













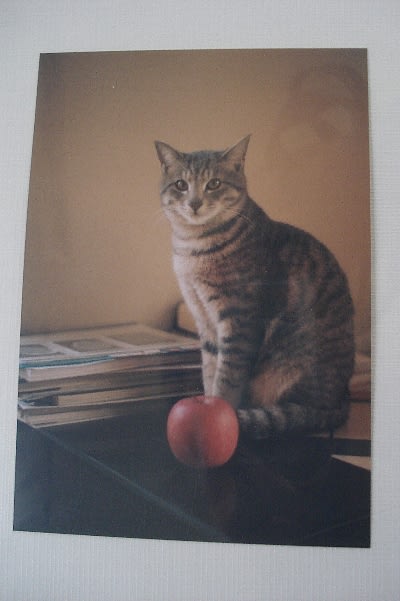
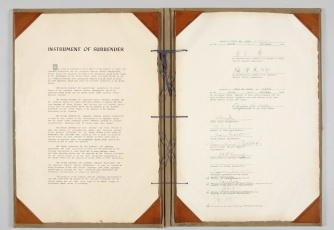

 9時4分
9時4分 9時8分
9時8分
























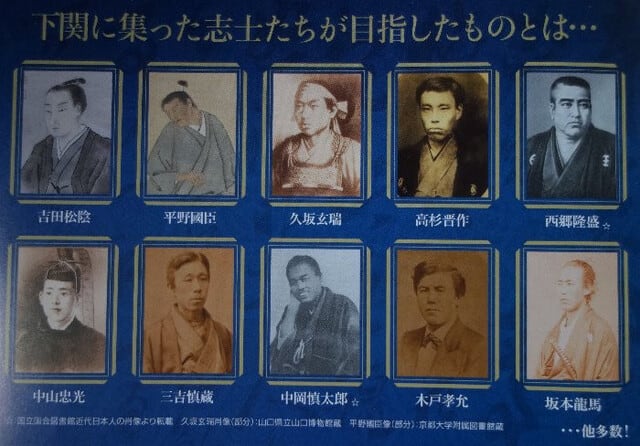

























































































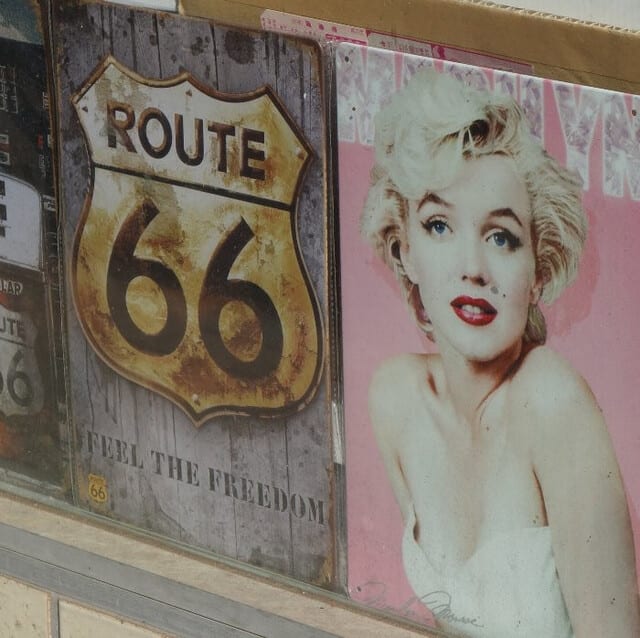



 Google 画像 [
Google 画像 [