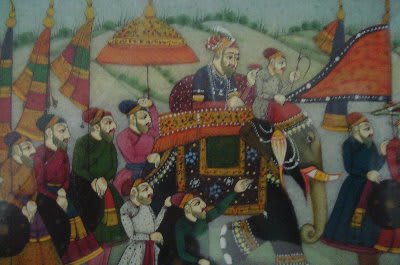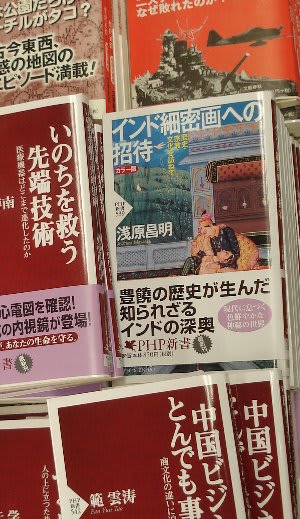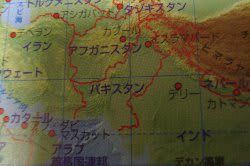荒松雄、『多重都市デリー』
■文芸春秋社の雑誌『諸君』の先月10月号から若泉敬の森田吉彦という若センセによる評伝の連載が始まった。若泉敬はAmazon: 『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』で知られた、沖縄返還の特使・密使だったとされる人物。公然の顔は国際政治学者。 今月号を読むと、若泉敬は、まだ学生時代に、1952年にインドに行き、二ヶ月半も滞在したとのこと。1952年と言えば前年にサンフランシスコ講和があって、やっと日本人が外務大臣が発行するパスポートで海外に行けることになった時期。もっとも一般の日本人が海外に行くことは事実上不可能。ちなみに、この時点で60万から100万の日帝兵士がいまだシベリアにいた。
■インドと沖縄;
「いつも沖縄のことを気に掛けている人だった。」と言われることになる若泉敬がなぜ1952年にインドに行ったのか? 森田吉彦による若泉評伝には「軍国少年であった若泉が、このときアメリカに対してわだかまりを残していたであろうことは容易に察しがつくし、生来完璧主義の傾向を持つ彼にしてみれば、多数講和(米国を中心とする諸国との講和を優先させる策:全面講和の反対。いか@註)という選択は、独立というには中途半端にすぎたのかもしれない。」とある。おいらが妄想するには、このサンフランシスコ講和の時点、つまり1951年に、若泉敬には「インド」幻想があったのではないか?つまり、ネルー率いるインドがサンフランシスコ講和に参加しなかった理由は、米国の沖縄占領に反対したからである。のちに沖縄問題に尽力することになる若泉を考えると、沖縄問題をその当時指摘したネルー・インドに「幻想」を持ったのではないかとおいらは空想している。これはなにも「空想的平和主義」ではなくむしろ現実的パワーポリティクスを考えてのこととも考えられる。事実、岸信介はインドとの外交を、実の方はともかく、象徴的に演出し、対米関係の「相対化」のテコにしようとしたフシがある。ちなみに、サンフランシスコ講和で調印しなかったインドは同年すぐに個別に日印平和条約を調印。だからこそ、1952年に若泉敬、荒松雄らはインドに行けたのである。
■インド幻滅と皮肉;
そんな若泉はインドに幻滅したと評伝は言う。帰国後若泉はインド見聞記を『独立インドの理想と現実 インドは「第三勢力」たりうるか』を著し、「現在、巨象インドは飢えていてほとんど立ち上がる気力すらないといってよい。それはひどい貧困であり、あとにのべるごとく飢餓が拡がり、加うるに無知と疾病である。大きな期待をいだいて渡印したわたくしがみたものは、薄汚い布をまとい跣足でとぼとぼ街を歩く民衆たち数知れぬ乞食の群れ、それに動物として尊重されているという甚大な牛群であった。」と報告。若泉はインド政府が後援する国連アジア学生会議に出席し、インド政府から「最大限の厚遇を受けた」が、経験したのは上記の食水準は東京より何倍も上がったというものではなかったらしい。そして、若泉は言う。「長い狡猾な英国の支配になれてしまったインド民族は、背骨まで麻痺させられて容易に立ち上がれないのではあるまいか。どうも、かれらには毅然たる独立精神とか、自主独立の気概といったものが欠けているように思われた。」
■核武装し大国化するインド;
56年前の若泉の見解を、歴史の結果が出た現在からの視点で、○×つけるつもりはないし、何も若泉がインドを侮っていたことを責めたいわけでもないが、米国や仏国などの既存核武装国家からの核武装の承認を事実上受け大国化したインドについて56年前に語ったその言葉のブーメラン・皮肉効果には笑ってしまった。
「長い狡猾な英国の支配になれてしまったインド民族は、背骨まで麻痺させられて容易に立ち上がれないのではあるまいか。どうも、かれらには毅然たる独立精神とか、自主独立の気概といったものが欠けているように思われた。」
もちろん、ブーメラン・皮肉効果とは、上記の批判の英国を米国に、そしてインドを現代日本として読み直すことに他ならない。
▼追記、インドは飢えていたのか?/餓えているか?
「(インドで)農耕に用いられている土地は、国土全体の52パーセント近くにも達する。日本場合はたかだか12パーセントにすぎないから、これは驚異的な数字である。
全耕地面積でも、旧ソ連、アメリカに次いで、世界第三位にランクされ、世界全体の14.4パーセントを占める。
インドの穀物自給率は107パーセントほどである。」
山下博司、『ヒンドゥー教 インドという<謎>』