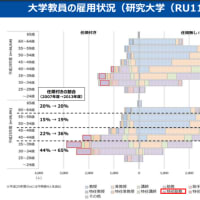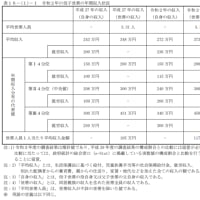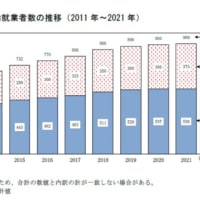昨日、フランシスコ教皇の逝去が報じられた。
BBC News:キリスト教カトリック教会のローマ教皇フランシスコが死去、88歳
キリスト教とは全く関係の無い生活をしている私でも、この訃報にはいろいろ思い、考えることがあった。
一つは世界で一番信者が多いとされるキリスト教のトップの発言力は、世界に与える影響が大きい。
それは、宗教という枠を超え様々な分野にまで影響を及ぼす、と言われている。
特に昨日逝去されたフランシスコ教皇は、「核なき世界」を訴えたり、「中世の悪しきしきたりを変える」など、改革を進めた教皇であったと言われている。
その変革の中でも大きかったのは、「女性の登用」だろう。
朝日新聞:女性登用を進めた「改革者」フランシスコ教皇の功績と残された課題
カソリックにおいて、司祭(=神父)は独身男性と決まっている。
妻帯することが、禁じられているのだ。
しかし、キリスト教という宗教の歴史を見ていくと、決して女性が信仰の中心にいなかったわけではないようだ。
上智学院カトリック・イエズス会センター:カトリック教会で女性が聖職者になれないというのは、女性蔑視ではないでしょうか。
このQ&Aの答えを読むと、キリストが捕らえられた時男性信者は逃げ、女性信者は処刑される十字架まで付き従った、という部分がある。
このような話が口伝えられ、残っていることを考えると、キリスト教の中で女性が果たした役割は大きかったのではないか?ということになる。
そのような歴史的背景を熟知した上で、フランシスコ教皇は女性登用を進めたのではないだろうか?
そう考えると、今問題になっている「安定的皇統の維持」ということにも、重なる部分があるのでは?という気がしてくるのだ。
今年国連から「男女平等」という視点で、皇室典範の「男系男子のみが継ぐ」ということに是正勧告が出た。
この時、「男系男子」を支持する団体の代表者である女性が、「ローマ教皇とダライ・ラマ」を取り上げ、「男性であらねばならないことがある」と、主張された。
この主張の問題の一つは、ローマ教皇もダライ・ラマも「生涯独身男性である」という点だ。
現在「男系男子」にこだわる方々が話される、「男系でなくてはならない」ということに、当てはまらないからだ。
ローマ教皇は「コンクラーベ」と呼ばれる、選ばれた司祭の中から人格・教養・功績などを含め検討され、選ばれる。
ダライ・ラマは、「輪廻転生」の考えを基に、血統ではなく「転生してきた少年」が選ばれる理由となっている。
しかしながら、現在のダライ・ラマ14世は、既にこのような継承をやめる必要がある、という考えを打ち出している。
理由は、「転生してきた少年」の存在が、中国政府によって操作され、次のダライ・ラマは中国政府によってつくられた、中国政府に都合の良い少年が仕立て上げられる、という懸念を持っているからだ。
厳しい戒律を中世から続けてきたカソリックであっても、大きな変化が生まれようとしている。
それは「原点に立ち返る」ということだ。
とすれば、世界各地が混乱の状況にある中、宗教であれ、国や企業のトップであれ、その存在意義の原点に立ち返ることが今求められているのでは?と、感じるのだ。
最新の画像[もっと見る]