朝日新聞ブログ「ベルばらkidsぷらざ」で連載中の世界史レッスン第117回目の今日は、「鬱病の音楽療法」⇒ http://bbkids.cocolog-nifty.com/bbkids/2008/06/post_6e73.html
カストラートの代名詞のようなファリネッリが、その美声でフェリペ5世の鬱治療をしていたエピソードについて書きました。
ファリネッリが日本でも知られるようになったのは、1994年フランス・イタリア・ベルギー合作映画「カストラート」からだろう。
この映画は、監督(ジェラール・コルビオ)の好みが(いつもながら)何とも怪しすぎて「いかがなものか」と言いたい箇所が多々あるにもかかわらず、やはり面白い! バロックのキンキラキンは日本の歌舞伎に通じますね!
画面中のファリネッリの声は、ソプラノとテノールを合成した人工音だそうだ。肉声でこうだったら、確かに観客は熱狂するでしょうね。
ところで本物のカストラートの声がCDで聴けるのをご存知ですか?
実は「最後のカストラート」と呼ばれたアレッサンドロ・モレスキが、晩年、レコードに歌声を吹き込み、それがCD化されているのだ。
『カストラートの時代』(EMI Classics)という輸入版で、コワルスキー、ヴィス、ヤーコプスといった現代のカウンターテナーたちの最後に、その録音が入っている。歌はロッシーニの「小荘厳ミサ曲~クルチフィクスス)。
なんというか、「地獄の底から響いてくる、か細い震え声」といった感じかな。以前、音大の学生にカストラートの説明をしてからこれを聞かせると、「こわ~い!!」と教室中大騒ぎ。
モレスキはオペラ歌手ではなく、教会の専属歌手だったし、とっくに最盛期を過ぎてあまり声もでなくなってからの録音なので、確かにこれではあまり参考にはならないかも。
☆「怖い絵2」、出版2ヶ月でもう4刷で嬉しいです。読者のみなさまに感謝♪

☆『怖い絵』、8刷になりました。ありがとうございます♪
☆マリーもお忘れなく!(ツヴァイク「マリー・アントワネット」(角川文庫、中野京子訳)


カストラートの代名詞のようなファリネッリが、その美声でフェリペ5世の鬱治療をしていたエピソードについて書きました。
ファリネッリが日本でも知られるようになったのは、1994年フランス・イタリア・ベルギー合作映画「カストラート」からだろう。
この映画は、監督(ジェラール・コルビオ)の好みが(いつもながら)何とも怪しすぎて「いかがなものか」と言いたい箇所が多々あるにもかかわらず、やはり面白い! バロックのキンキラキンは日本の歌舞伎に通じますね!
画面中のファリネッリの声は、ソプラノとテノールを合成した人工音だそうだ。肉声でこうだったら、確かに観客は熱狂するでしょうね。
ところで本物のカストラートの声がCDで聴けるのをご存知ですか?
実は「最後のカストラート」と呼ばれたアレッサンドロ・モレスキが、晩年、レコードに歌声を吹き込み、それがCD化されているのだ。
『カストラートの時代』(EMI Classics)という輸入版で、コワルスキー、ヴィス、ヤーコプスといった現代のカウンターテナーたちの最後に、その録音が入っている。歌はロッシーニの「小荘厳ミサ曲~クルチフィクスス)。
なんというか、「地獄の底から響いてくる、か細い震え声」といった感じかな。以前、音大の学生にカストラートの説明をしてからこれを聞かせると、「こわ~い!!」と教室中大騒ぎ。
モレスキはオペラ歌手ではなく、教会の専属歌手だったし、とっくに最盛期を過ぎてあまり声もでなくなってからの録音なので、確かにこれではあまり参考にはならないかも。
☆「怖い絵2」、出版2ヶ月でもう4刷で嬉しいです。読者のみなさまに感謝♪

☆『怖い絵』、8刷になりました。ありがとうございます♪
☆マリーもお忘れなく!(ツヴァイク「マリー・アントワネット」(角川文庫、中野京子訳)













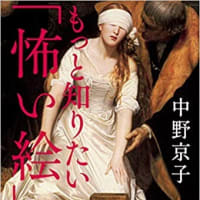







ザルツブルクのミラベル宮殿の大理石の間で、世紀末のピアノでの伴奏。
よくある、バリトンの演奏では、大人の男性(オジサン)の失恋に聴こえてしまうのに、カウンターテナーだと、少年の失恋の痛々しさが伝わってきて、一興でした。
ミラベル宮殿の大理石の間はお風呂の中のように反響するし、至近距離で生白い歌手の顔が見られるから、余計……。
モーツァルトやロッシーニのオペラのカストラートの役なども、今では殆ど、メゾやアルトで代用されていますよね。
一昨年見たヘンデルのオペラでもアルトでした。とってもうまいんですけど、何か根本的に違うかなあ、という気がしてしまいますよね。