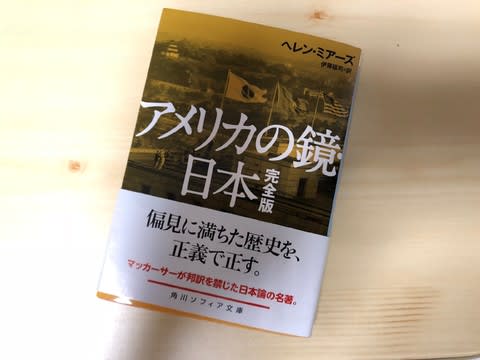 真夏の読書くらいはやはり先の大戦に関するものを、ということで今回はこちらをチョイスしました。表題の「アメリカの鏡・日本」(”Mirror for Americans:JAPAN”)が意味するところは、文字通り近代日本(=戦前の日本)は同じ時期の米国はじめ西洋列強が作り出した「映し鏡」であり、当時の日本に対する批判はそのまま西洋列強自身に跳ね返ってくる。鏡に映るのは自分たち自身の姿なのであり、近代の犯罪はそれを捌いた連合国の犯罪であるというものです。つまり、米国人が戦前及び戦中に「最も軍国主義的国家」、「ファナティックな好戦的民族」、「滅びるまで戦う覚悟の狂信的国民」であると国内で喧伝して対峙し、戦争により「懲罰し拘束する」としてきた近代日本だが、実はその日本というのは260年に及ぶパックストクガワーナの鎖国下で平和や安定を享受していたところ、黒船襲来という米国自身を含む列強の圧力を受けて「西洋文明を映す鏡を掲げてアジアの国際関係に登場してきた」のであるから、実のところ「アメリカ人は日本人の『本性に根ざす伝統的軍国主義』を告発して戦ってきた」が、実はその「告発はブーメランなのだ」(ブーメランという言葉は好きではありませんが…)というのが筆者の問題提起です。要するに(戦後の占領によって)「私たちが改革しようとしている日本は、私たちは最初の教育と改革でつくり出した日本なのだ」とも述べています(本作で著者は終始一貫して「合衆国は」、あるいは「連合国は」といった三人称は用いず「私たち」といった一人称を使用している点も感じるものがあります)。
著者であるヘレン・ミアーズさんは、豊富な日本滞在経験もある米国人の日本専門家です。戦中は米国陸軍省の占領地民政講座で講義を行い、戦後はGHQに設置された労働諮問委員会の委員も勤められた女性ジャーナリストで、本作はもともと彼女が帰国後の1948年に上梓した著作となります。ただ、当初こそ全米の注目の的となった著者ですが、本作の内容は当時の多くの米国人にとっては当然ながら不愉快なものであり、やがて無視されるようになったといいます。そして本作の日本での和訳出版については、当時占領軍のトップであるマッカーサー元帥が「私はいかなる形の検閲や表現の自由の制限も憎んでいるから、自分でこの本を精読したが、本書はプロパンガンダであり、公共の安全を脅かすものであって、占領国日本における同著の出版は、絶対に正当化しえない」と言い抜けて却下し、その後占領終了の翌年になりようやく出版が認められたという経緯があったようです。私は先の大戦で我が国が被害者で戦争責任はないといった論には与しませんし、戦に敗れサンフランシスコ講和条約を結んでしまった以上、ある程度の屈辱も受け入れるより致し方なしと思っています。加えて昨今の一部の排外主義的な動きには嫌悪感さえ抱いている立場ではありますが、こうした(日本人から見れば)ある程度フラットな見方が当時事実としてあり、それも敵対した米国人の中にこうした理解を示してくれていた人もいたのだ、という点は知っていて損のないことではないと思います。そういう意味で、やや終盤は冗長でだれるところはありますが、お薦めできる本と言えます。
以下中身に関して言えば、猪瀬直樹さんの「昭和16年夏の敗戦」においても同様でしたが、本作では日米各々の陸海軍の所有する飛行機の台数、戦前・戦中の飛行機の生産能力や生産の台数、保有する艦船のトン数、同じく戦前戦中の艦船の建造能力や建造実績、鉄鋼の生産実績といったデータで両国の「国力」を比較する箇所があります。要は戦前戦中に米当局が散々日本を「世界の脅威」として煽っていたが、実のところ彼我の国力差はこれだけあったのだ、ということを強調するのが狙いなのですが、この部分で両国の歴然とした当時の国力差を改めて定量的な数字をもって思い知らされ、読んでいて誠に誠に切なく、これだけ国力差がある敵国に玉砕覚悟で挑んで命を落としていった我々の先祖たちの無念を思うと心の底から悲しくなってきます。当時の日本が米国をはじめとした列強の一部に追い込まれて戦争に踏み切らざるを得なかった事情はある程度斟酌はしますが、それにしても、その時々の為政者は負け戦、それも完膚なきまでに負けるような戦は決してしてはいけないと、その後現代に至るまで数々のレガシーを我が国が抱え続けている現状にもかんがみ、あらためてそう思わざるを得ません。
そして冒頭申し上げたとおり、当時のアメリカはじめ連合国が満州事変以降の我が国の行為が「侵略的である」として批判をしているところ、著者は満州事変以降の日本のビヘイビアについても先輩である欧米列強から教わったプロトコルから外れないように日本は苦心して自らの行為を律していた、としています。そして、「日本の行為は侵略であり残虐な行為もあったが、それは他の列強の行動様式と特段に変わるものではない」と断じた上で、いわゆるリットン調査団の報告(1932年10月)で日本がその行為を「断罪」され満州からの撤退を勧告されたのは、恐らく日本としては青天の霹靂だったのではないかと同情さえしてくれています。その列強のご都合主義ぶりは、20世紀初頭にロシアの南下が脅威であれば日英同盟を組んだ上で「番犬」として日露戦争をさせてその南下を食い止め、その後共産主義化したロシア(ソ連)の南下を満州で食い止めていた日本を、今度は最終的に当時日本と不可侵条約を結んでいたそのロシアを味方引き入れて倒したという点に象徴される、とも述べています。
また、そうした当時の西洋列強及び日本のビヘイビアを説明する中で、本作においては「法的擬制」と言う言葉が多用されています。戦前に西洋列強がアジア等に植民地、あるいは勢力圏を作ろうという際に、国際法上合法であることを「擬態」した法的なフィクションのことで、植民地の解放、自由、独立(民族自立)、民主化などといった理想や大義とは大きくかけ離れたものである、というのが筆者の定義のようです。例えば、列強の国が援助してできた傀儡政府を中央政府であるとする擬制、実質列強の支配下にある国を独立国であるとする擬制、国際連盟がその実植民地を持つ列強諸国が自身の体制を維持するための装置であったにもかかわらず美しい理想を掲げていたこと、大東亜を解放するというスローガン、といったものが具体的な例としてこの文脈で掲げられています。当時の我が国も先輩である西洋列強に習ってこの法的擬制/プロトコルをしっかり維持していたにもかかわらず(西洋列強は自分たちのことは棚に上げて)日本を非難して侵略者に仕立て上げたのだ、ということです。
なお、筆者は執筆時点での日本の行く末について大変に案じてくれており、アメリカはじめ駐留軍が日本を金輪際戦争のできない国にするのはもちろんのこと、競合産業を縮小させる等してこのまま経済をシュリンクさせていけば、維新後に倍増した日本人の人口を食わせていくことも危ういのではないか、と危惧してくれています。筆者の見立てでは、米国は当時日本をやっと食べていける程度の国にするつもりだったようです。それが、この時期にロシア、やがて中国で共産主義が勃興してきたからこそ、それを食い止めるための砦として日本を本格的に復興させようと心変わりしたわけですから、このタイミングで共産主義がこの地域で勢いをもったことは結果的に我が国にとって僥倖だったと思わずにはいられません。全くもって皮肉なことです。
| Trackback ( 0 )
|